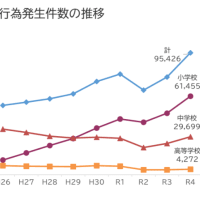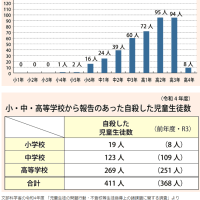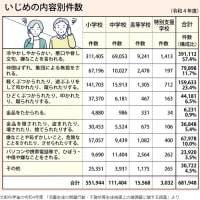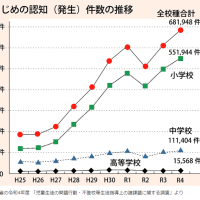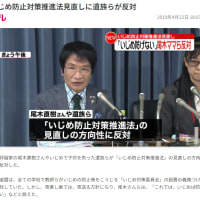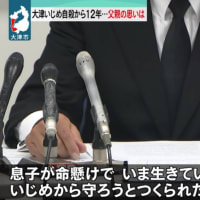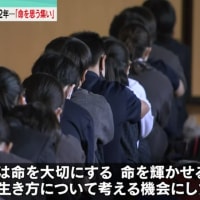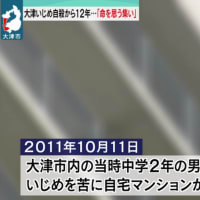凉森神社・美豆城跡


『涼森神社(すずもりじんじゃ)
仁徳天皇の難波高津宮遷都の時(四世紀初め)波・奈良への交通要所のこの地に休息所としての行宮をつくられた際に創建されたといわれる。
祭神は、白髭大神(しらひげのおおかみ)・神速須佐之男命(かみはやすさのおみこと)
大国主命・事代主命(ことしろぬしのみこと)・菅原道真朝臣を祀る。
古くは水豆野神社・水豆森といわれてきたが、樹木が繁茂し大変涼しいことから涼森神社といわれるようになった。また菅原道真公が九州に左遷されるときに、この地に立ち寄られ鈴を献上されたことから、鈴森神社とも別称された。
中世(十三世紀頃)、山城国に糺の森(ただすのもり)・久我の森(こがのもり)・涼の森等八つの大きな森があり、
「山城八森」としても知られていた。
元禄年間に火災焼失、昭和三十六年(一九六 一)の第二室戸台風により損壊したが、再建 し、現在に至る。
催事として、大祭が毎年十月二十三日に、とんど祭 (左義長)が正月十五日頃に開催される。
京都市』 (駒札より)





淀の競馬場から南西方向に1km 余りいくと凉森神社がある。隣が小学校になっており、場所的にも非常にわかりやすい。神社の入り口には石造鳥居とともに駒札があり、神社の由緒についてはその記載内容によってほぼわかる。
おそらく実在したであろう仁徳天皇の時代と言うから、大変な歴史を持っている。なぜこのような場所に神社が建てられたのか。今でもこの土地は桂川・宇治川・木津川と言う比較的大きな川が、この先で一本の川に合流し淀川となって、大阪方面へ流れて行く。さらに南東部の方はかつて巨椋池と言う大きな池があり、淀川を介して水上交通の要所だった場所でもある。また農産物等にとっても、水が豊富な土地でもあり、広く生産されていた。そのような場所柄であり、天皇が行き来する際の中継所として設けられたものが、同時にこの地域の産土神として位置づけられるに至ったものだと考えられる。
名称についても諸説あるが、上記駒札の中にも記されている。また祭神に菅原道真が名を連ねているが、彼が策略にあって九州の地へ流される途中、この地に寄って自画像と鈴を授けたと言う伝承に基づいた話から、祭神のひとつになったようだ。
凉森は比較的広い土地であり、それが境内にもなっている。大きな木々がいたるところに幹を伸ばしており、少し離れたところから見ると、この一帯がちょっとした森に見える。参道を進んでいくと、本殿の後ろ側が見えてくる。この時点で鉄筋コンクリート製であることがわかる。正面に回って拝殿を経て本殿に至る。これが木造であれば非常に趣もあるのだが、そこは致し方のないところかもしれない。1961年の第二室戸台風によって損壊、その経験から後に鉄筋コンクリート製として再建された。





『美豆城
戦国時代この地に美豆城があった。場所は凉森神社の西側に接し、広さは約百メートル四方と云われている。
古文書「春聞御記」に次のように記せられている。
応永廿五年十一月一日(一四一八年)『当国守護代、三方山城入道(範忠) 今日国に入部。・・・美豆に城郭を構え居住云々。』
又「足利季世記」にも
『三好三人衆ハ・・・・其勢一万余人、永禄十二己己正月三日(一五六九年)堺ヲ打・・・・三日ハ山城ノミヅト云処ニ陣取。』
と記せられている。
明治時代には城郭四辺のうち南辺と、西辺の南半の堀が存在、北辺は細い水路として存在していた。
大正時代には東側の堀が存続していた。
築城は三方山城入道(範忠)であるかは不明。
終末期の城主も不明である。
淀南地誌の会』 (説明書きより)

凉森神社の隣にかつて美豆城があった。今現在では一部の遺構が残っているだけだが、かつては100m四方と言うから、そこそこの広さを持っていた。詳細についてはわからないが、おそらく戦国時代に設けられたものと考えられている。周囲を城郭と堀が囲んでおり、内部はおそらく寝泊まりする程度の建物があっただけだと思われる。この地にあって約一万人の勢力を構えていたと言うから、なかなかのものだ。古文書資料に記載されているだけで絵図等はないので具体的な様子がわからないのは残念。