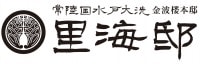水戸偕楽園「梅まつり」レポートの続きです。
かの明治神宮を設計した本多静六博士は
造園学の立場からすれば、
偕楽園は日本3大名園で最も優れたものであると述べています。
おお、凄いではないですか!
本多静六氏の主張によって決められたのかどうか分かりませんが、
現在の偕楽園の「おすすめ散策ルート」は、本多氏のお話通りになっています。
この通りに歩くと、偕楽園のデザインがいかにロケーションを生かした
魅力的な公園であるかを知ることができます。
ちょっと、長くなりますが、偕楽園を楽しみたい方は
読んで損はありませんので、お付き合い下さい。
公園散策スタートです。
徳川斉昭公が意図した「陰陽の世界」を歩いてみます。
<好文亭表門>

↑別名「黒門」と呼ばれる表門より。奥に見えるのは「一の木戸」。
<一の木戸>

↑コケラ葺きの「一の木戸」を通ると、そこは、左に孟宗竹、右に巨大な杉で覆い尽くされた幽遠閑寂の世界に入ります。

↑昼間なのに薄暗い森です。ものすごく高い木が空を覆い尽くしています。

↑歩くと、やがて、クマザサ、オカメザサに挟まれた笹叢の小道となり、中門へ向かいます。
<中門>

↑この門を抜けると好文亭前の広場に出ます。
<好文亭のアプローチ>

↑こちらが好文亭の門。入亭料190円でした。水曜日でしたが、観梅時期のため観光客でいっぱいでした。
<好文亭・玄関付近>

↑結構、庭の木が多くて、全体像は掴めず。。。
<奥御殿・広縁>

↑観覧コースは、好文亭の玄関からすぐに隣接する「奥御殿」へ向かいます。
奥御殿は写真のような広縁と庭に周囲を囲まれています。
<奥御殿・桃の間>

↑鮮やかな襖の絵に目を見張ります。
ほとんどの部屋にこのような草木の絵が描いてあります。
一見豪華なのですが、派手ではなく、渋い魅力を感じさせます。
<奥御殿・庭>

↑観光客が数珠つなぎで見学さえしていなければ、ここは凄く落ち着くところなんでしょうね。
<奥御殿・竹の間>

↑見る人を唸らせる竹の間。襖の爽やかな竹の絵が美しい。
ふと見上げると、なんと欄間が枝付きの竹で組まれているではありませんか!
<奥御殿と好文亭>

↑奥御殿の縁側を時計回りに歩いてゆくと、やがて好文亭が見えてきます。
手前が奥御殿、奥の2階建て(実は3階建て)の建物が好文亭です。
<太鼓橋廊下>

↑これまた暗い廊下です。斉昭公は陰影が好きのようで。。
<好文亭・東広縁>

↑ 好文亭に入りました。
最初に見るのは黒塗りの床が気持ちを引き締める大きな広縁の部屋です。
東広縁と西広縁があり、眺めも素晴らしい。
詩歌や茶の会合が行われたのはこのお部屋なのでしょう。
<好文亭・楽寿楼>

↑ 好文亭の中心には真っ暗な急階段があります。
そこを昇り、3階に出ると、急に明るくなって、ばっと視野が広がります。
偕楽園の梅林を足元に、千波湖と水戸の町並が広がる風景は、見る者を「おお!」と感動させます。
<楽寿楼から見る千波湖>

この素晴らしい眺めを最大限に演出するための伏線として、
表門からずっと幽遠な空間設計をしていたのでしょう。
偕楽園建設の頃を勝手に想像しました。
モノクロームな動線の後に到達する、突然広がる梅林と、水戸地方の広大な田園風景。
江戸時代は現在のように近代建築物や交通インフラがほとんど無かったので、
千波湖とその周囲に恐らく広がっていた水田風景は、見る者を圧倒させたかもしれません。
梅の時期のほか、田植えの頃も、素晴らしい風景だったのでしょうかね。
そんな想像をすると、興奮しちゃいます。
「水戸」って名前がとても素晴らしく感じられる、偕楽園のひとときでした。