本日からスタッフと研修生の半数が一緒の授業
記念写真


七五調、五七調、俳句、短歌の説明 歌詞にはこの七五調が多いことを!!
そして本日は七草粥 この春の七草の覚え方を紹介


春の七草とは、芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら) 、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)を指します。5・7・5・7・7のリズムに合わせて、「せり・なずな / ごぎょう・はこべら / ほとけのざ / すずな・すずしろ / 春の七草」と、子供の頃に覚えた方もいるのではないでしょうか。
●芹(せり)
……水辺の山菜で香りがよく、食欲が増進。
●薺(なずな)
……別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材でした。
●御形(ごぎょう)
……別称は母子草で、草餅の元祖。風邪予防や解熱に効果がある。
●繁縷(はこべら)
……目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなった。
●仏の座(ほとけのざ)
……別称はタビラコ。タンポポに似ていて、食物繊維が豊富。
●菘(すずな)
……蕪(かぶ)のこと。ビタミンが豊富。
●蘿蔔(すずしろ)
……大根(だいこん)のこと。消化を助け、風邪の予防にもなる。
七草粥の由来
年明けの1月7日は別名『七日正月』,『七日節句』とも呼ばれ、その日の朝になると七草がゆを作って食べる風習があります。
この風習の由来は、元々は中国の風習だったそうです。『七日正月』と言って中国ではお正月の7日後が1つの節目になっているので、七種類の野菜を汁物で食べて邪気を祓えると考え七草粥を食べていたみたいですよ。
昔の日本では七草とは、米,麦,稗(ひえ),粟(あわ)などの穀物の事で、これらを使ったおかゆを食べてその年の五穀豊穣を祈っていたのですが、時間が経つにつれ穀物が七種の野草や野菜に変化していったようです。
ちなみに、現在の日本で1月7日に七草粥を食べる風習には、その年の万病を避けられ元気に過ごせるという意味が込められています。
七草の種類と込められた意味について
七草には『春の七草』と『秋の七草』の合計14種あるのですが、無病息災を願った七草粥に使用されるのは『春の七草』です。なので、『春の七草』の種類と込められた意味について紹介しますね。
ちなみに『秋の七草』は基本的に食べられるものは少なく、鑑賞用として楽しむ植物が多いようですよ。
七草の名前 込められた意味
芹(セリ) 競り勝つ
薺(ナズナ) 撫でて汚れを除く
御形(ゴギョウ) 仏体
繁縷(ハコベラ) 繁栄がはびこる
仏の座(ホトケノザ) 仏の安座
菘・鈴菜(スズナ) 神を呼ぶ鈴
蘿蔔・清白(スズシロ) 汚れのない清白
ラッキーにも両替にお付き合いが
26日に鳥取県に行く彼女らに、組合の方の説明があるとのことでドタキャン
いつものようにComTamへ



昼寝しながらブログでした。

2回目の休憩
午後0時56分
記念写真


七五調、五七調、俳句、短歌の説明 歌詞にはこの七五調が多いことを!!
そして本日は七草粥 この春の七草の覚え方を紹介


春の七草とは、芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら) 、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)を指します。5・7・5・7・7のリズムに合わせて、「せり・なずな / ごぎょう・はこべら / ほとけのざ / すずな・すずしろ / 春の七草」と、子供の頃に覚えた方もいるのではないでしょうか。
●芹(せり)
……水辺の山菜で香りがよく、食欲が増進。
●薺(なずな)
……別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材でした。
●御形(ごぎょう)
……別称は母子草で、草餅の元祖。風邪予防や解熱に効果がある。
●繁縷(はこべら)
……目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなった。
●仏の座(ほとけのざ)
……別称はタビラコ。タンポポに似ていて、食物繊維が豊富。
●菘(すずな)
……蕪(かぶ)のこと。ビタミンが豊富。
●蘿蔔(すずしろ)
……大根(だいこん)のこと。消化を助け、風邪の予防にもなる。
七草粥の由来
年明けの1月7日は別名『七日正月』,『七日節句』とも呼ばれ、その日の朝になると七草がゆを作って食べる風習があります。
この風習の由来は、元々は中国の風習だったそうです。『七日正月』と言って中国ではお正月の7日後が1つの節目になっているので、七種類の野菜を汁物で食べて邪気を祓えると考え七草粥を食べていたみたいですよ。
昔の日本では七草とは、米,麦,稗(ひえ),粟(あわ)などの穀物の事で、これらを使ったおかゆを食べてその年の五穀豊穣を祈っていたのですが、時間が経つにつれ穀物が七種の野草や野菜に変化していったようです。
ちなみに、現在の日本で1月7日に七草粥を食べる風習には、その年の万病を避けられ元気に過ごせるという意味が込められています。
七草の種類と込められた意味について
七草には『春の七草』と『秋の七草』の合計14種あるのですが、無病息災を願った七草粥に使用されるのは『春の七草』です。なので、『春の七草』の種類と込められた意味について紹介しますね。
ちなみに『秋の七草』は基本的に食べられるものは少なく、鑑賞用として楽しむ植物が多いようですよ。
七草の名前 込められた意味
芹(セリ) 競り勝つ
薺(ナズナ) 撫でて汚れを除く
御形(ゴギョウ) 仏体
繁縷(ハコベラ) 繁栄がはびこる
仏の座(ホトケノザ) 仏の安座
菘・鈴菜(スズナ) 神を呼ぶ鈴
蘿蔔・清白(スズシロ) 汚れのない清白
ラッキーにも両替にお付き合いが
26日に鳥取県に行く彼女らに、組合の方の説明があるとのことでドタキャン
いつものようにComTamへ



昼寝しながらブログでした。

2回目の休憩
午後0時56分
















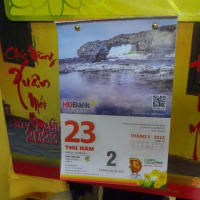



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます