
この本は、売り場に来たとき目を止め、しばらく置いていましたがやっぱり自分で買いました。
絵を観るのが好きです。先日もクリムト展に行きました。
若いころからの画風の変化がわかり、興味深かった。
美術館に行くようになったのは大学生のときからでしょうか。大学の近くに宮城県立美術館があったから。
観るということでは映画館にもよく行きました。駅前のツタヤで、もう観るものがない、と思うほどよくビデオも借りていた。
で、なぜ画家は長寿なのか?
東山魁夷も、ピカソも、熊谷守一も、もちろんシャガールも、実際の絵を観たことがある。
この本を読んで思った。絵が好き、というのもあるけど、その作品を手がけたその人が好き。
もっと言えば、生き様が好き。私が好む生き様は、長寿に通じてもいた。
具体的には、よく観察する。尽きない好奇心。終わらない魂の深化。体を動かし続けること。
画家に定年はない。脳にも定年はない。
逆に、安定したポストもない。自分が自分の主人になるしかない。
なぜ、描き続けるのか? 描き続けることが寿命を延ばしていた。
情熱によって、画家は生きていた。
入力だけでなく、出力することにより、脳が十分に機能する。
画家に限らず芸術家は、共感を生み出し、残すことができるという指摘には大きく肯きました。
共感(芸術)があるからこそ、人は人として生きていける。
逆に、共感が限りなく乏しく、孤立状態が続けば、人は死に近づく。
私にとって小説は、私の総合芸術だと思っています。
気持ちを言葉に乗せ、人物を言葉で浮き上がらせ、場面を言葉で描写し、時間を言葉ですくい取る。
ときには思考を砕いて散りばめる。発見を、主人公に続いて追体験する。
終わりのない道。仕上げるたびに成長していける仕事。
魂とは、自己同一性(アイデンティティー)のことでもあったと気づかされました。
最近は絵を観て励まされます。部屋にはムンクのカレンダーがかかっています。
夏目漱石も、ほとんど治療のために絵を描きました。
私も、心理療法の一環でコラージュ創作に親しんだ時期もありました。
表現、出力というものは楽しいものです。そしてその楽しさは、頭にも寿命にもよい影響があった。
私が書くことの根本にも自己治癒があります。
表現は、生きることそのもの。そして表現だけが共感を生むことができる。
問題があるとすれば、十分に表現できないことにある。
長寿画家たちの残した作品は、今を生きる私たちの財産です。
作品に立ち会い、その人が何か表現したくなったなら、その作品には力がある。
たくさんの絵、絵だけでなく音楽、映画、写真、彫刻、もちろん詩に小説に本。ときに哲学。
スポーツもまた表現の競技です。
また友人たちは、私のあるがままを共感してくれる、そのことで私を生かしてくれる存在でもあります。
たくさんの表現、共感に触れ、生かされ、促され、私もまた表現に希望を見出すようになったのだと、昇華される思いです。
霜田里絵 著/サンマーク出版/2018















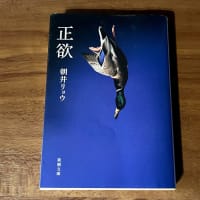









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます