という、”Competitor's Running"誌の記事です。
いわゆる「低炭水化物ダイエット」とは真逆の食事内容ですが、印象としては日本の伝統的食生活と似通っています。
論より証拠、まずは試してみるのも有りです。
ケニア人ランナーの食べ方、走り方
by Matt Fitzgerald, Punlished Jul. 26, 2015 on "Competitor's Running"
現在、世界の長距離走界を席巻しているのはケニア人ランナーである。その理由については、専門家達が様々な仮説を提唱している。例えば、
・居住地が高地である
・生活における主な移動手段が徒歩である
・(遺伝的に)脚が長く、痩せ型の体型(外胚葉型体型)である
などなど。
もちろん、食事にも何らかの秘密が隠されているだろう。ケニア人の伝統的な食生活を論じた専門家は殆どいないが、殆どのエリート選手が営んでいるのはそのような食生活であり、それこそが彼らの走りを支える第一の要因であろう。最近、筆者は"Run in Kenya"(http://www.runinkenya.com/)プロジェクトの援助を受けてケニアを訪問し、そこで得た知識を近著 "The Endurance Diet" にまとめた。2週間のケニア滞在中、筆者はWilson Kipsang(世界記録保持者)を始め多くのケニア人エリートランナーや、Vincent Onywera氏(Kenyatta University)等のケニア人栄養専門家に会った。
更に筆者は、ケニアの伝統的な食事が身体及びランニングに及ぼす影響を体感すべく、滞在中はケニアの伝統的な食事のみを摂取してみた。それは勿論きちんとした科学的体験には相当しないが、しかしその結果は刮目すべきものだった。滞在中に筆者はLewa Safaricomマラソンに出場した。当日は体調も良く、結果は総合17位/マスターズクラス3位/外国人クラスで優勝だった。これ迄20回近くフルマラソンを走った経験があるが、レース後の回復については今回が最も早かった。ケニア滞在中のトレーニング量はとても少なかったが、帰国後に体重を測定したら1.1kg近く減っていた。
上述の個人的な経験及び様々な調査の結果、筆者は、ケニア人の伝統的な食事こそがケニア人ランナーの成功の重要な鍵であり、ランナーとして成功したい全ての人はそのような食事を模倣すべきであると確信するに至った。以下に、ケニア人の伝統的な食事の特徴を列記する。
(1)新鮮な/地場の/加工していない食品を摂取する
ケニア人は加工食品を殆ど全くと言っていい程食べない。筆者を迎え入れてくれたホストファミリー(ナイロビ在住)のキッチンで見た、最も高度に加工された食品は市販のピーナッツバターだったくらいだ。典型的なケニア人の食事は、
・ウガリ(Ugali、とうもろこし粥の一種)
・スクマウィキ(Sukuma wiki、ケールの一種)
・ンデング(Ndengu、ムング豆の煮物)
・チャパティ(Chapati、小麦粉で作られた、トルティーヤに似たパン)
で構成される。筆者がケニア滞在中に食べた食事で最も記憶に残っているのは6品で構成されていたが、それらの原材料は全てホストファミリーが自給自足で調達したものだった。
我々もケニア人を真似て、冷蔵庫の野菜室を食材で満たす一方、戸棚は空っぽにしたいものである。
(2)毎食、澱粉を摂取する
ケニア人の主食は、精製していない澱粉質の食品である。最も普遍的な朝食はuji(発酵させた黍等の雑穀で作った粥にレモン果汁で味付けしたもの)である。筆者はItenにあるLornah Kiplagat's高地トレーニングセンターで2泊したが、昼食及び夕食ではウガリ/米/ジャガイモ/パスタが常に提供された。ケニア人の典型的な食事はそのようなものである。
ケニア人の主食は澱粉質の食品なので、栄養成分的には炭水化物の比率が極めて高い。Onywera氏が2004年に実施した調査では、ケニア人エリートランナーの食事の炭水化物比率(熱量ベース)は約76%であった。最近のアメリカでは炭水化物の摂取が敬遠される傾向にあるが、ケニア人のように走りたいのであれば、「炭水化物恐怖症」を克服すると共に、とうもろこし粉とコーンシロップ(とうもろこしから作った糖液。清涼飲料で使われる)の違いを正確に理解する必要がある。精製していない澱粉質の食品を主食とする食事こそが、高品質のエネルギー源と満腹感を同時にもたらしてくれると共に、高い運動能力の獲得と体脂肪の減少を同時に促進する。
(3)肉類の摂取頻度は減らす
ケニア人ランナーの典型的な食生活では、肉類/魚類の摂取頻度は3~4回/週である。現在では、パレオダイエット(肉類の摂取をもっと増やすべきである、と主張する)と菜食主義者の間で不毛な議論が続いている。ケニア人ランナーの食生活は、この両極端な食事方法の中間に於ける最適な妥協点を見出したものと言える。実際、2013年に行われた大規模な調査(対象者=400,000人)でも、少量の肉類を摂取することが健康にとって適切であると明らかにされている。
(4)間食では果物類を摂る
ケニア人はいわゆる菓子類を殆ど摂取しない。筆者は、ケニアの小学生が生のサトウキビを齧っている姿を目撃したが、これは炭酸飲料を飲むよりかリンゴを食べるのに近いことである。甘い物を食べたくなった時、ケニア人はキャンディーバーやクッキーに手を伸ばすのでなく、パパイヤやバナナを摂る。
現在のアメリカなどでは「糖質恐怖症」が席巻しており、果物類は他の菓子類と一緒くたに「不健康的」というレッテルを貼られている。しかし実際には、果物類は最も健康的な天然物の一つである。果物類の摂取量が増える程、望ましい健康状態を獲得している人が多いという調査結果も報告されている。例えば、2009年に公表された科学的レビューでは、果物類の摂取量と体重との関係を検討している。その結果、果物類の摂取量が増えるに連れ、体重増加が抑制されるか体重減少が促進されるという事実が明らかになっている。
(5)時々は空腹状態で走る
ケニア人エリートランナーは、通常は2~3回/日練習する。1回目のランは、早朝に空腹状態で行う。そのようなスケジュールは、科学的合理性というよりかはむしろ実用的な観点から決めているのだろう。ただ、低グリコーゲン状態(=筋グリコーゲンが半分程度枯渇している状態、起床直後などが相当する)でラントレーニングすることにより、運動能力を促進するような身体の変化が発生するという研究結果も報告されている。1回/日しかラントレーニングをしないという人(大半の人が該当するだろうが)にとっては、そのような低グリコーゲン状態でトレーニングを行いたいとは思わないだろう。しかし1~2回/週は低グリコーゲン状態でトレーニングすれば、ケニア人ランナーの如き高い運動能力を獲得出来るかもしれない。
いわゆる「低炭水化物ダイエット」とは真逆の食事内容ですが、印象としては日本の伝統的食生活と似通っています。
論より証拠、まずは試してみるのも有りです。
ケニア人ランナーの食べ方、走り方
by Matt Fitzgerald, Punlished Jul. 26, 2015 on "Competitor's Running"
現在、世界の長距離走界を席巻しているのはケニア人ランナーである。その理由については、専門家達が様々な仮説を提唱している。例えば、
・居住地が高地である
・生活における主な移動手段が徒歩である
・(遺伝的に)脚が長く、痩せ型の体型(外胚葉型体型)である
などなど。
もちろん、食事にも何らかの秘密が隠されているだろう。ケニア人の伝統的な食生活を論じた専門家は殆どいないが、殆どのエリート選手が営んでいるのはそのような食生活であり、それこそが彼らの走りを支える第一の要因であろう。最近、筆者は"Run in Kenya"(http://www.runinkenya.com/)プロジェクトの援助を受けてケニアを訪問し、そこで得た知識を近著 "The Endurance Diet" にまとめた。2週間のケニア滞在中、筆者はWilson Kipsang(世界記録保持者)を始め多くのケニア人エリートランナーや、Vincent Onywera氏(Kenyatta University)等のケニア人栄養専門家に会った。
更に筆者は、ケニアの伝統的な食事が身体及びランニングに及ぼす影響を体感すべく、滞在中はケニアの伝統的な食事のみを摂取してみた。それは勿論きちんとした科学的体験には相当しないが、しかしその結果は刮目すべきものだった。滞在中に筆者はLewa Safaricomマラソンに出場した。当日は体調も良く、結果は総合17位/マスターズクラス3位/外国人クラスで優勝だった。これ迄20回近くフルマラソンを走った経験があるが、レース後の回復については今回が最も早かった。ケニア滞在中のトレーニング量はとても少なかったが、帰国後に体重を測定したら1.1kg近く減っていた。
上述の個人的な経験及び様々な調査の結果、筆者は、ケニア人の伝統的な食事こそがケニア人ランナーの成功の重要な鍵であり、ランナーとして成功したい全ての人はそのような食事を模倣すべきであると確信するに至った。以下に、ケニア人の伝統的な食事の特徴を列記する。
(1)新鮮な/地場の/加工していない食品を摂取する
ケニア人は加工食品を殆ど全くと言っていい程食べない。筆者を迎え入れてくれたホストファミリー(ナイロビ在住)のキッチンで見た、最も高度に加工された食品は市販のピーナッツバターだったくらいだ。典型的なケニア人の食事は、
・ウガリ(Ugali、とうもろこし粥の一種)
・スクマウィキ(Sukuma wiki、ケールの一種)
・ンデング(Ndengu、ムング豆の煮物)
・チャパティ(Chapati、小麦粉で作られた、トルティーヤに似たパン)
で構成される。筆者がケニア滞在中に食べた食事で最も記憶に残っているのは6品で構成されていたが、それらの原材料は全てホストファミリーが自給自足で調達したものだった。
我々もケニア人を真似て、冷蔵庫の野菜室を食材で満たす一方、戸棚は空っぽにしたいものである。
(2)毎食、澱粉を摂取する
ケニア人の主食は、精製していない澱粉質の食品である。最も普遍的な朝食はuji(発酵させた黍等の雑穀で作った粥にレモン果汁で味付けしたもの)である。筆者はItenにあるLornah Kiplagat's高地トレーニングセンターで2泊したが、昼食及び夕食ではウガリ/米/ジャガイモ/パスタが常に提供された。ケニア人の典型的な食事はそのようなものである。
ケニア人の主食は澱粉質の食品なので、栄養成分的には炭水化物の比率が極めて高い。Onywera氏が2004年に実施した調査では、ケニア人エリートランナーの食事の炭水化物比率(熱量ベース)は約76%であった。最近のアメリカでは炭水化物の摂取が敬遠される傾向にあるが、ケニア人のように走りたいのであれば、「炭水化物恐怖症」を克服すると共に、とうもろこし粉とコーンシロップ(とうもろこしから作った糖液。清涼飲料で使われる)の違いを正確に理解する必要がある。精製していない澱粉質の食品を主食とする食事こそが、高品質のエネルギー源と満腹感を同時にもたらしてくれると共に、高い運動能力の獲得と体脂肪の減少を同時に促進する。
(3)肉類の摂取頻度は減らす
ケニア人ランナーの典型的な食生活では、肉類/魚類の摂取頻度は3~4回/週である。現在では、パレオダイエット(肉類の摂取をもっと増やすべきである、と主張する)と菜食主義者の間で不毛な議論が続いている。ケニア人ランナーの食生活は、この両極端な食事方法の中間に於ける最適な妥協点を見出したものと言える。実際、2013年に行われた大規模な調査(対象者=400,000人)でも、少量の肉類を摂取することが健康にとって適切であると明らかにされている。
(4)間食では果物類を摂る
ケニア人はいわゆる菓子類を殆ど摂取しない。筆者は、ケニアの小学生が生のサトウキビを齧っている姿を目撃したが、これは炭酸飲料を飲むよりかリンゴを食べるのに近いことである。甘い物を食べたくなった時、ケニア人はキャンディーバーやクッキーに手を伸ばすのでなく、パパイヤやバナナを摂る。
現在のアメリカなどでは「糖質恐怖症」が席巻しており、果物類は他の菓子類と一緒くたに「不健康的」というレッテルを貼られている。しかし実際には、果物類は最も健康的な天然物の一つである。果物類の摂取量が増える程、望ましい健康状態を獲得している人が多いという調査結果も報告されている。例えば、2009年に公表された科学的レビューでは、果物類の摂取量と体重との関係を検討している。その結果、果物類の摂取量が増えるに連れ、体重増加が抑制されるか体重減少が促進されるという事実が明らかになっている。
(5)時々は空腹状態で走る
ケニア人エリートランナーは、通常は2~3回/日練習する。1回目のランは、早朝に空腹状態で行う。そのようなスケジュールは、科学的合理性というよりかはむしろ実用的な観点から決めているのだろう。ただ、低グリコーゲン状態(=筋グリコーゲンが半分程度枯渇している状態、起床直後などが相当する)でラントレーニングすることにより、運動能力を促進するような身体の変化が発生するという研究結果も報告されている。1回/日しかラントレーニングをしないという人(大半の人が該当するだろうが)にとっては、そのような低グリコーゲン状態でトレーニングを行いたいとは思わないだろう。しかし1~2回/週は低グリコーゲン状態でトレーニングすれば、ケニア人ランナーの如き高い運動能力を獲得出来るかもしれない。











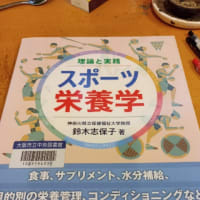





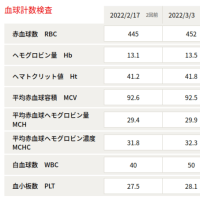
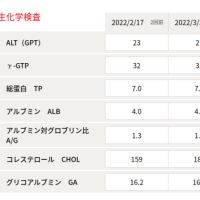
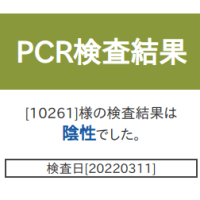





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます