【今朝の体組成】
体脂肪量 :6.6kg
除脂肪体重:58.3kg
------------------------------
体重 :64.9kg
体脂肪率 :10.2%
昨夜の時点では、今朝は自転車ロード練習@箕面と考えていたのですが、記憶を失ってしまい、気が付いたら7時でした。なので、お休みしました。
やはり、オッサンにとっては5日/週の有酸素運動が限界みたいです。ここは年齢に抗わず、素直に生きようと思います。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
標記の件に関する、"Competitor Running"誌の記事です。
やはり、自然のシステムには逆らわない方が良さそうです。
ランニングに於ける内分泌物質(ホルモン)の役割について
by Kelly O'Mara
真剣にトレーニングに取り組むほど、内分泌物質/内分泌系に何らかの影響が及ぶのは不可避である。しかし、テストステロンやヒト成長ホルモンの血中濃度を上げようという考えは、いわば内分泌系を台無しにすることに他ならず、その結果は悲惨なものとなる。
ノースカロライナ大学で運動生理学を研究し、「運動内分泌学("Sports Endocrinology")(第二版)」の共著者でもあるAnthony Hackney教授は、「中途半端な知識は危険である」と警告している。
Hackney教授は、内分泌物質同士のバランスを理解することが大切だと強調する。アスリートとして知っておくべき内分泌物質は、
・成長ホルモン(ヒト成長ホルモン、Human Growth Hormone)
・インスリン及びインスリン様成長因子
・コルチゾール
・テストステロン
である。
シアトルを拠点とする"Club Northwest"でランニングコーチを務めるTom Cotner (Ph.D)は、成長ホルモンは筋肉の適応反応を誘起すると指摘する。成長ホルモンはタンパク同化ホルモンであり、成長を促進する作用がある。具体的には、運動によるストレスを受けた筋肉/細胞に働きかけ、ストレスに適応出来るようにする。実際に筋肉がストレスに適応するのは、回復期間に於いてである。
人間では、睡眠中に脳波がデルタ波を示す期間に分泌される。ただ、加齢に伴い、睡眠中に脳波がデルタ波を示す期間は短くなる。また運動中にも成長ホルモンは分泌されるが、量としては少ない。Cotnerによると、成長ホルモンがその効力を発揮するのは、運動後10~75分の間である。
成長ホルモンはエネルギーの消費に反応して脳下垂体から分泌されるので、Cotnerによるとその系を「騙す」ことは可能である。例えば、
・1回/日以上トレーニングをする
・より強度の高いトレーニングをする
・トレーニング後に水風呂で身体を冷却する
等でエネルギーを消費する、といった方法によってである。
しかし、週単位でトレーニングを積み重ねていく内に、1回のトレーニングに伴い分泌される成長ホルモンの量は徐々に減少する。これは、肉体がトレーニングに伴いもたらされるストレスに適応した結果である。Hackney教授によると、成長ホルモンの効果を実感したいのであれば、それこそ体調が絶不調となる迄追い込み、その状態でトレーニングを行う必要があるのだそうだ。
運動に関連する内分泌物質の中で最も見落とされているのは、インスリン/インスリン様成長因子である。インスリン様成長因子は成長ホルモンによって活性化され、細胞に付着し、細胞の成長/代謝を調節する。インスリンは細胞によるグルコースの取り込み/グリコーゲンの貯蔵を調節する。この調節作用は、運動時にエネルギー代謝系が正しく活動するのに必要となる。
食事/休養/運動が規則正しく行われていれば、内分泌物質の間には相互調節作用が作動し、それらの均衡が維持される。Hackneyに言わせると、「(内分泌物質の)あるものは増加し、あるものは減少する」となる。
しかしオーバートレーニング状態になると、内分泌物質間の均衡が崩れる。Cotnerは「内分泌系に過剰な負荷を掛けるのは可能である」と指摘する。
コルチゾールは副腎で分泌され、抗炎症作用/細胞を破壊する異化作用を有する内分泌物質である。人間では通常、コルチゾールは筋タンパク質を1%/日のペースで破壊し、一方で成長ホルモン/インスリン様成長因子が破壊された筋タンパク質を再生/置換している。継続的にトレーニングをしていると、コルチゾールによる筋タンパク質の破壊量は3~5%/日に増大する。つまり、トレーニング量が増えるに伴い、コルチゾールの分泌量も増大し、その結果として筋タンパク質の破壊量も(基本的に)増大する。
トレーニング量が過剰になると、体内のテストステロン濃度も減少する。テストステロンは性別に関係無く体内に存在し、筋肉量の増大/回復に要する時間の減少に寄与している。テストステロン濃度はトレーニング強度と関係する。具体的には、トレーニング強度が高くなるとテストステロン濃度は増大し、逆に長時間×低強度のトレーニングではテストステロン濃度は減少する。
アスリートの場合、内分泌物質の均衡が崩れる第一の理由はオーバートレーニングである。内分泌物質の均衡が崩れた結果、オーバートレーニングに伴う様々な現象(不眠/酷い筋肉痛/安静時心拍数の上昇/全身的な疲労感等)が発現する。一般的には、このような現象が見られる場合、トレーニングを始めとする生活全般を見直す必要がある。ただ、どれ位のトレーニング量が適切かを正確に知ることは困難である。
Hackney教授は、「どれ位のトレーニング量が適切かを正確に予測出来るのであれば、私はもっとお金を稼げただろう」と笑いながら語る。
内分泌物質の均衡に影響を及ぼす他の要因に、日常生活で受けるストレスが挙げられる。それらはコルチゾール/エピネフリン/ノルエピネフリンの分泌を誘起する。Cotnerによると、睡眠不足/アルコール摂取によっても成長ホルモンの分泌が抑制される。アルコール摂取に関しては、ビール一杯(訳者注:正確な量は記載されていません)を飲むと、成長ホルモンの分泌量が25%減少するとのことである。また、加齢に伴い内分泌系の活動は低下し、成長ホルモンの分泌量は減少する。これがいわゆる「遅発痛」の原因と考えられている。なお、この遅発痛は、元々成長ホルモン/テストステロンの分泌量が少ない女性にも見られる現象である。
摂取エネルギー量が充分でない場合、内分泌系全体の活動が阻害されるという問題が発生し得る。これは女性アスリートにとっては深刻な問題となる。運動直後の「回復の為の時間帯」に(タンパク質6g+炭水化物30g)を摂るとコルチゾールの分泌が遅延される。また、体内で産生されるEPOによる調節作用が働いて赤血球が産生される為には、鉄分を充分に摂取する必要がある。そして、何らかの疾患等が発症している状態では、内分泌系はそれらへの対処を優先する。
特定の内分泌物質だけをより多く分泌させようとする方法は様々である。例えば、低酸素室で寝ると、EPOの血中濃度が自然に増大する。また、テストステロンやヒト成長ホルモン(HGH)の血中濃度を増大させる市販薬も存在する。しかしそれらも「やり過ぎは効かない」とHackneyは警告する。
特定の内分泌物質の血中濃度を短期的に操作する有効な方法は確かに存在する。例えば筋力トレーニングを行うと、成長ホルモン/テストステロン/インスリン様成長因子の血中濃度が短期的には増大する。しかしそれらが長距離走に有効=速く走られるようになる、ということは立証されていない。
違法なドーピング手法によって内分泌物質の血中濃度を増大させ、その結果として身体能力を向上させることが可能という点については、HackneyとCotnerも同意している。しかしあくまでもそれらは違法であると共に、健康上重大な問題を引き起こす。内分泌物質の均衡を人為的に操作することは、場合によっては死につながることもある。内分泌系は複雑な系なので、あくまでも固有の自己調節機構に任せるのが適切である。また、その複雑な系の一部を人為的に操作することでどのような副作用が現れるかを完全な把握することは不可能である。
Cotnerは「全ての内分泌物質を同等に扱うことは不可能である」と指摘する。
体脂肪量 :6.6kg
除脂肪体重:58.3kg
------------------------------
体重 :64.9kg
体脂肪率 :10.2%
昨夜の時点では、今朝は自転車ロード練習@箕面と考えていたのですが、記憶を失ってしまい、気が付いたら7時でした。なので、お休みしました。
やはり、オッサンにとっては5日/週の有酸素運動が限界みたいです。ここは年齢に抗わず、素直に生きようと思います。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
標記の件に関する、"Competitor Running"誌の記事です。
やはり、自然のシステムには逆らわない方が良さそうです。
ランニングに於ける内分泌物質(ホルモン)の役割について
by Kelly O'Mara
真剣にトレーニングに取り組むほど、内分泌物質/内分泌系に何らかの影響が及ぶのは不可避である。しかし、テストステロンやヒト成長ホルモンの血中濃度を上げようという考えは、いわば内分泌系を台無しにすることに他ならず、その結果は悲惨なものとなる。
ノースカロライナ大学で運動生理学を研究し、「運動内分泌学("Sports Endocrinology")(第二版)」の共著者でもあるAnthony Hackney教授は、「中途半端な知識は危険である」と警告している。
Hackney教授は、内分泌物質同士のバランスを理解することが大切だと強調する。アスリートとして知っておくべき内分泌物質は、
・成長ホルモン(ヒト成長ホルモン、Human Growth Hormone)
・インスリン及びインスリン様成長因子
・コルチゾール
・テストステロン
である。
シアトルを拠点とする"Club Northwest"でランニングコーチを務めるTom Cotner (Ph.D)は、成長ホルモンは筋肉の適応反応を誘起すると指摘する。成長ホルモンはタンパク同化ホルモンであり、成長を促進する作用がある。具体的には、運動によるストレスを受けた筋肉/細胞に働きかけ、ストレスに適応出来るようにする。実際に筋肉がストレスに適応するのは、回復期間に於いてである。
人間では、睡眠中に脳波がデルタ波を示す期間に分泌される。ただ、加齢に伴い、睡眠中に脳波がデルタ波を示す期間は短くなる。また運動中にも成長ホルモンは分泌されるが、量としては少ない。Cotnerによると、成長ホルモンがその効力を発揮するのは、運動後10~75分の間である。
成長ホルモンはエネルギーの消費に反応して脳下垂体から分泌されるので、Cotnerによるとその系を「騙す」ことは可能である。例えば、
・1回/日以上トレーニングをする
・より強度の高いトレーニングをする
・トレーニング後に水風呂で身体を冷却する
等でエネルギーを消費する、といった方法によってである。
しかし、週単位でトレーニングを積み重ねていく内に、1回のトレーニングに伴い分泌される成長ホルモンの量は徐々に減少する。これは、肉体がトレーニングに伴いもたらされるストレスに適応した結果である。Hackney教授によると、成長ホルモンの効果を実感したいのであれば、それこそ体調が絶不調となる迄追い込み、その状態でトレーニングを行う必要があるのだそうだ。
運動に関連する内分泌物質の中で最も見落とされているのは、インスリン/インスリン様成長因子である。インスリン様成長因子は成長ホルモンによって活性化され、細胞に付着し、細胞の成長/代謝を調節する。インスリンは細胞によるグルコースの取り込み/グリコーゲンの貯蔵を調節する。この調節作用は、運動時にエネルギー代謝系が正しく活動するのに必要となる。
食事/休養/運動が規則正しく行われていれば、内分泌物質の間には相互調節作用が作動し、それらの均衡が維持される。Hackneyに言わせると、「(内分泌物質の)あるものは増加し、あるものは減少する」となる。
しかしオーバートレーニング状態になると、内分泌物質間の均衡が崩れる。Cotnerは「内分泌系に過剰な負荷を掛けるのは可能である」と指摘する。
コルチゾールは副腎で分泌され、抗炎症作用/細胞を破壊する異化作用を有する内分泌物質である。人間では通常、コルチゾールは筋タンパク質を1%/日のペースで破壊し、一方で成長ホルモン/インスリン様成長因子が破壊された筋タンパク質を再生/置換している。継続的にトレーニングをしていると、コルチゾールによる筋タンパク質の破壊量は3~5%/日に増大する。つまり、トレーニング量が増えるに伴い、コルチゾールの分泌量も増大し、その結果として筋タンパク質の破壊量も(基本的に)増大する。
トレーニング量が過剰になると、体内のテストステロン濃度も減少する。テストステロンは性別に関係無く体内に存在し、筋肉量の増大/回復に要する時間の減少に寄与している。テストステロン濃度はトレーニング強度と関係する。具体的には、トレーニング強度が高くなるとテストステロン濃度は増大し、逆に長時間×低強度のトレーニングではテストステロン濃度は減少する。
アスリートの場合、内分泌物質の均衡が崩れる第一の理由はオーバートレーニングである。内分泌物質の均衡が崩れた結果、オーバートレーニングに伴う様々な現象(不眠/酷い筋肉痛/安静時心拍数の上昇/全身的な疲労感等)が発現する。一般的には、このような現象が見られる場合、トレーニングを始めとする生活全般を見直す必要がある。ただ、どれ位のトレーニング量が適切かを正確に知ることは困難である。
Hackney教授は、「どれ位のトレーニング量が適切かを正確に予測出来るのであれば、私はもっとお金を稼げただろう」と笑いながら語る。
内分泌物質の均衡に影響を及ぼす他の要因に、日常生活で受けるストレスが挙げられる。それらはコルチゾール/エピネフリン/ノルエピネフリンの分泌を誘起する。Cotnerによると、睡眠不足/アルコール摂取によっても成長ホルモンの分泌が抑制される。アルコール摂取に関しては、ビール一杯(訳者注:正確な量は記載されていません)を飲むと、成長ホルモンの分泌量が25%減少するとのことである。また、加齢に伴い内分泌系の活動は低下し、成長ホルモンの分泌量は減少する。これがいわゆる「遅発痛」の原因と考えられている。なお、この遅発痛は、元々成長ホルモン/テストステロンの分泌量が少ない女性にも見られる現象である。
摂取エネルギー量が充分でない場合、内分泌系全体の活動が阻害されるという問題が発生し得る。これは女性アスリートにとっては深刻な問題となる。運動直後の「回復の為の時間帯」に(タンパク質6g+炭水化物30g)を摂るとコルチゾールの分泌が遅延される。また、体内で産生されるEPOによる調節作用が働いて赤血球が産生される為には、鉄分を充分に摂取する必要がある。そして、何らかの疾患等が発症している状態では、内分泌系はそれらへの対処を優先する。
特定の内分泌物質だけをより多く分泌させようとする方法は様々である。例えば、低酸素室で寝ると、EPOの血中濃度が自然に増大する。また、テストステロンやヒト成長ホルモン(HGH)の血中濃度を増大させる市販薬も存在する。しかしそれらも「やり過ぎは効かない」とHackneyは警告する。
特定の内分泌物質の血中濃度を短期的に操作する有効な方法は確かに存在する。例えば筋力トレーニングを行うと、成長ホルモン/テストステロン/インスリン様成長因子の血中濃度が短期的には増大する。しかしそれらが長距離走に有効=速く走られるようになる、ということは立証されていない。
違法なドーピング手法によって内分泌物質の血中濃度を増大させ、その結果として身体能力を向上させることが可能という点については、HackneyとCotnerも同意している。しかしあくまでもそれらは違法であると共に、健康上重大な問題を引き起こす。内分泌物質の均衡を人為的に操作することは、場合によっては死につながることもある。内分泌系は複雑な系なので、あくまでも固有の自己調節機構に任せるのが適切である。また、その複雑な系の一部を人為的に操作することでどのような副作用が現れるかを完全な把握することは不可能である。
Cotnerは「全ての内分泌物質を同等に扱うことは不可能である」と指摘する。


















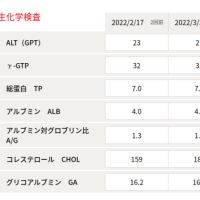
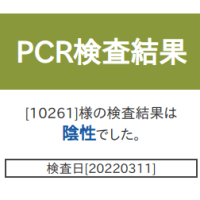
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます