…という、"Competitor Running"誌の記事です。
真面目な人ほどオーバートレーニングに陥り易いので、注意が必要です。
ご参考まで。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
オーバートレーニング:その原因/判定/解決について
by Jeff Gaudette, Jan. 22, 2014
ランナーの半分以上が、競技人生において少なくとも一度は経験している
オーバートレーニングという単語に恐れをなすランナーは多いだろう。ある研究によると、真剣にランニングに取り組んでいる人の約61%は、その競技人生において一度はオーバートレーニングを経験している。尤も、目的達成の為に自らを限界まで追い込むランナーにとっては何の役にも立たない研究結果だろうが。
オーバートレーニングが恐ろしいのは、自分がその状態に陥っていることを判定/測定する方法が殆ど無い、ということである。疲労骨折みたいにきちんと判断出来ないし、ハンガーノックみたいに明確に苦痛が知覚出来るものでもない。オーバートレーニングが原因で、痛みを始めとする何らかの兆候が表出することはない。研究室レベルでは、カテコールアミンの分泌量や筋神経系の活動パターンを測定して判定することも可能であるが、一般のランナーにとって、トレーニングに伴う単なる疲労とオーバートレーニングを区別するのは困難である。オーバートレーニングに伴う兆候は明確ではないが、
どのような行動がオーバートレーニングを招くかを同定し、オーバートレーニングに陥る一歩手前で現れる微かな兆候を認識するのは可能である。そこで本稿では、それらを紹介すると共に、オーバートレーニングに陥った場合にその状態から脱出する方法を考察する。
オーバートレーニングの原因
オーバートレーニングの根本的な原因は、反復/継続して運動を実践している場合、身体が充分に回復しないまま次の運動を行うことである。熱心なアスリート程、身体が充分に回復しないまま自らを限界まで追い込む傾向があるが、研究者らはオーバートレーニングを発生させ易い特徴を幾つか特定している。それらは以下の通りである。
(1)一回のトレーニング期間での負荷が大き過ぎる
筆者の経験からすると、オーバートレーニングの一般的な原因は、自己記録を更新しようとして一回のトレーニング期間で過大な負荷をかけることである。ランナーにとっては、ステップ・バイ・ステップで基礎能力を向上させることが大切である。それを怠ることがオーバートレーニングにつながり易い。
Jack Danielsが著書「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」(ベースボールマガジン社刊)で公開したVDOT表によって、適切なトレーニング負荷とその進展方法が明確になった。また、ランナーが自らのランニング能力を評価することも可能となった。彼は上述の著書において、ランナーは現時点でのレースでの成績を基にトレーニングするべきであり、それを超えて新しい段階に至るのは、レースで自己新記録を出してから、と主張している。というのも、レースで自己新記録を出すということは、身体能力が新しい段階に到達したことの証明だからである。筆者の経験からも、そうすることは最も安全/確実に身体能力を向上させる方法であると共に、オーバートレーニングを避ける事にもつながると考える。
(2)トレーニング間で適切な休養を取らない
オーバートレーニングのもう一つの原因は、トレーニング(期間)間で充分な休養を取らない事である。アスリートの多くは、トレーニング(期間)間で休養を殆ど取らないか、取っても短過ぎて身体を回復させるのには不充分である。大抵の場合、トレーニング/レースで肉体を限界迄追い込み、その後休む間もなく次の目標へ向けて強度の高いトレーニングを再開する、といった感じである。その結果、身体は疲労から完全に回復することは無い。常に疲労を覚えた状態となり、オーバートレーニングに陥る危険性が劇的に増大する。
身体能力を長期的に向上させるには、トレーニング/レースの後には適切な休養期間を設定し、身体を回復させるのが必要である。筆者としては、適切な休養期間とは
・5,000m程度のレース後 :1週間程度
・10,000m~ハーフマラソンの後:1~2週間
・フルマラソンの後 :2週間
であると考えている。長過ぎると感じるランナーもいるだろうが、大事なのは身体能力を長期的に向上させることである。
(3)強度の高いスピード練習の頻度が多い/期間が長い
スピード練習/最大酸素摂取量でのトレーニングの頻度が多過ぎる/期間が長過ぎると、オーバートレーニングに陥る危険性が増大することは既に立証されている。運動生理学者達は、スピード練習を8週間以上に渡って実践したランナーでオーバートレーニングの兆候が多く見られたが、その原因は血液のpH上昇/血中乳酸濃度の低迷ではないかという仮説を提唱している。
強度の高いスピード練習を多く行うことに伴うオーバートレーニングを回避する為には、そのようなトレーニングを行う前に既に強固な基礎的有酸素運動能力を構築/維持するのが大切となる。
オーバートレーニングの兆候
既に説明した通り、オーバートレーニングに陥っているか否かを正確に判定するには、様々な機器が必要である。しかし、身体が完全に回復しているかどうかを判断するのに役立つ判断基準が幾つかあるので、紹介する。
(1)心拍数
オーバートレーニングに陥った状態では、安静時心拍数が通常より高くなる。起床直後には安静時心拍数を測定→記録するのを習慣にしよう。安静時心拍数が通常より高い状態が継続する場合、オーバートレーニングに陥った可能性が疑われる。
注意:心拍数に影響を及ぼす因子は、トレーニング以外にも無数にある。例えば、ストレス/体の水分状態/カフェイン/睡眠時間等である。なので、日間変動は余り気にする必要は無い。あくまでも中長期的な傾向に着目する。
(2)イライラ感
オーバートレーニングは内分泌物質(特にカテコールアミン)の生成量減少を誘発する。カテコールアミンの生成量が減少すると、交感神経系に影響が及ぶ。その結果、被抑圧感/イライラ感が増大する。そのような感情が増大していると認知したら、それはオーバートレーニングの兆候である可能性が考えられる。
(3)病気になり易い
オーバートレーニングによって免疫力が低下し、その結果風邪/インフルエンザを始めとする感染症に罹患し易くなる。普段より病気になり易いかな?と感じたら、それはオーバートレーニングの兆候であるかも知れない。
(4)睡眠パターンが安定しない
オーバートレーニングに陥ると概日リズムが乱れ、睡眠障害が発生する場合がある。具体的には、起床時刻が格段に早くなる/熟睡出来ないといった状態になる。
注意:概日リズムは、日照量の季節的変化の影響も受ける。季節の変わり目に睡眠障害が発生した場合、それは日の出/日の入り時刻に対する自然な反応かもしれない。
勿論、これらの兆候は単独ではオーバートレーニングの明確な判断基準とはならないが、複数の兆候を認知したならば、オーバートレーニングに陥った事を疑い、適宜休養するのが望ましい。
オーバートレーニングの自己解決方法
これまでオーバートレーニングの原因/兆候について述べてきたが、次にその解決方法を端的に紹介する。オーバートレーニングに陥った場合、休養/回復に専念する必要がある。
(1)どれ位休むべきなのか?
残念ながら、オーバートレーニング状態から脱出する為に必要な休養期間については、研究者/コーチの間でも見解が分かれる。基本的には、休養期間はオーバートレーニングに伴う症状の深刻度や、それに対する身体の反応能力に左右される。筆者としては、オーバートレーニングに陥った場合、ラントレーニング再開まで最低3週間は休養すべきと考える。一般的には、身体を完全に回復させるには最低6~8週間の休養が必要と考えられている。身体の状態を的確に判断することが重要である。そして、時には「休む我慢」に耐えるのも必要である。
(2)回復過程を加速させるには
健康的な食生活を維持することが大切である。つまり、栄養に富む食材を必要十分量摂取することである。その他にも、ストレッチする/マッサージをしてもらう/しっかり睡眠する等も役立つ。
一般的なオーバートレーニングの原因について学習し、その徴候を早期に認知することで、オーバートレーニングに陥ることが回避可能となるし、仮にオーバートレーニングに陥ったとしても、早期に回復することが可能となる。
真面目な人ほどオーバートレーニングに陥り易いので、注意が必要です。
ご参考まで。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
オーバートレーニング:その原因/判定/解決について
by Jeff Gaudette, Jan. 22, 2014
ランナーの半分以上が、競技人生において少なくとも一度は経験している
オーバートレーニングという単語に恐れをなすランナーは多いだろう。ある研究によると、真剣にランニングに取り組んでいる人の約61%は、その競技人生において一度はオーバートレーニングを経験している。尤も、目的達成の為に自らを限界まで追い込むランナーにとっては何の役にも立たない研究結果だろうが。
オーバートレーニングが恐ろしいのは、自分がその状態に陥っていることを判定/測定する方法が殆ど無い、ということである。疲労骨折みたいにきちんと判断出来ないし、ハンガーノックみたいに明確に苦痛が知覚出来るものでもない。オーバートレーニングが原因で、痛みを始めとする何らかの兆候が表出することはない。研究室レベルでは、カテコールアミンの分泌量や筋神経系の活動パターンを測定して判定することも可能であるが、一般のランナーにとって、トレーニングに伴う単なる疲労とオーバートレーニングを区別するのは困難である。オーバートレーニングに伴う兆候は明確ではないが、
どのような行動がオーバートレーニングを招くかを同定し、オーバートレーニングに陥る一歩手前で現れる微かな兆候を認識するのは可能である。そこで本稿では、それらを紹介すると共に、オーバートレーニングに陥った場合にその状態から脱出する方法を考察する。
オーバートレーニングの原因
オーバートレーニングの根本的な原因は、反復/継続して運動を実践している場合、身体が充分に回復しないまま次の運動を行うことである。熱心なアスリート程、身体が充分に回復しないまま自らを限界まで追い込む傾向があるが、研究者らはオーバートレーニングを発生させ易い特徴を幾つか特定している。それらは以下の通りである。
(1)一回のトレーニング期間での負荷が大き過ぎる
筆者の経験からすると、オーバートレーニングの一般的な原因は、自己記録を更新しようとして一回のトレーニング期間で過大な負荷をかけることである。ランナーにとっては、ステップ・バイ・ステップで基礎能力を向上させることが大切である。それを怠ることがオーバートレーニングにつながり易い。
Jack Danielsが著書「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」(ベースボールマガジン社刊)で公開したVDOT表によって、適切なトレーニング負荷とその進展方法が明確になった。また、ランナーが自らのランニング能力を評価することも可能となった。彼は上述の著書において、ランナーは現時点でのレースでの成績を基にトレーニングするべきであり、それを超えて新しい段階に至るのは、レースで自己新記録を出してから、と主張している。というのも、レースで自己新記録を出すということは、身体能力が新しい段階に到達したことの証明だからである。筆者の経験からも、そうすることは最も安全/確実に身体能力を向上させる方法であると共に、オーバートレーニングを避ける事にもつながると考える。
(2)トレーニング間で適切な休養を取らない
オーバートレーニングのもう一つの原因は、トレーニング(期間)間で充分な休養を取らない事である。アスリートの多くは、トレーニング(期間)間で休養を殆ど取らないか、取っても短過ぎて身体を回復させるのには不充分である。大抵の場合、トレーニング/レースで肉体を限界迄追い込み、その後休む間もなく次の目標へ向けて強度の高いトレーニングを再開する、といった感じである。その結果、身体は疲労から完全に回復することは無い。常に疲労を覚えた状態となり、オーバートレーニングに陥る危険性が劇的に増大する。
身体能力を長期的に向上させるには、トレーニング/レースの後には適切な休養期間を設定し、身体を回復させるのが必要である。筆者としては、適切な休養期間とは
・5,000m程度のレース後 :1週間程度
・10,000m~ハーフマラソンの後:1~2週間
・フルマラソンの後 :2週間
であると考えている。長過ぎると感じるランナーもいるだろうが、大事なのは身体能力を長期的に向上させることである。
(3)強度の高いスピード練習の頻度が多い/期間が長い
スピード練習/最大酸素摂取量でのトレーニングの頻度が多過ぎる/期間が長過ぎると、オーバートレーニングに陥る危険性が増大することは既に立証されている。運動生理学者達は、スピード練習を8週間以上に渡って実践したランナーでオーバートレーニングの兆候が多く見られたが、その原因は血液のpH上昇/血中乳酸濃度の低迷ではないかという仮説を提唱している。
強度の高いスピード練習を多く行うことに伴うオーバートレーニングを回避する為には、そのようなトレーニングを行う前に既に強固な基礎的有酸素運動能力を構築/維持するのが大切となる。
オーバートレーニングの兆候
既に説明した通り、オーバートレーニングに陥っているか否かを正確に判定するには、様々な機器が必要である。しかし、身体が完全に回復しているかどうかを判断するのに役立つ判断基準が幾つかあるので、紹介する。
(1)心拍数
オーバートレーニングに陥った状態では、安静時心拍数が通常より高くなる。起床直後には安静時心拍数を測定→記録するのを習慣にしよう。安静時心拍数が通常より高い状態が継続する場合、オーバートレーニングに陥った可能性が疑われる。
注意:心拍数に影響を及ぼす因子は、トレーニング以外にも無数にある。例えば、ストレス/体の水分状態/カフェイン/睡眠時間等である。なので、日間変動は余り気にする必要は無い。あくまでも中長期的な傾向に着目する。
(2)イライラ感
オーバートレーニングは内分泌物質(特にカテコールアミン)の生成量減少を誘発する。カテコールアミンの生成量が減少すると、交感神経系に影響が及ぶ。その結果、被抑圧感/イライラ感が増大する。そのような感情が増大していると認知したら、それはオーバートレーニングの兆候である可能性が考えられる。
(3)病気になり易い
オーバートレーニングによって免疫力が低下し、その結果風邪/インフルエンザを始めとする感染症に罹患し易くなる。普段より病気になり易いかな?と感じたら、それはオーバートレーニングの兆候であるかも知れない。
(4)睡眠パターンが安定しない
オーバートレーニングに陥ると概日リズムが乱れ、睡眠障害が発生する場合がある。具体的には、起床時刻が格段に早くなる/熟睡出来ないといった状態になる。
注意:概日リズムは、日照量の季節的変化の影響も受ける。季節の変わり目に睡眠障害が発生した場合、それは日の出/日の入り時刻に対する自然な反応かもしれない。
勿論、これらの兆候は単独ではオーバートレーニングの明確な判断基準とはならないが、複数の兆候を認知したならば、オーバートレーニングに陥った事を疑い、適宜休養するのが望ましい。
オーバートレーニングの自己解決方法
これまでオーバートレーニングの原因/兆候について述べてきたが、次にその解決方法を端的に紹介する。オーバートレーニングに陥った場合、休養/回復に専念する必要がある。
(1)どれ位休むべきなのか?
残念ながら、オーバートレーニング状態から脱出する為に必要な休養期間については、研究者/コーチの間でも見解が分かれる。基本的には、休養期間はオーバートレーニングに伴う症状の深刻度や、それに対する身体の反応能力に左右される。筆者としては、オーバートレーニングに陥った場合、ラントレーニング再開まで最低3週間は休養すべきと考える。一般的には、身体を完全に回復させるには最低6~8週間の休養が必要と考えられている。身体の状態を的確に判断することが重要である。そして、時には「休む我慢」に耐えるのも必要である。
(2)回復過程を加速させるには
健康的な食生活を維持することが大切である。つまり、栄養に富む食材を必要十分量摂取することである。その他にも、ストレッチする/マッサージをしてもらう/しっかり睡眠する等も役立つ。
一般的なオーバートレーニングの原因について学習し、その徴候を早期に認知することで、オーバートレーニングに陥ることが回避可能となるし、仮にオーバートレーニングに陥ったとしても、早期に回復することが可能となる。











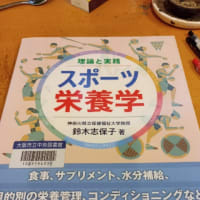





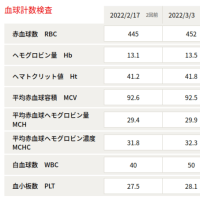
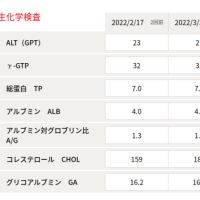
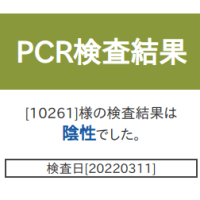





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます