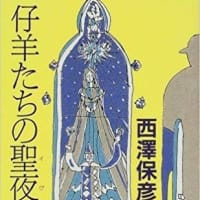先日伝法を訪れた折、淀川の堤防の上を散歩していて、ひどくノスタルジックな感覚に見舞われた。
どうやら私が幼稚園児ぐらいの頃の、遠い記憶が甦ってきたようなのだ。
大阪府下の某所、そこはとある川の堤防の近くに建つ、小さな一軒家だった。
桜が咲こうとする候、両親は幼い私を連れてその家に引越した。
かなり老朽化した二階家だったことを憶えている。
父の仕事の都合だと思うのだが、そこにはほんの二年ほど住んでいたにすぎない。
ちょっとした庭があり、日当たりがよいので、主に物干しとして使っていた。
植木とか鉢植え花壇の類は、まったくなかったように思う。
一階は畳敷きの二間で、それぞれ何畳だったかは、今となってはもう分からない。
それにトイレと風呂と台所があった。
二階は一間で、一階のどちらの部屋より、少し広かったように思う。
ここは板の間だったのを、父が越して直ぐに畳を入れてもらったのだと思うのだが、はっきりとは憶えていない。
というのも、この二階の部屋には、父の弟、私とっては叔父が住むことになり、あまり上がった記憶はないのだ。
その家の周辺は民家より、圧倒的に田んぼや畑が多かったように思う。
暫く続く畦道を歩いていると、やがて大きな舗装された道路にまで出る。
確かそこを渡ると、途端に家屋や色んな建物が建ち並ぶ、駅や商店街なんかもある町になっていたはずだ。
私が通っていた幼稚園は、畦道を堤防に沿うように歩いて行くとお寺があり、そこの隣だったと思う。
恐らくそのお寺が運営していたのであろう。
このお寺の境内の桜が、満開に咲いている頃に入園した。(古いアルバムに写真が残っている)
母は毎朝、父や叔父が出勤した後、この幼稚園にまで私を送ってから、その足でそこからもう暫く歩いた所にある、漬物工場のお手伝いをしに行っていた。
工場といっても農家の納屋みたいな所にあった、作業場といったような類だったように思う。
私は幼稚園が終わると、真直ぐにこの漬物工場にやってきた。
ここの人達は幼い私を大変可愛がってくれ、私のためにおやつ{%ケーキwebry%}まで、用意していてくれたものだった。
私がおやつを食べ終える頃には、母も漬物工場のお手伝いが終わった。
その後母は私を連れ町まで出て、お買い物をしてから帰宅するといったのが日常だった。
父も叔父も仕事が忙しいのか、帰宅するのはいつも私が眠ってしまってからだった。
当時の私はあまりに幼く、どうしてそこに越してきたのかとか、母がどんな経緯で漬物工場のお手伝いをするようになったのかは、まったく理解してはいなかった。
今ではある程度解っているのだが、ここで記すのはやめておくことにする。
そこに越す前はごちゃごちゃした街中の、団地のような場所に住んでいたような、どうにも曖昧な記憶が残っている。
私みたいな幼い子供が、近所にはいっぱい走り回っていたような気がする。
しかし越してきた家の周辺には、私と同じぐらいの年頃の子供はいなかった。
幼稚園の方とか漬物工場の付近には、幼児が結構いたように思うのだが…。
その家の近所には小学校に通う子供もいなく、もう中学生とか高校生とかだったはずだ。
それだけに幼かった私は、一際目立つ存在だったのであろう。
付近のお爺さんお婆さん、小父さん小母さん、お兄さんお姉さん等の注目を、一身に集めていたのであろう。
それだけの目で、温かく私は見守られていたので、母も安心していられたようだ。
「ひとりでは決して小川で遊んだり、遠い所や堤防の方に行ってはいけないのよ」との、母の厳命を私は守って、家の周辺で遊んでいたと思う。
畦道とかにはこれまで見たこともない、草花が生え虫達が息づいていたのだ。
幼い私にとって、毎日が「なんだこれへんなの!の連続であった。
その延長線上にあった、私達の家からは最寄の、お隣さんとなる農家には、よく遊び行っていたように記憶する。
私に残るその家の印象は、なんだか時代劇にでも登場しそうな、実に古風な農家。
ここにはお婆さんと小父さん小母さん、それに高校に通うお姉さんと、中学に通っているお兄さんがいた。
それにミケちゃん{%ネコdeka%}という三毛猫さんがいた。
大きな犬もいたらしいのだが、もうかなりの高齢だったようで、私達が引越すちょっと前に天寿を全うしたのだそうだ。
この界隈の殆どの農家では、犬や猫が飼われていたようだ。
特に猫は多かったと両親は話していた。
そういえば、ニャンコの集会をよく見掛けた。
隣家のお婆さんは、私達が住む家の大家さんだったと思う。
お爺さんは戦死されていて、若い時のままの写真だけが、仏間に飾られていたと記憶する。
私はその写真の主が、初めのうちは一番上のお兄さんだと思っていた。
お婆さんの旦那さんで、小父さんのお父さんということは、暫くして孫である高校生のお姉さんからちゃんと教わったのだ。
このお隣さんは一家総出で、私達の引越しを手伝ってくれたと思う。
お婆さんと小母さんのふたりして蕎麦を作ってくれていて、引越し作業がひと段落すると、まだ段ボール箱が積まれている一階の二間に皆集まり、車座になって食べたのを、私ははっきりと憶えている。
なんだかお祭りみたいで、随分楽しかった思い出なのだ。
引越して間もなくだったと思う、家の近くの畦道で遊んでいて三毛猫を見つけた。
母は台所で夕飯の支度かなにかを、していたのだ思う。
三毛猫の後をついて行ったら、いつの間にかお隣さんの縁側に着いていた。
その日初めて、ひとりでお隣さんの家へお邪魔したのだ。
お婆さんが温かく迎えてくれ、母が心配してはいけないと、私がきていることを直ぐに知らせていた。
その日からお隣さんへは、ひとりでちょくちょく遊びに行くようになった。
お婆さんやお姉さんとお兄さんは、私をよくかまってくれた。
小父さんと小母さんは、いつも忙しそうに立ち働いていた。
でも私を見かけると、ふたりとも優しい微笑みを向けてくれたものだ。
きっと、いったいどちらの子なのか分からないほど、お隣さんには頻繁に行っていたのだろう・・・。
私の猫好きは幼児の頃からなのだろうか、ミケちゃんとも直ぐに仲良しになった。
当時猫のことを、ニャンコタン♪と私はいっていた。
恥ずかしながら、今でもたまにそう呼ぶこともある・・・。
隣家ですごしていて、いつの間にか眠ってしまって、目覚めれば自分の家だったことも多くあったと思う。
母も私がお隣さんにお邪魔しているぶんには、安心していられたのだろう。
だから時として両親は、私を隣家に預けて出掛けたりもしていた。
冠婚葬祭の関係だったようだが、案外ふたりして羽を伸ばしていたかも・・・。
小父さんとか小母さんが、幼稚園にまで迎えにきてくれて、そのまま隣家で両親が帰るまで待っていたりもした。
後に聞いた話によると、戦死されたお爺さんは、母の大伯父とかにあたるそうなのだ。
つまりお隣さんとは遠戚関係にあり、母の父(私には祖父)の生家だったのだ。
どうりで私を可愛がってくれたわけだと、この話を聞いた折に納得した。
母方の祖父は他家に養子として迎えられ、この生家からは離れた。
もちろんその他家とは、母にとっては生家である。
頭がこんがらがりそうなので、余談はこれぐらいにしておこう。
そんな風に私はお隣さんでも、家族同然として扱われていたのである。
お姉さんやお兄さんは、土手へ土筆採りとか、夏には鎮守の森へ蝉捕りとか、小川でオタマジャクシやメダカ捕りをしに、連れて行ってくれた。
お婆さんはオジャミというお手玉を私に作ってくれ、やり方を教えてくれたりした。
幼なかったのでよくは憶えていないが、自然を相手にする農家は季節感が強く、折々のイベントがあったのだろう。
農業には素人であったろう両親や叔父も、出来ることは手伝っていたようだ。
当時の父と叔父は、体力には自信があったようなので、休日返上でやっていたように思う。
お盆には隣家にいっぱい人が集まり法要があって、幼稚園横のお寺の和尚さんがお経を唱えていた。
秋には一帯で収穫祭があり御神輿が舞ったり、お月見をしたり、そして年の瀬にはサンタさんもやってきたし、盛大にお餅つきもやって、年が明けお正月を迎えた。
そんな断片的な記憶が脳裏を駆け巡る。
その地へ引越した翌年、幼稚園では私は年長さんということになる。
夏から初秋にかけ、台風の上陸や接近が多い年だったそうで、その幼稚園もしばしば休園となった。
夏も終わろうとするある日、大きな台風がゆっくりと近づき、やがて日本列島を襲った。
激しい風雨を受け続けた堤防が、ついに夜半になって決壊し川が氾濫した。
家は風に軋み瓦も吹き飛ばされ、二階の叔父の部屋では、随分雨漏りがしていたようだ。
やがて水が床下に浸水してきて、どんどん水嵩が増していったそうだ。
幸い畳を濡らすまでは増水しなかったが、電線が切れたものか停電したりして、蝋燭の火に頼っていたようだ。
堤防沿いの家屋に避難勧告が出たらしいが、どうにも身動きが取れなかったようなのだ。
この状態ではノンビリ布団で寝るというわけにはいかず、大人達は一晩中起きていたらしい。
母は一晩中私を抱きしめていたように、ぼんやりとした記憶が残っている。
私もコクリコクリとしながらも、尋常ではない大人達の様子に、緊張していたように思う。
「オウチだいじょうぶ?」と母に尋ねたら、「だいじょうぶよ」と微笑んでいた顔を、なんとなく憶えている。
父が母に木場町にいた時に遭った、あの第二室戸を思い出すな」、とか話していたのも憶えている。
翌朝風雨が去り水が少し引いてから、父と叔父は外へ様子を見に行ったらしい。
周辺は惨憺たる有様で、田畑は水に浸かり、作物が壊滅状態だったようだ。
もちろんお隣さんも例外ではなかった。
暫く大人達は台風一過の処理に、大童だったようである。
そんな中、隣家のお婆さんが倒れたのだ。
お婆さんはあっけなく、天に召されてしまった。
隣家では葬儀が営まれ、両親や叔父もお手伝いしていた。
大人達が皆泣いていた・・・。
お婆さんは色んな人達から慕われ、敬われていたのであろう。
ご主人を戦争で奪われ後、気丈にも家を守り続け、ついに力尽きたのだ。
当時の私がどこまで人の死を理解していたかは分からないが、切なく悲しかった{%泣くwebry%}思いは記憶に残っている。
父も母も叔父も、悲しそうに咽び泣いていたのを、私は鮮明に憶えているのだ。
お婆さんとお別れする前夜、そのお通夜でのこと、私は不思議な体験をしている。
ここからは模糊たる記憶から、なんとか引きずり出して、大体こんな状況だったのではないかとの、概ねの推測による話になってしまう。
私は母の横に座りコクリコクリとなっていたので、結局お婆さんの遺体が安置された部屋から、ちょと離れた所に布団を敷き寝かされていたようだ。
もう夜中だったろう、私はふと目覚めたのだ。
多分オシッコに行きたくなっていたのだろう、起きて直ぐ辺りを見回して母を捜したがいなかったので、ひとりでトイレに行った。
廊下とかは電灯が灯って明るいし、大人達の声があちらこちらから聞こえていたのもあり、怖いという意識はなかった。
小母さんが私を見つけて、「どうしたの?」と声を掛けてきた。
私が「オシッコ」と返事したら、トイレまでついてきてくれた。
ここのトイレは少し前まで汲み取り式だったのを、私達親子が住んでいる家のと一緒に水洗に改修したので、おどろおどろしい田舎の便所とは違っていた。
といっても、当時の私は田舎のボットン便所の存在自体、知るよしもなかったろうが。
トイレの前まできて、小母さんは誰かに呼ばれたようで、「ひとりで大丈夫?」と訊いた。
勝手知ったるという家のことでもあり、私は「ウン」と頷いたので、小母さんは行ってしまった。
私は少し心細くなったが、なんとかオシッコを済ませトイレから急いで出た。
そして母を捜そうと思い、廊下を歩いて行ったのだが、その時何処からかチリンチリンという音が聞こえてきた。
何故か私はその音に惹かれるようにして、とある小部屋に入って行った。
これまでその部屋に入ったことはなかったろう。
私が寝かされていた部屋には、小さな電球が灯っていたが、そこは真っ暗だった。
だが不思議と恐怖感はなかった。
暫くすると薄明かりでも灯ったように、ぼんやりと白むかのように部屋の中が明るくなった。
目が慣れたのではなく、何かが光っているようなのだ。
灯りを得たので、漸く三毛猫のミケちゃんが、座布団に丸まっているのに気づいた。
さっきの音はミケちゃんの首の鈴?
いや違った、ミケちゃんがじっとしているのに、また聞こえてきたのだ。
そのうちミケちゃんがいる辺りが、ぼんやりと光っているのにも気づいた。
その光はどんどん大きくなって、やがてお婆さんになってしまった!
死んだはずのお婆さんが、座布団に正座していて、その膝にはミケちゃんが丸まっていた。
「お婆ちゃんは死んだんじゃないの?と私が訊ねると、お婆さんはそれには答えず襖を指差した。
見ればなんと襖に、みるみる映像が浮かび上がってきたのだ。
とある農家に、花嫁さんが迎え入れられる、そんな結婚式の場面から始まった。
その後花嫁さんは、旦那さんやその一家の人達とともに、農作業や家の仕事に勤しんでいた。
そして赤ん坊がめでたく誕生した。
男の子だった。
ところが幸せな日々ばかりではなかった、何度も近くの川が氾濫し、その度に農作物は多大な被害を受けることになった。
旦那さんのご両親が心労からか、相次ぎに亡くなってしまう。
そして悲劇はまだ続く、ある日無情にも、旦那さんに赤紙(召集令状)が届けられた。
お嫁さんが中心になり、千人針が縫われた。
千人針で縫われた布を卓袱台に置き、旦那さんは泣いているお嫁さんに何かを手渡した。
それから旦那さんは、お嫁さんや村の衆に見送られ、出征して行ったのだ。
だが願いも空しく旦那さんは生還を果たせず、お嫁さんには戦死通知のみが届けられ、やがて終戦となった。
まだ幼い子供を抱えながら、戦争未亡人となってしまったお嫁さんは、それでも戦死した旦那さんに代わり一家の大黒柱となって、気丈に働き続けた。
暫くして世の中が落ち着き、川にも漸くしっかりした堤防が設けられた。
しかし安心していたのも束の間、その護岸工事はずさんな手抜きだったのだ。
ある日の風雨により、脆くも決壊してしまい、田畑等を水浸しにしてしまった・・・。
多分映像はここまでだったように思う。
襖からお婆さんの方に目を戻すと、手に鈴をぶら下げていて、私の方へ差し出した。
ミケちゃんの首にあるのより、もっと大きな鈴だった。
私がその鈴を受け取ると、お婆さんは次第に元の光に戻り、やがて消えてしまった。
お婆さんはずっと微笑みを浮べていたが、ついに言葉を発することはなかった。
この後の記憶は途絶えてしまっている。
お婆さんがいたその部屋で、ミケちゃんと一緒に眠りこけている私が、母と小母さんによって発見された。
見当たらないので、心配してふたりで捜したようだ。
寝惚けて迷い込んだ、ことになっているのだとか・・・。
母がいっていたが、その部屋はお婆さんが、寝室として使っていたのだそうだ。
戦死した旦那さんと若い頃のお婆さんが、仲良く肩を並べて写っている写真の入った写真立てが、小さな箪笥の上に置かれていたのだそうだ。
その翌年、私が小学校へ上がるのに合わせるかのように、私達一家はその地より引越して行ったのだ。
叔父はその後間もなく、綺麗なお嫁さんをもらった。
幼児だった私にとって、襖に映し出されたあの映像の意味は、理解の範疇を超えていたろう。
時とともに理解していったのであろうか?
いや、私の夢の中の模糊とした抽象が時を経て具象化し、記憶となって残っているのやも知れない。
本当にあったことかどうかは、はなはだ心もとないのだが、私にとってこれが唯一の霊体験である。
お婆さんから手渡された鈴なのだが、小父さんも小母さんもお姉さんもお兄さん、見たことがない物だったようである。
もちろん両親や叔父も知らなくて、私がどこで拾ったのか、小首を傾げていたようだ。
両親が当時の話をする時は、漬物工場の漬物も美味しかったが、お婆さんの漬けた糠漬けの方がもっと美味しかったとか、決まってそんな方向に行ってしまう。
お婆さんの作ったおはぎや、土筆のお浸しも美味しかったとか、懐かしそうに話し合っているのだ。
今となっては鈴のことなど何処へやらである。
幼児だった私は、おはぎは別として、漬物やお浸しはあまり好きではなかったようだが、今ならその味が分かるだろう。
あの堤防決壊の一件は、やはり業者による手抜き工事が原因だったようだ。
工事に関与した人間が、何人も処罰されたのだそうだ。
ところで、鈴は今も尚私の手元に残っている。
もしかしたら、旦那さんが出征前にお嫁さんに手渡していたのは、この鈴だったのだろうか?
お婆さんは誠実であること、そして平和であることの意味を、私に伝えたかったのかも知れないな・・・。完