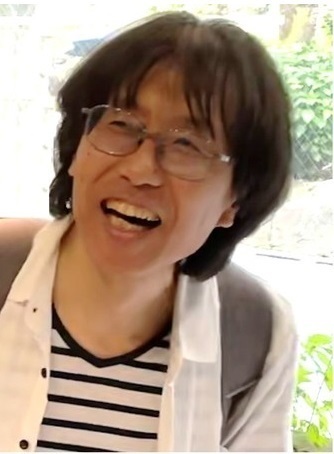血糖値低下はショウガが三冠王!
スペインZaragoza大学のMaria C. Garza氏らは、2023年9月までPubMed、Web of Science、Scopusの各データベースを検索し、
地中海食に一般的に含まれるハーブ/スパイス(ブラッククミン、クローブ、パセリ、サフラン、タイム、ショウガ、黒コショウ、ローズマリー、ターメリック、バジル、オレガノ、
シナモン)が2型糖尿病患者の血糖プロファイルにどのくらい影響を及ぼすかについて、
システマティックレビューおよびメタ解析を行なった結果(77論文をシステマティックレビューの対象とし、そのうち45(3050例)をメタ解析の対象としたもの)、
いくつかのハーブ/スパイス、なかでも特にショウガの摂取が空腹時血糖、HbA1cおよびインスリン値の低下に有意に関することを明らかにしました。
具体的には――
◇空腹時血糖値が有意に改善したのは、ブラッククミン、シナモン、ショウガ、ターメリック、サフラン(以下、カッコ内は95%信頼区間)。
・ブラッククミン摂取群:26.33mg/dL低下(-39.89~-12.77、p=0.0001)
・シナモン摂取群:18.67mg/dL低下(-27.24~-10.10、p<0.001)
・ショウガ摂取群:17.12mg/dL低下(-29.60~-4.64、p=0.0004)
・ターメリック摂取群:12.55mg/dL低下(-14.18~-10.86、p<0.001)
・サフラン摂取群:7.06mg/dL低下(-13.01~-1.10、p=0.020)
◇HbA1cが有意に改善したのは、ショウガとブラッククミンであった。
・ショウガ摂取群:0.56%低下(-0.90~-0.22、p=0.0013)
・ブラッククミン摂取群:0.41%低下(-0.81~-0.02、p=0.0409)
◇インスリン値が有意に改善したのは、ショウガとシナモンであった。
・ショウガ摂取群:1.69 IU/μL低下(-2.66~-0.72、p=0.0006)
・シナモン摂取群:0.76 IU/μL低下(-1.13~-0.39、p<0.0001)
※各ハーブ/スパイスの最も一般的な摂取量は、ブラッククミン:500mg、シナモン:1,000mg、ショウガ:2,000mg、ターメリック:2,000mg、サフラン:30~100mg。
著者らは、本研究の限界として「それぞれのハーブ/スパイスの用量が不均一であるため、有効用量を考慮することはできなかった」ことなどを挙げつつも、
「ショウガは、地中海食のハーブ/スパイスの中で、空腹時血糖、HbA1cおよびインスリン値の3つの検査結果すべてに有意な影響をもたらす独特のものであるようだ」と
まとめています。
<文 献>
Garza MC, et al., 2024 Effect of Aromatic Herbs and Spices Present in the Mediterranean Diet on the Glycemic Profile in Type 2 Diabetes Subjects: A Systematic Review and Meta-Analysis, in Nutrients, vol. 16, no.6, p.756. https://doi.org/10.3390/nu16060756