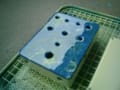いやいや、時間が掛かりました。
このZendrive Clone 一号機ですが、
記念すべき処女作でもあるし、音もいいので非常に思い入れがあります。
しかし、この時期はまあ作り初めということで右も左もわからず・・
なんとか音が出るようになったというありさまで、
今考えるとよく音が出たよなぁ・・・(^^;;
それもこれも「まっぱさん」のおかげです。_o_
しかも技術が無いのにいわゆるポイント . . . 本文を読む
先日の鴻巣実験場での実験結果からすると若干ゲインが足りない!
と思っていた ZDr 2号改 ですが、中身の確認を行ってみた。
すると案の定ダイオードの配線ミスを発見!
この配線ミスって以前もやってたんだけど・・・(^^;;
初期のやまさん2号と同じ状態かな。
ダイオードの向きの問題でした。
とほほほ・・・懲りないやつ・・・
この結果思うようにゲインが出なかったことが過去にもあるので、
修正した . . . 本文を読む
置き場所の関係で、さいたまの妻の実家に置きっぱになっている。
Mesa Boogie NOMAD55でも
Zendrive Clone 2号機改
苺ミルクこと5号機を試してみた。
大音量でのテストは出来ないが、やまさんのところで試した時に感じた良さがここでもそのまま生かせそうだ。
ただしギターがシングル・コイルのFender Cycloneなのでそれほど太いサウンドは出ないのだが、それでも充分良 . . . 本文を読む
本日自作エフェクターおよびK&R Groove Compを持って、
通称鴻巣第一研究所(Jaco Guitars:やまささん宅)にお邪魔してきました。
こんな感じで小型ボードにいくつかセットしていきました。
前回の訪問は確か3月9日でしたね。
その時はZendrive Clone1・2・3号比較実験ってな内容でその時は2号機3号機のクリーンブーストがかなり使えるということが分かったんでしたね . . . 本文を読む
さてさて、組込みが完了したZendrive Clone 2号機改ですが、
時間がとれたのでエフェクトボードに繋いでサウンドテストを行ってみました。
まずは適当につまみを合わせて、全てのポジションでのサウンドの変化を体感!
あれれ???
SW2の効きがおかしいのとダイオードの2番の音が出ない??
一度落としたときにおかしくなったか?(^^;;;;
仕方が無いので裏を空けて診断してみると、
あら . . . 本文を読む
ついに2号改造が完成した。
完成というか取り敢えず組みあがったというのが正しいところだろう。
途中はこんな感じでした。
これは丁度通常のZendrive Cloneを組み込んだところですね。
この後に蛸だの蟹だの・・(笑)を組み込んでいくわけです。
上段の4つのコントロールが通常のZendrive Cloneのコントロールつまみです。
下段の3つのSWが蛸と蟹です。(笑)
左からコンデンサそ . . . 本文を読む
懲りずにマーブル塗装です。
しかし、なかなか上手くならない・・・orz
これも気に食わなくて都合4回くらいやってみて・・・
これならクリア吹けば何とかいけるかな?という感じになったというか・・
というか時間切れというか塗料切れというか・・・(^^;;;
使う塗料の色なんかでも微妙に違うのだろうかねぇ??
正直上手くいくパターンがよくわからないんだよなぁ。。
前回の5号のマーブル塗装ではなかな . . . 本文を読む
蟹にロータリースイッチを装着してみた。
これでコンデンサも5パターンずつ切替可能だ。
そして蛸入道と組み合わせるのだ。
この回路を使ってZendrive Clone 2号をリニューアルしちまおうっていう作戦ですね。
色々試していた結果2号機がなかなか出音がいいので、これをベースに更に上を目指そうって言うことですね。
5号で実現できなかったダイオードチェンジャー+コンデンサ切替です。
ハッハッハ! . . . 本文を読む
昨晩は久々の「健康」リハ
1月の「正月早々めでたいなライブ」以来からだから、一同顔をあわせての音出しは約3ヶ月ぶりということになる。いやいや楽しかったね。
さて、昨年末くらいから「健康」のリハが、平日にリハーサルスタジオ(って普通の時間貸しのスタジオなんだけどね)で行われるようになった関係で楽器を持って出勤という状況になっている。以前はメンバーの車に機材を積んで運んでもらったりもしていたのだが、 . . . 本文を読む
ZDr Type-S(Zendrive Clone 5号機 主審モデル)の出来の良さに気を良くして、2号機をリニューアルしようと思い立った。
そう、実はダイオード切替機蛸入道が入らなかったから余ってるのよ。(爆)
つまり2号機を大き目のケースに入れ替えて蛸入道と蟹を一緒に入れちゃうって事ね。
今回はBoosterなしで単体でサウンドバリエーションを増やしてみる作戦だ。
Othello Boos . . . 本文を読む
・・・と思ったら
悪い予感は当たるものでギリギリ入らないよ・・・・
とほほほほ・・・・・(;_;)
音的にはばっちり、例の「蛸入道」もコンデンサ切替SWも搭載という、
とってもHyperで贅沢な仕様で出音もかなりいけてる感じで、正に多機能Over Driveって感じなんだけどねぇ。
でもね、裏蓋が締まらないのよ・・・・
SWのレイアウトもFoot SWとロータリーSWが近いので上手く踏めな . . . 本文を読む
またまたマーブルだ。
多少回数を重ねたことで経験値が上がったのかも。
ちょっと腕を上げたかな?
でも、まだまだ、ですけどね。。
マーブル自体はいいんだけど、色の組み合わせがあまりよろしくなかったりして。orz
実はその後ケースの仕上げの磨き&クリア塗装も終り組み込みを開始しているのですが、
ちょっとケースが小さいようでSWのレイアウトがかなり厳しいです。(^^;;
まあなんとかおさめてみよう . . . 本文を読む
コンデンサの切替実験の好結果にすっかり気を良くしたあっしはもちろん更に上を狙いに行きます。(爆)
そうです。今度はダイオードです!
そんな訳で
こんなものを用意しました。
そうです。ロータリーSWにダイオードが接続されているのです。
やはり見た目はほとんど「蛸」ですな。(笑)
さて、先日装着したコンデンサ切替実験装置つきのZendrive Cloneに「蛸入道」を接続する。
どれどれ? . . . 本文を読む
構想3日製作どのくらいだ?(笑)
作り始めたら早いんですけどね。
SWの動作確認(どこにどう繋げばいいのかが最初わからなくてね。テスター使っていろいろテストしてたら時間食っちゃったよ。)半田付けは早いんだけどね。
仕組みは、2回路6接点のロータリーSWにダイオードを2系統
(1、1+1)のソケットがついてるだけのシンプルなもの。
見た目はどうみても蛸入道だよね。(笑)
ソケットが並んでいる . . . 本文を読む
昨年の11月10日前後に1号機の作成を開始して、紆余曲折しながらも「まっぱさん」のお力を借りつつなんとか12月4日に完成!(まっぱさん本当にありがとうございました。mOm)
その後は2号,3号(やまさんモデル)4号(博士モデル)と都合4台のZendrive Cloneを作成してきたわけだが、そこそこのパーツ(オペアンプ、ダイオード、配線材、抵抗)によるサウンドの傾向などは多少見えた部分もあるのだ . . . 本文を読む