9月県議会 代表質問1日目
http://cr.e-catv.ne.jp/gikai/streaming/index.html
から、本会議についてはライブや、数日遅れですが録画を視聴することもできます。
本宮勇議員(自民党)(テープ起こしをしました。質問部分は歯抜け状のメモになっています。)
−−−
次に核燃料税についてお伺いをいたします。
平成23年3月11日東日本大震災の影響により、東京電力福島第一原発事故が発生し、国民の安全および原子力行政への信頼は大きくゆらぎ、回復にはほど遠いのは皆さんご招致のとおり。
本県でも伊方原発は、平成23年4月からの間に、1から3号機が定期検査のため相次いで停止し、全ての原子炉は稼働しない状況が続いております。
こうした中になって、国の原子力災害対策指針が改定されたことを受け、本県では今年2月と7月に地域防災計画、原子力災害対策編を修正し、
同計画においては、従来の原発から10kmまでを半径30kmまで大幅拡大し、広域避難の対策が必要とされたところであります。
県民の安全安心を確保するためにも、さらには本県が四国で唯一の原発の立地県として四国の住民の方々のためにも、十分な安全防災対策を着実に実行していくことがきわめて重要であると思うのであります。
これまで本県では、法定外普通税として核燃料税を創設し、原子力防災対策等に使用してきたところですが、防災地域の重点地域の拡大等によって、これまで以上の対策が求められているにも関わらず、平成23年以降、核燃料税の収入実績が無い状況が続いております。
原発が立地しているのであれば、原子炉が稼働していようと居なかろうと、安全防災対策は必要であります。このようなことから、増加する防災対策等の財政需要に対応するには、安定した税収が必要不可欠であり、そのためには26年1月に失効する核燃料税条例を更新し、他の立地県の取り組みを参考に、本県にも新しい核燃料税を導入すべきではないかと思うのであります。
福島第一原発事故以降、更新した他県においても、防災対策等の必要が増加し、新しい課税方式として出力割が導入されています。
核燃料税の納税者であります四国電力においては、燃料費の増加等によって2年連続の赤字決算となり、経営が苦しい状況にあることは察しますが、本県においても、税率の引き上げおよび出力割の導入はやむを得ないと思うのであります。
また、税率の引き上げ等が電気料金に影響を与えるとしても、それはわずかな額でもあり、一方原発の防災対策は、原発が停止していても必要であるため、核燃料税を活用して、防災対策を拡充することは原発に対する不安感の軽減に寄与することと考えられることから、本県ならびに四国他県の住民の方のご理解ご協力を得られると思うのであります。
そこでおうかがいいたします、今回の提案されている核燃料税更新に当たり、税率を引き上げる理由と、新しく導入される出力割りの考え方、また、伊方原発の再起動はまだまだ白紙の状況でありますが、核燃料税の更新は伊方原発の稼働と関連しているのかどうか、お伺いいたします。
上甲総務部長)答弁
本県の核燃料税は昭和54年1月に創設されまして、伊方原発の放射線監視や避難路の整備などの安全防災対策を始め、地域産業の振興や住民生活の安定等の財源として、地域住民の安全安心のために重要な役割を果たしてきたところでございます。
しかしながら福島第一原発の事故を受けて、原発に関わる安全防災対策等が求められる区域も拡大していることや、その区域において、一層の対策強化が必要なことから、今回の核燃料税の更新に当たりましては、安全防災対策等に必要な財源を確保するため、税率を現行の13%から17%相当に引き上げるものでございます。
さらに従来からの課税方式であります価額割りは、核燃料の価額を課税標準として課税するものであり、原子炉の稼働状況等の影響を受けましたが、今回導入する出力割は、原子炉の出力に応じて課税する方式であり、安定した税収に寄与するものと考えております。
また今回の更新は、現行の核燃料税条例の有効期間の満了により、伊方原発の再起動とは全く関係なく実施するものでございまして、これは福井県など先行している道県と同様でございます。以上でございます。
原子力防災対策について
関連しまして、原子力防災対策についてもお伺い。
伊方原発をどうあるべきか、我々県議会としても、安全対策、原子力防災や、エネルギーの安定供給を含め、本会議などのさまざまな場で議論を行ってまいりました。
国の原子力規制委員会では、新規制基準を7月8日に施行をし、現在四国電力伊方3号機を一として6原発12基の原子炉設置変更許可申請書が提出され、原子力規制委員会による新規制基準に基づく安全審査が開始をされております。
審査中の原発の中でも、伊方3号機は唯一、免震棟が整備をされており、また敷地内に活断層がないなど大きな問題がないなどのことから、他の原発に比べて先行しているとの報道がなされているところであります。
県に対しても7月8日に、安全協定に基づく、事前協議書が提出されており、県議会でも7月30日にエネルギー防災対策特別委員会を開催、原子力規制委員会や四国電力から参考人を招致し、新規制基準の概要や今後の審査の進め方、四国電力の申請の内容などについて説明を受けた所であります。
原子力規制委員会には、安全審査において、福島第一原発事故の教訓を反映した原発の安全対策の妥当性についてしっかり検証をお願いするとともに、われわれとしても確認をしていく必要があると考えております。
一方、この事故では原子力防災対策についても、多くの教訓が抽出されました。まず、原発から10キロ以内に設定されていました防災対策重点地域、EPZを超えて、放射性物質が拡散したことであります。
そのため、特にEPZ圏外での防災資機材や、モニタリング資機材が不足したこと。また広域的な避難への備えが十分でなかったこと、さらには原発から近距離にあったOFCが機能しなかったことが大きな課題としてあげられています。
また、原子力災害に限ったことではありませんが、災害時要援護者への支援強化の必要性や、複合災害への対応も改めて認識されたところ。
県においては23年の事故後、国の対応を待つことなく危機感を持って、福島第一原発事故を踏まえた防災対策の課題抽出に取り組まれ、地域防災計画の修正や、広域避難計画の策定など順次対応を進めてきており、その対応を評価するものではありますが、防災対策にはここまででよいという基準はなく、一人でも多く、よりはやく、より円滑に対策を講じることをめざして、常に向上を図っていく、べきものと考えるのであります。
防災計画あるいは、具体的な避難計画を策定しなければ伊方原発を再稼働すべきではない、との論も一部にはありますが、さきほど申し上げたとおり、現に伊方原発が立地している以上、再稼働する、しないにかかわらず、福島事故の教訓を踏まえ、さらなる原子力防災対策の充実を図っていくことが重要であると考えるのであります。
そこでお伺いいたします、県は今後、防災対策の充実強化にどのように取り組んで行くのかお伺いいたします。
中村県知事)
県では福島第一原発事故を踏まえた、昨年12月の、国の原子力災害対策指針の策定を受けまして、本年2月に防災対策の基本となる、地域防災計画を修正し、原子力災害対策重点地域を伊方原発から30km圏に拡大したところであり、また、その後の同指針の改定を受け、7月にも地域防災計画の修正を行い、緊急事態区分の基準や、防護対策基準を導入するなど、緊急時における防護対策の拡充強化を図ってきたところでございます。
また本年6月には、この地域防災計画に基づいて、愛媛県広域避難計画を策定し、重点区域内の最大約13万人が避難する場合の、受入市町や避難経路を複数選定した広域避難の基本フレームを示すと共に、西予市への移転整備を進めているオフサイトセンターについては、平成26年度中の完成を目指して、今議会に建設予算を計上させて頂いているところであります。
現在、重点区域内の7市町については、県広域避難計画を元に、具体的な避難ルートや要援護者への対応などを盛り込んだ、避難行動計画の策定を進めておりまして、この秋に実施する原子力防災訓練での検証等も見据え、できるかぎり早期に策定されるよう、県としても関係市町間や隣県との調整を図るなど積極的に計画策定の支援に努めているところでございます。
原子力防災対策は原発の安全対策と並行して充実強化を図っていくべきものであると考えており、県民の安全安心の確保のため今後国や関係市町等と連携を図りながら実効性のある訓練を積み重ね習熟を図るなど最大限の対応を行っていきたいと思います。
−−−−













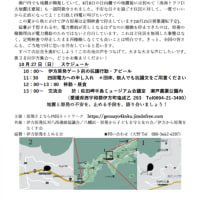

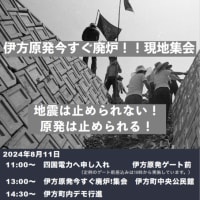
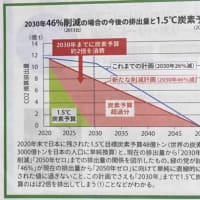
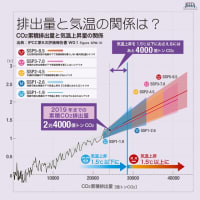
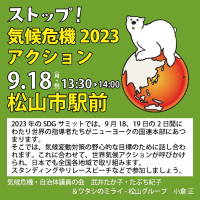
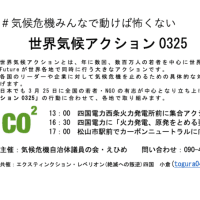
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます