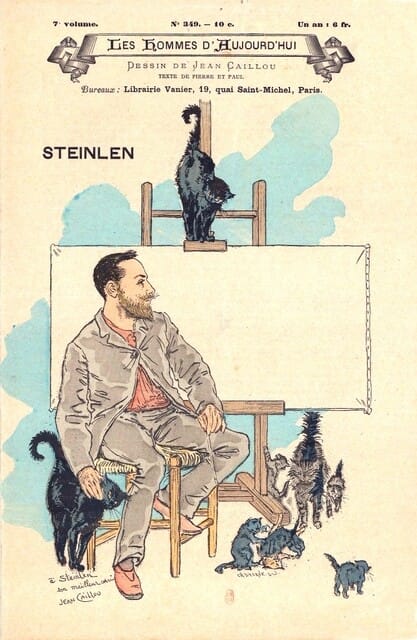《エルザの冒険旅行》 (『ジロー先生の獣医日誌(仮)』より)
**********
(4/4)
私は何段もひとまたぎにして、すっ飛んでいった。そこに、玄関マットの上に、廊下の暗がりの中に、丸くなって、自宅のドアの前で心安らかな眠りに沈んでいるのは! エルザ! エルザは、帰っていたのだ!
エルザは快挙をなしとげたのだ。私はこの目を疑った。明白な事実を前にして、肩から超重量の荷物が落ちるのと同時に、不信感が倍にもりあがった。エルザはやってのけた。とても信じられない、超人的なことだ。それはまるで、私が単独で、サンダルでもつっかけて、濃霧のヒマラヤにでも登ったようなものなのだ……。
再会と抱擁と涙のあと、ジャック夫人は感激にあえぎながらも私を気遣って、スコッチでも飲んで落ち着いていってくださいと、中へ招き入れてくれた。
最悪のことを考えていたときに、あまりに親切にされてどぎまぎしながら、私は彼女の部屋へ案内された。エルザはまっすぐに自分の籠の中に入って寝てしまった。
安心したジャック夫人は、手術はできたのですかときいた。私は、それはうまくいきました、エルザは半分眠ったままでここまでたどり着いたのですと答えた。
ジャック夫人はすると、無言で私を見つめ、しばらく考えてから、重々しい口ぶりでこう続けた。
「先生、これは何かのしるしですよ。きっとそうです。何かの預言です。でなければ不可能です。肝に銘じておかなくてはなりません。案内されずにどうしてこんなことができましょう。エルザは私たちに何かを伝えているのです。誰かが、エルザを通して私たちに何かを訴えているのです。これはメッセージです」
この珍しい論説に唖然として、グラスから目を上げたとき、私は自分がカウンセラーの相談室にいることに気がついた。テーブルの上にはタロットカードが積まれ、水晶玉が背景を鮮やかな曲線に凝縮している。おだやかな雰囲気は均衡に満ち満ちていた。すべてが、エルザのイニシエーションの旅と同じく、ふいに超現実的で不可思議になった。
ジャック夫人は、占い師だったのだ。彼女の疑問も、深い当惑も、納得がいく。
エルザの脱走は、私の課題となったあとで、最も予期しない形で、ジャック夫人の課題となった。私には何の役割もなかったのだ。違う世界からやって来た者が、もってこいの機会を選んで、エルザを医院の外に不思議な力をもっていざなったのだ。そして意味深い旅をさせた。その意味はまだ解明されてはいなかった。

残念ながら、この世の人間に霊界からどんなメッセージが送られてきたのかを、私はついに知ることはなかった。タロットカードも水晶玉も、教えてはくれなかった。エルザの訴え方が強すぎたのにちがいない。しかし、生ける者たちに関しては、このとてつもない冒険旅行は、長い年月を超えて続く、ひとつの厚い友情のきっかけとなった。親愛なるすてきなジャック夫人!
エルザの傷は癒着して、ジャック夫人は自分の時空旅行を再開した。エルザが本当に消えてしまう日まで。こうして、すべての扉は永遠に閉ざされた。英雄も死ぬ。そして彼らの偉業が、伝説となって語り継がれるのだ。
みなさんもパリの街を歩くことがあるかもしれない。小さな物語、大きな事件の証人であるこの庶民的な界隈、世界中の人々がパリジャンになるために落ち合う型破りな界隈、ひとつ通りを渡るだけで、カラチからイスタンブール、北京からサマルカンドへと、一万キロの旅ができるこの界隈を、もしもぶらつくことがあれば、よく見ていただきたい。パリを見るべき目、もちろん心の目で。
歩道のアスファルトを見てください。四つの小さな足跡が見えるでしょう。そしてまた四つの足跡が、そしてまた、ずっと、ずっと……。それは、エルザの足跡です。それをたどれば愛に出会えるのだと、伝説は語っています……。
(終)
著者/クリスチアン・ジロー
翻訳/大串 久美子
装画/ジル・ベロディエ
(K)