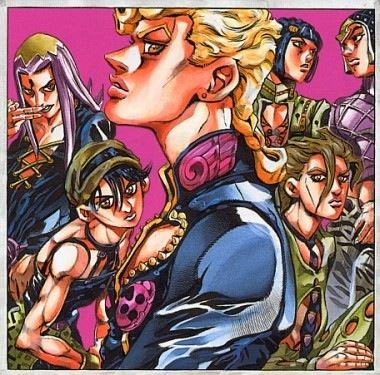小林よしのりさんの「ゴー宣」。立ち読みしたことはあったけど、きちんと読み通したのは初めて。
今回の『戦争論』( 1 )は初刷が1998年ということで、もうかなり前の本なのだけど、その主張内容は古びている印象はない。というより、最近の中国、韓国との敵対感情とかを考えると、むしろ刊行当時より今のほうがより説得力を持っているのでは、という気もする。
簡単に言ってしまうと、大東亜戦争(太平洋戦争)を肯定する立場の本書。しかし、では右翼的かというといわゆる純粋な右翼ではなく、愛国心や武力行使を極端に否定する(本書で言うところのカタカナ書きでの)「サヨク」を真っ向否定するというのが基本姿勢。要するに、戦後民主主義のゆるーい左翼的な雰囲気が嫌いなんですね。
ただし、膨大な資料に基づく豊富な知識と、「(自分が)悪人と言われても祖父たちを守る」という強い意思表示には確かな説得力があったと思う。当時の戦場の場面なんかはマンガならではの迫力とおもしろさで描かれていて、そのひとつひとつにも感動を覚えるものがある。
祖父たちが命をかけて戦った戦争には「正義」や「物語」があったわけで、それは軽々に否定してよいものではない。このメッセージは大きく響いた。
ちなみに、今日のニュースでは集団的自衛権に対する公明党合意の動き、さらには新宿駅南口で集団的自衛権に抗議する男性が焼身自殺を図るという事件が報じられた。この是非についてはともかく、アメリカを守るために命を落とすかもしれない自衛隊員に対して国(というか我々)がどのような物語を用意してるのか? そこに関する議論はほとんど聞こえてこない気がする。