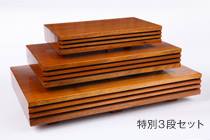この一文は2006年の七夕の日に書いたものである。当然、書かれている話題は古びている。まだ松井秀喜は現役の大リーガーであった。私は彼が打てないことに苛つき、ずいぶん酷いことを言い、彼のファンたちから顰蹙を買って叱られたものである。しかしそれらはテーマの周辺のことであって、本質は今も重大である。
さて最近NHKは、さっぱりNYヤンキースの二流スラッガーでミスター・セカンドゴロとして人気も高い松井秀喜の近況を報道してくれない。ゴジラの手首がどうなったかホントに心配だ。淋しいではないか。
なにせ彼が怪我をしたときは、2日間にわたってトップニュースで報道するほどの大ニュースだったはずではないか。NHKにとって重大なのは、北朝鮮のテポドン2より松井の手首ではなかったのかネ。
あの時私は、NHKにはジャーナリストはいないのかと嘆じたが、よくよく考えれば端からいないことは明らかだった。NHKにジャーナリズム精神を期待することが誤りであったのだ。NHKは「不偏不党」「起こった事実のみを公正に」淡々と伝えていくのみ。
つまり御上から記者クラブに配られる報道資料を、記者がリライトし、アナウンサーが読み上げるだけなのだ。だから「経済成長には自由貿易が欠かせないことから…」と、何ら正当性や納得のいく説明もなく、全く疑問も抱かず、ただ読み上げるのみなのである。
しかしジャーナリストとは、沸々と滾る反逆精神が必要で、常に権力を監視し、疑い、批判する存在でなければならない。
17世紀初めトーマス・ホッブズは国家を巨大な怪物「リヴァイアサン」に譬えた。この大著は人類最初の近代的国家論であり、自然権としての生存権、平等な個々人の社会契約を語った。ホッブズは個人・人権と国家・国権の「緊張関係」を初めて語った哲学者だった。彼によって近代的国家と国民(市民)の関係、権利等が哲学の視野に捉えられたのだ。彼の後にジョン・ロックが続いた。
シュテファン・ツヴァイクは「ジョセフ・フーシェ」の中で、フーシェについて「夜こそ、彼の本質」と書いた。フーシェはその濃い影の巨大さ故の象徴に過ぎない。権力・政治・政治家の本質は、夜=闇なのである。
民主主義は本質的に危うい制度であり、民衆はポピュリストやアジテーター政治家によって、いとも簡単に誘導される。権力は常に情報操作に腐心し、民衆世論の誘導を考えている。また権力は「民は愚かに保て」「知らしむべからず、由らしむべし」と考えている。権力は時とともに腐るのではなく、最初から饐えているものなのであり、その本質は卑劣なのである。そして国家とは狂気を孕んだリヴァイアサンなのである。
近現代の個人とその人権、国家とその権力の相関は、常に本質的な緊張関係が存在し、また緊張関係が必要なのだ。国家とその権力は、常に監視の眼と批判・批評に曝されなければならず、そのために世界の現代的憲法権利として「The right to know 知る権利」がある。これこそ民主主義国家の言論報道の自由や、情報公開制度を正当化するための個人(市民・国民)の憲法権利なのである。
「知る権利」は「accountability 説明責任・説明義務」と対をなす概念である。ちなみに見出し語数38万語と語源を含めた詳細解説を誇る英和辞典「ランダムハウス第2版」によれば「accountability は responsibility と異なり、果たせば報酬を伴う」とある。つまり、本来「accountability」は権力を持つ者、その権力を行使した行為で報酬を得る者、つまり政治家や官僚、経営者らに課せられる説明義務、釈明義務のことなのである。
個人の権利、市民・国民の権利として、国の政治・行政に関する公的な情報、また権力を行使する者たちとその行使した事柄に関して、人々は知る権利があり、政治家・官僚・財界人等はそれらに応える説明義務がある。人々は彼らに「説明を求めること interpellation 、demand an explanation」ができる。この「知る権利」は権力を行使する者たちに対しての権利であって、決して他人のプライバシーを知る権利ではない。これを曲解し、あるいは知らず、全く品位と自制を欠いている今日この頃のマスコミである。
ジャーナリストの監視の目と懐疑と批判精神は、本来は権力者に向けられるものなのだ。それが本質的には危うい制度である民主主義や、言論の自由や表現の自由を守ることにつながる。
何度でも繰り返すが、権力は常に監視と懐疑と批判と批評に曝されなければならない。その監視と懐疑と批判がジャーナリストの仕事と精神である。民主主義下のジャーナリストの要諦は、権力への徹底監視と懐疑と批判精神にある。
その精神は、古くは桐生悠々の「関東防空大演習を嗤う」の心意気であり、後の「他山の石」の精神である。また山田風太郎が喝破した「正義の政府はあり得るか」と言う権力への徹底懐疑精神や、フランスの哲学者でジャーナリストのレジス・ドブレイの「疑え、見抜け、疑え、見抜け」の精神なのである。
腰の引けた「不偏不党」にジャーナリズム精神は存在しない。むしろ全ての権力に対し「旗幟鮮明」に徹底懐疑、徹底批判すべきである。疑え、見抜け、疑え、見抜け!
さて最近NHKは、さっぱりNYヤンキースの二流スラッガーでミスター・セカンドゴロとして人気も高い松井秀喜の近況を報道してくれない。ゴジラの手首がどうなったかホントに心配だ。淋しいではないか。
なにせ彼が怪我をしたときは、2日間にわたってトップニュースで報道するほどの大ニュースだったはずではないか。NHKにとって重大なのは、北朝鮮のテポドン2より松井の手首ではなかったのかネ。
あの時私は、NHKにはジャーナリストはいないのかと嘆じたが、よくよく考えれば端からいないことは明らかだった。NHKにジャーナリズム精神を期待することが誤りであったのだ。NHKは「不偏不党」「起こった事実のみを公正に」淡々と伝えていくのみ。
つまり御上から記者クラブに配られる報道資料を、記者がリライトし、アナウンサーが読み上げるだけなのだ。だから「経済成長には自由貿易が欠かせないことから…」と、何ら正当性や納得のいく説明もなく、全く疑問も抱かず、ただ読み上げるのみなのである。
しかしジャーナリストとは、沸々と滾る反逆精神が必要で、常に権力を監視し、疑い、批判する存在でなければならない。
17世紀初めトーマス・ホッブズは国家を巨大な怪物「リヴァイアサン」に譬えた。この大著は人類最初の近代的国家論であり、自然権としての生存権、平等な個々人の社会契約を語った。ホッブズは個人・人権と国家・国権の「緊張関係」を初めて語った哲学者だった。彼によって近代的国家と国民(市民)の関係、権利等が哲学の視野に捉えられたのだ。彼の後にジョン・ロックが続いた。
シュテファン・ツヴァイクは「ジョセフ・フーシェ」の中で、フーシェについて「夜こそ、彼の本質」と書いた。フーシェはその濃い影の巨大さ故の象徴に過ぎない。権力・政治・政治家の本質は、夜=闇なのである。
民主主義は本質的に危うい制度であり、民衆はポピュリストやアジテーター政治家によって、いとも簡単に誘導される。権力は常に情報操作に腐心し、民衆世論の誘導を考えている。また権力は「民は愚かに保て」「知らしむべからず、由らしむべし」と考えている。権力は時とともに腐るのではなく、最初から饐えているものなのであり、その本質は卑劣なのである。そして国家とは狂気を孕んだリヴァイアサンなのである。
近現代の個人とその人権、国家とその権力の相関は、常に本質的な緊張関係が存在し、また緊張関係が必要なのだ。国家とその権力は、常に監視の眼と批判・批評に曝されなければならず、そのために世界の現代的憲法権利として「The right to know 知る権利」がある。これこそ民主主義国家の言論報道の自由や、情報公開制度を正当化するための個人(市民・国民)の憲法権利なのである。
「知る権利」は「accountability 説明責任・説明義務」と対をなす概念である。ちなみに見出し語数38万語と語源を含めた詳細解説を誇る英和辞典「ランダムハウス第2版」によれば「accountability は responsibility と異なり、果たせば報酬を伴う」とある。つまり、本来「accountability」は権力を持つ者、その権力を行使した行為で報酬を得る者、つまり政治家や官僚、経営者らに課せられる説明義務、釈明義務のことなのである。
個人の権利、市民・国民の権利として、国の政治・行政に関する公的な情報、また権力を行使する者たちとその行使した事柄に関して、人々は知る権利があり、政治家・官僚・財界人等はそれらに応える説明義務がある。人々は彼らに「説明を求めること interpellation 、demand an explanation」ができる。この「知る権利」は権力を行使する者たちに対しての権利であって、決して他人のプライバシーを知る権利ではない。これを曲解し、あるいは知らず、全く品位と自制を欠いている今日この頃のマスコミである。
ジャーナリストの監視の目と懐疑と批判精神は、本来は権力者に向けられるものなのだ。それが本質的には危うい制度である民主主義や、言論の自由や表現の自由を守ることにつながる。
何度でも繰り返すが、権力は常に監視と懐疑と批判と批評に曝されなければならない。その監視と懐疑と批判がジャーナリストの仕事と精神である。民主主義下のジャーナリストの要諦は、権力への徹底監視と懐疑と批判精神にある。
その精神は、古くは桐生悠々の「関東防空大演習を嗤う」の心意気であり、後の「他山の石」の精神である。また山田風太郎が喝破した「正義の政府はあり得るか」と言う権力への徹底懐疑精神や、フランスの哲学者でジャーナリストのレジス・ドブレイの「疑え、見抜け、疑え、見抜け」の精神なのである。
腰の引けた「不偏不党」にジャーナリズム精神は存在しない。むしろ全ての権力に対し「旗幟鮮明」に徹底懐疑、徹底批判すべきである。疑え、見抜け、疑え、見抜け!