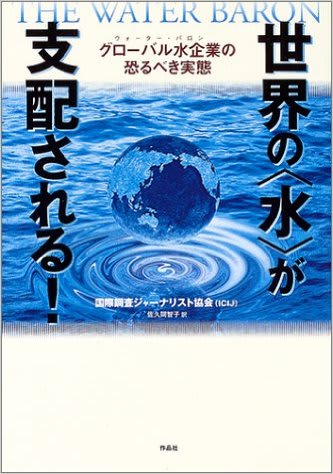私は温順、穏やかな性格にして、政治や社会に無関心なため、あまりそれらに目くじらを立てて激しく非難することもほとんどない。
話が変わるが、私は辞典辞書が大好きで、よく引いていたが、最近は目が疲れるので、字の細かい辞書をほとんど見ることもなくなってしまった。しかしたまに自ら辞書を編むという、途方もない野望に唆されることもある。その辞書を「口辞苑」と名付け、以前から少しづつ、すでに何度か公開してきたが、その度に後悔の念に囚われる。
公開、後悔、航海……「辞書は言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」…至言である。小説や映画に「舟を編む」という良い作品があった。私は自前の辞書を編みながら、退屈さからいつしか「舟を漕ぐ」状態となり、そのまま横倒しになって眠りにつく。
【青天井(あおてんじょう)】青空の下で開催されるオリンピックのように、開催費用、建設費用に上限がないこと。
【唖然(あぜん)】安全と同義。
【アベ過ぎる】JKの間で使われる流行語で①馬鹿すぎるの意。②度し難い嘘つきのこと。
【アベノミクス】①経済が好転するという幻想のこと。②転じて「おまじない」③手段を選ばず株価をあげる経済政策のこと。
【甘利(あまり)】斡旋利得など甘い利を吸うこと。医学的に覚醒剤同様の常習性があり、吸い過ぎると睡眠障害に陥るとされる。
【安全(あんぜん)】事故が起きる前の状態のこと。「唖然(あぜん)」とも言う。事故後については→「想定外」の項。
【育休(いくきゅう)】国会議員が使う売名パフォーマンスのこと。用例「育休不倫」
【噓(うそ)】総理が連発したヒット曲。党員がカラオケでよく歌う。
【衛星(えいせい)】ミサイルのこと。恫喝衛星ともいう。「衛星」の字に「ミサイル」とルビをふって使用することが多い。
【大飯原発(おおいげんぱつ)】大災害や重大事故が起きないことを想定して稼働した原子力発電所のこと。N国の第一標的。
【オトタケもの】①江戸川乱歩「芋虫」など、世にも不思議な興味をそそる愛憎劇。②手も足も出ない苦境を指す。
【黒田(くろだ)バズーカ】①禁じ手をもってしても効果が全くないこと。②空砲と同義。転じて③大失敗のこと。
【権力濫用(けんりょくらんよう)】①政治資金 規正法というザル法・虚偽記載といった些末な罪で起訴すること。②天の声を頻繁に響かせること。
【高校生未来会議(こうこうせいみらいかいぎ)】安倍官邸の指示で安倍の親類が作った「アベッチユーゲント」のこと。
【ケーソン】瓦礫処理の画期的な一方法。
【県外移設(けんがいいせつ)】福島原発による放射能で住民の帰還困難地域に、米軍普天間基地を移転させるという画期的計画のこと。
【鼓腹撃壌(こふくげきじょう)】日本のテレビ界の現状を表す四文字熟語で、白痴的ノーテンキに天下太平を謳歌するさま。
【ジェー(J)アラート】①いざという時に鳴らない広域警報システムのこと。②ミサイル等が着弾してから相当の時間を経ても、なお沈黙したままの 広域警報システム。
【サノケン】物真似名人。特にビリケンの顔真似が上手い。
【笑止化(しょうしか)】少子化対策のこと。育児・子育て支援の減額や廃止、待機児童対策に手をこまねき、一億総活躍社会などと言うこと。
【ジョンウン】①「ねエねエ、あれ撃ったことあるの」って子供のようにはしゃぐこと。②おじいちゃんの物真似をすること。用例 :「話し方から敬礼までも見事にジョンウンせしが…」(金怪集)
【仁義(じんぎ)なき分裂(ぶんれつ)】①おおさか維新と維新の党の下らない分裂のこと。転じて②山口組と神戸山口組の分裂のこと
【スピーディ(SPEEDI)】①宝の持ち腐れの意。②いざという時のために準備していても、その時が来ても全く「信用しない、活用しない、知らせない」の意。
【尖閣諸島(せんかくしょとう)】実効支配のため右翼的愛国者やヤクザ、半グレ、ヤンキーと呼ばれる暴走族たちの移住予定地。→尖閣セツルメント(定住)計画。
【想定外(そうていがい)】事故後に使用する便利な言葉。
【待機児童対策(たいきじどうたいさく)】①参院選対策のこと②ブログやツィッターなどSNSの監視対策③保育士に平均4千円賃上げする温情政策。④保育士にも叙勲するというありがたい政策のこと。
【大補凶(だいほきょう)】野球界用語で、他チームやメジャーリーグ等からスラッガー、エース級を豊富な資金力にものを言わせて獲得するも、その意図ことごとく失敗し低迷すること。
【高木効果(たかぎこうか)】巨人軍の高木投手の野球賭博を受け、老害をトップから排除した功績を指す。高木投手唯一の功とされる。
【高木出世(たかぎしゅっせ)】①下着泥棒でも出世できること。②親の威で出世する世襲議員。③原発利権享受者。
【掌返(てのひらがえ)し】政治家が選挙前にとった態度や公約と、当選後の態度と政策の大きな差をいう。ほとんどの場合、ペコペコからゴーマンに変じ、公約は180度変更される。実例「TPP断固反対。ブレない」
【凍土壁(とうどへき)】地下水の建屋への流入と汚染水の海への流出が、全く止まらぬことに気付いた関係者が、土色の顔になって壁のように凍りくこと。
【トランプ旋風(せんぷう)】アメリカの伝説のコメディアン「レニー・ブルース」風のタブーを恐れぬ大放言、大暴言の嵐を意味する。
【林立ち往生症候群(はやしたちおうじょうしょうこうぐん)】①先天性アルツハイマー症。②転じて、質問に応えられないさま。③不勉強の意。
【保育園(ほいくえん)】保健所のこと。
【朝鮮中央咆哮(ちょうせんちゅうおうほうこう)】①某国のアナウンサーが過剰な激情演技で原稿を読み上げること。②あまりにも大袈裟なので思わず笑っちゃうこと。
【日米同盟(にちべいどうめい)】①日本を思考停止にさせる呪いの言葉。②安全保障の意。用例 :「日米同盟のためにもTPPという笑止な論」
【ハシズム】橋下徹的な子供じみた暴言、放言、虚言ポピュリズムと全体主義的な傲慢、傲岸主義を言う。主張の内容はほぼアメリカの新自由主義的市場原理主義の口移し。
【酷(ひど)い】帰還困難地域に補助金で野菜工場を建設し、その野菜をスーパーなどで販売する復興計画のこと。
【ひな壇(だん)】①バラエティ番組で芸人たちが座る段々状の席。②無意味に笑ったり、雰囲気を盛り上げるために手を打ったり騒いだりすること。 用例 :「ひな壇芸人」③鼓腹撃壌のためのステージ。→鼓腹撃壌。
【ベントフィルター】原発で重大事故が起きるまでは不要なフィルターのこと。
【放送遵守(ほうそうじゅんしゅ)を求める視聴者の怪(しちょうしゃのかい)】安倍官邸の走狗として政権を批判するジャーナリストたちを潰す言論弾圧の怪グループ。
【ホラッチョ】熊本出身のホラ吹きを指す言葉。熊本の隠れキリシタンの賛美歌「ほーらしょほらしょ」から派生したと考えられる。
【免震重要棟(めんしんじゅうようとう)】原発の安全性を措置するための施設ではないので、重大事故が起きるまでは不要な建物のこと。
【松龍(まつりゅう)】①下品で恫喝的に威張り散らすこと。②○差別長者のこと。
【ゆ党】野党に徹しきれず与党との政策の違いも曖昧で、野党と与党の中間「やゆよ」の中間を立ち位置とする「ぬるま湯」のような政党のこと。党のシンボルマークは♨で「揶揄(やゆ)」の意を含む。
【翼賛系新聞(よくさんけいしんぶん)】旧産経新聞のこと。あまりにも官邸・政権寄りの偏向記事が多いという指摘を受けて、社名と紙名を「翼賛系新聞」に変更した。
【読売虚人(よみうりきょじん)】①日本最大の発行部数を誇る読売新聞グループ会長で尊大な領導者を指す。蔑称・別称「ナベツネ」とも。②転じて老害の意。