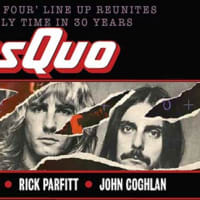ホール&オーツというとポップ・ミュージックだ。が、ただポップ・ミュージックと一言で言っても、彼らのポップ・ミュージックの素地となるものに目を向けなければ、いまのホール&オーツのライヴを楽しむには不十分な気がする。この日のライヴを観てそう痛感した。
彼らの嗜好はデビュー前からフィリー・ソウルにあった。そして、そのスタイルを踏襲しながら独自のポップ・テイストを磨き上げ、ポップ・デュオとしての地位を築いてきた。彼らの曲はその時代時代によってアレンジや音色を変えるが、しかしそのほとんどの曲はフィリー・ソウルそのまんまのコーラスで彩られ、伸びやかで艶のあるダリル・ホールのリード・ヴォーカルがグイグイと引っ張ることで成り立っている。フィリー・ソウルへのリスペクトが彼らのポップ・ミュージックの原動力となっていることは明らかで、それはただの物真似に終わることなく、彼らのポップ・センスと重なり合う。その二つの甘美な融和がホール&オーツの音楽を形作っているのだ。
80年代、ヒット・チャートを席巻していたころの彼らは、ポップ・ミュージックとして語られることはあっても、ソウルとして語られることは少なかったように思う。ソウルというキーワードで彼らを語るときは必ず"ブルー・アイド・ソウル"と揶揄されるなど、そんな評価を二人は忌ま忌ましく思っていたというが、そんな彼らの志向と一般の人たちが彼らに抱くイメージの乖離はいまから30年も前に始まっていた。
ライヴは、去年から続いている"Do What You Want, Be What You Are Tour"の固定されたセットリストで、日本向けにアレンジされたサプライズは無し(ただ、曲数は若干多かった)。演奏面では、メンバー個々の音が不明瞭なうえ、バンドの音もグシャッと潰れて聴こえる武道館ならではの音響。
去年亡くなったTボーン・ウォークの不在も、バンドに与えた影響は大きかったようだ。バンドをビシッと引き締める、サウンドの核がいないステージはいまだに代役を見つけることができていない。
なかなか満足できる環境でのライヴではなかったが、しかし、なによりダリルの歌がえらく良かったことは断言できる。ネットでは「ダリルは声が出ていなかった」「声に伸びがない」「高音がまるでダメ」など批判的なコメントが少なくなかったけれど、あれは、声が「出ていない」のではなく、「歌い方のスタイル」に過ぎないのではないか。ライヴのときの彼は、原曲のメロディどおりには歌わず、かなり崩して歌う(ただし主たるメロディを逸脱することはない)。原曲に忠実に歌いあげるのではなく、歌い方を微妙にコントロールしながら、その瞬間瞬間で自由に歌うスタイルだ。この日、その歌い方に情緒や深みはあまり感じられなかったが、テクニカルな上手さは秀逸だった。高音もその気になればまだまだ出せるだろうことは十分見てとれたし、歌の表現を探究していくなかであの歌い方になっていったのだと思うのだが…。
そのスタイルに見えたのはダリルが長年敬愛してきたフィリー・ソウルからの影響だ。彼のポップ・ミュージックの中に込められたソウルへの強い畏敬の念を感じると、その歌の上手さはより強く実感できる。
ただ、ソウルフルな歌い手というより、ソウルを咀嚼した一流ポップ・シンガーのうまいカラオケのように見えた瞬間もあったにはあった。けれど、彼が本気になって情感たっぷりに歌うことがあるとすれば、それは感動的なライヴになるはず。今回は長いツアーのせいか、丁寧に歌っているようにも、本気に歌っているようにも見えなかったのは残念だし、物足りなかったが、それでも歌の上手さは際立っていて、フィリー・ソウルとポップ・ミュージックの間にかかる橋のように、成熟した歌を聴かせてくれた。ライヴにおいて、ダリルの歌はポップというよりずっとソウル寄りに傾くこともあって、ポップに接する視点だけではその魅力を感じきれないシンガーになってきている。
全体としてみるとあまり覇気の感じられないライヴだったが、なによりソウルからの影響を強く感じるダリルの歌の上手さばかりが目立つステージだった。
今度は、そんなダリルにもう少し気合いが入ったライヴを望みたい。
1. Maneater
2. Family Man
3. Out of Touch
4. Method of Modern Love
5. Say It Isn't So
6. It's A Laugh
7. Las Vegas Turnaround
8. She's Gone
9. Sara Smile
10. Do What You Want, Be What You Are
11. I Can't Go For That (No Can Do)
<encore>
12. Rich Girl
13. You Make My Dreams
<encore>
14. Kiss on My List
15. Private Eyes
彼らの嗜好はデビュー前からフィリー・ソウルにあった。そして、そのスタイルを踏襲しながら独自のポップ・テイストを磨き上げ、ポップ・デュオとしての地位を築いてきた。彼らの曲はその時代時代によってアレンジや音色を変えるが、しかしそのほとんどの曲はフィリー・ソウルそのまんまのコーラスで彩られ、伸びやかで艶のあるダリル・ホールのリード・ヴォーカルがグイグイと引っ張ることで成り立っている。フィリー・ソウルへのリスペクトが彼らのポップ・ミュージックの原動力となっていることは明らかで、それはただの物真似に終わることなく、彼らのポップ・センスと重なり合う。その二つの甘美な融和がホール&オーツの音楽を形作っているのだ。
80年代、ヒット・チャートを席巻していたころの彼らは、ポップ・ミュージックとして語られることはあっても、ソウルとして語られることは少なかったように思う。ソウルというキーワードで彼らを語るときは必ず"ブルー・アイド・ソウル"と揶揄されるなど、そんな評価を二人は忌ま忌ましく思っていたというが、そんな彼らの志向と一般の人たちが彼らに抱くイメージの乖離はいまから30年も前に始まっていた。
ライヴは、去年から続いている"Do What You Want, Be What You Are Tour"の固定されたセットリストで、日本向けにアレンジされたサプライズは無し(ただ、曲数は若干多かった)。演奏面では、メンバー個々の音が不明瞭なうえ、バンドの音もグシャッと潰れて聴こえる武道館ならではの音響。
去年亡くなったTボーン・ウォークの不在も、バンドに与えた影響は大きかったようだ。バンドをビシッと引き締める、サウンドの核がいないステージはいまだに代役を見つけることができていない。
なかなか満足できる環境でのライヴではなかったが、しかし、なによりダリルの歌がえらく良かったことは断言できる。ネットでは「ダリルは声が出ていなかった」「声に伸びがない」「高音がまるでダメ」など批判的なコメントが少なくなかったけれど、あれは、声が「出ていない」のではなく、「歌い方のスタイル」に過ぎないのではないか。ライヴのときの彼は、原曲のメロディどおりには歌わず、かなり崩して歌う(ただし主たるメロディを逸脱することはない)。原曲に忠実に歌いあげるのではなく、歌い方を微妙にコントロールしながら、その瞬間瞬間で自由に歌うスタイルだ。この日、その歌い方に情緒や深みはあまり感じられなかったが、テクニカルな上手さは秀逸だった。高音もその気になればまだまだ出せるだろうことは十分見てとれたし、歌の表現を探究していくなかであの歌い方になっていったのだと思うのだが…。
そのスタイルに見えたのはダリルが長年敬愛してきたフィリー・ソウルからの影響だ。彼のポップ・ミュージックの中に込められたソウルへの強い畏敬の念を感じると、その歌の上手さはより強く実感できる。
ただ、ソウルフルな歌い手というより、ソウルを咀嚼した一流ポップ・シンガーのうまいカラオケのように見えた瞬間もあったにはあった。けれど、彼が本気になって情感たっぷりに歌うことがあるとすれば、それは感動的なライヴになるはず。今回は長いツアーのせいか、丁寧に歌っているようにも、本気に歌っているようにも見えなかったのは残念だし、物足りなかったが、それでも歌の上手さは際立っていて、フィリー・ソウルとポップ・ミュージックの間にかかる橋のように、成熟した歌を聴かせてくれた。ライヴにおいて、ダリルの歌はポップというよりずっとソウル寄りに傾くこともあって、ポップに接する視点だけではその魅力を感じきれないシンガーになってきている。
全体としてみるとあまり覇気の感じられないライヴだったが、なによりソウルからの影響を強く感じるダリルの歌の上手さばかりが目立つステージだった。
今度は、そんなダリルにもう少し気合いが入ったライヴを望みたい。
1. Maneater
2. Family Man
3. Out of Touch
4. Method of Modern Love
5. Say It Isn't So
6. It's A Laugh
7. Las Vegas Turnaround
8. She's Gone
9. Sara Smile
10. Do What You Want, Be What You Are
11. I Can't Go For That (No Can Do)
<encore>
12. Rich Girl
13. You Make My Dreams
<encore>
14. Kiss on My List
15. Private Eyes