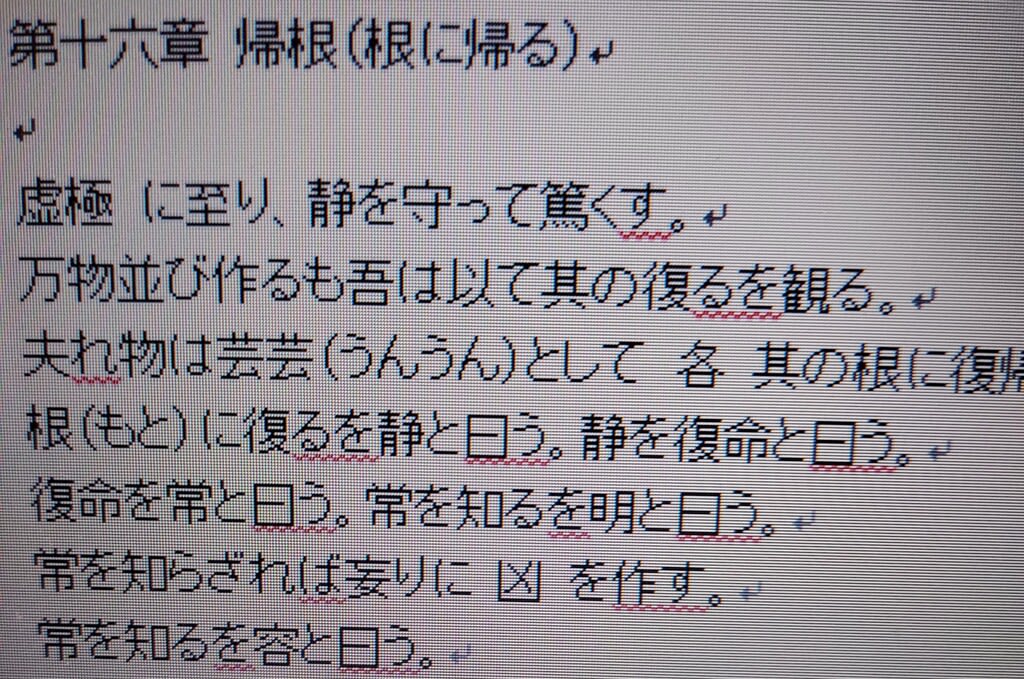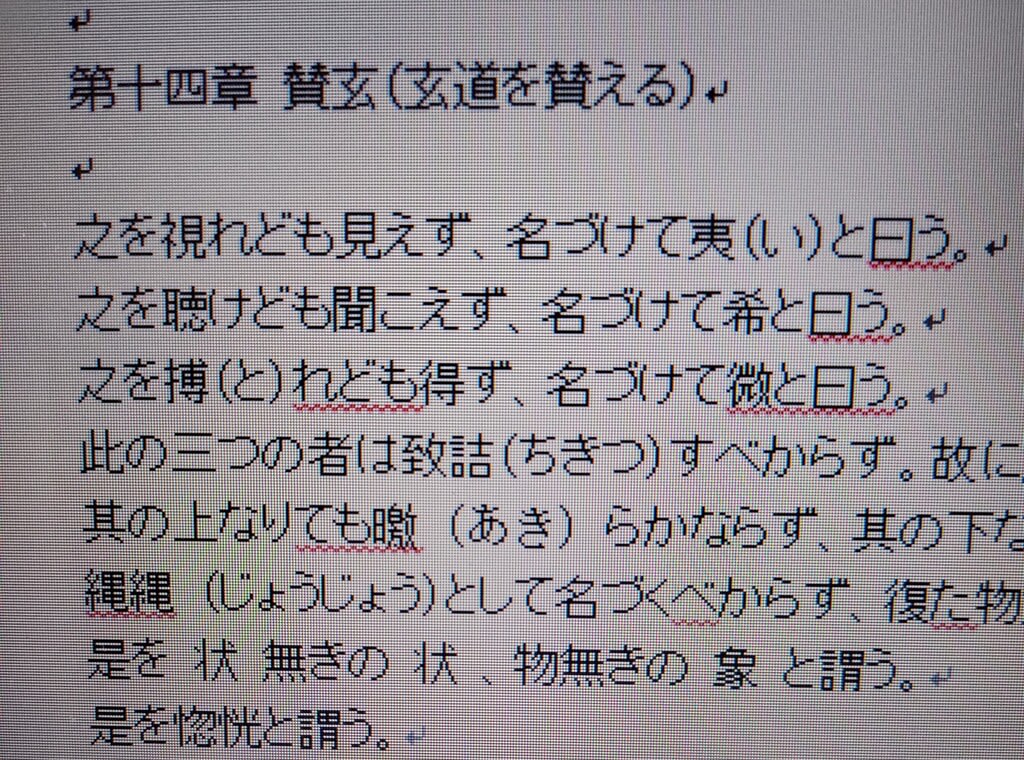第二十一章 虚心(虚心によって知る)
孔徳の容るること、唯り道に是 従 う。
道の物為る、唯り恍(こう)たり、唯り惚(こつ)たり。
惚たり恍たり、其の中に 象 有り。
恍たり惚たり、其の中に物有り。
窈(よう)たり冥(めい)たり、其の中に精有り。
其の精 甚 だ真なり、其の中に信有り。
古 より今に及ぶまで、其の名去らず。
以て衆甫を閲(う)けたり。
吾何を以て衆甫の然ることを知らんや。
此を以てなり。
聖人、有道者は、総てのことを道によって行い、道から離れたこと、道にかなわないことは行わない。
道は、宇宙の始めから万物を支配していたものであり、道の名は太古から存在していたものである。
孔徳の容の、孔は、甚、或は、大の意。孔徳は、大徳の人、聖人、有道者を指す。
唯道に是 従 うは、総てのことを、道に基づいて行い、道に合わないことは、行わないことをいう。
恍(こう)たり 惚(こつ)たりの恍は、うっとりとする。ぼんやりとして、定かでない。微妙にして測り難い。惚は、うっとりとする。かすか。奥深くして測り難い。
其の中に象ありの、其は、恍惚を指す。象は、容姿である。判然としない、ぼんやりとしたものの中に、道の姿がある、の意。
窈(よう)たり冥(めい)たりの、窈は、深し、遠し、静か。冥は、昏し、遠し。窈たり冥たりは、道に対しての、これを形容した言葉であって、道は、深く、遠く、静かにして、昏い所に相対しているようである、の意。
其の精 甚 だ真なりの、真は、真実、真理とすべきものを指す。
其の中に信有りの、其は、真実なるものを指す。信は、何人も信じることができることを指す。
其の名去らずの、名は、道のことを指すと同時に、道の働きも指す。
以て衆甫(しゅうほ)を閲(う)けたりの、以ては、窈(よう)たり冥(めい)たりから、其の中に信有り、までの文章に説かれている、道の働きともいうべきことを指す。
甫は、始め。衆甫は、宇宙万物の始めを指す。 以て衆甫(しゅうほ)を閲けたりは、道は、宇宙の始めから、宇宙を支配し、万物のあらゆる現象を総べおさめている、の意。
此を以てなりは、以上に説明したことによる、の意。
この章は、聖人、有道者は、総ての行動を道に基づいて行っているものであって、道は、宇宙の始から万物を支配しているものであることは、古から知られていたものであることを説いているのです。