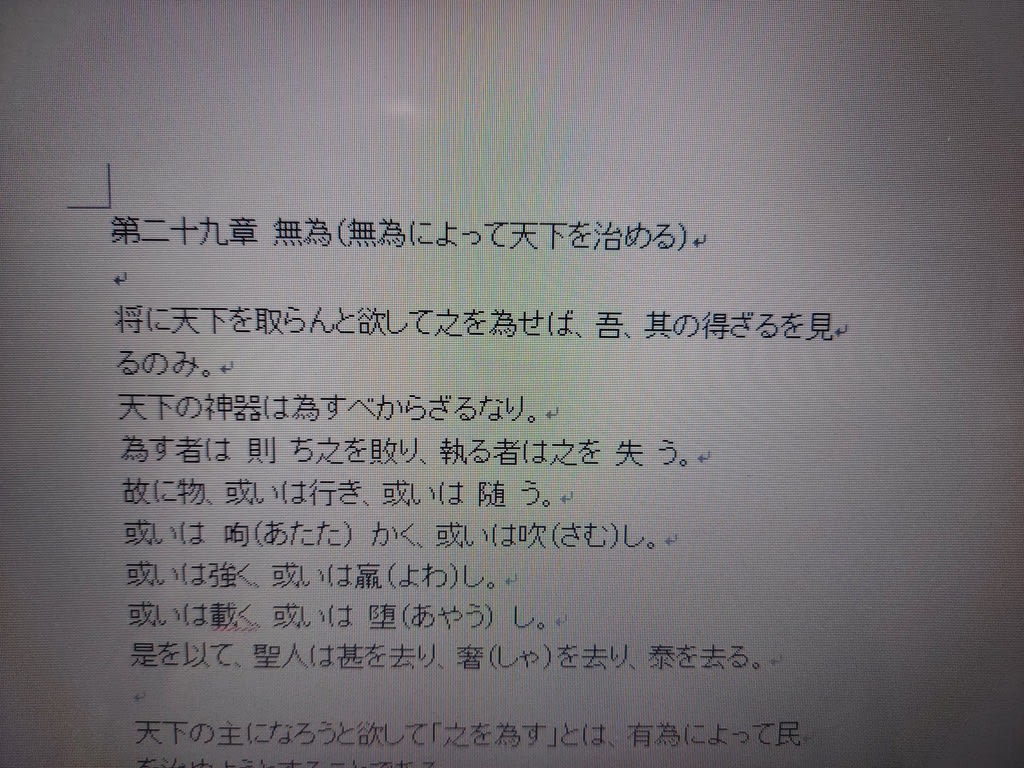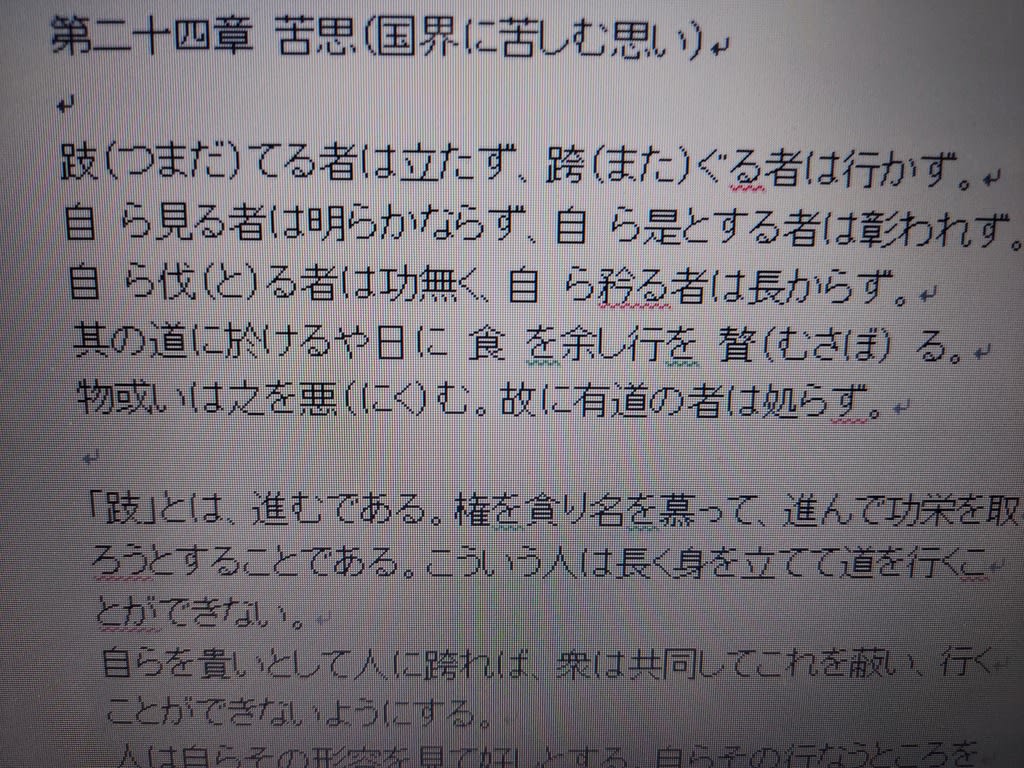第三十一章 偃武(えんぶ)(武勇を偃(や)める)
夫れ兵を飾る者は不祥の器なり。
物之を悪(にく)むこと有り。故に有道の者は処らず。
君子居るときは 則 ち 左 を 貴 ぶ。兵を用いるときは 則 ち右
を 貴 ぶ。
故に、兵は不祥の器にして君子の器に非ず。
已むことを得ずして之を用いるときは恬淡(てんたん)を 上 と為す。
勝ちて而も美しとせず。而るに之を美しとする者は、是れ人
を殺すことを楽しむなり。
夫れ人を殺すことを楽しむ者は、則 ち以て 志 を天下に得べからず。
吉事には 左 を 上 とし、凶事には右を 上 とす。
偏将軍は 左 に居り、 上将軍 は右に居る。
上勢 に居れば 則 ち葬礼を以て之に処すを言う。
人を殺すことの衆ければ以て悲哀して之に泣く。
戦 い勝ちては葬礼を以て之に処す。
この章も前章と同様に、兵は狂器であることを説き、狂器を用いなければならない戦争は、あくまでも避くべきものであることを説く。
立派な兵器は、人を殺傷し、物資を破壊し、土地を荒廃させるところの、不幸を招くものである。従って、万物を愛し育てようとする造物主は、この狂気となるものを悪むのである。
もし、戦に勝つことを結構なことだとして祝賀するようなことがあれば、それは、人を殺すことを楽しむことになるわけである。そのように、人を殺すことを楽しむ者は、志を天下に得ることは、到底できないことであるのは明らかである。古事は左を貴び、凶事は右を貴ぶことは、古来からの習わしである。
ところで、兵事に於いては、偏将軍は左により、上将軍は右によることになっている。総大将が右によることになっているのは、兵に関することは、葬礼によって、右を貴ぶことになっているからである。
偏将軍は、上将軍の下にあって、これを補佐し、或は、代理を務めることのある副将軍。上将軍は、全軍を指揮する総大将を指す。喪礼は、葬式を行う場合の礼式である。
戦に勝っても、軽々しく喜んだり、騒いだりすることなく、喪礼をもって静かにつつしんでいるのである。