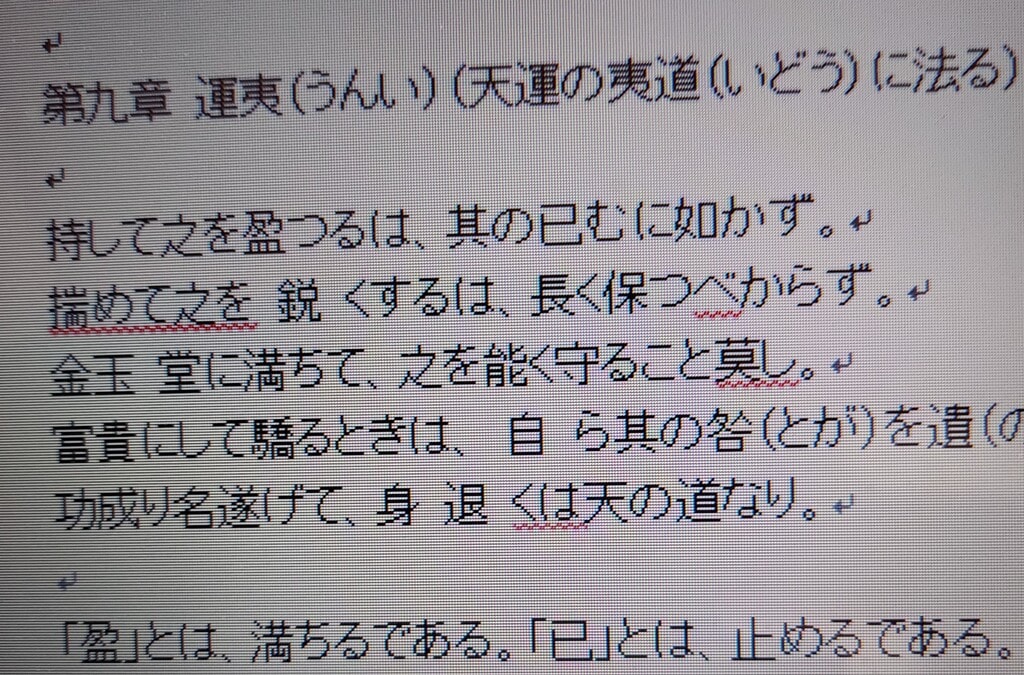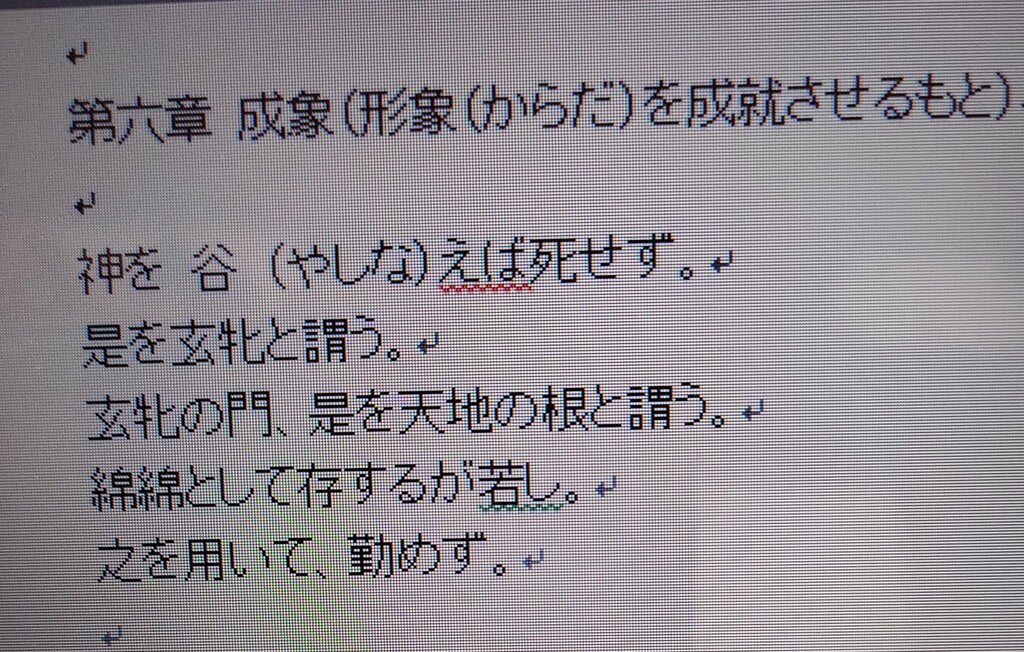第十一章 無用(無の 用(はたら) き)
三十の輻(や)は一つの 轂(こしき) を共にす。其の無に当りて 車 の用有り。
埴((つち)を埏(やわ)らげて以て器を為(つく)る。其の無に当りて器の用有り。
戸牖(こゆう)を鑿(うが)ちて以て室を為る。其の無に当りて室の用有り。
故に有の以て利を為すは、無の以て用を為せばなり。
この章は、無の働きというものは、いかなるところにおいても、なくてはならぬものであることを、車轂や、戸牖の喩えを挙げて説くものである。
車の輪には、三十本の輻(や)があって、輻は、輪の中心に在る轂(こしき)に集まっている。轂の中心には円形の孔があいていて、そこえ、両輪をつなぐ、車軸を通すことになっている。轂の空所、すなわち、無なる所があるから、車軸を通すことができ、また、車が進行するときは、車軸は、轂内を回転することができるのである。
従って、空なる所、無の果たす役割も大切であることを認めなければならない
陶器や磁器等の容器のことであるが、これらのものは、粘土に水を加え、練ったり、打ったりして粘質のものとなし、皿のようなものや、鉢のようなものや、壺のようなもの等、種々の器物を造るわけであるが、造られた器物が容器として役に立つのは、その中心部、或は、その上方に空所が存在するからである。
室が、人間の役に立つのは、戸のある所、空なるところがあるから出入りすることができ、また、牖のある所が、空なる所とすることができるので、室内を明るくすることができるのであるから、空である所、無の果たす役割も大切であることを認めなければならない。
戸牖(こゆう)の戸は、室の入口にある戸、牖(ゆう)は、光線を室に入れるために壁にあけたまどのことです。