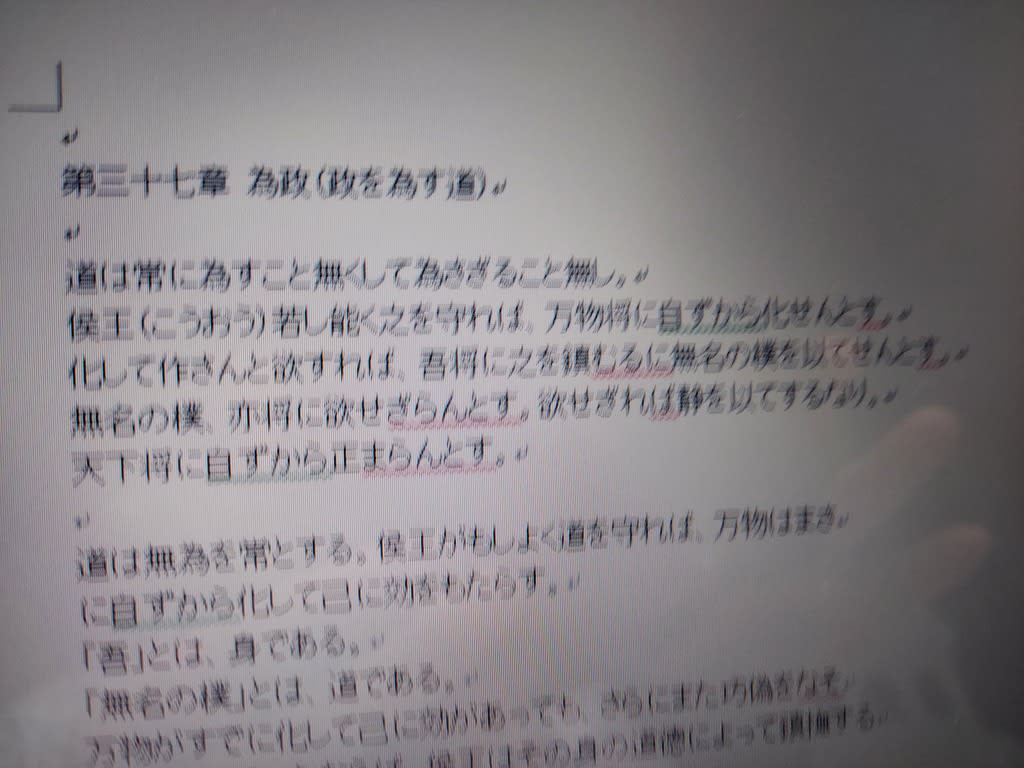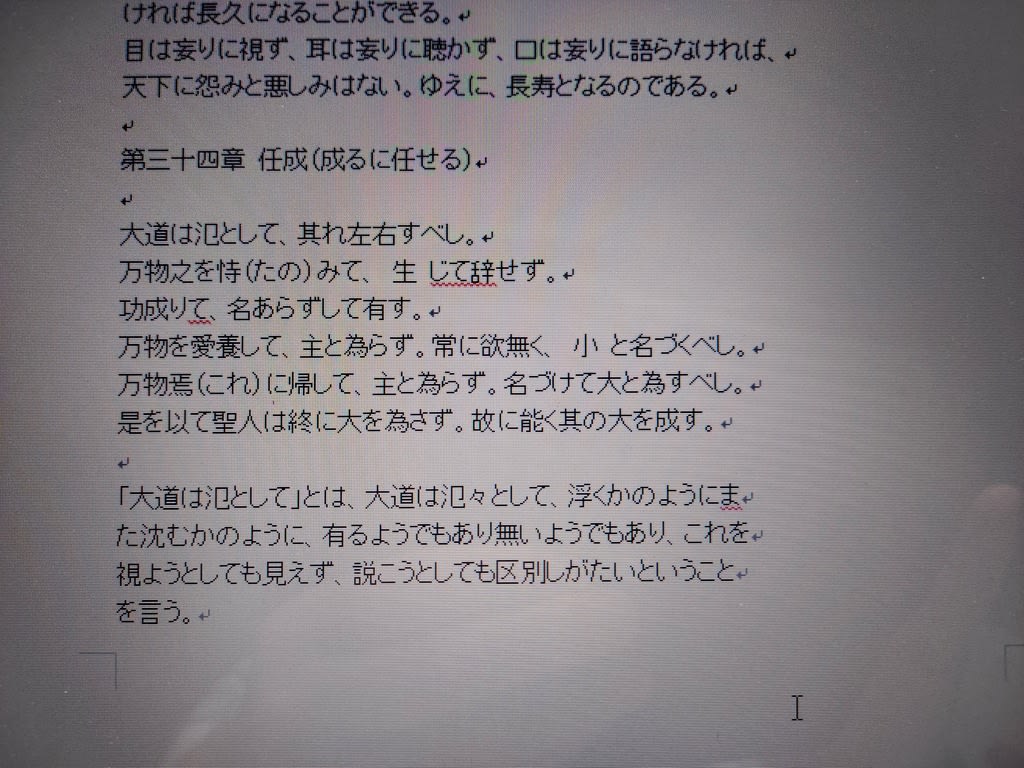第四十一章 同異(道の異同)
上士は道を聞いて、勤めて之を行なう。
中士は道を聞いて、存するが若く 亡(うしな) うが若(ごと)し。
下士は道を聞いて、大いに之を笑う。笑われずんば以て道
と為るに足らず。
言を建けて之を有す。
道に明るきは昧きが若し。道に進むは 退 くが若し。
道に夷(ひと)しきは類するが若し。
上徳は谷の若し。大白は 辱 なるが若し。
広徳は足らざるが若し。建徳は揄(ひ)くが若し。
質直は渝(あ)せたるが若し。大方は隅無し。
大器は晩く成る。大音は声 希(すくな) し。
大象は 形 無し。道は隠れて名無し。
夫れ唯道は善く貸(あた)えて且つ成す。
上士というのは、道を聞いて、忠実に道を行う人である。忠実に道を行っているうちには、無限の妙味のあることが次第に会得できるようになり、道から離れないようになるのである。
中士というのは、道を聞いて、或時は了解しているようであるが、或時は、納得がゆかないというような様子をする人である。争う心、対立する心がなかなかぬけきらないで、道に従っていては、損をするのではないか、どうも、自分の存在が、はっきりしないことになるのではないかというように、後になってから考えてみれば、どちらでもよいようなことにこだわって、確りと信頼して、深く道に入ってゆけないため、道が進んだり、止まったりするような人のことをいうのである。
下士というのは、道のことを聞けば大いに笑うのである。下士は争う心、対立的の心が脱けそうにないのである。人に譲ったり、敗けたりすることは、絶対に承知できないのである。しかるに、道は、争わぬように、人に譲るようにと教えるから、そんな愚かなことができるかと、大いに笑うのである。下士の笑わないことは、勝つ方法とか、利益を得る方法とか、利己的のことのみであるから、もし下士が笑わないことを言ったとすれば、功利的のことか、それに近いことであるから、道とするに足らないのである。
下士が道を聞いて大いに笑うのは、外見に心を取られて信実が解らないからである。
万物は、道から借りたものは一時的のもので、時期が来れば皆返してしまうのである。
以上のことから考えると、人がどんな成功を収めても、それを自分の力だと思うことも、それを長く維持することができると思うことも誤りであることが明らかである。