【笑顔で「シュッ」と】“また来たい”の思いあふれ 愛子さま初の単独公務 国立公文書館へ…源氏物語で質問も【教養としての皇室17】 (youtube.com)
天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、初めてお一人での公務にのぞまれました。 鑑賞されたのは、国立公文書館で開催されていた「夢みる光源氏ー公文書館で平安文学ナナ読み!ー」という特別展。「夢」をテーマにして「源氏物語」をはじめとする平安文学の資料を展示したもので、愛子さまは、専門的な質問をまじえ、およそ1時間じっくりとご覧になりました。 ーー笛吹雅子解説委員 私も現地で取材していましたが、 愛子さまに初めてという緊張や気負いは感じられず、本当にこうした古典文学が好きで興味がつきないと、楽しく鑑賞されている様子でした。 愛子さまを案内した星瑞穂調査員は、愛子さまの古典文学の造詣の深さに驚き、感銘を受けたといいます。後日、改めて日本テレビの取材にご様子を語ってくれました。 まず、愛子さまのお人柄については。 ーー国立公文書館 星瑞穂調査員 「終始笑顔でいらっしゃって、また目を合わせて近くでお話いただいて、大変気さくで飾らないお人柄なんだなという印象を受けました」 「お帰りになる際に当館の館長から、またおいでくださいと申し上げましたところ、『はい。近くですので、シュッと来られます』っておっしゃって。『シュッ』とおっしゃったのが大変おかわいらしくて、私は失礼ながら笑ってしまいまして、宮さま(愛子さま)も笑顔でお応えいただきました」 ーー 笛吹雅子解説委員 「シュッ」というところに、お世辞では無い「また来たい」という気持ちがあふれていると感じました。他にもこんなやりとりがあったそうです。 ーー国立公文書館 星瑞穂調査員 「私、目が悪いんです」とおっしゃって、こう眼鏡をかけて、「これで見えるようになりました」と仰せで、それでじっくりとご覧になっておいででした。 「枕草子」の「うれしきもの」という章段をご紹介したんですけれども、そこでは悪い夢を見ても、誰かに分析してもらって悪いことが起きるわけではないよと言ってもらえるとうれしいというようなことが書いてあるんですけれども、こちら、宮さま(愛子さま)に案内しましたところ、「夢占いは現代でもありますよね。例えば、人が死ぬ夢、自分が死ぬ夢なんかを見たときには、かえって良いことが起こるということもありますね」と仰せでした。 そういった一般の方が気にするようなことも宮さま(愛子さま)もご存じなんだなと思わず笑ってしまいました。失礼なことなんですけれども、でも宮さま(愛子さま)も笑顔になっておいででした。 愛子さまは、「枕草子」のすごいところは、現代の我々でもわかることがみずみずしく描かれているという星さんの話を聞き、「だから1000年残るのでしょうね」と深くうなずかれていたそうです。気さくなご様子の一方、星さんは愛子さまの専門的な質問にドキリとさせられたといいます。それは、鑑賞の冒頭でした。 ーー国立公文書館 星瑞穂調査員 一番最初に江戸時代の注釈書である「窺原抄(きげんしょう)」という資料をご紹介したんですけれども、その際に「江戸時代といえば『湖月抄(こげつしょう)』という注釈書がありますね」と仰せで、 「それとの関係性は?」という大変専門的なご質問、ご下問がございまして、私としてもちょっとドキリとさせられるところがありまして。 江戸時代に流布し、広く知られた「源氏物語」の注釈書は、「湖月抄(こげつしょう)」ですが、今回の特別展では、この公文書館と東北大学にしかないという大変珍しい「窺原抄(きげんしょう)を展示していました。 ーー国立公文書館 星瑞穂調査員 源氏(物語)の注釈書で、江戸時代で「湖月抄(こげつしょう)」がぱっと出てくるというのは、やはり大変勉強されている方だなという印象を受けました。 学部4年生でご卒業されて、ご就職されたと伺っておりますけれども、修士大学院生以上の知識があるのではないかなと拝察いたしました 星さんは、愛子さまの知識は修士の大学院生以上と驚いていました。この時、愛子さまは、 「注釈書としての論拠がしっかりしているのか」、「どれくらいの年数を掛けてつくられのか」などと、次々と質問をされていました。 「窺原抄(きげんしょう)」を執筆したのは江戸時代、代々牢屋奉行を務めた石出帯刀の3代目石出常軒で、1657年の明暦の大火の際、独断で囚人を解放し、多くの命を救ったとして知られる人物です。 愛子さまは、「こういう人が注釈書を書いているのは興味深いですね」と、満面の笑顔で感想を述べられていて、古典文学や研究者への愛着が感じられました。 愛子さまは大学で古典文学を学ばれていますが、高校の卒業レポートも、源氏物語や枕草子など古典文学の猫や犬と人との関わりについてまとめたものでした。 「平安時代の猫と犬 一文学作品を通して一」という題で、400字詰め原稿用紙30枚以上という学校の基準の倍近い分量に及ぶレポートだったそうです。 この日の鑑賞ではどんな内容だったかにも話が及びました。 「栄花物語」の中の藤原隆家が花山法皇に矢を放って襲った「長徳の変」の場面を紹介した際のやりとりでした。 ーー国立公文書館 星瑞穂調査員 「私、この場面はとても思い入れがあるんです」と仰せで。 「それはどういったことでしょうか」とお伺いしましたところ、 「高校のレポートで『枕草子』に登場する翁丸(おきなまろ)という犬を取り上げた際に、背景に『長徳の変』があるのではないか」と、そういった内容でレポートを書かれたとおっしゃっておいでした。大変難しいレポートではなかったのかなと思います。 「枕草子」に出てくる、宮中で飼われていて外に出されよれよれになって戻ってくる「翁丸」。この犬が「長徳の変」で追放された藤原伊周の姿を暗示しているのではないか、星さんはそういうレポートではないかと思ったそうです。 ーー笛吹雅子解説委員 伊周は藤原道長との権力闘争に敗れた訳ですが、愛子さまが小学6年生の時に書かれた 「藤原道長」について調べたレポートが学習院初等科の小冊子に残されています。 この時代のことは、長く愛子さまの関心の対象であったのだろうと思います。 また、この日の鑑賞では、「古今和歌集」を見た時に、「きれいですね」と保存状態が良いことにも感心されていた愛子さま。 大学の卒業論文のテーマは中世の和歌だったので、様々な文献を目にされる機会も多かったのだろうと思いました。 愛子さまの初めてのお一人での公務、星さんはこう振り返りました。 ーー国立公文書館 星瑞穂調査員 私の方も大変勉強になりましたし、やはり私も好きでこの研究の世界に入りましたので、熱心に聞いていただけると本当にうれしいことでして、何か恐れ多いことなんですが、二人で大変有意義な時間を過ごさせていただいたのが本当に光栄に思っております ーー 笛吹雅子解説委員 星さんは終始笑顔で愛子さまのことを語っていて、愛子さまの笑顔はこうして伝わっていくのだなぁと感慨を覚えました。 国立公文書館は、皇居から道をはさんで向かい、すぐのところにあります。愛子さまは、これからも「シュッ」と訪問されることがあるでしょうか。













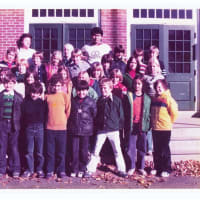
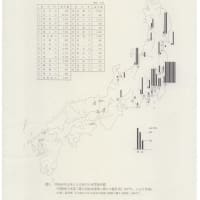













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます