
鎚に次いで鍛冶屋の大事な道具の一つです。熱した材料をつかむ「手の延長」となる道具で鍛冶屋さんや鋳物屋さんで使われます。「火挟み・やっとこ」など呼び方は様々なようですが、私の親方は小箸(こばし)と呼びます。小箸でつかむ対象によってかたちは様々あり、仕事の内容で上手く使い分けます。
今回「捻り鉉」の仕事で使うために新しく製作しました。熱した材料を捻るので、輻射熱で火傷しないよう、長めのものにします。2つの小箸をそれぞれ両手に持って、材料を捻ります。そのため、同じ形状のものを2つで一組として作りました。

私なりに考えた小箸の制作方法です。まず、必要な寸法の2倍の長さに丸棒を細く伸ばします。


小箸の先になる部分(中央)を残して両側を平らに打ちます。平らに打った部分が持ち手になります。その後真ん中を切断し、小箸の先になる部分を作ります。


2本を互い違いに組んで一組になるので、全く同じ形のものを2組作ることになります。同じラインを描くように打って曲げます。その後小箸の動く支点となる部分に穴を穿ちます。

穿った穴に合うピンを作って差し込み、赤くなるまで熱して打ってカシメ(接合し)ます…が、写真を撮り忘れてしまいました。申し訳ありません。
カシメが終わった後、先の部分を赤くなるまで熱して微調整します。小箸でつかむ対象に合わせて調整します。金鎚と同じように一度作れば寿命の長い道具なので、しっかり作り込むよう心掛けていますが、なかなか思うように上手くいきません。道具は基本。必要な際には必ず作るようにしていきたいです。












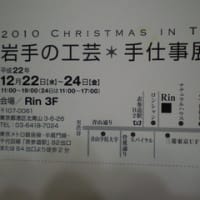
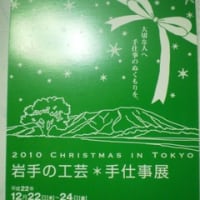
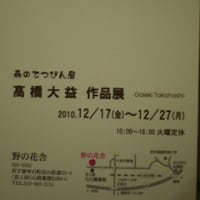
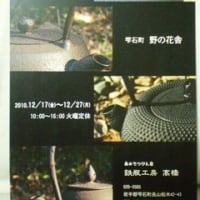




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます