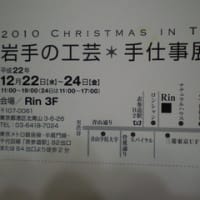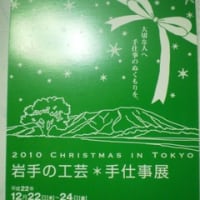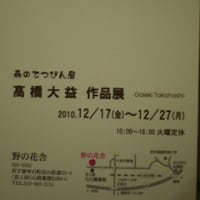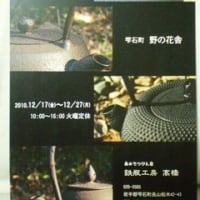前回ご紹介しました鉉の修理(http://blog.goo.ne.jp/forginer1984/e/a0b5f43be13dafdcea6e9ac10af744d5)の続きです。
鉉は鉄瓶本体と同じ色に着色されて、本体に取り付けられます。ご存知の方も多いと思われますが、着色には主に漆(生漆)を使います。鉄瓶本体をある程度の温度まで加熱し、漆を焼付けます。漆の焼きついた被膜ができ、黒系統の色合いになります。茶系統の着色がされた鉄瓶のありますが、そちらはまた別の方法となります。どちらも塗装では得ることのできない趣があり、使い込むほどに風合いが出てきます。
今回鉉を修理した鉄瓶本体は内側も外側も大変状態が良く、いい古び方をしていました。鉉だけ漆で着色をし直すと雰囲気を壊しかねないと思い、今回ある方法を取りました。

普段「私事」で着色に使う「錆出し液」で黒錆を付けます。この錆はまだ不安定ですので、赤錆に変化する場合があります。

この日の朝飲んだお茶(煎茶)の出涸らしをさらしに包んでおいたものです。金属製の器に水を張り、少し沸かしておきます。お茶が煮出してきたら常温まで冷まします。

錆付けした鉉を炭火で加熱し、表面に水を落とし蒸発するくらいの温度になったら先ほどの布タンポで軽く叩く感じで押していきます。黒っぽく色が変化しているのがお分かりいただけるでしょうか。この方法は「お茶刷き」といい、鉄とお茶に含まれる「タンニン」の反応を利用した方法で鉄瓶の着色の仕上げにも使われます。鉄とタンニンが反応してできる「タンニン鉄」は比較的安定した被膜となり、赤錆などを発生しにくくしてくれます。
普段鉄瓶を使っていらっしゃる方はお手入れの方法としてご存知かもしれません。

左側がお茶刷きをした部分です。画像では分かりづらいと思いますが、タンニンの力で驚きの黒さになります。
余談ですが、時代劇などで既婚の女性が歯を黒くする「お歯黒」ですが、あれも鉄とタンニンの反応を利用しています。
まず、カルシウム質の歯に鉄漿(てっしょう/おはぐろ)液を塗ります。この後タンニンが含まれたお茶でうがいをすることによって、鉄漿の鉄分とタンニンが反応し、カルシウム質の歯の上に被膜を作ります。
もちろん風習の意味合いが強かったのでしょうが、栄養状態も悪く、歯科学も発達していなかった時代ですので女性は出産などでの体への負担で歯を悪くすることが多かったのかもしれません。ある意味予防医学だったのでは、という話を大学時代聞いたことがあります。
続きます。
鉉は鉄瓶本体と同じ色に着色されて、本体に取り付けられます。ご存知の方も多いと思われますが、着色には主に漆(生漆)を使います。鉄瓶本体をある程度の温度まで加熱し、漆を焼付けます。漆の焼きついた被膜ができ、黒系統の色合いになります。茶系統の着色がされた鉄瓶のありますが、そちらはまた別の方法となります。どちらも塗装では得ることのできない趣があり、使い込むほどに風合いが出てきます。
今回鉉を修理した鉄瓶本体は内側も外側も大変状態が良く、いい古び方をしていました。鉉だけ漆で着色をし直すと雰囲気を壊しかねないと思い、今回ある方法を取りました。

普段「私事」で着色に使う「錆出し液」で黒錆を付けます。この錆はまだ不安定ですので、赤錆に変化する場合があります。

この日の朝飲んだお茶(煎茶)の出涸らしをさらしに包んでおいたものです。金属製の器に水を張り、少し沸かしておきます。お茶が煮出してきたら常温まで冷まします。

錆付けした鉉を炭火で加熱し、表面に水を落とし蒸発するくらいの温度になったら先ほどの布タンポで軽く叩く感じで押していきます。黒っぽく色が変化しているのがお分かりいただけるでしょうか。この方法は「お茶刷き」といい、鉄とお茶に含まれる「タンニン」の反応を利用した方法で鉄瓶の着色の仕上げにも使われます。鉄とタンニンが反応してできる「タンニン鉄」は比較的安定した被膜となり、赤錆などを発生しにくくしてくれます。
普段鉄瓶を使っていらっしゃる方はお手入れの方法としてご存知かもしれません。

左側がお茶刷きをした部分です。画像では分かりづらいと思いますが、タンニンの力で驚きの黒さになります。
余談ですが、時代劇などで既婚の女性が歯を黒くする「お歯黒」ですが、あれも鉄とタンニンの反応を利用しています。
まず、カルシウム質の歯に鉄漿(てっしょう/おはぐろ)液を塗ります。この後タンニンが含まれたお茶でうがいをすることによって、鉄漿の鉄分とタンニンが反応し、カルシウム質の歯の上に被膜を作ります。
もちろん風習の意味合いが強かったのでしょうが、栄養状態も悪く、歯科学も発達していなかった時代ですので女性は出産などでの体への負担で歯を悪くすることが多かったのかもしれません。ある意味予防医学だったのでは、という話を大学時代聞いたことがあります。
続きます。