「シルバーエコーささやま」で、今、時の人となっている、アンネット・カズエ・ストゥルナートさんの「ウィーン わが夢の町」(新潮社)を読み終えました。
いろんな意味で、すごい!の一語に尽きます。
この本の帯の、
『ひとは、これほどの目に遭っても花を咲かすことができるのか。
極貧生活、いじめ、音大受験失敗、人種差別・・・
それでも夢を捨てず、東洋人初のウィーン国立歌劇場団員歌手となって30年余。
その壮絶な半生を自ら明かす、感動・勇気・驚愕の自伝。』と
紙表紙裏には、
「昭和13年(1938)年、兵庫県西宮市生まれ。
上海で幼少期を過ごし、中国大陸放浪を経て岡山県に引き揚げ。
現在の高梁市(たかはしし)成羽(なりわ)町で育つ。
だが、一家離散で広島の知人宅に預けられ、高校中退。
中卒のまま準看護婦に。
歌手を目指して通信教育で音楽を勉強。
その後、親戚の養女となって東京へ行き、夜間高校に通いながら、声楽家・坂本博士に師事。
24歳で夜間高校を卒業し、音楽大学を受験するが、すべて失敗。
合唱団に入り、オペラやCMソングをこなす。
31歳で日本脱出を決意。
ロシアを経てウィーンに渡り、生涯の師ロッテ・パブシカに出会う。
やがてウィーン・アカデミーを経て、1971年、東洋人として初めて、ウィーン国立歌劇場団員歌手のオーディションに合格。
以後、今日まで、同歌劇場を中心に、ウィーン・フォルクスオーバー、ザルツブルク復活祭音楽祭など、ヨーロッパ各地で歌い続けている。
現在は、1年の半分近くを日本での声楽指導にあてている。」
と、彼女の人生を要約した文章がありますが、実際に、本を読んでみると、もっと細かなエピソードなどが記載されており、本当に壮絶な人生です。
悩み苦しみ、自殺未遂も何度か経験しています。
一人のひとに、これだけいろいろなできごとが起こりうるのか、と思うほどの波乱万丈のすごい人生をおくりながら、「歌手になりたい」という夢を持ち続け、ついにはそれを実現してしまうすごさ!
まさに、ドラマのような生きざまです。
彼女が、ウィーン国立歌劇場(オペラ座)団員歌手としての最初の仕事は、1971年4月14日の舞台だそうですから、今から、39年も前の、まさに今日です。
第9章の、「ウィーン国立歌劇場へ」で、オーディションに受かり、団員になれた件では、本を読みながら、涙があふれてとまりませんでした。
中には、平穏無事なまま、一生を終える方もおられるでしょうが、人は、大なり小なり、山あり谷ありの人生を送り、一人一人の歴史がありますが、ここまで、ドラマチックな人生も稀有だと思います。
興味を感じられた方は、ぜひ一読をお勧めします。
勇気と感動を与えてもらえる本です。
『「みんな、聞いてくれ」
その声に、下がっていた歌手たちが、いっせいにカラヤンの周囲に寄ってきた。
「この娘は、東洋の果ての、日本という国から一人でやってきた。私は、日本へは何度も公園で行っているから、どんなに遠い所か、よく知っている。寂しい思いをしているに違いない。どうかみんな、これから、彼女の支えになってあげてほしい。」
足が震えた。
立っていられなかった。
私は、カラヤンの前で、膝をついてしまい、その場で号泣した。』
これも本の帯に印刷されている、本書からの抜粋です。
上記は、長い間の夢がかなって、ようやくウィーン国立歌劇場団員歌手になれたものの、今度は東洋人ということで、4年間も、言われなきいじめや人種差別を受け続けていた、アンネットさんの苦悩を見抜いて、カラヤンが他の団員歌手たちに発してくれた言葉だったのです。
ここに出てくるカラヤンとは、あの世界最高の指揮者カラヤンのこと。
(※アンネットさんの、二人の娘さんのミドル・ネームは、いずれもカラヤンの命名だそうです。)
この「ウィーン わが夢の町」という本には、カラヤンやレナード・バーンスタインを初め、世界的に著名な、名だたる音楽家の名前が次々と出てくることにも、驚かされます。
いろんな意味で、すごい!の一語に尽きます。
この本の帯の、
『ひとは、これほどの目に遭っても花を咲かすことができるのか。
極貧生活、いじめ、音大受験失敗、人種差別・・・
それでも夢を捨てず、東洋人初のウィーン国立歌劇場団員歌手となって30年余。
その壮絶な半生を自ら明かす、感動・勇気・驚愕の自伝。』と
紙表紙裏には、
「昭和13年(1938)年、兵庫県西宮市生まれ。
上海で幼少期を過ごし、中国大陸放浪を経て岡山県に引き揚げ。
現在の高梁市(たかはしし)成羽(なりわ)町で育つ。
だが、一家離散で広島の知人宅に預けられ、高校中退。
中卒のまま準看護婦に。
歌手を目指して通信教育で音楽を勉強。
その後、親戚の養女となって東京へ行き、夜間高校に通いながら、声楽家・坂本博士に師事。
24歳で夜間高校を卒業し、音楽大学を受験するが、すべて失敗。
合唱団に入り、オペラやCMソングをこなす。
31歳で日本脱出を決意。
ロシアを経てウィーンに渡り、生涯の師ロッテ・パブシカに出会う。
やがてウィーン・アカデミーを経て、1971年、東洋人として初めて、ウィーン国立歌劇場団員歌手のオーディションに合格。
以後、今日まで、同歌劇場を中心に、ウィーン・フォルクスオーバー、ザルツブルク復活祭音楽祭など、ヨーロッパ各地で歌い続けている。
現在は、1年の半分近くを日本での声楽指導にあてている。」
と、彼女の人生を要約した文章がありますが、実際に、本を読んでみると、もっと細かなエピソードなどが記載されており、本当に壮絶な人生です。
悩み苦しみ、自殺未遂も何度か経験しています。
一人のひとに、これだけいろいろなできごとが起こりうるのか、と思うほどの波乱万丈のすごい人生をおくりながら、「歌手になりたい」という夢を持ち続け、ついにはそれを実現してしまうすごさ!
まさに、ドラマのような生きざまです。
彼女が、ウィーン国立歌劇場(オペラ座)団員歌手としての最初の仕事は、1971年4月14日の舞台だそうですから、今から、39年も前の、まさに今日です。
第9章の、「ウィーン国立歌劇場へ」で、オーディションに受かり、団員になれた件では、本を読みながら、涙があふれてとまりませんでした。
中には、平穏無事なまま、一生を終える方もおられるでしょうが、人は、大なり小なり、山あり谷ありの人生を送り、一人一人の歴史がありますが、ここまで、ドラマチックな人生も稀有だと思います。
興味を感じられた方は、ぜひ一読をお勧めします。
勇気と感動を与えてもらえる本です。
『「みんな、聞いてくれ」
その声に、下がっていた歌手たちが、いっせいにカラヤンの周囲に寄ってきた。
「この娘は、東洋の果ての、日本という国から一人でやってきた。私は、日本へは何度も公園で行っているから、どんなに遠い所か、よく知っている。寂しい思いをしているに違いない。どうかみんな、これから、彼女の支えになってあげてほしい。」
足が震えた。
立っていられなかった。
私は、カラヤンの前で、膝をついてしまい、その場で号泣した。』
これも本の帯に印刷されている、本書からの抜粋です。
上記は、長い間の夢がかなって、ようやくウィーン国立歌劇場団員歌手になれたものの、今度は東洋人ということで、4年間も、言われなきいじめや人種差別を受け続けていた、アンネットさんの苦悩を見抜いて、カラヤンが他の団員歌手たちに発してくれた言葉だったのです。
ここに出てくるカラヤンとは、あの世界最高の指揮者カラヤンのこと。
(※アンネットさんの、二人の娘さんのミドル・ネームは、いずれもカラヤンの命名だそうです。)
この「ウィーン わが夢の町」という本には、カラヤンやレナード・バーンスタインを初め、世界的に著名な、名だたる音楽家の名前が次々と出てくることにも、驚かされます。










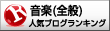















(「障害の師」は「生涯の師」の転換ミスでしょうね。)
私も一気に読みました。
何のも何度も泣きながら・・・。
187ページでは、感動のあまり声をあげて泣いてしまいました。
アンネットさんのCDを毎日車の中で聞いているのですが、何故か涙が出てしまいます。
アンネットさんの歌唱は良い声とか、上手とか経たとかでは無く、歌を超えてしまっています。
魂の叫び声です。
魂が揺さぶられてしまいます。
また、彼女のCDを聴くと背筋がゾクゾクしてきます。
できれば、この感動を、もっと多くの方に味わってもらいたいものです。
また、こんなすごい方にお目にかかれる私たちは、とても幸せだと思います。