吉原治良と「具体美術協会」、そして、パリのS.W.ヘイター (by東浦哲也)
吉原治良のこと
吉原治良は、1905年(明治38年)生まれ、1972年(昭和47年)に亡くなっている。しかし、40年ほどの時を越えて、今も世界で “Jiro YOSHIHARA” そして “GUTAI” の展覧会が企画され、研究が進み、「具体」の作品群が、ますます評価を高めているのである。
吉原治良と吉原の元に集まった若い作家たち(「具体美術協会」)は世界の美術史にその名をとどめる日本を代表する前衛集団であった。吉原治良が美術界にもたらした多くの影響は今も水脈のごとく現代の作家たちに繋がっている。
「誰もやらないことをやれ!」
吉原治良が当時、自分の下に集まってきた若者たちに徹底して突きつけた姿勢である。
それは、1929年神戸に立ち寄った藤田嗣治から、「君の絵は他の画家の影響がありすぎる」と指摘され、オリジナリティーの重要性を強く認識し、人のまねはしないという戒めを自分の哲学とした吉原の自分自身へのメッセージでもあった。
吉原治良は1924年関西学院高等商学部(神戸原田の森)に入学し、絵画クラブ「弦月会」に入会、絵画制作にのめりこんでいく。1930年代には二科展に出品。このころ日本の多くの画家たちがヨーロッパ前衛美術運動であったアンフォルメルの影響を受けて抽象的な絵画を制作しており、吉原も抽象表現を模索しつつ、さまざまな状況を越えて絵を描き続ける。
戦後間もない1948年に芦屋市美術協会が立ち上がり、吉原はその代表を務め、そのころから吉原の周りに若い作家たちが集まるようになってくる。また、1952年には須田剋太らと現代美術懇談会(ゲンビ)に関わり、ジャンルを超えたさまざまな前衛活動の表現者と交流が深められ、そうした中で感じた表現の可能性をより明確にしていくため、1954年「具体美術協会」を自ら立ち上げる。
「具体美術協会」として作品を発表するだけではなく、機関紙『具体』を発行し、活動の記録のみならず、メッセージを世界に発信し続けたことも特筆に価する。
そして、1972年67歳で亡くなるまで、日本の前衛美術の第一人者として活躍した。
具体美術協会のこと
「われわれにとって最も大切な事柄は現代の美術が厳しい現代を生きぬいて行く人々の最も解放された自由の場であり自由の場に於ける創造こそ人類の進展に寄与し得る事であると深く信じるからです。われわれはわれわれの精神が自由であるという証しを具体的に提示したいと念願しています。新鮮な感動をあらゆる造型の中に求めて止まないものです。」
(機関紙『具体』創刊号1955年1月より)
「具体美術は物質を変貌しない。具体美術は物質に生命を与えるものだ。具体美術は物質を偽らない。具体美術に於ては人間精神と物質とが対立したまま握手している。物質は精神に同化しない。精神は物質を従属させない。物質は物質のままでその特質を露呈したとき物語りをはじめ、絶叫さえする。物質を生かし切ることは精神を生かす方法だ。精神を高めることは物質を高き精神の場に導き入れることだ。」
(『具体美術宣言』1956年12月)
上記の宣言にも表されているように、人間のイメージや作為を超えたものをどうやって表現として定着させていくのか。表現手段としての物質を生かしきるような表現を「具体美術協会」のメンバーは模索していくこととなる。そんな中で、絵画の枠を越えたインスタレーション、パフォーマンスの先駆的な取り組みも生まれていくのである。
パリに住む堂本尚郎を介してその機関紙『具体』の内容に注目していたアンフォルメルの主唱者である美術評論家ミシェル・タピエは、1957年来日し吉原治良と具体のメンバーと交流し、「具体」の活動は、アメリカやヨーロッパにも紹介されていくこととなる。現在でも戦後の代表的な前衛活動として『GUTAI』は世界の美術史の文脈に位置づけられている。しかし、1972年吉原治良の死により「具体美術協会」は解散し、メンバーはそれぞれの道を歩んでいくこととなる。
今回の企画にあたって、当時「具体美術協会」の最も若いメンバーで、現在も世界で活躍されている松谷武判、堀尾貞治 両氏にご協力をいただいた。
松谷武判は、パリに渡り、ヨーロッパの空気の中で今も変容し続けている。堀尾貞治は神戸に住み、誰もやったことの無い表現に挑み続けている。現在、国際的に活躍する松谷武判、堀尾貞治 両氏の精神の中に、吉原治良の精神が脈々と受け継がれていることを改めて確信する。そして、その精神はこれからも受け継がれていくべきものである。
松谷武判とS.W.ヘイター
具体美術の洗礼を受けた松谷武判は、パリ留学で飛び込んだ版画工房「アトリエ17」の主宰者S.W.ヘイターに、吉原治良と通ずる芸術家のタイプを感じたのかもしれない。
S.W.ヘイターは「*一版多色刷り」という画期的な版画の刷りの技術を確立する。しかし60年代は表現の模索を続けており、その時期の作品は、銅版を酸で腐食させた凸凹を表現に結びつけたものなど、「具体」が「物質がその特質を露呈する」と宣言した思想とも重なって見えてくる。その後、身体の動きが銅版の上にラインとなって空間を生み出していく独特のスタイルを確立していく。
S.W.ヘイターは表現として自由なラインを導き出すために、身体をリラックスさせることを重要視した。自然、宇宙と一体化していくような純粋な身体活動によって表現が深化していくという考え方は、抽象表現に向かっていた吉原治良にも大きな影響を与えたと考えられる。
今回、吉原治良を通して、時空を越えた作品が結びつくのである。
吉原治良のこと
吉原治良は、1905年(明治38年)生まれ、1972年(昭和47年)に亡くなっている。しかし、40年ほどの時を越えて、今も世界で “Jiro YOSHIHARA” そして “GUTAI” の展覧会が企画され、研究が進み、「具体」の作品群が、ますます評価を高めているのである。
吉原治良と吉原の元に集まった若い作家たち(「具体美術協会」)は世界の美術史にその名をとどめる日本を代表する前衛集団であった。吉原治良が美術界にもたらした多くの影響は今も水脈のごとく現代の作家たちに繋がっている。
「誰もやらないことをやれ!」
吉原治良が当時、自分の下に集まってきた若者たちに徹底して突きつけた姿勢である。
それは、1929年神戸に立ち寄った藤田嗣治から、「君の絵は他の画家の影響がありすぎる」と指摘され、オリジナリティーの重要性を強く認識し、人のまねはしないという戒めを自分の哲学とした吉原の自分自身へのメッセージでもあった。
吉原治良は1924年関西学院高等商学部(神戸原田の森)に入学し、絵画クラブ「弦月会」に入会、絵画制作にのめりこんでいく。1930年代には二科展に出品。このころ日本の多くの画家たちがヨーロッパ前衛美術運動であったアンフォルメルの影響を受けて抽象的な絵画を制作しており、吉原も抽象表現を模索しつつ、さまざまな状況を越えて絵を描き続ける。
戦後間もない1948年に芦屋市美術協会が立ち上がり、吉原はその代表を務め、そのころから吉原の周りに若い作家たちが集まるようになってくる。また、1952年には須田剋太らと現代美術懇談会(ゲンビ)に関わり、ジャンルを超えたさまざまな前衛活動の表現者と交流が深められ、そうした中で感じた表現の可能性をより明確にしていくため、1954年「具体美術協会」を自ら立ち上げる。
「具体美術協会」として作品を発表するだけではなく、機関紙『具体』を発行し、活動の記録のみならず、メッセージを世界に発信し続けたことも特筆に価する。
そして、1972年67歳で亡くなるまで、日本の前衛美術の第一人者として活躍した。
具体美術協会のこと
「われわれにとって最も大切な事柄は現代の美術が厳しい現代を生きぬいて行く人々の最も解放された自由の場であり自由の場に於ける創造こそ人類の進展に寄与し得る事であると深く信じるからです。われわれはわれわれの精神が自由であるという証しを具体的に提示したいと念願しています。新鮮な感動をあらゆる造型の中に求めて止まないものです。」
(機関紙『具体』創刊号1955年1月より)
「具体美術は物質を変貌しない。具体美術は物質に生命を与えるものだ。具体美術は物質を偽らない。具体美術に於ては人間精神と物質とが対立したまま握手している。物質は精神に同化しない。精神は物質を従属させない。物質は物質のままでその特質を露呈したとき物語りをはじめ、絶叫さえする。物質を生かし切ることは精神を生かす方法だ。精神を高めることは物質を高き精神の場に導き入れることだ。」
(『具体美術宣言』1956年12月)
上記の宣言にも表されているように、人間のイメージや作為を超えたものをどうやって表現として定着させていくのか。表現手段としての物質を生かしきるような表現を「具体美術協会」のメンバーは模索していくこととなる。そんな中で、絵画の枠を越えたインスタレーション、パフォーマンスの先駆的な取り組みも生まれていくのである。
パリに住む堂本尚郎を介してその機関紙『具体』の内容に注目していたアンフォルメルの主唱者である美術評論家ミシェル・タピエは、1957年来日し吉原治良と具体のメンバーと交流し、「具体」の活動は、アメリカやヨーロッパにも紹介されていくこととなる。現在でも戦後の代表的な前衛活動として『GUTAI』は世界の美術史の文脈に位置づけられている。しかし、1972年吉原治良の死により「具体美術協会」は解散し、メンバーはそれぞれの道を歩んでいくこととなる。
今回の企画にあたって、当時「具体美術協会」の最も若いメンバーで、現在も世界で活躍されている松谷武判、堀尾貞治 両氏にご協力をいただいた。
松谷武判は、パリに渡り、ヨーロッパの空気の中で今も変容し続けている。堀尾貞治は神戸に住み、誰もやったことの無い表現に挑み続けている。現在、国際的に活躍する松谷武判、堀尾貞治 両氏の精神の中に、吉原治良の精神が脈々と受け継がれていることを改めて確信する。そして、その精神はこれからも受け継がれていくべきものである。
松谷武判とS.W.ヘイター
具体美術の洗礼を受けた松谷武判は、パリ留学で飛び込んだ版画工房「アトリエ17」の主宰者S.W.ヘイターに、吉原治良と通ずる芸術家のタイプを感じたのかもしれない。
S.W.ヘイターは「*一版多色刷り」という画期的な版画の刷りの技術を確立する。しかし60年代は表現の模索を続けており、その時期の作品は、銅版を酸で腐食させた凸凹を表現に結びつけたものなど、「具体」が「物質がその特質を露呈する」と宣言した思想とも重なって見えてくる。その後、身体の動きが銅版の上にラインとなって空間を生み出していく独特のスタイルを確立していく。
S.W.ヘイターは表現として自由なラインを導き出すために、身体をリラックスさせることを重要視した。自然、宇宙と一体化していくような純粋な身体活動によって表現が深化していくという考え方は、抽象表現に向かっていた吉原治良にも大きな影響を与えたと考えられる。
今回、吉原治良を通して、時空を越えた作品が結びつくのである。










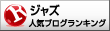










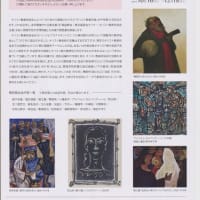






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます