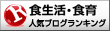◎ビタミンB1:Vitamin B1 びたみんびーわん
1910年に鈴木梅太郎によって発見され最初オリザニンOryzaninと命名した最も重要なビタミンで一番最初に見出され結晶化されています。
1880年に、脚気は麦飯で予防できることを高木兼寛が発見していました。さらに1897年には、白米で飼育された鶏は、人の脚気に似た多発性神経炎を起こしこれが米糠で回復したことをエイクマンEijkmanが観察していました。
1911年に同様の有効物質がフンクFunkにより酵母から見出しVita-amineとしました。
欠乏することによって動物の成長が不能となり、倦怠感(けんたいかん)から、疲労しやすく、食欲不振となり、やがて手足に浮腫(むく)みを生じ心悸亢進(しんきこうしん)もみられます。弱塩基性化合物でピリミジン核Pyrimidineとチアゾール核ThazoleがCH2(メチレン基)を介して結合した形をして遊離の状態では結晶しにくく、通常特異臭のある塩酸塩として分離されています。神経炎Neuritis(ノイリーチス)を防ぐという生理作用から抗多発性神経炎という意味でアノイリンAneurinともいい、イオウ(S)を含むアミンAmineということからサイアミンThiamineともいわれますが、チアミンThiamineという名称が国際的化学名として採用です。
硫黄(S)は、蛋白質を保護し酸化されて硫酸塩となって体内の解毒作用を行い尿中に排出しますが、この排出量は代謝した蛋白質量に関係しています。一部は、炭水化物、脂質とも結合してビタミンB1などの構成要素となり免疫力強化に働いています。多くは他の元素と結合していないものがミネラルといわれていますが、硫黄は例外でミネラルのひとつとして存在しています。
アミンは、NH3(アンモニア)の(H)水素原子をR(炭化水素基)で他のものに置き換えた化合物の総称です。アミノ酸より脱炭酸作用(アミノ酸デカルボキシラーゼ)により生成されるアドレナリン、セロトニン、コリン、ドーパミン、チラミンなどがあります。
ビタミンB1塩酸塩は水に溶けやすく、分解しやすい欠点があることから食品強化などの必要から各種の塩類が合成され用いられています。硝酸塩は、水に難溶(25℃ 2.7g/100mL)、ロダン塩(37℃ 0.9g/100mL)で安定性があります。DPT:Di-BenzoylThiamin:ジベンゾイルサイアミン(25℃ 0.001g/100mL)の糠臭さがなく吸収がよいといいます。吸収を良くする物質としてアリチアミンがよく知られていますが、他にも製剤としてTPA(Thiaminepropyl disulfide)などの各種の誘導体があります。
通常は水温20℃、1mLに1g溶ける水溶性ですが、アルコールには難溶です。弱酸性でPH5以下では熱にかなり安定していますが、中性、アルカリ性では熱すると容易に分解し、水洗い、ボイル、加工調理によって半分ほども失われます。
ビタミンB1をアルカリ性で、赤血塩、プロムシアンなどで、ゆるやかに酸化させるとチオクロームThiochromeとなり、これは強い紫色の蛍光を呈する反応を示し定量に使われています。
ビタミンB1(化学名チアミンThiamine、アノイリンAneurin)は、腸からの吸収が一定(5mg~10mg程度)になると尿中に排出してしまい常に補給が必要なビタミンです。代謝の盛んな妊婦、授乳婦、肉体労働者、スポーツをする人では必要量が高くなります。人が摂取している熱量素は、炭水化物が最も多く炭水化物は、体内で多くがグルコース、グルコースリン酸となって分解されエネルギー源となっているのです。その分解には、ビタミンB1が不可欠で、不足すると炭水化物の分解が進まないこととなりエネルギーを得ることができません。エネルギーの要求量が多い時、炭水化物の摂取量が多い時には、ビタミンB1の要求量も増大します。
糖質の代謝には最も重要で動物体内にはB1ピロリン酸エステル(ピロリン酸塩)として存在しカルボキシラーゼの助酵素コカルボキシラーゼCocarboxylaseという補酵素として作用し存在しています。糖質が体内で分解する途中でピルビン酸が生じ、これをさらに分解するには、カルボキシラーゼ、その他の酵素が働くことが必要です。ビタミンB1が不足するとコカルボキシラーゼが不足してピルビン酸Pyruvicacid が分解されず、そのままか、または乳酸となって組織に蓄積し、これが脚気の原因となっているのです。
また糖の分解が進み、クレーブスのクエン酸サイクル(TCAサイクル)に入ってからはα-ケトグルタール酸(α-ketogurlutaric acid)の脱炭酸反応が順調に進行しなくなりこれらの酸が蓄積して諸症状がでてくるものと考えられています。
ピルビン酸は、糖が分解する過程で生ずる物質で焦性(しょうせい)ブドウ酸ともいい有機化合物でケト酸に属します。アルコール発酵と解糖作用はピルビン酸に至るまでの反応は同一となります。ここから先は発酵ではピルビン酸はカルボキシラーゼによってアセトアルデヒドを生じ、これが還元されアルコールになります。解糖では筋肉中にはカルボキシラーゼが存在しないので乳酸脱水酵の働きによって乳酸を生じます。糖の代謝はピルビン酸よりピルビン酸脱炭酸酵素の働きで循環経路(TCAサイクル)に入り最終的に二酸化炭素と水とに完全に酸化され全エネルギーが放出します。
ピルビン酸脱炭酸酵素が働くためには、リポ酸、アセチル化反応を行なう補酵素コエンザイムA(Coenzyme A:CoA)の構成成分となるパントテン酸、ニコチン酸、ビタミンB2なども必要となります。
α-ケトグルタール酸にα-ケトグルタール酸脱炭酸酵素が働いてコハク酸・CoA+CO2(二酸化炭素)となりますが、TCAサイクルでの反応ですので炭水化物(糖質)のみならず脂肪、アミノ酸の体内での酸化分解にも関与していることになります。
血液の基準値は、35~76ng( 1ng:1ナノグラムは10億[1,000,000,000]分の1g)/ml、尿中、血中ピルビン酸(B1の欠乏により増加)の定量によって欠乏の有無を判定します。ビタミンB1の大量投与(DBT〈難溶性:ポリライスなど〉により神経系疾患、リウマチ、心不全、腎疾患に有効との報告があります。同時にアミノ酸酸化酵素(ビタミンB2含有)活性を阻害し他のビタミンの作用を阻害することも考えられています。薬理的に5~100mgとして成長促進、糖代謝重要な働きをしており皮膚・粘膜の再生に役立たせています。活性型のフルスルチアミンには苦味がありますが即効性が強いといわれます。不足してくると 倦怠感、食欲不振、多発性神経炎(脚気心悸亢進)等を起こすようになります。
アノイリナーゼAneurinase(魚介類の内臓・しだ類に多い)の酵素によってB1の分解がされ効力を失います。チアミナーゼThiaminaseともいわれています。鯉の内臓に多く赤貝を除いた多くの貝類に含むものは加熱によって破壊され特にアサリに多く生食はしません。カキの含量は少なく生食しています。
山菜(わらび、ぜんまい)のシダ類は、アノイリナーゼの他に耐熱性のビタミンB1分解因子を共存して含みます。アノイリナーゼが人の腸に存在することもありビタミンB1欠乏症になりやすく日本人で1~3%にアノイリナーゼを生成する菌をもっているといわれます。このような時には、ビタミンB1がかなり腸内で破壊をされています。
にんにくなどの辛味の成分アリシンがビタミンB1の吸収をよくします。
ビタミンB1とニンニクやねぎ類などに含まれているアリシンが結びついて生成されるアリチアミンは活性型ビタミンB1ともいわれています。ビタミンB1のチアゾール核が開いて、これにニンニクなどの香気成分アリシンAllicinと反応しアリチアミンAllithiaminとなります。
ビタミンB1と違い体外に排出されにくく、アリチアミンは長く体内に留まり血中のB1濃度も高まり吸収効率も高くなります。アノイリナーゼによっても破壊を受けません。水に溶けにくく、熱にも強い脂溶性物質で調理による損失も少ない傾向です。アリチアミンは体内のビタミンB6と結合すると糖質の代謝に関係するインスリンの分泌を助ける働きをして血糖値を下げます。
ビタミンB1は、おもに糖質代謝に関係し、成人の必要量を2000kcalとすると、実験により1000kcalあたり0.2~0.3mgで欠乏症状が出現しないことから安全率を考慮し2倍し0.45mg/1000kcalを推奨量算出の元にし定めています。ビタミンB群は、一般に腸内細菌によっても合成、ビタミンB1はアノイリナーゼによって分解されることもありこのことから2000kcalで1.0mg程度としています。
また尿排泄剤を服用でビタミンB1が十分に機能しないうち尿中に排泄されやすいといいます。
栄養機能食品としての上限が25mg、下限0.3mgとし示されています。多く含まれる食品は、穀類、豆類、肉類、胚芽、酵母などで成人の推奨量は1.4~ 0.8mg/1日、上限量は特に定められていません。
100g中でインスタントラーメン1.46~0.21mg、鰻蒲焼0.75mg、たらこ生0.71mg、豚肩ロース0.63mg、炒り松の実0.61mg、カシューナッツ0.54mg、炒り胡麻0.49mg、ライ麦全粒粉0.47mg、炒りピスタチオ0.43mg、玄米0.41mg、干しソバ0.37mg、炒りくるみ、0.26mg、枝豆0.24mg、アーモンド乾0.24mg、茹でぎんなん0.24mg、炒りラッカセイ、0.23mg、国産茹で大豆0.22mg、炒りマガダミアンナッツ0.19mg、茹で栗0.17mg、玄米飯0.16mg、ライ麦パン0.16mg、茹で小豆0.15mg、茹で栗0.17mg、かずのこ生0.15mg・塩蔵水戻しTr、茹で芽きゃべつ、0.13mg、やつがしら0.13mg、さつま芋0.11mg、みかん0.10mg、椎茸0.10mg、じゃが芋0.09mg、胚芽米飯0.08mg、うるめ鰯0.08mg、食パン0.07mg、木綿豆腐0.07mg、納豆0.07mg、精白米0.08mg、鶏卵0.06mg、牛乳0.04mg、ヨーグルト0.04mg、精白米飯0.02mgを含みます。
ビタミンB1は、不足しやすいビタミンとして、強化米などが使用されることがありますが、ビタミンB1を効率よく働かせるためには、栄養バランスのとれた食事とすることが求められます。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。