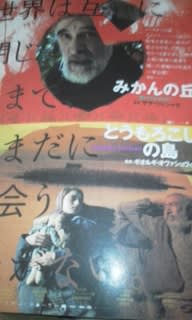 午後は渋谷から神保町へ移動。さらにグルジア(今はジョージアか、あるいは正しくサカルトヴェロ?)映画を2本観る。この後観賞する作品と共に、ジョージア第二世代と呼べる監督。つまりテンギス・アブラゼ監督(懺悔)やギオルギ・シェンゲラヤ監督(放浪の画家ピロスマニ)の後、アブハジア紛争の後に登場した監督たちである。
午後は渋谷から神保町へ移動。さらにグルジア(今はジョージアか、あるいは正しくサカルトヴェロ?)映画を2本観る。この後観賞する作品と共に、ジョージア第二世代と呼べる監督。つまりテンギス・アブラゼ監督(懺悔)やギオルギ・シェンゲラヤ監督(放浪の画家ピロスマニ)の後、アブハジア紛争の後に登場した監督たちである。そのアブハジア紛争の時代を描いた作品。山奥でみかん作りをする男とそのみかんを運搬する木箱を作る男、2人のエストニア人が敵対するチェチェン人とジョージア人の兵士(二人とも重症)をかくまう物語。民族対立が複雑に絡み合うジョージア、エストニア人と言う移民が中立者として両者を和解させる。戦争なんて昔話になってしまったこの平和な国日本で、ジョージア人、チェチェン人の心情を丁寧に描いていて、完全に同じ目線で物語に入り込める。だからこそ、本当にこの人里離れた場所で争いが始まり、犠牲者が出た時の悲しみが深く、とてもハンカチなしでは見られない傑作。後半、一つ屋根の下で治療を共にする敵同士が和解するが、最後にやはり悲しい出来事の犠牲になって行く。
敵同士の会話は共通語としてロシア語が話されるので部分的に理解できるが、エストニア人同士の会話はさすがに何を言ってるのか全く分からない。と言うか、部分的であれ、言葉が分かるとこんなにも入り込めるものなのか、と言うことを実感する。言葉は大事。
敵同士、憎しみあってはいるが、どうやらこうした国ではお金のために自ら志願する。いわゆる傭兵が多いようだ。日本だと強制的に赤紙で徴兵される徴兵制を連想してしまうが、こういう紛争地域では志願兵ばかりなので皆勇ましい。そして、その勇ましさこそが逆に、イヴォの家の中では停戦せよ、と言う約束を守る男気につながり、2人は和解する。平和に必要なのは戦争を怖がる弱気よりも約束を守る勇気なんだな、と思わせる。
とにかく、つい最近まで紛争の絶えなかった地域からの映画はその経験ゆえに重く問いかけるものがあり、味わい深い傑作になっている。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます