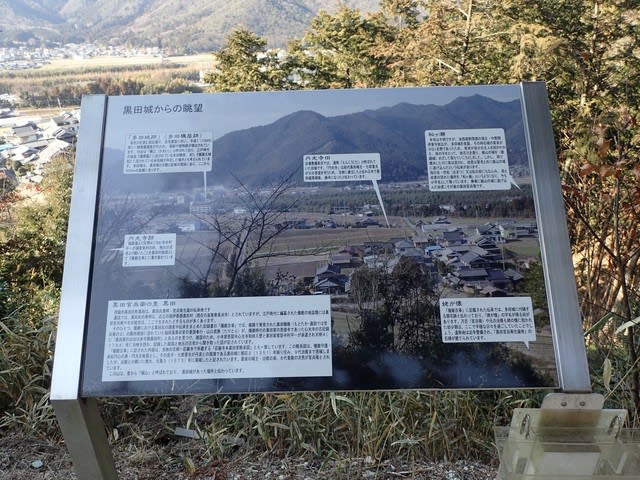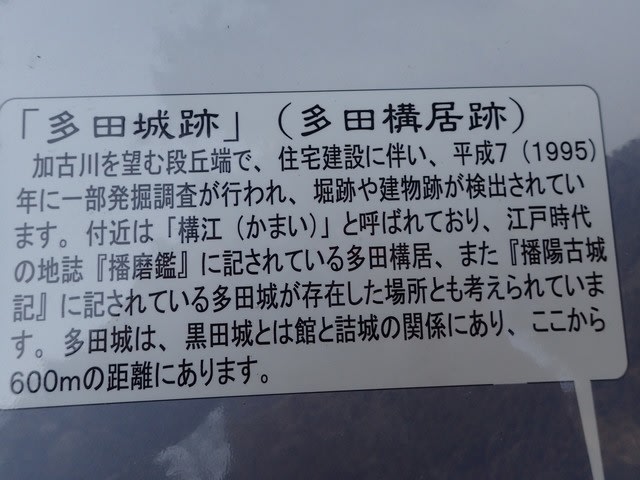2017年10月28日(土)曇り⇒雨

東西を山に囲まれた利根・沼田周辺は、鎌倉時代から戦国時代にかけて沼田氏が支配していたが、戦国時代の天文の頃、小田原の北条氏が利根に進行し利根沼田一帯は北条氏の支配となった。
永禄3年(1560)越後の上杉謙信が三国峠を越えて進攻し、山城や砦を攻略し、北条氏の城となっていた沼田城を手中にし、天正6年(1578)上杉謙信が春日山城内で急死すると、北条氏が沼田に進攻し、再び北条氏の支配となった。
武田勝頼の命により真田昌幸が吾妻の岩櫃城、利根に入って名胡桃城を始め山城や砦を攻略し天正8年沼田城を調略した。
その後、真田氏と北条氏の間で攻防が続くが、関白豊臣秀吉の調停で東と赤谷川の左岸を北条領、西(名胡桃城)を真田領とする裁定を下したが、北条氏の沼田城代となった猪俣邦憲が調略により名胡桃城(城将の真田昌幸家臣鈴木主水は割腹)を不法に攻略してしまった。
この名胡桃事件に激怒した秀吉は、大名間の私闘を禁じた惣無事令に反したとして、天正17年11月北条氏に対して戦いを宣し(宣戦布告)、全国の大名に命じて小田原攻めを開始し、天正18年小田原の役が勃発した。 名胡桃城は、北条氏の滅亡後、役割を終え廃城となった。
史料によれば、天正7年利根に進行した真田昌幸によって現在の城址に築城されたとされています。
名称・・・・名胡桃城跡(なぐるみじょうせき)
所在・・・・群馬県利根郡みなかみ町下津
形態・・・・連郭式の山城
築城・・・・室町時代(伝承)
築主・・・・沼田氏
主な城主・・沼田、北條、真田、
遺構・・・・遺構は馬出しから三郭・二郭・本郭・ささ郭と主要な郭が直に並ぶ連郭式の山城
土塁址・三日月堀・虎口・通路・門礎石址・掘立柱建物址
駐車場・・・・無料(国道17号線から名胡桃城址前交差点より入る。名胡桃城址の般若郭に位置する場所)


























名胡桃城跡案内所


東西を山に囲まれた利根・沼田周辺は、鎌倉時代から戦国時代にかけて沼田氏が支配していたが、戦国時代の天文の頃、小田原の北条氏が利根に進行し利根沼田一帯は北条氏の支配となった。
永禄3年(1560)越後の上杉謙信が三国峠を越えて進攻し、山城や砦を攻略し、北条氏の城となっていた沼田城を手中にし、天正6年(1578)上杉謙信が春日山城内で急死すると、北条氏が沼田に進攻し、再び北条氏の支配となった。
武田勝頼の命により真田昌幸が吾妻の岩櫃城、利根に入って名胡桃城を始め山城や砦を攻略し天正8年沼田城を調略した。
その後、真田氏と北条氏の間で攻防が続くが、関白豊臣秀吉の調停で東と赤谷川の左岸を北条領、西(名胡桃城)を真田領とする裁定を下したが、北条氏の沼田城代となった猪俣邦憲が調略により名胡桃城(城将の真田昌幸家臣鈴木主水は割腹)を不法に攻略してしまった。
この名胡桃事件に激怒した秀吉は、大名間の私闘を禁じた惣無事令に反したとして、天正17年11月北条氏に対して戦いを宣し(宣戦布告)、全国の大名に命じて小田原攻めを開始し、天正18年小田原の役が勃発した。 名胡桃城は、北条氏の滅亡後、役割を終え廃城となった。
史料によれば、天正7年利根に進行した真田昌幸によって現在の城址に築城されたとされています。
名称・・・・名胡桃城跡(なぐるみじょうせき)
所在・・・・群馬県利根郡みなかみ町下津
形態・・・・連郭式の山城
築城・・・・室町時代(伝承)
築主・・・・沼田氏
主な城主・・沼田、北條、真田、
遺構・・・・遺構は馬出しから三郭・二郭・本郭・ささ郭と主要な郭が直に並ぶ連郭式の山城
土塁址・三日月堀・虎口・通路・門礎石址・掘立柱建物址
駐車場・・・・無料(国道17号線から名胡桃城址前交差点より入る。名胡桃城址の般若郭に位置する場所)


























名胡桃城跡案内所