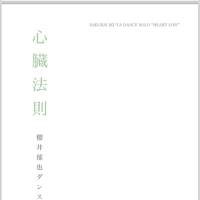クリスチャン・ウォルフという作曲家が、こんなにおもしろい存在とは知らなかった。やはりナマで聴いてみるものだ。
音楽家の足立智美さんがプロデュースするチクルス(1/18アサヒスクエア)に出かけたのだが、とても得した気分だ。
やはり演奏会での発見から縁がつながり連動するようになった鈴木悦久さんが演奏するというので、行った。
足立さんという存在も実に気になっていたし、それから今、僕は久々にジョン・ケージを踊りにしようと譜読みなど始めたところで、ケージと関わりの深いウォルフを体験しておきたかったから、いろんな偶然が重なったのだった。(偶然と言えば、美術の中ザワヒデキさんと初対面。少しだけ踊りの話、えらく気の利いた方で、ちょっとした一言にヒントいっぱいなのだ。この場を借りて感謝!)
さて、ウォルフ体験は一曲目から爽快だ。超シンプルな音の響きから演奏者の微妙なバランス感覚が空間を明るく照らす。奏でることと、聴くこと。そのあわいに「音楽」がうまれる。時が進むにつれ、作曲者と演奏者の、演奏者と聴衆の、演奏者と演奏者の、キャッチボールのような関わりが立体化されてゆく。コンサート、ワークショップ、祭り・・・。気がつくと、音楽と僕らの色んな関係をさらりと一巡している。そして最後に輪になった演奏家によるユニゾン。制度的な仕組みを外したユニゾン(普通、音楽でもダンスでも「揃える」ということになっちゃっているが、もともとは「響き合う」という意味だ)が、むつかしおもしろく、ゆえに、優しく響く。指揮者統制者がいないところで響き合おうとする、大事な事、素敵な事。
しかし、何よりも良かったのは、音と音の隙き間だった。余韻、間、沈黙とか。
さすがケージの弟子。だけど、ケージ独特の、あの「間」感覚とはちょっとちがう。
僕は、ケージの「間」から、求心的な沈黙や、張りつめた透明、を感じる。対して、ウォルフのそれは、ユーモラスな「待ち」の「呼吸」であり、音の「バウンス」であり、さまざまなノイズさえ許容する「遊びの空間」なんだと感じた。
このような感覚の違いはCDなどでは感じにくい。CDは音が在ることと無いことの2分法による感受だけれど、生演奏は状況というノイズが入る。演奏者にとって偶発的・想定外である音の到来はもちろん、聴衆である僕ら自身の身体がたてる音やイスや衣服がたてるかすかな音。息の音だって。それがまた、いい具合に静寂と溶け合うから、知覚も大きく開かれてゆく。皮肉な事にノイズミュージックを称する大部分は意図された音が多すぎて実際のノイズを許してくれないのだけれど・・・。
プロデュースの足立さんがパンフに詳しく書いておられたが、ケージは演奏について厳格な指示を与えるが、その弟子であるウォルフは即興や自由な連鎖に音楽をゆだねようとするそうだ。まったく勝手な直感だけど、ケージが作曲を内界と外界の交信システムであろうとするのに対し、ウォルフは作曲を新たな縁をつむぐ方法であろうとしたのだろうか、なんて想像してみた。どうだったんだろう、興味あるので、ちょっと調べてみようかな。ともかくウォルフの音楽はいろんな感性にジョイントしながら、その場ならではの響きを生み出してゆくものなんだろう。コンサートではそのことを良く感じとることができた。聴きながら、これはウォルフの作品でありながら、いま集う皆の作品でもあるのだと思った。人や場所や時代が変われば、音も変わるにちがいない。間章さんなんかがプロデュースして60年代あたりの新宿でやったらどんな音になったのかしら?そんなことまで想像しながら聴くことができた。曲の選び方や進行の流れが実に親切だったからにちがいない。同じ音楽を聴きながら、いろんな人がいろんな想像を膨らませていたのだと思う。ともかく、いい時間をもらえた。足立智美さんという人は、聴衆と音楽の接点をとても大事にしてくれる人なんだと思った。足立さん、ありがとうございます!
PS:この会に誘ってくれた鈴木氏は、石による音楽を演奏したが、強烈な集中力が響いて惚れ直した。機をみてまた書こうと思う。
音楽家の足立智美さんがプロデュースするチクルス(1/18アサヒスクエア)に出かけたのだが、とても得した気分だ。
やはり演奏会での発見から縁がつながり連動するようになった鈴木悦久さんが演奏するというので、行った。
足立さんという存在も実に気になっていたし、それから今、僕は久々にジョン・ケージを踊りにしようと譜読みなど始めたところで、ケージと関わりの深いウォルフを体験しておきたかったから、いろんな偶然が重なったのだった。(偶然と言えば、美術の中ザワヒデキさんと初対面。少しだけ踊りの話、えらく気の利いた方で、ちょっとした一言にヒントいっぱいなのだ。この場を借りて感謝!)
さて、ウォルフ体験は一曲目から爽快だ。超シンプルな音の響きから演奏者の微妙なバランス感覚が空間を明るく照らす。奏でることと、聴くこと。そのあわいに「音楽」がうまれる。時が進むにつれ、作曲者と演奏者の、演奏者と聴衆の、演奏者と演奏者の、キャッチボールのような関わりが立体化されてゆく。コンサート、ワークショップ、祭り・・・。気がつくと、音楽と僕らの色んな関係をさらりと一巡している。そして最後に輪になった演奏家によるユニゾン。制度的な仕組みを外したユニゾン(普通、音楽でもダンスでも「揃える」ということになっちゃっているが、もともとは「響き合う」という意味だ)が、むつかしおもしろく、ゆえに、優しく響く。指揮者統制者がいないところで響き合おうとする、大事な事、素敵な事。
しかし、何よりも良かったのは、音と音の隙き間だった。余韻、間、沈黙とか。
さすがケージの弟子。だけど、ケージ独特の、あの「間」感覚とはちょっとちがう。
僕は、ケージの「間」から、求心的な沈黙や、張りつめた透明、を感じる。対して、ウォルフのそれは、ユーモラスな「待ち」の「呼吸」であり、音の「バウンス」であり、さまざまなノイズさえ許容する「遊びの空間」なんだと感じた。
このような感覚の違いはCDなどでは感じにくい。CDは音が在ることと無いことの2分法による感受だけれど、生演奏は状況というノイズが入る。演奏者にとって偶発的・想定外である音の到来はもちろん、聴衆である僕ら自身の身体がたてる音やイスや衣服がたてるかすかな音。息の音だって。それがまた、いい具合に静寂と溶け合うから、知覚も大きく開かれてゆく。皮肉な事にノイズミュージックを称する大部分は意図された音が多すぎて実際のノイズを許してくれないのだけれど・・・。
プロデュースの足立さんがパンフに詳しく書いておられたが、ケージは演奏について厳格な指示を与えるが、その弟子であるウォルフは即興や自由な連鎖に音楽をゆだねようとするそうだ。まったく勝手な直感だけど、ケージが作曲を内界と外界の交信システムであろうとするのに対し、ウォルフは作曲を新たな縁をつむぐ方法であろうとしたのだろうか、なんて想像してみた。どうだったんだろう、興味あるので、ちょっと調べてみようかな。ともかくウォルフの音楽はいろんな感性にジョイントしながら、その場ならではの響きを生み出してゆくものなんだろう。コンサートではそのことを良く感じとることができた。聴きながら、これはウォルフの作品でありながら、いま集う皆の作品でもあるのだと思った。人や場所や時代が変われば、音も変わるにちがいない。間章さんなんかがプロデュースして60年代あたりの新宿でやったらどんな音になったのかしら?そんなことまで想像しながら聴くことができた。曲の選び方や進行の流れが実に親切だったからにちがいない。同じ音楽を聴きながら、いろんな人がいろんな想像を膨らませていたのだと思う。ともかく、いい時間をもらえた。足立智美さんという人は、聴衆と音楽の接点をとても大事にしてくれる人なんだと思った。足立さん、ありがとうございます!
PS:この会に誘ってくれた鈴木氏は、石による音楽を演奏したが、強烈な集中力が響いて惚れ直した。機をみてまた書こうと思う。