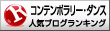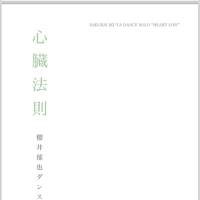来年3月に来日するスティーブ・ライヒの曲を幾つか聴き返した。
この人の音楽に直接に関わった踊りといえば、ベルギーの振付家アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの「レイン」が僕には特に素敵に思い出すが、同作に重なっていたのは余りにも有名な「18人の音楽家のための音楽」だ。周りにもクラスにも好きな人がすこぶる多い。
木琴の繰り返す粒立ちの良い音に呼吸のようなヴォカリゼーションが重なり幾重にも音の層が重なってゆく有様は、鼓動や疾走を促すように身体に直接響いてくる。
「18人の...」は、ミニマルミュージックの代表とも言われるが、一見単純で淡々としたこの響きの素晴らしさは、生身の演奏家が体をつかって息を合わせて演奏しているところだと思う。フェーズを用いる初期の作品を始め機械的な演奏を伴う曲も多数あるが、ここでは18名もの人間の手と呼吸によるアンサンブルがやはり凄い。この緻密さの中に独特の温かみと求心力と解放感が渾然とした雰囲気は、機械的な作業では出ないと思う。
この音楽を聴いていると、なんだか大きな樹木の下にいるような気分になる。淡々と、軽く穏やかに続いてゆく音は、時に樹の枝や葉から滴り落ちる雨のように、いつしか木漏れ日と影のように、気がつくと微風のざわめきのように、自然な変化を走ってゆく。
この音楽を初めて聴いたのは大学に入ってすぐだったが、それは次々に新しい思潮が紹介され、もしかしたら20世紀がやっと明るみに向かうのではないか、いや、そうありたいという気運が高まってゆく時期でもあった。
しかし、その息の波に立ちはだかる巨大な壁が見えてくるのに時間はかからなかった。
同じ作曲家の足跡を辿りながら、そのことを考えてしまった。
「WTC9/11」という音楽がある。2001年9月11日のニューヨーク、あの日のことを音と体験者の声で綴った作品だ。
9.11。それは「現在」が露わになった日だった。
そして個人的には白紙還元=タブラ・ラサという脳の状態を初めて味わった長い夜だった。
あの日、白くなった脳ミソが何を何故いかに思ったのか、未だ整理などつくはずはないが、急速に
それまでの人生の過ごし方や踊りや人との関わりかたにメスを入れざるを得ない気持ちになったのは確かで、それは僕自身の21世紀の始まりでもあり、結果、しばらくは独舞に専念し、一から立ち方をやり直してみようと心を決めた日になったのだが、そのままの試行錯誤のなかで3.11をも経験し、さらに「今」を迎えている、、、。
「WTC9/11」は先の音楽とは明らかに別の響きに満たされていて、身体はその衝撃的な音の連続を受け止め切れない。胸に手を触れ膝を地に折る。例えばそのような仕方のほかに、どうにも出来ないような内省に向かわざるを得ない響きを、この音楽は響かせる。
ライヒはこの曲に関するコメントのなかで、リサイト、という言葉を投げた。リサイトとは繰り返し唱えること。演奏会を「リサイタル」と言う事もあるが、絶えざる言葉、声を絶やさぬこと、という意味が根にあるのだとライヒはいう。僕にはその言葉は自分自身の踊りにも深く結びついて聞こえて仕方がない。
この曲のほかににも近年の作品を聴くと、言葉の作用が非常に深い。
言葉を絶やさぬように、声を絶やさぬように、という気持ちが沈黙のなかにまで浸透したカタチとして「踊り」が湧いてあるのだとすれば、僕は沈黙に込めざるを得ない声や言葉を孕み得ているのだろうか。
身体が現在この現実に結びつこうとするとき、一体どのような行為が誠実なのだろうか。
と、この音楽の響きのなかで考えさせられる。
ライヒは僕にとって解放を促した作曲家であると同時に、自省を促す作曲家でもある。
この人の音楽に直接に関わった踊りといえば、ベルギーの振付家アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの「レイン」が僕には特に素敵に思い出すが、同作に重なっていたのは余りにも有名な「18人の音楽家のための音楽」だ。周りにもクラスにも好きな人がすこぶる多い。
木琴の繰り返す粒立ちの良い音に呼吸のようなヴォカリゼーションが重なり幾重にも音の層が重なってゆく有様は、鼓動や疾走を促すように身体に直接響いてくる。
「18人の...」は、ミニマルミュージックの代表とも言われるが、一見単純で淡々としたこの響きの素晴らしさは、生身の演奏家が体をつかって息を合わせて演奏しているところだと思う。フェーズを用いる初期の作品を始め機械的な演奏を伴う曲も多数あるが、ここでは18名もの人間の手と呼吸によるアンサンブルがやはり凄い。この緻密さの中に独特の温かみと求心力と解放感が渾然とした雰囲気は、機械的な作業では出ないと思う。
この音楽を聴いていると、なんだか大きな樹木の下にいるような気分になる。淡々と、軽く穏やかに続いてゆく音は、時に樹の枝や葉から滴り落ちる雨のように、いつしか木漏れ日と影のように、気がつくと微風のざわめきのように、自然な変化を走ってゆく。
この音楽を初めて聴いたのは大学に入ってすぐだったが、それは次々に新しい思潮が紹介され、もしかしたら20世紀がやっと明るみに向かうのではないか、いや、そうありたいという気運が高まってゆく時期でもあった。
しかし、その息の波に立ちはだかる巨大な壁が見えてくるのに時間はかからなかった。
同じ作曲家の足跡を辿りながら、そのことを考えてしまった。
「WTC9/11」という音楽がある。2001年9月11日のニューヨーク、あの日のことを音と体験者の声で綴った作品だ。
9.11。それは「現在」が露わになった日だった。
そして個人的には白紙還元=タブラ・ラサという脳の状態を初めて味わった長い夜だった。
あの日、白くなった脳ミソが何を何故いかに思ったのか、未だ整理などつくはずはないが、急速に
それまでの人生の過ごし方や踊りや人との関わりかたにメスを入れざるを得ない気持ちになったのは確かで、それは僕自身の21世紀の始まりでもあり、結果、しばらくは独舞に専念し、一から立ち方をやり直してみようと心を決めた日になったのだが、そのままの試行錯誤のなかで3.11をも経験し、さらに「今」を迎えている、、、。
「WTC9/11」は先の音楽とは明らかに別の響きに満たされていて、身体はその衝撃的な音の連続を受け止め切れない。胸に手を触れ膝を地に折る。例えばそのような仕方のほかに、どうにも出来ないような内省に向かわざるを得ない響きを、この音楽は響かせる。
ライヒはこの曲に関するコメントのなかで、リサイト、という言葉を投げた。リサイトとは繰り返し唱えること。演奏会を「リサイタル」と言う事もあるが、絶えざる言葉、声を絶やさぬこと、という意味が根にあるのだとライヒはいう。僕にはその言葉は自分自身の踊りにも深く結びついて聞こえて仕方がない。
この曲のほかににも近年の作品を聴くと、言葉の作用が非常に深い。
言葉を絶やさぬように、声を絶やさぬように、という気持ちが沈黙のなかにまで浸透したカタチとして「踊り」が湧いてあるのだとすれば、僕は沈黙に込めざるを得ない声や言葉を孕み得ているのだろうか。
身体が現在この現実に結びつこうとするとき、一体どのような行為が誠実なのだろうか。
と、この音楽の響きのなかで考えさせられる。
ライヒは僕にとって解放を促した作曲家であると同時に、自省を促す作曲家でもある。