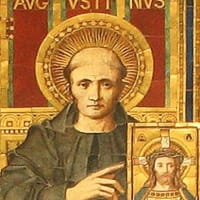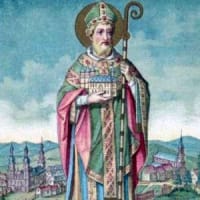『古代ヨーロッパ 世界の歴史2』社会思想社、1974年
6 ギリシアを二分した大戦争 ―ペロポネソス戦争―
3 ペロポネソス戦争
アテネの支配が強引だったため、デロス同盟諸市のなかには不満を持つものが、しだいにふえていった。他方、アテネが急に繁栄して、ギリシア第一の強国にのしあがってきたことに、スパルタは恐れを感じ、またしっとを感じていた。
スパルタは、デロス同盟に加わっていないペロポネソス半島の諸ポリスを率いて、ペロポネソス同盟をつくっていた。
どういう事情からか、その原因はよくわからないが、アテネはペロポネソス同盟に属しているメガラとデロス同盟諸市の貿易を禁止し、そのうえ毎年メガラを攻める決議をした。
また同じペロポネソス同盟に属していたコリントは、商業貿易で栄えていた町だったが、アテネの商業貿易の発展によって、打撃をうけた。そのうえコリントはコルキュラ島をめぐって、アテネと衝突した。
コルキュラはコリントの植民市だった。
コルキュラとコリントは共同で植民し、エピダムノスという植民市をつくった。
このエピダムノスで内乱が起こり、これがきっかけとなって、コリントとコルキュラのあいだに戦争が起こった。
両市ともアテネに助けを求めた。
アテネとコリントは、商業貿易のうえでそのころ敵対していたので、アテネはコルキュラを助けた。
こうしてアテネはコリントと戦うことになり、コリントの力をそぐために、コリントの植民市ボディダイアに城壁をこわすことを命じた。
ボディダイアはデロス同盟に加入していたが、この横暴な命令には従えないと、アテネに謀反し、コリントはボディダイアを助けた。
コリン卜、ボディダイア、メガラ、それにアイギナなどは、スパルタにアテネの不法を訴えた。
スパルタはペロポネソス同盟諸市を集めて、会議を開いた。スパルタはそのころアテネと「三十年の和約」を結んでいたので、これらの諸市をむしろなだめようとしたが、諸市の不満は強く、つき上げられる形で、アテネとの戦争を開始することになってしまった。
スパルタ王アルキダモスは、紀元前四三一年の夏、アテネ地方に攻め入った。
全ギリシアのポリスは、アテネとスパルタのどちら側かに味方し、ギリシアは二つの陣営にわかれて、二十七年間におよぶ大戦争を戦った。
これを「ペロポネソス戦争」という。
アテネは民主政体の国だったが、スパルタは寡頭(かとう)政体の国だった。
アテネに味方したポリスの多くは民主政体であり、スパルタに味方したポリスの多くは寡頭政体だった。
したがってペロポネソス戦争は民主政と寡頭政の戦いでもあった。
民主政のポリスのなかにも、寡頭的な政治を良しとする者もおり、寡頭政のポリスのなかにも民主主義者はいた。
これらの人々は、機会があれば政権を握っている者を倒して、自分らが政権を握りたいと考えていた。
つまり戦争はポリスとポリスどうしで戦われていたと同時に、ポリスの内部でも戦われていたわけであった。
当時アテネを支配していたのは、ペリクレス(紀元前四九五年ごろ~四二九年)だった。
彼はダモン(ダモニデスともいわれる)という先生に音楽を学んだが、ダモンは本当はソフィストだったと伝えられている。
ペリクレスはまた哲学者のアナクサゴラス(紀元前五〇〇年ごろ~四二八年ごろ)にも学んだ。
そして合理的に考えることを学んだ。
ペリクレスはデロス同盟の基金を使って、パルテノン神殿をはじめ、立派な神殿をアテネ市にいくつも建てた。
同盟の金をこのように使うことは、同盟市にアテネ市非難の口実を与えることになると、ペリクレスを攻撃する人々がいた。
するとペリクレスは、「同盟市は国防のために金を出しているのだが、アテネはよく防衛の責任は果たしている。
商人は商品を売ってうけ取った金は何に使ってもよいように、防衛をしてやれば、そのかわりにうけとった金を何に使おうと自由だ」といったという。
ペリクレスはたいへん弁舌がうまく、彼の話し方は人の心を強くうったので、彼の弁舌は「雷のようだ」といわれた。
スパルタのアルキダモス王が、アテネ人のある人に、
「あなたとペリクレスが相撲をとると、どちらが勝つか」 ときいたところ、
「それはペリクレスにきまっています。たとえ私が彼を投げとばしても、彼は自分が勝つたといいはるでしょう。そうすれば、私たちの勝負を見ていた人も、自分たちの目よりも、彼の言葉を信じるにちがいありませんから」
と答えたという。
こういう逸話類は、彼がソフィストの影響をうけていたことを思わせる。
ペロポネソス戦争がはじまったとき、たまたま日蝕が起こった。
アテネの兵士たちは、これを不吉の前兆だといって恐れ、さわいだ。
ペリクレスは着ていたマントをぬいで、ある兵士の目の前にこれを下げ、またそれをどけていった。
「お前はこれを不吉の前兆だと思うかね」。兵士は「いいえ」と答えた。
ペリクレスは「日蝕だって同じことなのだ。日蝕は、マントより大きなものが太陽をさえぎったにすぎないのだから」
といって、兵士らを安心させたという。
彼はアナクサゴラスのような自然哲学者に学んでいたために、このような説明ができたのだった。
ペリクレスは、このように雄弁を身につけ、立派な教養を積んでいたが、若いころには政治には乗り出さなかった。
そして軍務にはげみ、軍事的な知識を身につけ、軍人として名声をあげていった。
彼がアテネの指導者になるのに、これはかえって早道で賢明なやり方だった。
政界に早く乗り出せば、当時の他の多くの人々のように、彼もたぶん陶片追放(オストラキスモス)にあったことだろう。
しかし彼は政治に早く頭をつっこまなかったので、オストラキスモスにあわずにすんだ。
軍人として名声をあげたため、彼は将軍(ストラテゴス)に選ばれた。
他の役人が大部分希望者のなかから抽選で選ばれるようになっても、将軍は例外的に選挙で選ばれた。
将軍は国の運命を左右する戦争の指揮をするのだから、特に経験と知識を必要とする職で、だれでも望んだ人を任じてよいような職ではないと考えられたからだった。
また他の役人は再任を許されなかったのに、将軍は再任を許された。
こういうふうだったので、将軍はひじょうに重要な役になった。
ペリクレスは紀元前四五四年以後、連年将軍に選ばれた。
そのため彼はひじょうに強力になった。
彼は「地上のゼウス」とよばれるようになり、アテネは「名目上は民主政だが事実はペリクレスの独裁だ」といわれるようになった。
ペリクレスはスパルタがアテネ地方に侵入してくると、アテネ人たちに、市の城壁内に籠城するようにすすめた。
スパルタはギリシアの最強の陸軍国だったが、アテネは海軍国で、陸軍ではスパルタにかなわなかった。
したがって強力なスパルタ軍とまっとうにぶつかって、大きな打撃をうけることを避けたのだった。
アテネはもともと食糧は自給自足できなかった。
しかし有力な海軍を堅持していさえすれば、黒海方面から穀物を輸送してくることができた。
またデロス同盟諸市を支配して、割当金をとり立てることもできた。
またおりをみて、ペロポネソス沿岸を荒らして、敵を苦しめることもできた。
アテネと外港のペイライエウスを囲む二重の長城は堅固で、敵襲をうけても守りとおせる自信があった。
ペリクレスが籠城戦術をとったのは、そのためだった。しかし籠城は思いがけない結果を生んだ。
当時オリエントではペストが流行していたが、それがペイライエウス港から、アテネ市中にはいってきたのだった。
籠城のため急激に人口がふえたアテネ市は、非衛生になっていたため、病気はひじょうな勢いでひろがった。
人々はばたばたと倒れ、ついには病人を看護する人も、死体を世話する人もまに合わなくなってしまった。
最後の水を飲もうと、泉に手をかけたまま死んでいる人も多かったし、死骸は埋葬もされず、そのままほうり出されていた。
これを食ったためか、犬も鳥も少なくなった。
疫病は戦争がはじまるとすぐ流行しはじめ、冬には少し下火になったが、その後も何年か、夏になると流行した。
この病気の打撃は、戦争よりも大きかった。アテネの人口の四分の一以上が死んだといわれる。
ペリクレスの妹や息子たちもこれにかかって死に、紀元前四二九年には、ペリクレスも同じ病気で死んだ。
ペリクレスの死んだ後、アテネの指導者になったのは、クレオンだった。
彼は喜劇作家のアリストファネスに「皮なめし屋」といわれているが、商人の出で、抗戦派だった。
アテネ軍はペロポネソス半島のスファクテリア島で戦果をあげ、多数のスパルタ兵を捕虜にし、戦いを終わらせる好機にめぐまれたのだが、抗戦論者のクレオンにひきずられて、なかなか戦争は終わらなかった。
しかし紀元前四二二年に、クレオンと、スパルタのプラシダス将軍がともに戦死し、急に和平の気分が高まり、翌年の四二一年に、いわゆる「ニキアスの和」が結ばれた。
6 ギリシアを二分した大戦争 ―ペロポネソス戦争―
3 ペロポネソス戦争
アテネの支配が強引だったため、デロス同盟諸市のなかには不満を持つものが、しだいにふえていった。他方、アテネが急に繁栄して、ギリシア第一の強国にのしあがってきたことに、スパルタは恐れを感じ、またしっとを感じていた。
スパルタは、デロス同盟に加わっていないペロポネソス半島の諸ポリスを率いて、ペロポネソス同盟をつくっていた。
どういう事情からか、その原因はよくわからないが、アテネはペロポネソス同盟に属しているメガラとデロス同盟諸市の貿易を禁止し、そのうえ毎年メガラを攻める決議をした。
また同じペロポネソス同盟に属していたコリントは、商業貿易で栄えていた町だったが、アテネの商業貿易の発展によって、打撃をうけた。そのうえコリントはコルキュラ島をめぐって、アテネと衝突した。
コルキュラはコリントの植民市だった。
コルキュラとコリントは共同で植民し、エピダムノスという植民市をつくった。
このエピダムノスで内乱が起こり、これがきっかけとなって、コリントとコルキュラのあいだに戦争が起こった。
両市ともアテネに助けを求めた。
アテネとコリントは、商業貿易のうえでそのころ敵対していたので、アテネはコルキュラを助けた。
こうしてアテネはコリントと戦うことになり、コリントの力をそぐために、コリントの植民市ボディダイアに城壁をこわすことを命じた。
ボディダイアはデロス同盟に加入していたが、この横暴な命令には従えないと、アテネに謀反し、コリントはボディダイアを助けた。
コリン卜、ボディダイア、メガラ、それにアイギナなどは、スパルタにアテネの不法を訴えた。
スパルタはペロポネソス同盟諸市を集めて、会議を開いた。スパルタはそのころアテネと「三十年の和約」を結んでいたので、これらの諸市をむしろなだめようとしたが、諸市の不満は強く、つき上げられる形で、アテネとの戦争を開始することになってしまった。
スパルタ王アルキダモスは、紀元前四三一年の夏、アテネ地方に攻め入った。
全ギリシアのポリスは、アテネとスパルタのどちら側かに味方し、ギリシアは二つの陣営にわかれて、二十七年間におよぶ大戦争を戦った。
これを「ペロポネソス戦争」という。
アテネは民主政体の国だったが、スパルタは寡頭(かとう)政体の国だった。
アテネに味方したポリスの多くは民主政体であり、スパルタに味方したポリスの多くは寡頭政体だった。
したがってペロポネソス戦争は民主政と寡頭政の戦いでもあった。
民主政のポリスのなかにも、寡頭的な政治を良しとする者もおり、寡頭政のポリスのなかにも民主主義者はいた。
これらの人々は、機会があれば政権を握っている者を倒して、自分らが政権を握りたいと考えていた。
つまり戦争はポリスとポリスどうしで戦われていたと同時に、ポリスの内部でも戦われていたわけであった。
当時アテネを支配していたのは、ペリクレス(紀元前四九五年ごろ~四二九年)だった。
彼はダモン(ダモニデスともいわれる)という先生に音楽を学んだが、ダモンは本当はソフィストだったと伝えられている。
ペリクレスはまた哲学者のアナクサゴラス(紀元前五〇〇年ごろ~四二八年ごろ)にも学んだ。
そして合理的に考えることを学んだ。
ペリクレスはデロス同盟の基金を使って、パルテノン神殿をはじめ、立派な神殿をアテネ市にいくつも建てた。
同盟の金をこのように使うことは、同盟市にアテネ市非難の口実を与えることになると、ペリクレスを攻撃する人々がいた。
するとペリクレスは、「同盟市は国防のために金を出しているのだが、アテネはよく防衛の責任は果たしている。
商人は商品を売ってうけ取った金は何に使ってもよいように、防衛をしてやれば、そのかわりにうけとった金を何に使おうと自由だ」といったという。
ペリクレスはたいへん弁舌がうまく、彼の話し方は人の心を強くうったので、彼の弁舌は「雷のようだ」といわれた。
スパルタのアルキダモス王が、アテネ人のある人に、
「あなたとペリクレスが相撲をとると、どちらが勝つか」 ときいたところ、
「それはペリクレスにきまっています。たとえ私が彼を投げとばしても、彼は自分が勝つたといいはるでしょう。そうすれば、私たちの勝負を見ていた人も、自分たちの目よりも、彼の言葉を信じるにちがいありませんから」
と答えたという。
こういう逸話類は、彼がソフィストの影響をうけていたことを思わせる。
ペロポネソス戦争がはじまったとき、たまたま日蝕が起こった。
アテネの兵士たちは、これを不吉の前兆だといって恐れ、さわいだ。
ペリクレスは着ていたマントをぬいで、ある兵士の目の前にこれを下げ、またそれをどけていった。
「お前はこれを不吉の前兆だと思うかね」。兵士は「いいえ」と答えた。
ペリクレスは「日蝕だって同じことなのだ。日蝕は、マントより大きなものが太陽をさえぎったにすぎないのだから」
といって、兵士らを安心させたという。
彼はアナクサゴラスのような自然哲学者に学んでいたために、このような説明ができたのだった。
ペリクレスは、このように雄弁を身につけ、立派な教養を積んでいたが、若いころには政治には乗り出さなかった。
そして軍務にはげみ、軍事的な知識を身につけ、軍人として名声をあげていった。
彼がアテネの指導者になるのに、これはかえって早道で賢明なやり方だった。
政界に早く乗り出せば、当時の他の多くの人々のように、彼もたぶん陶片追放(オストラキスモス)にあったことだろう。
しかし彼は政治に早く頭をつっこまなかったので、オストラキスモスにあわずにすんだ。
軍人として名声をあげたため、彼は将軍(ストラテゴス)に選ばれた。
他の役人が大部分希望者のなかから抽選で選ばれるようになっても、将軍は例外的に選挙で選ばれた。
将軍は国の運命を左右する戦争の指揮をするのだから、特に経験と知識を必要とする職で、だれでも望んだ人を任じてよいような職ではないと考えられたからだった。
また他の役人は再任を許されなかったのに、将軍は再任を許された。
こういうふうだったので、将軍はひじょうに重要な役になった。
ペリクレスは紀元前四五四年以後、連年将軍に選ばれた。
そのため彼はひじょうに強力になった。
彼は「地上のゼウス」とよばれるようになり、アテネは「名目上は民主政だが事実はペリクレスの独裁だ」といわれるようになった。
ペリクレスはスパルタがアテネ地方に侵入してくると、アテネ人たちに、市の城壁内に籠城するようにすすめた。
スパルタはギリシアの最強の陸軍国だったが、アテネは海軍国で、陸軍ではスパルタにかなわなかった。
したがって強力なスパルタ軍とまっとうにぶつかって、大きな打撃をうけることを避けたのだった。
アテネはもともと食糧は自給自足できなかった。
しかし有力な海軍を堅持していさえすれば、黒海方面から穀物を輸送してくることができた。
またデロス同盟諸市を支配して、割当金をとり立てることもできた。
またおりをみて、ペロポネソス沿岸を荒らして、敵を苦しめることもできた。
アテネと外港のペイライエウスを囲む二重の長城は堅固で、敵襲をうけても守りとおせる自信があった。
ペリクレスが籠城戦術をとったのは、そのためだった。しかし籠城は思いがけない結果を生んだ。
当時オリエントではペストが流行していたが、それがペイライエウス港から、アテネ市中にはいってきたのだった。
籠城のため急激に人口がふえたアテネ市は、非衛生になっていたため、病気はひじょうな勢いでひろがった。
人々はばたばたと倒れ、ついには病人を看護する人も、死体を世話する人もまに合わなくなってしまった。
最後の水を飲もうと、泉に手をかけたまま死んでいる人も多かったし、死骸は埋葬もされず、そのままほうり出されていた。
これを食ったためか、犬も鳥も少なくなった。
疫病は戦争がはじまるとすぐ流行しはじめ、冬には少し下火になったが、その後も何年か、夏になると流行した。
この病気の打撃は、戦争よりも大きかった。アテネの人口の四分の一以上が死んだといわれる。
ペリクレスの妹や息子たちもこれにかかって死に、紀元前四二九年には、ペリクレスも同じ病気で死んだ。
ペリクレスの死んだ後、アテネの指導者になったのは、クレオンだった。
彼は喜劇作家のアリストファネスに「皮なめし屋」といわれているが、商人の出で、抗戦派だった。
アテネ軍はペロポネソス半島のスファクテリア島で戦果をあげ、多数のスパルタ兵を捕虜にし、戦いを終わらせる好機にめぐまれたのだが、抗戦論者のクレオンにひきずられて、なかなか戦争は終わらなかった。
しかし紀元前四二二年に、クレオンと、スパルタのプラシダス将軍がともに戦死し、急に和平の気分が高まり、翌年の四二一年に、いわゆる「ニキアスの和」が結ばれた。