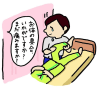厚生労働省の「平成28年 国民生活基本調査」によると、「転倒・骨折」は、主な原因の第4位になります(厚労省の報告書類に飛びます)。
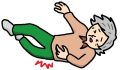
若い頃はおもいっきり転んでも手足を擦りむいた程度で済んでいたのですが、歳を重ねるとおもいっきり転ぶ…なんてことを想像するだけでも恐ろしいものですね。
高齢者に多い骨折は、足の付け根(大腿骨頸部骨折)、手首付近(橈骨遠位端骨折)、背骨(脊椎圧迫骨折)といわれています。 いずれも転倒がきつかけになるいずれも転倒がきつかけになることが多いです。
ところで、転倒しても必ず骨折する訳ではなく、高齢者であっても頻繁に転んでいるのに骨折されない方もいらっしゃいます。 転ぶのが上手な方もいらっしゃるのでしょうか^-^?
私の祖母のスーザンは、大腿骨頸部骨折を受傷してから、ほとんど寝たきり状態になり、その後数年は自宅で介護していましたが、2016年に亡くなりました。 寝たきり状態になったきっかけが転倒による骨折でしたが、それ以前もよく転んでいました。 けれどその頃は、骨折することなく、下手をすると転んだことすら隠していたと思いますので、私達家族が分かっている回数以上に転倒していたかも知れません(^-^;
そのスーザンが骨折を伴わずに転んでいた時、まるで転がるように静かに転んでいました。 そばで見ていて「うまい転び方だなぁ…」と思っていました。
お若い頃に柔道などの武道を行っていた高齢者は、きっと転ぶのが上手なのかなぁ…? と素朴な疑問を持っていました。
なので、先ほどインターネットで調べてみました。 転倒による骨折を予防するのに、「転ぶ練習」をすることがあるのか? あるとしたら、どんな風にやってるのか?
ありました^-^
ブレンダ・グローウェンという女性の博士が2007年や2009年にかけて報告していました(学生さんや理学療法士さんなど、興味がありましたら論文をご覧ください)。
簡単にお伝えしますと、柔道などで行う受け身の練習を高齢者に行っていただき、その前後で、わざと転んだ際に太ももの横にある大腿骨大転子という部位(転倒の際、ここが床にぶつかり衝撃を受けます)にかかる衝撃度を調査しました。
受け身の練習を行った前に比べ、後の方が衝撃が減少していた、というのがグローウェン博士の報告でした。 まだ詳細なところまで読めておりませんが、面白そうなのでじっくり読んでみたいと思います。 苦手な英語の論文ですが…(^-^;
転倒・骨折は、予防さえできれば要介護状態を回避できると思われます。 ぜひぜひ、転ばない機能や能力を維持しましょう。 せめて、転んでも骨折しない、ただでは起きないような状態にもなっておきましょう^-^
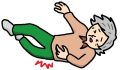
若い頃はおもいっきり転んでも手足を擦りむいた程度で済んでいたのですが、歳を重ねるとおもいっきり転ぶ…なんてことを想像するだけでも恐ろしいものですね。
高齢者に多い骨折は、足の付け根(大腿骨頸部骨折)、手首付近(橈骨遠位端骨折)、背骨(脊椎圧迫骨折)といわれています。 いずれも転倒がきつかけになるいずれも転倒がきつかけになることが多いです。
ところで、転倒しても必ず骨折する訳ではなく、高齢者であっても頻繁に転んでいるのに骨折されない方もいらっしゃいます。 転ぶのが上手な方もいらっしゃるのでしょうか^-^?
私の祖母のスーザンは、大腿骨頸部骨折を受傷してから、ほとんど寝たきり状態になり、その後数年は自宅で介護していましたが、2016年に亡くなりました。 寝たきり状態になったきっかけが転倒による骨折でしたが、それ以前もよく転んでいました。 けれどその頃は、骨折することなく、下手をすると転んだことすら隠していたと思いますので、私達家族が分かっている回数以上に転倒していたかも知れません(^-^;
そのスーザンが骨折を伴わずに転んでいた時、まるで転がるように静かに転んでいました。 そばで見ていて「うまい転び方だなぁ…」と思っていました。
お若い頃に柔道などの武道を行っていた高齢者は、きっと転ぶのが上手なのかなぁ…? と素朴な疑問を持っていました。
なので、先ほどインターネットで調べてみました。 転倒による骨折を予防するのに、「転ぶ練習」をすることがあるのか? あるとしたら、どんな風にやってるのか?
ありました^-^
ブレンダ・グローウェンという女性の博士が2007年や2009年にかけて報告していました(学生さんや理学療法士さんなど、興味がありましたら論文をご覧ください)。
簡単にお伝えしますと、柔道などで行う受け身の練習を高齢者に行っていただき、その前後で、わざと転んだ際に太ももの横にある大腿骨大転子という部位(転倒の際、ここが床にぶつかり衝撃を受けます)にかかる衝撃度を調査しました。
受け身の練習を行った前に比べ、後の方が衝撃が減少していた、というのがグローウェン博士の報告でした。 まだ詳細なところまで読めておりませんが、面白そうなのでじっくり読んでみたいと思います。 苦手な英語の論文ですが…(^-^;
転倒・骨折は、予防さえできれば要介護状態を回避できると思われます。 ぜひぜひ、転ばない機能や能力を維持しましょう。 せめて、転んでも骨折しない、ただでは起きないような状態にもなっておきましょう^-^