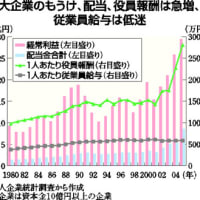1999年に出版された『買ってはいけない』に次のような一節がある。
冒頭の洗剤の話は「ライオン」だが、次の洗剤の話は「花王」である。
ここに書かれているのは昭和30年代の出来事で、著者によれば、
寺川氏は当時東京都衛生局臨床実験部長だった柳沢文正博士に、「この毒性はジワジワと内蔵を侵す。しかもまだ誰も知らない。中性洗剤は大量に売られ、野放し状態になっている。放っておくと大量の患者を発生させ、国民の健康にとって重大な問題になる。ジャーナリストなら、徹底的に調べて、世の中に警鐘を鳴らすべきではないか」と、中性洗剤の毒性を指摘され、取材を開始する。中性洗剤は当時、一般の市販の他に、デパートの大売出しの景品、また新聞拡張の景品としてもよく使われていた。柳沢文正博士は、それまでに何度も問題を提起したがその都度黙殺されたということだった。ちなみに、文中の≪安全保障の根拠が、先に触れた噴飯ものの「厚生省実験済み」≫というのは次のようなものである。
ともあれ、寺川氏の「中性洗剤反対」キャンペーンは、日本での消費者運動のはしりだった。
寺川雄一氏は、『小泉純一郎と日本の病理 Koizumi`s Zombie Politics』(光文社)の著者の藤原肇氏の『朝日と読売の火ダルマ時代』を出版した国際評論社の会長兼編集長であり、「日本には経済誌はあるけれどどれもメーカーサイドの記事の編集ばかりであり、消費者の立場での取材がない」と読売の経済部の記者を辞め、『国際経済』という月刊経済誌を35年間発行してきた人であった。
『小泉純一郎と日本の病理 Koizumi`s Zombie Politics』は元原稿の3分1がカットされ、また文章もむずかしいということから編集者が読者が読み易いように(?)全面的に書き直したが、新聞や諸権力の事実史を綴った『朝日と読売の火ダルマ時代』は寺川氏でさえ出版を請け負うことには躊躇したようだった。
藤原肇氏によると、39社に断られ、国際評論社を訪れたのだが、寺川氏は読んだ後、次のように言ったという。
「とても面白かった。実際に取材している生の声は貴重だ。しかし、こんな内容の本は日本では出ない。なぜなら、朝日と読売を相手に喧嘩しているみたいだが、よく読めば検察とも取次ぎとも政府とも電通ともやっていて、日本中の権力を相手にして喧嘩しているから、こんな本を出した出版社は潰されるに決まっている」
しかし、藤原氏も引き下がらない。
「でも、不正行為に加担している相手ならば、それを追及するのがジャーナリズムの責任だし、今の日本の亡国現象はジャーナリズムの堕落と腐敗が、その原因を作り権力に追従しているからです」
その時は「とても駄目だね」と寺川氏は断るのだが、その後の交渉で結局『朝日と読売の火ダルマ時代』は出版されることとなった。
国際評論社は数年前に、まず営業の責任者のかたが亡くなり、続いて社長がガンのために亡くなる不幸が続き、さらに寺川氏も入院をしたため、現在経営を休止している。『朝日と読売の火ダルマ時代』も絶版となっている。
ともあれ、はたして、ライブドアショックは他の全企業にとって教訓となったのだろうか。僕は疑問に思わざるをえないのである。つまり、世の中はホリエモンを葬り去ることに過大な、また誤った意味付けをしてはいないのだろうかと思う次第だ。
日本消費者連盟にいたときに、九州でせっけん運動を10年以上やっている女性から電話がかかってきました。ライオンの小林社長(当時)が、ライオン奥様サロンとかいった集まりに妻を連れてきたので、「ライオンさんはあれだけ合成洗剤のテレビ広告をやって、なんですか。今日はライオンの社長さんがおるから聞きたいのだけど、あんたのところは、おたくのライオンの合成洗剤を使うておらっしゃるとでしょうね」と社長に聞いたそうです。『買ってはいけない』は、『「買ってはいけない」は買ってはいけない』という対抗本も出版されるなど侃々諤々の議論を巻き起こしたが、キリンの「ラガービール」が今は遺伝子組換え麦を原料にしていないこと、また同じくキリンが開発しようとしていた「日持ちのするトマト」(遺伝子組換えで表面の皮のみ張りが持続するという何とも気味の悪いトマト)が店頭で売られていないことなどは、この『買ってはいけない』が提起した告発と、その論争で、企業に遺伝子組換え種を使った商品は売れないと観念させたことが大きいのだ。
「もちろん、わたしの家ではわが社の合成洗剤を愛用しております」と答えたけれど、妻が袖を引っぱって「あれは危ないからというのでみんなせっけんに替えたじゃないですか」とやったので、会場がみんなア然となったというんだね。
冒頭の洗剤の話は「ライオン」だが、次の洗剤の話は「花王」である。
こうしたデータを集めて、洗剤メーカーに取材を始めたが、花王もライオンも責任者は逃げ回って出てこようとしない。これは『経営者に良心はあるか』寺川雄一著(1995年刊)の一節。
いま思い出しても怒りを覚えるのは、丸田専務の冷笑を浮かべながら言ってのけた、次の大嘘発言だ。
「洗剤の安全性は保証されている。我が家では節約のため古米を食べているが、研ぎ水にもウチの洗剤を入れて使っている。よく研げて新米並みに美味しくなる」。
安全保障の根拠が、先に触れた噴飯ものの「厚生省実験済み」だが、花王の専務の家庭で「古米」を洗剤で研いで食べていると、白々しい大嘘をヌケヌケと、言ってのけたのには二の句が継げず、唖然としてしまった。
取材記者の枠を越えて、「中性洗剤反対」キャンペーンに走らせた契機は、この丸田氏の大嘘に始まる。
なお念のため、丸田家に電話を掛け「古米を洗剤入りの水で研いでいるかどうか」を問い質してみた。答えは案の定というべきか、「ウチでは古米など一粒たりとも食べてはいません」と、丸田夫人は、電話の向こう側で、柳眉を逆立てた形相を想像させるような、カナキリ声を上げておられた。
この会見の後、花王石鹸の植草秘書課長は「お前は共産党だろう。街なかで出会うことがあったら、棍棒で殴ってやる」と息巻いていた。丸田専務によほど激しく叱責されたものと推察した。
これまで、私は数々の悪評を受けていたが、面と向かって「共産党」呼ばわりをされたのは、このときが初めてだった。
自ら顧みて、これほど私に相応しくないレッテルはないと思ったが、企業の「反社会的行為」の糾弾は、十把一絡げに「共産党」と呼ぶところに、当時の日本企業の文化水準が、示されているような気がする。
ここに書かれているのは昭和30年代の出来事で、著者によれば、
「成長神話」に支えられた生産者と、消費者の「古き良き」蜜月時代だったと言えようか。という時代だった。
アメリカのカーソン女史の「沈黙の春」が話題になるのも、もう少し後になってからであり、水俣病の有機水銀原因説が表沙汰になり、四日市喘息が社会問題化しようとしていたが、「公害」という言葉も、まだ生まれていない。
BHCの牛乳混入事件、カネミ油症事件、森永砒素ミルク事件、薬禍によるサリドマイド症事件などが頻発しているが、これはまだ単なる「事件」であり、「事故」であった。「欠陥商品」を生み出す社会経済的背景への追及のメスは、まだ入っていなかった。
寺川氏は当時東京都衛生局臨床実験部長だった柳沢文正博士に、「この毒性はジワジワと内蔵を侵す。しかもまだ誰も知らない。中性洗剤は大量に売られ、野放し状態になっている。放っておくと大量の患者を発生させ、国民の健康にとって重大な問題になる。ジャーナリストなら、徹底的に調べて、世の中に警鐘を鳴らすべきではないか」と、中性洗剤の毒性を指摘され、取材を開始する。中性洗剤は当時、一般の市販の他に、デパートの大売出しの景品、また新聞拡張の景品としてもよく使われていた。柳沢文正博士は、それまでに何度も問題を提起したがその都度黙殺されたということだった。ちなみに、文中の≪安全保障の根拠が、先に触れた噴飯ものの「厚生省実験済み」≫というのは次のようなものである。
安全性は厚生省の実験証明済みとある。今のBSE問題とよく似ているなと思うが、寺川氏は企業商品などの安全性などの問題は、≪コンシューマーズ・ユニオンのウォーン博士の忠告から私は、洗剤「企業」が「進歩」しているかどうか……が、カギになるのではないかと思っている≫と述べている。これからいけば、冒頭の一つのエピソードはその答えを表しているのかもしれない。
調べてみると「厚生省」が実験を委嘱したのは「日本食品衛生協会」という財団法人であり、その会長は元厚生省の技官。塩野義製薬社長の女婿であり、当時順天堂大学の教授を兼任していた。
この経歴は厚生省と製薬メーカーとの、官財癒着そのもを想像させるが、それはともかく「日本食品衛生協会」は、事務局があるわけでもない、当の理事長がたった一人の、いわばペーパー財団だった。
厚生省とあるから、厚生省に存在するものと思い、厚生省に行くと、そんなものが厚生省にある訳がないという。よく調べてみると、有楽町の勧業銀行の2階の一室に、事務所だけはあった。
実験内容を追及したところ、簡単にいうと「ボールの中に鯉を泳がせて、何日間か、洗剤を投与したが、鯉は死ななかった」という程度のものだった。
幽霊財団の杜撰な実験だけで、「厚生省実験証明済み」と権威付けされていたわけだ。
ともあれ、寺川氏の「中性洗剤反対」キャンペーンは、日本での消費者運動のはしりだった。
寺川雄一氏は、『小泉純一郎と日本の病理 Koizumi`s Zombie Politics』(光文社)の著者の藤原肇氏の『朝日と読売の火ダルマ時代』を出版した国際評論社の会長兼編集長であり、「日本には経済誌はあるけれどどれもメーカーサイドの記事の編集ばかりであり、消費者の立場での取材がない」と読売の経済部の記者を辞め、『国際経済』という月刊経済誌を35年間発行してきた人であった。
『小泉純一郎と日本の病理 Koizumi`s Zombie Politics』は元原稿の3分1がカットされ、また文章もむずかしいということから編集者が読者が読み易いように(?)全面的に書き直したが、新聞や諸権力の事実史を綴った『朝日と読売の火ダルマ時代』は寺川氏でさえ出版を請け負うことには躊躇したようだった。
藤原肇氏によると、39社に断られ、国際評論社を訪れたのだが、寺川氏は読んだ後、次のように言ったという。
「とても面白かった。実際に取材している生の声は貴重だ。しかし、こんな内容の本は日本では出ない。なぜなら、朝日と読売を相手に喧嘩しているみたいだが、よく読めば検察とも取次ぎとも政府とも電通ともやっていて、日本中の権力を相手にして喧嘩しているから、こんな本を出した出版社は潰されるに決まっている」
しかし、藤原氏も引き下がらない。
「でも、不正行為に加担している相手ならば、それを追及するのがジャーナリズムの責任だし、今の日本の亡国現象はジャーナリズムの堕落と腐敗が、その原因を作り権力に追従しているからです」
その時は「とても駄目だね」と寺川氏は断るのだが、その後の交渉で結局『朝日と読売の火ダルマ時代』は出版されることとなった。
国際評論社は数年前に、まず営業の責任者のかたが亡くなり、続いて社長がガンのために亡くなる不幸が続き、さらに寺川氏も入院をしたため、現在経営を休止している。『朝日と読売の火ダルマ時代』も絶版となっている。
我々世代にとって、20年代は戦後の廃墟の中であっても、厚い雲にぽっかりあいた、青空を見上げるような新時代への希望があった。昭和30年代は、アメリカが掲げた戦争責任者の「追放」も有名無実に終わり、「追放」の対象者であった人間たちが現場に復帰し、「完全に蘇生し、政界、財界、官界、あらゆる所で安楽に活動をつづけ」(松本清張)始めた時期であったが、それは書かれていることに無関係であったろうか。
アメリカに与えられたものだったかどうか、また民主主義、自由主義と、呼び名などはどうでもよい。日本は変わる、という希望だった。
漠然としてはいたが、これは「自由、民主」を支えるフェア、公正の観念が、日本社会に定着するのではないかという期待、精神構造の変化への、期待のようなものだったのではなかろうか。
閉塞的社会から、溌剌としたオープンな社会に変わるという期待でもあり、確かにその芽はあったと思う。
30年代は、これが変質する経過だったような気がする。いま、当時が、閉塞的「秩序」に回帰する動きが、強くなった時代だったように感じているわけだ。
当時、左翼陣営は「反動」と呼んだが、これとは違った意味でまさに「反動」だった。
モラル・ハザードというか、企業社会には、倫理感の欠如を示す事例が頻発する。その典型例を、証券界にみることができる。
株式市場は、言うまでもなく資本主義の代表だ。その意味で、この時代の証券界は、当時の企業社会を象徴的に示しているとも考えている。
そして、つい3、4年前に起こった、バブル経済崩壊と共に明らかにされた「飛ばし」や「損失補填」を始めとする証券不祥事に、形態、規模こそ違うが類似点が多いことに、改めて驚いたのを覚えている。(『経営者に良心はあるか』寺川雄一著)
ともあれ、はたして、ライブドアショックは他の全企業にとって教訓となったのだろうか。僕は疑問に思わざるをえないのである。つまり、世の中はホリエモンを葬り去ることに過大な、また誤った意味付けをしてはいないのだろうかと思う次第だ。