食品業界で「添加物の神様」と言われていた安倍司氏の著作『食品の裏側』を読みながら、これは清貧のきっこさんも読むべきだ、とつらつら思った。
その昔、「しょうゆライス」なる清貧の極みのような一品があった。もちろん、今でも作ればある。(笑)
作るといっても簡単至極で、フライパンにご飯と醤油を入れて炒めるだけのものである。しかしながら、これが中々に美味い。たとえば、これも作るのが簡単な、七輪で焼いた秋刀魚のように美味である。
作るのは簡単だと書いたが、材料のほんとの醤油のほうは作るのに一年以上かかるらしい。「しょうゆライス」の美味しさの由来は、どうもこの醤油の手間暇かける一年余月の月日のなかにあるのかもしれない。
しかし、この「しょうゆライス」が「今」危ない。
次の材料名は、上の昔ながらの醤油を作る時に使用するもの。これ以外のものは使わない。
丸大豆
小麦
食塩
こうじ
店頭では、『丸大豆しょうゆ』という品名がつき、1リットルで1000円くらいするらしい。醤油として出来上がるまでに一年以上かかる。
一方、店頭では1リットル200円くらいで、『新式醸造しょうゆ』なる呼び名で売られている”醤油”の材料名は、次のとおり。ちなみに出来上がるのにこちらは1カ月もかからないそうである。
脱脂加工大豆
アミノ酸液
ブドウ糖加糖液糖
グルタミン酸ナトリウム
5’-リボヌクレオチドナトリウム
グリシン
甘草
ステビア
サッカリンナトリウム
CMC-Na(地粘多糖類)
カラメル色素
乳酸
コハク酸
安息香酸プチル
「醤油」と言うより、まるで「添加物の嵐」のような風情だ。現在の官房長官の安倍氏なら、
「日本の技術の勝利」
と褒め称えそうであるが、添加物の専門商社に勤め、神様とまで言われていたが、ある日自分が作製を手伝った「食品」を家で娘が食べているのに気付いて愕然とし、次の日には会社を辞めて今は食品添加物のことを広く世の中に知ってもらおうと行脚をしているほうの安倍氏は、
「しゅうゆ風調味料」もしくは「しゅうゆ風塩水」
と呼ぶ。
「醤油」ではないのだ。味は多少「醤油」に似ていても。
しかし、普段自分がどちらの醤油を食しているか、わかっている人がどれくらいいるだろうか。
もちろん、「しゅうゆ風調味料」で作った「しゅうゆライス」は、とても食べられたものではないだろうし、考えただけでも僕などは気分が悪くなってくる。とはいえ、僕も普段どっちの醤油を食しているのか、意識したこともないほうの人間なのだ。そもそも、醤油にニセモノがあり、それが堂々と”醤油”として売られている(合法的に!)ことなど考えたこともないのだから。それに、もちろん、1000円と200円の醤油があれば、僕は多分迷うことなく、200円のほうを買うほうだったのだ。
けれど、知った以上はニセモノのほうは食したくはない、と思うし、やはり考えただけでも気分が悪くなってくる。
「醤油」ばかりではない。同じようなものは沢山あるらしい。
この『食品の裏側』を読んでいてちょっと思ったのは、人間はロボットだな、化学品をこんなにも沢山食べているんだから、ということだった。
でも、著者も書いているように、この今の現実は変えることができる。多くの人が食品の実態を知り、それにNo!と言えば、売れないものは作れないという企業法則がある以上、変えることができるのである。
しかし、そのためにはまず知ることから始めなければならない、と著者は言う。
これは、食品添加物のことに限らず、世の中のありとあらゆるものについて言えることでもある。
そして、世の中はこの意味ではまだ中世の時代を馬鹿にはできない有様といっていいように思われる。
今日のニュース記事にも次のようなものがあった。
あのアヤシイ読売新聞社で、最後まで反骨記者を貫いたらしい黒田清氏の伝記『黒田清 記者魂は死なず』(有須和也著)が出版されているらしい。『週刊ポスト』の書評に、その中の一節が記されていた。
「ボクは決して、自分が初めから世の中のために記事を書きたかったちゅうようなことは言わん。三十何年かの間に、反省を繰り返すうちに、そないなっていったんや」
何だかわかるような気もする。単なる純粋な意志、熱情だけでは何も出来ないのが大メディアというシステムなのだろうけど、そのなかで自分のできることをやってきた人間のそれが姿なのかもしれない。
ともあれ、大メディアの記事からは、『食品の裏側』の内容のようなことはまだ知らされない。
健康で毎日を過ごしてほしいきっこさんや、世の多くの人に読んでほしい一冊だ。
その昔、「しょうゆライス」なる清貧の極みのような一品があった。もちろん、今でも作ればある。(笑)
作るといっても簡単至極で、フライパンにご飯と醤油を入れて炒めるだけのものである。しかしながら、これが中々に美味い。たとえば、これも作るのが簡単な、七輪で焼いた秋刀魚のように美味である。
作るのは簡単だと書いたが、材料のほんとの醤油のほうは作るのに一年以上かかるらしい。「しょうゆライス」の美味しさの由来は、どうもこの醤油の手間暇かける一年余月の月日のなかにあるのかもしれない。
しかし、この「しょうゆライス」が「今」危ない。
次の材料名は、上の昔ながらの醤油を作る時に使用するもの。これ以外のものは使わない。
丸大豆
小麦
食塩
こうじ
店頭では、『丸大豆しょうゆ』という品名がつき、1リットルで1000円くらいするらしい。醤油として出来上がるまでに一年以上かかる。
一方、店頭では1リットル200円くらいで、『新式醸造しょうゆ』なる呼び名で売られている”醤油”の材料名は、次のとおり。ちなみに出来上がるのにこちらは1カ月もかからないそうである。
脱脂加工大豆
アミノ酸液
ブドウ糖加糖液糖
グルタミン酸ナトリウム
5’-リボヌクレオチドナトリウム
グリシン
甘草
ステビア
サッカリンナトリウム
CMC-Na(地粘多糖類)
カラメル色素
乳酸
コハク酸
安息香酸プチル
「醤油」と言うより、まるで「添加物の嵐」のような風情だ。現在の官房長官の安倍氏なら、
「日本の技術の勝利」
と褒め称えそうであるが、添加物の専門商社に勤め、神様とまで言われていたが、ある日自分が作製を手伝った「食品」を家で娘が食べているのに気付いて愕然とし、次の日には会社を辞めて今は食品添加物のことを広く世の中に知ってもらおうと行脚をしているほうの安倍氏は、
「しゅうゆ風調味料」もしくは「しゅうゆ風塩水」
と呼ぶ。
「醤油」ではないのだ。味は多少「醤油」に似ていても。
しかし、普段自分がどちらの醤油を食しているか、わかっている人がどれくらいいるだろうか。
もちろん、「しゅうゆ風調味料」で作った「しゅうゆライス」は、とても食べられたものではないだろうし、考えただけでも僕などは気分が悪くなってくる。とはいえ、僕も普段どっちの醤油を食しているのか、意識したこともないほうの人間なのだ。そもそも、醤油にニセモノがあり、それが堂々と”醤油”として売られている(合法的に!)ことなど考えたこともないのだから。それに、もちろん、1000円と200円の醤油があれば、僕は多分迷うことなく、200円のほうを買うほうだったのだ。
けれど、知った以上はニセモノのほうは食したくはない、と思うし、やはり考えただけでも気分が悪くなってくる。
「醤油」ばかりではない。同じようなものは沢山あるらしい。
この『食品の裏側』を読んでいてちょっと思ったのは、人間はロボットだな、化学品をこんなにも沢山食べているんだから、ということだった。
でも、著者も書いているように、この今の現実は変えることができる。多くの人が食品の実態を知り、それにNo!と言えば、売れないものは作れないという企業法則がある以上、変えることができるのである。
しかし、そのためにはまず知ることから始めなければならない、と著者は言う。
これは、食品添加物のことに限らず、世の中のありとあらゆるものについて言えることでもある。
そして、世の中はこの意味ではまだ中世の時代を馬鹿にはできない有様といっていいように思われる。
今日のニュース記事にも次のようなものがあった。
世の中にはこういう重要度の高い告発をした人間を守るシステムさえまだ存在せず、今後いつできるのかさえおぼつかないのだ。
“良心の医師”を守って 医療ミスで遺族らが会設立 共同通信社 2006/4月/15日
医療ミスを内部告発しようとする医師や看護師らを支援しようと、遺族や医師、弁護士らが15日、「医療の良心を守る市民の会」(永井裕之代表)を設立、都内で開いたシンポジウムに約300人が集まった。
病院など組織の中では、医師がミスを患者や家族に伝えられずに悩んだり、内部告発をしたために嫌がらせを受けたりすることもあり、こうした医療従事者の支援態勢をつくるのが会の目的。被害者団体などと連携し、具体的な相談体制を今後検討する。
医療事故で妻を亡くしている永井代表は、あいさつで「一番悲しいことは真実を語ってもらえなかったり、隠されたりすること。医療従事者と患者の間にある溝を少しずつでも埋めていきたい」と語った。
あのアヤシイ読売新聞社で、最後まで反骨記者を貫いたらしい黒田清氏の伝記『黒田清 記者魂は死なず』(有須和也著)が出版されているらしい。『週刊ポスト』の書評に、その中の一節が記されていた。
「ボクは決して、自分が初めから世の中のために記事を書きたかったちゅうようなことは言わん。三十何年かの間に、反省を繰り返すうちに、そないなっていったんや」
何だかわかるような気もする。単なる純粋な意志、熱情だけでは何も出来ないのが大メディアというシステムなのだろうけど、そのなかで自分のできることをやってきた人間のそれが姿なのかもしれない。
ともあれ、大メディアの記事からは、『食品の裏側』の内容のようなことはまだ知らされない。
健康で毎日を過ごしてほしいきっこさんや、世の多くの人に読んでほしい一冊だ。










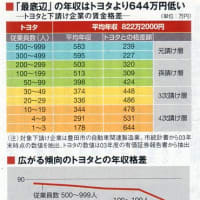
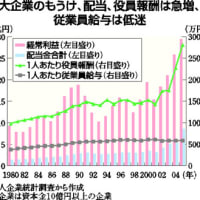



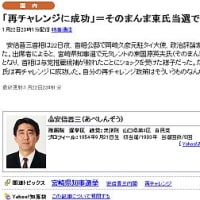

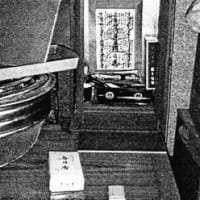
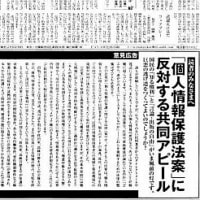
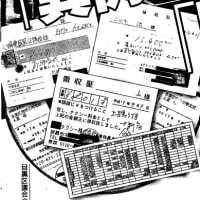
・・・・・はじめに企業の利益最優先だし。
そもそも『自然循環社会を目指す』のであれば、リサイクルを阻む悪法PSE(電気用品安全法)の施行なんて、真っ先に弾劾すべきことなわけで・・・。
・・・・・これまた企業の利益最優先だし。
話を元に戻せば、食に関しては、私も2人の子(しかも内1人は喘息アレルギー)を持つ母親なので、食に関しては随分以前からあらゆる方法で情報を得てきました。
加えて、人間の体を汚染していくのは食だけではなく、食品を調理する時に使用する調理器具・用品や食器、はたまた食材を育てる土壌や水質、また様々な化学物質や薬など、身の回りに溢れているという意味で、そういった書物も数多く読んで情報収集した経験があります。
以下ご参考までに。
『食品を見分ける』磯部晶策
『食品・化粧品 危険度チェックブック』体験を伝える会添加物110
『沈黙の春』レイチェル・カーソン
『メス化する自然』デボラ・キャドバリー
『奪われし未来』シーア・コルボーン他
しかしながら、そうした危険から我が身を守って生きていくためには、個人の力だけでは到底無理・・・という所に行き着くんですよね。
従って、仰るように、マスコミは、バカバカしい芸能人ネタなんか放送している暇があったら、こうした人の生命に関わる問題に関してもっともっと真実を追求してほしいと思います。
・・・・・企業の利益には著しく反しますが。。。
(だから、敢えてフューチャーしないのかも?)
その元農水相は、農薬の問題は政府ではタブーになっている、それを持ち出すと追い出される、と言い、関係する政治家、官僚は危険だとわかっているので、自分の家では高い無農薬野菜をわざわざ買って食べている、と指摘。
一方、別の番組では、農家の人間が、自分の家で食べるものは、出荷するものとは別の、農薬を使わない畑でとれたものだ、とインタビューで答えていました。「いけないのは国の農薬基準だ」とも言っていました。
『食品の裏側』をみると、今、添加物で同じことが起きているようです。添加物を多く使っている食品企業の現場では、自分のところで作った製品は食べないという人が出ているのです。
けれど、添加物の問題は大メディアにとっては、多くの大スポンサー企業を巻き込むものでもあるので、農薬よりも出しにくい問題だと思います。
世の中の多くの人が食品添加物の問題を知り、つとめて買わないようにすれば、市場はその時それが標準となり競争原理の面でも大きな問題もなくなるのですが、まず新聞・テレビが実態を知らせないことには多くの人にとっては問題は無いのと同じです。
現状では、スーパーで食品の材料名表示を見ても、添加物を避けていては、庶民にはほんとに食べるものがありません。