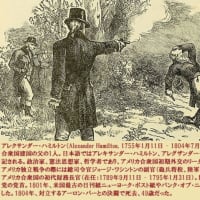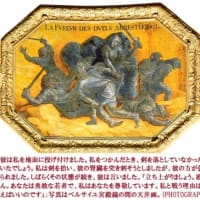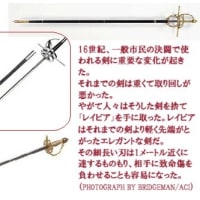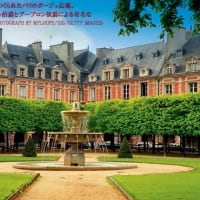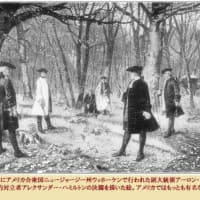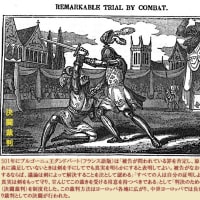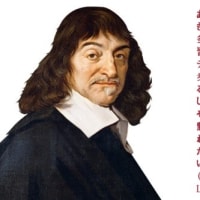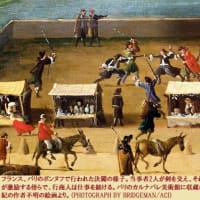本日記載附録(ブログ)
アフリカでしばしば大発生し、ユーラシアの農作物に深刻な被害を及ぼすサバクトビバッタ。
防除のために巨額の費用が投じられているが、未だに根本的な解決策は見出されていない。
『バッタを倒しにアフリカへ』と単身、西アグリカ・モーリタニアに渡った日本人がいる。
”愛するものの暴走を止めたい”と語る前野ウルド浩太郎、秋田市土崎港出身の人である。
【この企画はWebナショジオ】を基調に編纂(文責 & イラスト・資料編纂=涯 如水)
参考資料: バッタに人生を捧げます!!
番外編 ;前野ウルド浩太郎(23)
◇◆ 天災レベルに大発生する害虫を愛する男が行き着いた"ある場所" ◆◇

相棒は「音速の貴公子」 / 4_「頭の上、疲れている」
研究所内で知り合いのスタッフが増えてきた。「おー、コータロー元気か」と握手をして挨拶を交わすと、すかさずティジャニが寄ってきて、「アイツは使えないやつだ」「アイツは泥棒するから危ない」と報告してくることがよくあった。自分のことを思ってくれて、そんな裏情報まで流してくれていると感謝していた。ところが、すごく仲良くなった人が挨拶しにきたときまでティジャニが露骨に追い返したことに違和感を覚えた。なぜティジャニは私が他の人と仲良くなるのを嫌がっているのだろうか。嫉妬だろうか。
いずれバッタを大量に飼育し、実験を進めたい。そのために、バッタの飼い方や飼育容器の作り方などを専門でやってくれる人を雇おうと考えた。適任者がいないかティジャニに聞いたところ、みんな真面目に働かず補助は不可能だから自分がやりたいとのこと。一人の人間が複数の業務を行うと、効率は悪くなるし、万が一病気でもした日には、すべての負担が一気に私にのしかかってくる。それは私の望むところではない。
私「いや、別の人がいい」
ティジャニ「ここには誰もいない。私しかいない。他の人は忙しい」
ここに来てティジャニがスタッフを自分から遠ざけようとしていた意味がようやくわかった。ティジャニは自分を常に雇ってもらいたいから、ライバルたちから私を引き離し、独り占めしようとしていたのだ。金遣いはともかく、仕事そのものが真面目なのはわかってきたので、追加で1万円払い、ティジャニをなんでも屋さんとして雇うことにした。

たまにお願いした仕事をティジャニが忘れることがあるのだが、そういうときは怒りにまかせて「やれ」と命令するのではなく、私は自分でやってしまう。あとで「お願いしてたんだけどなんでやらなかったの?」と聞くのだが、「忙しいコータローに仕事をさせてしまった」と罪悪感を感じるのと、「マズイ、自分が必要とされなくなる」という焦りで、より一層働く気が生まれるようだ。
ティジャニのほうも、さらに自分の付加価値を高める手を打ってきている。フランス語、いや、あの「新言語」だ。私は研究所の研究者と会話するときは英語を使っており、それ以外はほとんどティジャニとしか会話をしていなかった。その調子で他の人と話そうとしてもまったく通じない。
ティジャニでなければ会話が成立しないのだ。「この車、ガソリン、よく食べる」は「この車超燃費が悪い」、「頭の上、疲れている」は「ハゲ」となる。今やティジャニに通訳をお願いして他の人と会話をするようになっている。自分自身でフランス語をきちんと勉強してこなかったため、ティジャニなしでは生活できなくなっている。
現状はたんにティジャニが苦労して外人の私に合わせてくれているだけにすぎない。ティジャニが苦労していることはわかっている。そして私がお人好しかもしれないという自覚は深まっている。人を雇うということの難しさもわかってきた。ただ、それはそれとして、貯金はどんどん減っていくのである。

敵は組織?―現場の人に愛されるには― / 1_職場の方針は「バッタ退治」
2012年9月、大干ばつの前年とはうって変わってサバクトビバッタが発生し、研究所は慌ただしくなった。モーリタニア(国土は日本の3倍)の各方面に、バッタがどこにどのくらい発生しているのかを突き止める調査隊を送りこむ。大量のバッタを発見次第、殺虫剤を満載した防除隊がすみやかに派遣される。砂漠の真ん中からでも無線通信を使って数百キロ離れた首都の研究所本部に情報が届くため、ただちに対策を練ることができる。バッタがモーリタニアのあちこちで発生しはじめると、合計車両50台、総員100名がフル稼働して対応する。
私も調査地を決めるときは調査隊からの情報を利用する。待ちに待っていたバッタの群れが発見され、すぐに調査の準備にとりかかったのだが、手違いでバッタの群れが退治されてしまった。喜んでいる職員の傍らでやりきれない自分。そんな悲劇が3回続いた。バッタを退治することを目的とする研究所と、生きたバッタの調査を目的とする自分。自分が身を置いている研究所が、バッタ研究の天敵だということに気づく。盲点だった。
バッタは過去100年以上にわたり、膨大な数の研究がおこなわれてきたが、いまだに不明な点が多く、合理的な防除技術が確立されていない。このため、大発生がおこってしまったあとの対策としては、大規模な殺虫剤の散布に頼るしかないのが現状であり、広範囲に渡る環境汚染が問題となっている。

サバクトビバッタ問題が解決されない理由は、これまでの研究のほとんどが、このバッタが生息しない地域の実験室内でおこなわれていることにある。生息地での野外調査が十分におこなわれないため、詳しい生態がわかっていないのだ。しかし、本来のサバクトビバッタの生態を知らずに殺虫剤の撒き方だけを向上させようとしても、いつまで経ってもサバクトビバッタの大発生は阻止できないのではないだろうか?
バッタがいつ、どこで、なにをしているかという生態を明らかにできれば、その習性に基づいて大発生を予知し、環境に対する負荷のすくない害虫管理技術を開発できるはずだ。私はこれを成し遂げるために、モーリタニアで研究を続けているのだ
この地の人びとがバッタをすぐに退治したい気持ちもわかる。だが、私には以前から温め続けてきた、殺虫剤に頼らずに一網打尽にバッタを防除できるアイデアがある。それをかたちにするためにバッタの現地調査が重要なのだ、とババ所長に訴えた。所長は研究の重要性を理解してくれた。防除の前に調査が優先されることになった。
しかし、手違いがまたおこった。
明日に続く・・・・・
https://youtu.be/X4XGBBYQqkg == Devastates East Africa ==
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
前節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/a75b0e420053813e14f7fd95a16ff294
後節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/0254a8ee17f40573bf20a1f2fa03b698 >
----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------
【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/
【壺公夢想;如水総覧】 :https://thubokou.wordpress.com/
================================================
森のなかえ
================================================