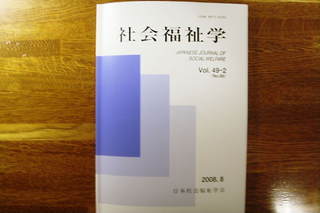
社会福祉学を代表する学会である
日本社会福祉学会が発行する『社会福祉学』第49巻ー2号(通算86号)が届いた。
(写真は、表紙)
巻末の編集後記によると、年4回発行の本誌には、毎号30~40の原稿が寄せられるという。査読付の学会誌ということでハードルが高い。
この号では、12の論文が収載されている。
【分野】
12の論文のテーマをみると
福祉哲学 1
歴史 3(ベンサム、高木健次、石井十次)
高齢者福祉5
知的障害 難病 国際福祉 各1
となる。
【方法論】
統計ソフトSPSSを使用しての分析が3件
インタビューなどによる質的調査 5件
*KJ法、グランディッド・セオリーの併用
・・・最近のエビデンス・ベースト(証拠にもとづく研究)の流れから当然かとも思いますが、私には読みこなせない難しいものが多くなってきた。
*文献研究は、4件ですが、いずれの論文にも末尾に掲げる文献欄にはウェブサイトのリストはなかった。
【地域的な偏在】
掲載論文12件のうち、関東・関西圏から9件。
地方からのものは、新潟、岡山、山口の3件でした。
*機関紙編集委員は16人ですが、12大学に勤務している先生方。
東京9大学、大阪2、名古屋1 となっています。
【福祉哲学】
冒頭の論文:
中村剛:社会福祉における正義ー「仕方ない」から「不正義の経験」へー
pp.3-15
を読みました。
内外の文献を駆使した力作ですが、はっきりいってよく理解できませんでした。
ここにかかれていることを学部学生に伝えるのは相当読み返さないと無理だと思われました。
この論文の最後は、次のように結ばれています。
・・・行うべきことは、社会福祉による正義により、現行の法を脱構築することである。社会福祉の正義によって駆動する脱構築の営みこそが、岡村(重夫)が指摘する「社会福祉全体の自己改造の原動力」となるのではないだろうか。
皆さん、意味はわかりましたか?
*「脱構築」とは、哲学者デリデの提唱した概念。
「岡村」とは、岡村重夫で、その『社会福祉原論』(1983年)は、今日まで社会福祉学の基礎理論として読まれている。
【年金や医療は社会福祉学の関心ではないのか?】
多くの人々が関心を持ち、不安を持っている問題。
医療、年金、介護、社会福祉専門職、社会福祉の営業・経営など、
政策的な課題の論文はありませんね。
この学会誌を見る限り、方法論的には精緻を極めてきたようですが、目下の政策課題を分析したものはないようです。
日本社会福祉学会が発行する『社会福祉学』第49巻ー2号(通算86号)が届いた。
(写真は、表紙)
巻末の編集後記によると、年4回発行の本誌には、毎号30~40の原稿が寄せられるという。査読付の学会誌ということでハードルが高い。
この号では、12の論文が収載されている。
【分野】
12の論文のテーマをみると
福祉哲学 1
歴史 3(ベンサム、高木健次、石井十次)
高齢者福祉5
知的障害 難病 国際福祉 各1
となる。
【方法論】
統計ソフトSPSSを使用しての分析が3件
インタビューなどによる質的調査 5件
*KJ法、グランディッド・セオリーの併用
・・・最近のエビデンス・ベースト(証拠にもとづく研究)の流れから当然かとも思いますが、私には読みこなせない難しいものが多くなってきた。
*文献研究は、4件ですが、いずれの論文にも末尾に掲げる文献欄にはウェブサイトのリストはなかった。
【地域的な偏在】
掲載論文12件のうち、関東・関西圏から9件。
地方からのものは、新潟、岡山、山口の3件でした。
*機関紙編集委員は16人ですが、12大学に勤務している先生方。
東京9大学、大阪2、名古屋1 となっています。
【福祉哲学】
冒頭の論文:
中村剛:社会福祉における正義ー「仕方ない」から「不正義の経験」へー
pp.3-15
を読みました。
内外の文献を駆使した力作ですが、はっきりいってよく理解できませんでした。
ここにかかれていることを学部学生に伝えるのは相当読み返さないと無理だと思われました。
この論文の最後は、次のように結ばれています。
・・・行うべきことは、社会福祉による正義により、現行の法を脱構築することである。社会福祉の正義によって駆動する脱構築の営みこそが、岡村(重夫)が指摘する「社会福祉全体の自己改造の原動力」となるのではないだろうか。
皆さん、意味はわかりましたか?
*「脱構築」とは、哲学者デリデの提唱した概念。
「岡村」とは、岡村重夫で、その『社会福祉原論』(1983年)は、今日まで社会福祉学の基礎理論として読まれている。
【年金や医療は社会福祉学の関心ではないのか?】
多くの人々が関心を持ち、不安を持っている問題。
医療、年金、介護、社会福祉専門職、社会福祉の営業・経営など、
政策的な課題の論文はありませんね。
この学会誌を見る限り、方法論的には精緻を極めてきたようですが、目下の政策課題を分析したものはないようです。

























