映画のあらすじ
主人公のビリー・ビーン(ブラッド・ピット)は高校時代は花形選手だったがメジャーリーグでは大成することなく引退した。引退後は球団のスカウト業務を経験して、現在は球団のゼネラルマネージャーである。
この辺のいきさつはわからない。というか映画の中でも語られていない。本筋ではないのであろう。
球団はいわゆる貧乏弱小球団。優勝争いに食い込むための有名選手を採る資金がなく、ジリ貧で負けが見えている。
そんな球団のGM(ゼネラルマネージャー)であるビリーは、イェール大学経済学部卒の青年ピーター・ブランドと出会い、セイバーメイトリクス理論に傾倒、データーに基づいた選手評価法を実践することで、チームの建て直しを謀る。
実話を基にした作品。
余談だが、ハリウッドではスポーツクラブのマネジメントをテーマにした作品が意外と多い(日本映画では皆無だが)。その中でも、アメリカと言うお国柄のためか、野球、アメフトが多い。“インビクタス/負けざる者たち”や“リプレイスメント”など。意外なことにコメディーでも“がんばれベアーズ”など、マネジメントをテーマに据えた映画があったりする。映画を大別するジャンル(アクション、コメディーサスペンスなど)と別の軸で“マネジメント映画”というカテゴリーを設定しても面白い。
なお、マネーボールの監督はベネット・ミラー。知名度はないが、オフビートで淡々とした作品をとる監督である。脚本は、アーロン・ソーキン。恋愛以外をテーマに据えることのできる、ハリウッドでは比較的珍しい脚本家である。
ポイント
ストーリーは、ビリーが弱小球団の改革を始めるところから始まる。
優秀な選手は金持ち球団(ヤンキースなど、日本で言えば巨人軍)にとられているため、安い選手を探すしかない、どうやって探すか。従来であればスカウトが実績はないが将来有望な選手を探してくる。この映画の中の一般的なスカウトもそうだ。しかしこの映画では、そのスカウトを旧態依然とした抵抗勢力として描いている。ビリーはスカウトをまったく頭から信用しない。
なぜなら
“ 実績はないが将来有望な選手”
が
“結果を出す選手”
であるかわからないからだ。データ(未来の結果)による裏付けはない。裏付けがあるとしたら、“スカウトの勘”だけである。
なぜ、ビリーはスカウトを信用しないのか、これも掘り下げると主人公の過去にかかわりが深そうで面白いが、映画ではそのあたりの時間軸が割愛されているので、本稿でも記載しない。
結果的にこの作品では、
従来のやり方で選手を集めた金持ち球団ヤンキースが、一試合勝つために150万ドルを投資していたのに対して、
球団内の抵抗勢力を黙らせて、同シーズンで同じくらいの勝ち星をとった主人公のアスレチックスは一試合25万ドルでそれを実現している。
どうやってそれを実現したか。
それはセイバーメイトリクス理論に基づいて、「300万ドルの価値の選手を27万ドルで買った」
ことではない。
どうやって、抵抗勢力を抑え
どうやって、人を動かしたか
である。
1.選択肢を狭める
ビリーはGMであり、その下に、チームを実務的に取仕切る監督が別に居る。しかしこの監督はビリーのイエスマンではない。つまりスカウトと同じく、ビリーの改革の抵抗勢力である。この監督を、どうコントロールして、ビリーの求める目標達成のために利用するか。
ビリーは理論に基づき、ハッテバーグという選手を一塁手にしろと監督に詰め寄るが、ハッテバーグは一塁手の経験がない。監督は当然これを拒否する。実例がないからだ。それよりも監督は実績もあり(スカウト曰く)将来有望な一塁手ペーニャを使いたくて、GMであるビリーの命令を無視する。
部下(監督)が、命令を実行しないときに、上司(ビリー)はどうしたか。
実は監督がペーニャを使いたい理由は、チームの勝利のためだけではない。将来有望な選手を出さないという采配をすれば、評論家やファンから何を言われるかわからない。チームが負けても既得権益をもった人間に嫌われたら、監督自身の再就職すら危うくなる。このような自己保身によるところもあり、ビリーの命令に従わない。そのものずばり「俺がこの仕事を続けるためにも、俺はペーニャを使う」というセリフを、監督はビリーに伝えている。
ここでビリーは、監督を更迭する、というオプションを使用しない。自己保身しか頭にないダメ監督を切ることはしない。ではどうしたか。
ビリーは、監督ではなく、監督お気に入りのペーニャをトレードに出す。こうなっては監督はビリーの命令にあるハッテバーグを使用せざるを得ない。監督には他に選択肢がなくなるからである。
ビリーはすべてを賭けてチームを改革しようとしている。当然である。ビリーの信じる理論で成功しなければビリー自身、今後の野球界でのポジションはない。
“データ分析で野球の結果を出せるというヨタ話を信じたGM”
なんて誰からもお呼びはかからないためだ。結果がでなければそうなる。
ビリーのモチベーションを他人(この場合は監督)と共有することはできない。それでも目標を達成しなくてはならない。どうしたのか。
ビリーは目的達成のために、部下の選択肢を制限した。
このビリーの手法のすばらしいところは、もしビリーの理論で勝利を重ねることができれば(もちろんそれができなければビリーは破滅だが)、監督の評価は「無茶なGMの采配にもめげずにチームを勝利に導いた名称」となるところだ。監督の目標達成のためのメリットには合致している。
さらには、「俺のお気に入りのペーニャをトレードに出すなんて!もういいやめてやる!あとは勝手にやってくれ!」と監督が言えないのである。
“自分から辞めた監督”
なんて誰からもお呼びはかからないためだ。
ここで、目標が異なっていても、GMと監督のベクトルが一致する。
2.目標とはなにか
「GMは金を出して選手を買うことが目標ではない。金を出して勝利を買うことである」映画の中でも印象的に使われるこのセリフは、ビリーの改革意識を強固なものとしている。
優先順位を如何につけるかが、目標達成には不可欠である。また、上記1.にあるように、ポジションによって目標は異なる。
おわりに
客観的評価は、誰にとっても難しくない。上記の目的達成のための行動は映画の中では理論だてて理解できるが、実際はどうであろうか。
当事者が如何に理解しているかはわからない。しょせん映画である。
と思考停止することもできるが、マネーボールではこの逃げ道を与えていない。
イェール大卒のピーターが、ビリーにマイナーリーグの試合映像を見せるシーンだ。
何が正しいかは、わからないのである。
『マネーボール』予告編
主人公のビリー・ビーン(ブラッド・ピット)は高校時代は花形選手だったがメジャーリーグでは大成することなく引退した。引退後は球団のスカウト業務を経験して、現在は球団のゼネラルマネージャーである。
この辺のいきさつはわからない。というか映画の中でも語られていない。本筋ではないのであろう。
球団はいわゆる貧乏弱小球団。優勝争いに食い込むための有名選手を採る資金がなく、ジリ貧で負けが見えている。
そんな球団のGM(ゼネラルマネージャー)であるビリーは、イェール大学経済学部卒の青年ピーター・ブランドと出会い、セイバーメイトリクス理論に傾倒、データーに基づいた選手評価法を実践することで、チームの建て直しを謀る。
実話を基にした作品。
余談だが、ハリウッドではスポーツクラブのマネジメントをテーマにした作品が意外と多い(日本映画では皆無だが)。その中でも、アメリカと言うお国柄のためか、野球、アメフトが多い。“インビクタス/負けざる者たち”や“リプレイスメント”など。意外なことにコメディーでも“がんばれベアーズ”など、マネジメントをテーマに据えた映画があったりする。映画を大別するジャンル(アクション、コメディーサスペンスなど)と別の軸で“マネジメント映画”というカテゴリーを設定しても面白い。
なお、マネーボールの監督はベネット・ミラー。知名度はないが、オフビートで淡々とした作品をとる監督である。脚本は、アーロン・ソーキン。恋愛以外をテーマに据えることのできる、ハリウッドでは比較的珍しい脚本家である。
ポイント
ストーリーは、ビリーが弱小球団の改革を始めるところから始まる。
優秀な選手は金持ち球団(ヤンキースなど、日本で言えば巨人軍)にとられているため、安い選手を探すしかない、どうやって探すか。従来であればスカウトが実績はないが将来有望な選手を探してくる。この映画の中の一般的なスカウトもそうだ。しかしこの映画では、そのスカウトを旧態依然とした抵抗勢力として描いている。ビリーはスカウトをまったく頭から信用しない。
なぜなら
“ 実績はないが将来有望な選手”
が
“結果を出す選手”
であるかわからないからだ。データ(未来の結果)による裏付けはない。裏付けがあるとしたら、“スカウトの勘”だけである。
なぜ、ビリーはスカウトを信用しないのか、これも掘り下げると主人公の過去にかかわりが深そうで面白いが、映画ではそのあたりの時間軸が割愛されているので、本稿でも記載しない。
結果的にこの作品では、
従来のやり方で選手を集めた金持ち球団ヤンキースが、一試合勝つために150万ドルを投資していたのに対して、
球団内の抵抗勢力を黙らせて、同シーズンで同じくらいの勝ち星をとった主人公のアスレチックスは一試合25万ドルでそれを実現している。
どうやってそれを実現したか。
それはセイバーメイトリクス理論に基づいて、「300万ドルの価値の選手を27万ドルで買った」
ことではない。
どうやって、抵抗勢力を抑え
どうやって、人を動かしたか
である。
1.選択肢を狭める
ビリーはGMであり、その下に、チームを実務的に取仕切る監督が別に居る。しかしこの監督はビリーのイエスマンではない。つまりスカウトと同じく、ビリーの改革の抵抗勢力である。この監督を、どうコントロールして、ビリーの求める目標達成のために利用するか。
ビリーは理論に基づき、ハッテバーグという選手を一塁手にしろと監督に詰め寄るが、ハッテバーグは一塁手の経験がない。監督は当然これを拒否する。実例がないからだ。それよりも監督は実績もあり(スカウト曰く)将来有望な一塁手ペーニャを使いたくて、GMであるビリーの命令を無視する。
部下(監督)が、命令を実行しないときに、上司(ビリー)はどうしたか。
実は監督がペーニャを使いたい理由は、チームの勝利のためだけではない。将来有望な選手を出さないという采配をすれば、評論家やファンから何を言われるかわからない。チームが負けても既得権益をもった人間に嫌われたら、監督自身の再就職すら危うくなる。このような自己保身によるところもあり、ビリーの命令に従わない。そのものずばり「俺がこの仕事を続けるためにも、俺はペーニャを使う」というセリフを、監督はビリーに伝えている。
ここでビリーは、監督を更迭する、というオプションを使用しない。自己保身しか頭にないダメ監督を切ることはしない。ではどうしたか。
ビリーは、監督ではなく、監督お気に入りのペーニャをトレードに出す。こうなっては監督はビリーの命令にあるハッテバーグを使用せざるを得ない。監督には他に選択肢がなくなるからである。
ビリーはすべてを賭けてチームを改革しようとしている。当然である。ビリーの信じる理論で成功しなければビリー自身、今後の野球界でのポジションはない。
“データ分析で野球の結果を出せるというヨタ話を信じたGM”
なんて誰からもお呼びはかからないためだ。結果がでなければそうなる。
ビリーのモチベーションを他人(この場合は監督)と共有することはできない。それでも目標を達成しなくてはならない。どうしたのか。
ビリーは目的達成のために、部下の選択肢を制限した。
このビリーの手法のすばらしいところは、もしビリーの理論で勝利を重ねることができれば(もちろんそれができなければビリーは破滅だが)、監督の評価は「無茶なGMの采配にもめげずにチームを勝利に導いた名称」となるところだ。監督の目標達成のためのメリットには合致している。
さらには、「俺のお気に入りのペーニャをトレードに出すなんて!もういいやめてやる!あとは勝手にやってくれ!」と監督が言えないのである。
“自分から辞めた監督”
なんて誰からもお呼びはかからないためだ。
ここで、目標が異なっていても、GMと監督のベクトルが一致する。
2.目標とはなにか
「GMは金を出して選手を買うことが目標ではない。金を出して勝利を買うことである」映画の中でも印象的に使われるこのセリフは、ビリーの改革意識を強固なものとしている。
優先順位を如何につけるかが、目標達成には不可欠である。また、上記1.にあるように、ポジションによって目標は異なる。
おわりに
客観的評価は、誰にとっても難しくない。上記の目的達成のための行動は映画の中では理論だてて理解できるが、実際はどうであろうか。
当事者が如何に理解しているかはわからない。しょせん映画である。
と思考停止することもできるが、マネーボールではこの逃げ道を与えていない。
イェール大卒のピーターが、ビリーにマイナーリーグの試合映像を見せるシーンだ。
何が正しいかは、わからないのである。
『マネーボール』予告編










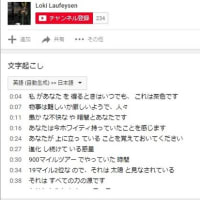
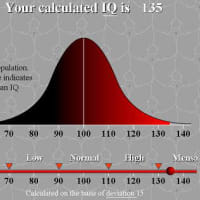
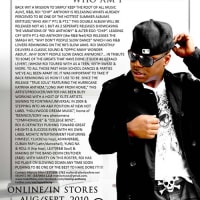




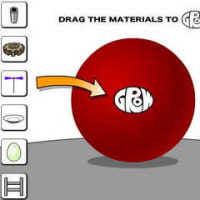

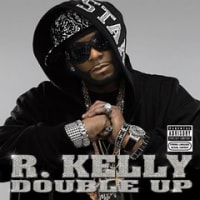
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます