昨日、ちょっと時間がありましたので、アメフトの関西学生リーグのファンなら誰でも知っている、あの「涙の日生球場」(ご存じなくてご興味のある方は、検索でもしていただければすぐにわかります)の試合の映像を視ましたので、その感想でも書いてみたいと思います。
私が視たのは、当時毎日放送で放送され、GAORAで再放送されたものを以前録画したもので、試合結果(スコア含む)はとうに知っているものではありますが、改めてちゃんと視てみると、知らなかったことも多く、結果が分かっているにもかかわらず、本当に面白かったです。
私の「事前知識」としては、「関学のパントフェイクからの越中のラン」といったものがあったということですが、ああいったトリックプレーは、いわば関学の「お家芸」であって、それ自体には意外性といったものはなく(もちろん食らった側が痛いことは痛いのですが)、しかもその後に京大がパスインターセプトを食らわせ、関学の攻撃の流れを一旦は切っているので、映像を視た限り、そのこと自体が試合結果を左右した印象はないです。
とはいえ、下馬評で優勢を伝えられていた京大にとって、あの試合では「誤算」といったものが数多くあり、例えば、試合の初めの方の、距離的にどう考えても外すはずのない先制FGを外してしまったのも、今回初めて知りました。さらに、雨の試合ということもあって、ボールを持つ手が滑って、ファンブルロストということになってしまい、関学に攻撃権を奪われて、結果として失点につながったというケースもありました。しかし、関学の方もターンオーバーで攻撃権を失ったことも一度や二度ではないので、それはお互い様ですね。
「誤算」というより「勝負のアヤ」といった方がいいのかもしれませんが、関学が1点差に迫るTDの後、最初TFPのキックで同点を狙うのですが(これが私には意外でした。いつもの関学の「やり口」を考えると、最初から2点コンバージョンを狙うと思っていました)、京大の反則でハーフディスタンス(といってもたった1.5ヤードですが)の罰退をゲットした時点で、2点コンバージョンでの逆転の意志を明確にし、QB猿木を投入して、実際に逆転してしまうわけですが、これがもし反則がなくて「同点」に終わっていたら、京大選手たちの「心理」もどうなっていたのかと思わずにはいられません。
その後、関学がさらに7点を追加して、京大は8点差を追って(TDを決めて、2点コンバージョンを成功させれば、同点(そしてたぶん「引き分け」)のチャンスはあります)、最後のドライブに挑むわけですが、結果的にこの試合最後になってしまったプレーにおいて、4thダウンという状況で(つまりこのプレーが失敗すれば試合は事実上「終わり」ということです)、1stダウン獲得につながるパスを成功させるのですが、パスをキャッチしたレシーバーがボールを持ったままサイドラインから出たつもりになっていた(そうなれば時計は止まりますから、少なくともあと1回ぐらいは攻撃ができます)にもかかわらず、インバウンズでのダウンという判定になってしまったので、そのまま時計が進んでしまい(タイムアウトも使い果たしていました)、なんと試合が終わってしまったのです。上記判定を京大オフェンスがちゃんと認識していれば、急いでセットしてスパイクでもやって、やはりもう1回ぐらいは攻撃できたかもしれないのに、本当にもったいないことでした。
とまあ、細々としたことを書きましたが、京大側にとって「最大の誤算」は、関学QB猿木の「ラン」ではなかったかと思います。この年、ミルズ杯を獲得したエースランナー越中に走られてしまうのは、ある程度想定内だったと思いますが(実際結構走られてしまいました)、肝心なところで、これほど猿木に走られてしまうとは(典型的な例が2Q終了間際ぐらいのTDランですね)、京大側も思っていなかったのではないでしょうか。京大もこの試合に際して何の対策も立てていなかったわけではなく、むしろ猿木の「パス」は完全に封じていたのです。
上記の一連の光景を目の当たりにした私は、「勝負事というのは本当に難しいものなのだなあ」という、当たり前といえば当たり前のことを感じました。対戦相手を上回る地力を持ち、ちゃんと対策を打っていても、想定外のことが次々と起こってしまって、思ってもいない結果になってしまう。だから見ている方にとっては面白いのですが、当事者にとっては本当に大変なことなんだなあということを、「涙の日生」を視てしみじみと思いました。
私が視たのは、当時毎日放送で放送され、GAORAで再放送されたものを以前録画したもので、試合結果(スコア含む)はとうに知っているものではありますが、改めてちゃんと視てみると、知らなかったことも多く、結果が分かっているにもかかわらず、本当に面白かったです。
私の「事前知識」としては、「関学のパントフェイクからの越中のラン」といったものがあったということですが、ああいったトリックプレーは、いわば関学の「お家芸」であって、それ自体には意外性といったものはなく(もちろん食らった側が痛いことは痛いのですが)、しかもその後に京大がパスインターセプトを食らわせ、関学の攻撃の流れを一旦は切っているので、映像を視た限り、そのこと自体が試合結果を左右した印象はないです。
とはいえ、下馬評で優勢を伝えられていた京大にとって、あの試合では「誤算」といったものが数多くあり、例えば、試合の初めの方の、距離的にどう考えても外すはずのない先制FGを外してしまったのも、今回初めて知りました。さらに、雨の試合ということもあって、ボールを持つ手が滑って、ファンブルロストということになってしまい、関学に攻撃権を奪われて、結果として失点につながったというケースもありました。しかし、関学の方もターンオーバーで攻撃権を失ったことも一度や二度ではないので、それはお互い様ですね。
「誤算」というより「勝負のアヤ」といった方がいいのかもしれませんが、関学が1点差に迫るTDの後、最初TFPのキックで同点を狙うのですが(これが私には意外でした。いつもの関学の「やり口」を考えると、最初から2点コンバージョンを狙うと思っていました)、京大の反則でハーフディスタンス(といってもたった1.5ヤードですが)の罰退をゲットした時点で、2点コンバージョンでの逆転の意志を明確にし、QB猿木を投入して、実際に逆転してしまうわけですが、これがもし反則がなくて「同点」に終わっていたら、京大選手たちの「心理」もどうなっていたのかと思わずにはいられません。
その後、関学がさらに7点を追加して、京大は8点差を追って(TDを決めて、2点コンバージョンを成功させれば、同点(そしてたぶん「引き分け」)のチャンスはあります)、最後のドライブに挑むわけですが、結果的にこの試合最後になってしまったプレーにおいて、4thダウンという状況で(つまりこのプレーが失敗すれば試合は事実上「終わり」ということです)、1stダウン獲得につながるパスを成功させるのですが、パスをキャッチしたレシーバーがボールを持ったままサイドラインから出たつもりになっていた(そうなれば時計は止まりますから、少なくともあと1回ぐらいは攻撃ができます)にもかかわらず、インバウンズでのダウンという判定になってしまったので、そのまま時計が進んでしまい(タイムアウトも使い果たしていました)、なんと試合が終わってしまったのです。上記判定を京大オフェンスがちゃんと認識していれば、急いでセットしてスパイクでもやって、やはりもう1回ぐらいは攻撃できたかもしれないのに、本当にもったいないことでした。
とまあ、細々としたことを書きましたが、京大側にとって「最大の誤算」は、関学QB猿木の「ラン」ではなかったかと思います。この年、ミルズ杯を獲得したエースランナー越中に走られてしまうのは、ある程度想定内だったと思いますが(実際結構走られてしまいました)、肝心なところで、これほど猿木に走られてしまうとは(典型的な例が2Q終了間際ぐらいのTDランですね)、京大側も思っていなかったのではないでしょうか。京大もこの試合に際して何の対策も立てていなかったわけではなく、むしろ猿木の「パス」は完全に封じていたのです。
上記の一連の光景を目の当たりにした私は、「勝負事というのは本当に難しいものなのだなあ」という、当たり前といえば当たり前のことを感じました。対戦相手を上回る地力を持ち、ちゃんと対策を打っていても、想定外のことが次々と起こってしまって、思ってもいない結果になってしまう。だから見ている方にとっては面白いのですが、当事者にとっては本当に大変なことなんだなあということを、「涙の日生」を視てしみじみと思いました。



















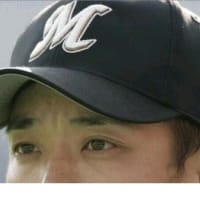
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます