本作で長編監督デビューとなる米林宏昌。
声の出演:志田未来、神木隆之介
ストーリー:主人公の小人族のアリエッティは14歳になり、自らの生活の糧を稼ぐ方法である「借り」を父親から教わるようになる。小人族は人間に姿を見せてはならないという掟があるが、アリエッティは病を抱える少年、翔に姿を見られてしまう。
思ったよりはいいと思ったけれども、突き抜けた面白さは全く感じない。一度観れば二度と観ない類の映画であるかもしれません。
「異種間コミュニケーション」が本作のテーマですね。
【滅びゆく生命】
本作に描かれた主人公二人の性質には共通点があります。それがこの物語の重要な前提になっています。それはアリエッティと翔は共に滅びゆく(可能性が高い)存在であるということ。
アリエッティは小人族。小人族はどうやら昔と比べて衰退してしまっている。昔近くに住んでいた種族は人間に見つかり、姿を消してしまった。翔の祖母も「昔はよく小人を見たけど、最近はすっかり見なくなってしまった」と言う。アリエッティの家族も僅か3人。他の小人族との交流もない。小人族は最早滅びる運命にある種族なのです。
そして、翔の方は病を抱えています。どのような病か忘れてしまいましたが(心臓だっけ?)、とにかく結構重い病気で手術しないと死にそうだ。という情報が映画からは読み取れます。

大事なのは翔がアリエッティに語りかけるシーンで、かなり劇中で浮いているシーンでもありますのでギョッとして覚えている方も多いかと思いますが、翔はアリエッティに「君らはどうせ滅びゆく種族なんだよ」と言います。この台詞は翔の死生観を端的に示しており、この言葉はむしろアリエッティというより翔が自分に向けて語っていると考えられます。それに対しアリエッティは猛然と反論します。この反応に翔はハッとします。明らかに滅びゆく種族であるアリエッティは、こんなにも生きる力に溢れている。それなのに自分は何だ、と。
【異種間のコミュニケーションと、それがもたらすもの】
異種間のコミュニケーションはアリエッティと翔のやり取りだけに止まりません。この映画に描かれた猫にも、その関係性は描かれています。猫は物語序盤にはアリエッティと翔に対し敵対的な行動を見せます。そしてそれは物語が進むにつれて、心を許すようになっていきます。最後に猫はどういった役割を担うのか?それはアリエッティと翔を「繋ぐ」役割を果たします。これがこの映画の根本的なテーマを集約した行動です。
異種間のコミュニーケーション、それは何をもたらすか?それは「明日を生きる力」です。前章で書いたようにメインキャラクターは滅びゆく存在ですが、アリエッティと関わることで翔は自らの死生観が打ち壊され、生きる力を取り戻していきます。一方アリエッティが翔と関わることで得た「生きる力」とは未来の亭主でした。アリエッティは一族の掟を守り、人間と関わることがなければ、家族3人静かに滅びていくのをただ待つばかりでした。しかし、翔と関わることによって発生した「引っ越し」の過程で他の小人族の男性と知り合うことになる。この出会いはアリエッティが子どもを授かる機会が生まれ、「小人族の滅亡」に対する小さな希望として描かれます。

主人公二人は本来決して関わることのない種族間のコミュニケーションによって「生きる力」を獲得していくのです。
【冒険活劇としての物足りなさ】
テーマ的なところはともかくとして『~アリエッティ』にはカタルシスが決定的に欠けるように思えます。それは勿論「冒険活劇ではないから」と言われてしまえばそれまでですが、これぐらいの内容であればテーマをもっと裏側に潜ませて、エンタメ要素を全面に打ち出してもいいようなものです(こんなにいい冒険が出来そうな設定があるのに)。
しかし映画を思い返すと、冒険活劇はしなかったのではなく、出来なかったのではないかという気がします。それは劇中内の描写に表れていると思うのですが、例えば、アリエッティが棚の上から居間の風景を見渡す一幕があるますが、このシーンに全くダイナミックさに欠ける。ただ我々が自分の家の中を見渡すのと同じような印象しか受けない。ここは絶対に失敗。もっと大胆な演出を付ける必要があったと思う。風がビュウビウ強く吹いてるとか、日差しが強く照りつけているとか。ここはアリエッティが初めて経験する広い世界なのだから、普通の人が初めて見るナイアガラの滝ぐらい強烈なインパクトが絶対に必要。それが出来ないのはやはり絵的な面白さを追求出来ないところの弱さがあったと思う。他にも意味ありげに拾う針とか、怪物的恐さを漂わせたネズミとか出しておきながら全く役に立ててない。こういうの無駄だと思います。こういうのをやるなら最低限『ミクロキッズ』ぐらいは楽しませて欲しかったです。
【最後に】
薄々感づいてはいましたが、『~アリエッティ』で確信しました。
ジブリはそう遠くない未来に日本を代表するアニメーション会社ではなくなるでしょう。なぜなら、我々が熱狂したジブリはイコール宮崎駿であり、彼の表現の根幹部分は伝承されることはなかったと見えたからです。ジブリは今後『~アリエッティ』の様な、そこそこの内容の映画を作ることは出来るでしょうが、宮崎駿が生み出したような圧倒的な世界観を駆け巡る体験や、抑えつけられていた力が暴発する瞬間のアニメーションカタルシスを見せることはきっとないでしょう。残念です。
オススメ度:


記事の内容がよかったら下のリンクをポチったって下さい。
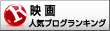
声の出演:志田未来、神木隆之介
ストーリー:主人公の小人族のアリエッティは14歳になり、自らの生活の糧を稼ぐ方法である「借り」を父親から教わるようになる。小人族は人間に姿を見せてはならないという掟があるが、アリエッティは病を抱える少年、翔に姿を見られてしまう。
思ったよりはいいと思ったけれども、突き抜けた面白さは全く感じない。一度観れば二度と観ない類の映画であるかもしれません。
「異種間コミュニケーション」が本作のテーマですね。
【滅びゆく生命】
本作に描かれた主人公二人の性質には共通点があります。それがこの物語の重要な前提になっています。それはアリエッティと翔は共に滅びゆく(可能性が高い)存在であるということ。
アリエッティは小人族。小人族はどうやら昔と比べて衰退してしまっている。昔近くに住んでいた種族は人間に見つかり、姿を消してしまった。翔の祖母も「昔はよく小人を見たけど、最近はすっかり見なくなってしまった」と言う。アリエッティの家族も僅か3人。他の小人族との交流もない。小人族は最早滅びる運命にある種族なのです。
そして、翔の方は病を抱えています。どのような病か忘れてしまいましたが(心臓だっけ?)、とにかく結構重い病気で手術しないと死にそうだ。という情報が映画からは読み取れます。

大事なのは翔がアリエッティに語りかけるシーンで、かなり劇中で浮いているシーンでもありますのでギョッとして覚えている方も多いかと思いますが、翔はアリエッティに「君らはどうせ滅びゆく種族なんだよ」と言います。この台詞は翔の死生観を端的に示しており、この言葉はむしろアリエッティというより翔が自分に向けて語っていると考えられます。それに対しアリエッティは猛然と反論します。この反応に翔はハッとします。明らかに滅びゆく種族であるアリエッティは、こんなにも生きる力に溢れている。それなのに自分は何だ、と。
【異種間のコミュニケーションと、それがもたらすもの】
異種間のコミュニケーションはアリエッティと翔のやり取りだけに止まりません。この映画に描かれた猫にも、その関係性は描かれています。猫は物語序盤にはアリエッティと翔に対し敵対的な行動を見せます。そしてそれは物語が進むにつれて、心を許すようになっていきます。最後に猫はどういった役割を担うのか?それはアリエッティと翔を「繋ぐ」役割を果たします。これがこの映画の根本的なテーマを集約した行動です。
異種間のコミュニーケーション、それは何をもたらすか?それは「明日を生きる力」です。前章で書いたようにメインキャラクターは滅びゆく存在ですが、アリエッティと関わることで翔は自らの死生観が打ち壊され、生きる力を取り戻していきます。一方アリエッティが翔と関わることで得た「生きる力」とは未来の亭主でした。アリエッティは一族の掟を守り、人間と関わることがなければ、家族3人静かに滅びていくのをただ待つばかりでした。しかし、翔と関わることによって発生した「引っ越し」の過程で他の小人族の男性と知り合うことになる。この出会いはアリエッティが子どもを授かる機会が生まれ、「小人族の滅亡」に対する小さな希望として描かれます。

主人公二人は本来決して関わることのない種族間のコミュニケーションによって「生きる力」を獲得していくのです。
【冒険活劇としての物足りなさ】
テーマ的なところはともかくとして『~アリエッティ』にはカタルシスが決定的に欠けるように思えます。それは勿論「冒険活劇ではないから」と言われてしまえばそれまでですが、これぐらいの内容であればテーマをもっと裏側に潜ませて、エンタメ要素を全面に打ち出してもいいようなものです(こんなにいい冒険が出来そうな設定があるのに)。
しかし映画を思い返すと、冒険活劇はしなかったのではなく、出来なかったのではないかという気がします。それは劇中内の描写に表れていると思うのですが、例えば、アリエッティが棚の上から居間の風景を見渡す一幕があるますが、このシーンに全くダイナミックさに欠ける。ただ我々が自分の家の中を見渡すのと同じような印象しか受けない。ここは絶対に失敗。もっと大胆な演出を付ける必要があったと思う。風がビュウビウ強く吹いてるとか、日差しが強く照りつけているとか。ここはアリエッティが初めて経験する広い世界なのだから、普通の人が初めて見るナイアガラの滝ぐらい強烈なインパクトが絶対に必要。それが出来ないのはやはり絵的な面白さを追求出来ないところの弱さがあったと思う。他にも意味ありげに拾う針とか、怪物的恐さを漂わせたネズミとか出しておきながら全く役に立ててない。こういうの無駄だと思います。こういうのをやるなら最低限『ミクロキッズ』ぐらいは楽しませて欲しかったです。
【最後に】
薄々感づいてはいましたが、『~アリエッティ』で確信しました。
ジブリはそう遠くない未来に日本を代表するアニメーション会社ではなくなるでしょう。なぜなら、我々が熱狂したジブリはイコール宮崎駿であり、彼の表現の根幹部分は伝承されることはなかったと見えたからです。ジブリは今後『~アリエッティ』の様な、そこそこの内容の映画を作ることは出来るでしょうが、宮崎駿が生み出したような圧倒的な世界観を駆け巡る体験や、抑えつけられていた力が暴発する瞬間のアニメーションカタルシスを見せることはきっとないでしょう。残念です。
オススメ度:



記事の内容がよかったら下のリンクをポチったって下さい。


































