出張明けの金曜日は休暇を取ってぶらぶら足を伸ばす計画、
目的地は定めていても、雨空はこのまま「ぼお~っ」と電車に揺られていたい気分にさせます。
でも、広島から山陽線を西へ1時間半ほど行くと、車窓から見える曇り空の瀬戸内海が穏やかに晴れてきました。
柳井(やない)の町並み
室町時代から瀬戸内海交易の主要港として栄え、江戸時代には岩国藩の「御納戸」と呼ばれるほど繁盛し、
港町の町割りがそのまま残っています。
京都や名古屋と同じで間口が狭く奥行きが深いのが特徴ですが、建物の白壁と格子窓が美しい調和を見せ、
建築様式も妻入り・入母屋・白漆喰の土蔵造で統一されています。
< <
<
<
<
<
<
<
ぶちええ‥ <
<
<

<

<

<

<

洒落たジャズピアノが流れる中、萩焼の御椀に注いでもらった珈琲を啜りながら、とりとめも無い話題…
小路は舟荷を荷車で蔵まで運ぶ通路、間口の狭いのは税金対策で、場所によっては奥行きが100mもある。
柳井は観光ルートの立ち寄り所の一つで、町興しにはまだまだ店の数が少ない。
東京から故郷の柳井に戻って蔵を改装して店を開いたとき、先祖が集めた高価な質草が蔵に眠っていて、
借用書も札束のように残っている。
店に飾ってあるものはすべて本物、団体客のマナーの悪さはなってない(笑)。
このご主人、なかなか気さくな人柄です^^
上質の西欧調度品にかこまれて、展示されている骨董と石庭を眺めながら、まったりとした時間が過ぎていく…。
「ぶちええ、珈琲専門の店」、堪能しました。
蔵屋&茶房難波庵
山口県柳井市古市481(掛屋小路)
TEL 0820-22-3791
10~18時 定休日 水曜定休
柳井散策
 to be continue?..
to be continue?..今からでも遅くない。もっと夏を見つけに行こう。と思っていたら、8月ももう終わり。
というわけで、今年の夏の画像を集めてみました。
宇治川花火大会
源氏絵巻の鳳凰の飛翔のごとく、川面の夜空に上がる花火。
口を開けて「すっげぇ、きれ~っ」って、首が痛くなった夏。






クマゼミ
ジャンジャンうるさい鬼の子を探し当てて追い払ったら、
思わぬ「お返し」を引っ掻けられた夏。



くいだおれ太郎
通りがかりの道頓堀のひとコマ、
こんなに人気者だったとは知らなかった夏。





あの苦しかった熱帯夜もすっかりなくなって、セミもぴたりといなくなり、
今、裏の畑で秋の虫が合唱を始めています。
このまま秋?。そんなわけないか(笑)
やるべきことは決まっているのに、頭が朦朧としてすっきりしない。こんなことってありませんか?
< | 曇り空の中、庭を眺めながら仕事のポジショニングを意識してみる。 常にグイグイ、「私が私が!・・・」って自己主張の強いタイプは、自らの意見と称してとんちんかんな主張をしたがってやがて敬遠されるもの・・・。 かといって「私は決められたことだけしかやりません」ってのは最悪です。 <  仕事には決まったルールや、やり方があるものの、常に空気は動いているから、その場その場でベストな選択を求めて、押したり引いたり・・・。 |
仕事のほとんどはこの調整ごとの繰り返しなのですが、後で振り返れば理に適った選択をしていることは少ないのが現実です。 その場の空気がどういう風に流れているのか?どういう目的を持っているのか?どうやったら結論が出るのか? 雑多な庭にヒントを探してみても、今一歩、踏み込めない自分を正当化するネガティブさにどっぷり浸かるだけ^^。 【アカンサスモリス(Acanthus mollis)】 |
地植えにしたジャネットが勢いよくシュートをあげてきました。 鉢植えのバラには、調子を崩すものも出てきていますが、維持することに振り回されることなく、 手のかからない範囲に縮小していくことにします。    できれば、アカンサスのように黙っていても存在感があって、暑さ寒さに耐える立派な根を張っていきたいものですね。 うぉっし、ファイト!だぁ~ |
ジューンベリーに絡みつくように咲く紫の名前のわからない品種です。
ホントはアリスタステラグレイと組み合わせたんですが、この組み合わせもいい感じです。



フィリスバイド(Phyllis Bide)は、開きかけのオレンジからゆっくりと虹色に変化します。



  | 【竹紙(ちくし)って】 和紙の原料には、こうぞやみつまた、葦やケナフなどの材料が一般的ですが、今回の竹紙(ちくし)は古くから伝承してきた材料で、和紙とは違った素朴な味わいを持っています。なお、竹の肉質部分(木質部)ではなく、竹の皮を使ってもいい風合いが出るそうです。 材料は2年間もかけて熟成させる必要があるとか。 ①若竹を夏に伐採し、溜池に100日以上漬けて発酵させます。 ②柔らかくなった竹を槌で叩いて粗い表皮を洗い去ると竹麻(ちくま)ができます。 ③この竹麻に石灰の液をまぜ八昼夜のあいだ煮立て、清水でよく漱ぎ、草木灰とともに煮ては冷ましを繰り返します。 ④10日あまり経つと繊維がふやけてきます。これを穀粉のようにどろどろにして清水に漬けたものが材料になります。 竹紙も和紙と同じく煮熟の際に木灰、石灰などのアルカリを煮熱剤(軟化剤)として使用し、「八昼夜」煮熟し、清水洗浄、そしてさらにこれを「十余日」繰り返し続ける必要がありますが、体験コースでは、この手間隙のかかる作業は割愛して、竹麻を扱いやすくふやけさせた材料が用意されています。 |
【竹紙漉き】 専用のすき枠の網の部分がちょうど浸かるくらいの水を入れたバットにすき枠を沈め、紙の材料をすき枠に流し込みます。何度か繰り返して、すき枠の隅々まで、均等になるように拡げていきます。   | 【水分の吸い取り】 すき枠を水から取り出し、枠を取り外してから布の上にひっくり返し、網の裏側から乾いたタオルを当てて、余分な水分を吸い取ります。    |
【トッピング】 モミジや松葉の色目のものを漉きこみます。そっと乗せた上から竹麻の液体をかぶせて、繊維のあいだに挟み込んでいきます。      |
| 【乾燥はアイロンで】 すきこんだ面を逆さに置き乾燥させます。本当は天日に晒して丸1日かかるんですが、体験コースではアイロンで、布から剥がれるのを確認しながら乾燥させます。温度を上げて、一度に乾燥させようとすると瘡蓋(かさぶた)のように剥がれなくなるので結構根気が要ります。   | 【切り離し】 十分に乾くと「するめ」が焼きあがるように剥がれてきます。板からはがれたら、切り目に折り目をつけて霧吹きで水分をさっとかけ、慎重に切り離します。     |
| 【できあがり】 最後はまたアイロンで仕上げます。竹の繊維は木材繊維に比べて手強く、パルプ化できないので、工業製品は作り出せないそうです。 【私の楽しみ】 美山の空気と手作り竹紙の旅は、娘の自由研究のテーマにと奥さんが前々から計画していたもの…。私はといえば、名物の「自家栽培のばら風呂(画像はありません)」を堪能しました。 でも、たしかバラは全く咲いて無かったのに…、 まぁ、いいか(笑) |


バックヤードには、たくさんの鉢植えが元気に開花を待っていましたが、これらは販売用のようでした。
でも、今回のほんとの目的は・・・(to be continued)。








庭のあちこちで、バラの蕾がスタンバっています。
朝からお向かいで引越しがあったようです。
社会人になった娘さんが近くで一人暮らしを始めるそうで、トラック一杯に荷物が運び出されていきました。思えば、最先端のブランドを身に着け、新車を2年ごとに買い換え、年に数度の海外旅行・・・








人は、自分の価値観で、こだわるところと手を抜くところが明確ですが、努力と偶然の曲がり角の先に幸運があるとすれば、その角を曲がるのは、年齢に関係なく自由なはずです。
その気になれば、時が遷っても変わらないであろう今の生活をリセットして、新たなチャレンジをすることも可能なはずです。




でも、結局、家族で外出するのは近所のホームセンターと回転寿司屋だったり・・・、今日の私の買い物はバラの薬と壊れた蛇口の先っぽ・・、
自分の将来への投資は、こんなんでいいのか?
お向かいの二階の部屋の電気が消えた休日の夜、ある種の焦燥感に駆られながら、こんなことを考えています。
社会人になった娘さんが近くで一人暮らしを始めるそうで、トラック一杯に荷物が運び出されていきました。思えば、最先端のブランドを身に着け、新車を2年ごとに買い換え、年に数度の海外旅行・・・








人は、自分の価値観で、こだわるところと手を抜くところが明確ですが、努力と偶然の曲がり角の先に幸運があるとすれば、その角を曲がるのは、年齢に関係なく自由なはずです。
その気になれば、時が遷っても変わらないであろう今の生活をリセットして、新たなチャレンジをすることも可能なはずです。




でも、結局、家族で外出するのは近所のホームセンターと回転寿司屋だったり・・・、今日の私の買い物はバラの薬と壊れた蛇口の先っぽ・・、
自分の将来への投資は、こんなんでいいのか?
お向かいの二階の部屋の電気が消えた休日の夜、ある種の焦燥感に駆られながら、こんなことを考えています。
各地で桜祭が真っ盛りですが、庭でも春の新芽があちこちから伸びてきて、賑やかになってきました。
朝からデジカメ片手にめぼしい花は無いかと・・









 ・・大した花はありませんでした(汗)
・・大した花はありませんでした(汗)
うちの庭は土が露出しているところが多くて、春になると、タンポポやカタバミがあちこちから芽を出し、放置しておくと瞬く間に雑草だらけになります。
野生のすみれもいつの間にか大株になっていますが、すみれの場合、秋に咲く目立たない花が結実するらしいので、春の花はこのまま咲かせることにしました。
ギボウシの株分けを今年も忘れていました。
ぶつくさ・・・、
あれもこれも反省の弁を綴っている時間があったら何とかしなくては(汗)
あれを・・ウッドフェンス製作日記(その1)
朝からデジカメ片手にめぼしい花は無いかと・・









 ・・大した花はありませんでした(汗)
・・大した花はありませんでした(汗)うちの庭は土が露出しているところが多くて、春になると、タンポポやカタバミがあちこちから芽を出し、放置しておくと瞬く間に雑草だらけになります。
野生のすみれもいつの間にか大株になっていますが、すみれの場合、秋に咲く目立たない花が結実するらしいので、春の花はこのまま咲かせることにしました。
ギボウシの株分けを今年も忘れていました。
ぶつくさ・・・、
あれもこれも反省の弁を綴っている時間があったら何とかしなくては(汗)
あれを・・ウッドフェンス製作日記(その1)
桜が満開になる頃ですが、今年の関西は異様に寒い日が多くて桜も関東から南下してきているようです。
この週末、お花見でも良かったんですが、肌寒いのは避けて、花鳥園に行ってきました。
おらぁ、花になんぞに興味はねえ、という方もラブリーな野鳥とふれ合えますよ^^。





この週末、お花見でも良かったんですが、肌寒いのは避けて、花鳥園に行ってきました。
 今回行ったのは、神戸花鳥園ですが、各地に姉妹店があります。 こういう所では、なぜか、私はかお客さんの表情を観察してしまいます。しばし、見ていると・・ ・はしゃぎ回るように見て回る人 ・ぼーっと眺めて見入っている人 ・花よりおしゃべりに夢中の人 ・ひたすら食べてるだけの人 ・無理やり連れてこられてうんざりな人 | 温室育ちの花が天井から集団で咲き乱れていて、そのボリューム感に圧倒されます。   |
おらぁ、花になんぞに興味はねえ、という方もラブリーな野鳥とふれ合えますよ^^。





勾玉(曲玉)作りに挑戦してきました。
勾玉といえば、古代の装身具の一つで、「魔を避け、幸運を授かる物」とされています。
最近、パワーストーンとして身に着ける人も多いのですが、あの湾曲した形の由来には諸説があります。
どれが正しいのでしょう?
古墳などから見つかる高価なヒスイの勾玉は、死者が身に着けたまま埋葬されたようですが、
古代シャーマニズムのミスマルの力で神政を治めたのでしょうか。
でも、何の為に?、謎は深まるばかり・・・
 今回は体験コースの簡単なものでしたが、本格的には石がローズクォーツやアメジスト等の硬い石になりますので、専用の工具が必要になります。
今回は体験コースの簡単なものでしたが、本格的には石がローズクォーツやアメジスト等の硬い石になりますので、専用の工具が必要になります。 形にも微妙なバリエーションがあるようですが、
形にも微妙なバリエーションがあるようですが、 世界に一つの自分だけのオリジナル勾玉を自分で磨いてみるのも楽しいですね。
世界に一つの自分だけのオリジナル勾玉を自分で磨いてみるのも楽しいですね。
ただ、石を磨く前に自分を磨くのもお忘れなく。
勾玉といえば、古代の装身具の一つで、「魔を避け、幸運を授かる物」とされています。
最近、パワーストーンとして身に着ける人も多いのですが、あの湾曲した形の由来には諸説があります。
・食べ物の動物や魚の骨や牙 ・月信仰から三日月 ・母親の胎内の初期の胎児 ・釣り針が装飾化したもの ・太極図を表すもの |   |
古墳などから見つかる高価なヒスイの勾玉は、死者が身に着けたまま埋葬されたようですが、
古代シャーマニズムのミスマルの力で神政を治めたのでしょうか。
 | 実際作ってみると、この柔らかい滑石(交通事故現場で道路にマークするときに使う石です)でも、時間のかかること・・・、2時間かけて、石の粉塗れになりました(笑) これが本物の翡翠(ひすい)や瑪瑙(めのう)だと優に1ヶ月ぐらいはかかりそうですね。 一番最初は暇をもてあました古代人の誰かが、自分が身に着けるために彫ったのだという気がしてなりません。 |
| 【製作工程】 ①材料は石版、やすり(大中小)とサンドペーパー。 ②石版に厚紙の型紙で形を書き込みます。 ③玉から尾が出たような形に削っていきます。 ④丸く膨らんだ一端に紐を通す為の穴をあけます。 ⑤最後はサンドぺーパーで磨いて水で洗い流します。 |    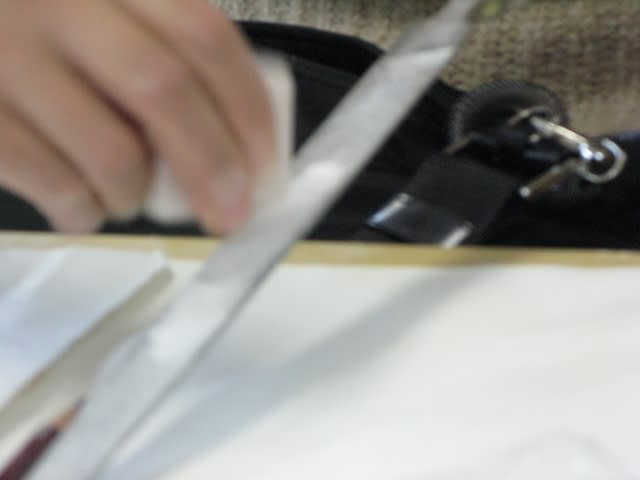   |
 今回は体験コースの簡単なものでしたが、本格的には石がローズクォーツやアメジスト等の硬い石になりますので、専用の工具が必要になります。
今回は体験コースの簡単なものでしたが、本格的には石がローズクォーツやアメジスト等の硬い石になりますので、専用の工具が必要になります。 形にも微妙なバリエーションがあるようですが、
形にも微妙なバリエーションがあるようですが、 世界に一つの自分だけのオリジナル勾玉を自分で磨いてみるのも楽しいですね。
世界に一つの自分だけのオリジナル勾玉を自分で磨いてみるのも楽しいですね。ただ、石を磨く前に自分を磨くのもお忘れなく。
画像は春霞の中の梅林です。



「違うんです。切った方がいい枝と切っちゃいけない枝があるんです」
結論は、相手に応じた剪定の仕方があるということに落ち着くようですが、植物も十人十色、同じ対応をしても相手によって全然違う結果が生まれるのは当然のこと。



しかし、春に咲く花をもじって「馬鹿」と言い切るこの諺・・、婉曲が多い諺の世界って奥が深い。
もうすぐ新年度がスタートしますが、春は人の心が沸き立つシーズン、
こんなときこそ、相手への気配りとその場にあった対応が必要です。
枝なら諦めもつきますが、人間関係だと後々まで後悔することもあり、柔軟な対応を心がけたいものですね。
別に枝のように切る必要は無いんですが(笑)

| 「桜切る馬鹿 梅切らぬ馬鹿」 古くからの園芸界の教えだとばかり思っていましたが・・・、これって諺だったんですね。 桜は切るとそこから腐って枯れるから切らない方がいい、梅は切らないと樹形が乱れて花が咲かなくなる。 この時期、バラの剪定の話題でも喧々諤々(けんけんがくがく)いろんな考え方が錯綜します。 「枝は切るから咲くんでしょ♪」 「んにゃ、枝は切っちゃいかん^^」 |



「違うんです。切った方がいい枝と切っちゃいけない枝があるんです」
結論は、相手に応じた剪定の仕方があるということに落ち着くようですが、植物も十人十色、同じ対応をしても相手によって全然違う結果が生まれるのは当然のこと。



しかし、春に咲く花をもじって「馬鹿」と言い切るこの諺・・、婉曲が多い諺の世界って奥が深い。
もうすぐ新年度がスタートしますが、春は人の心が沸き立つシーズン、
こんなときこそ、相手への気配りとその場にあった対応が必要です。
枝なら諦めもつきますが、人間関係だと後々まで後悔することもあり、柔軟な対応を心がけたいものですね。
別に枝のように切る必要は無いんですが(笑)
























 >
> <
< >
>




 >
>






















 >
>


 <
< <
< <
< <
< <
<





 >
>

