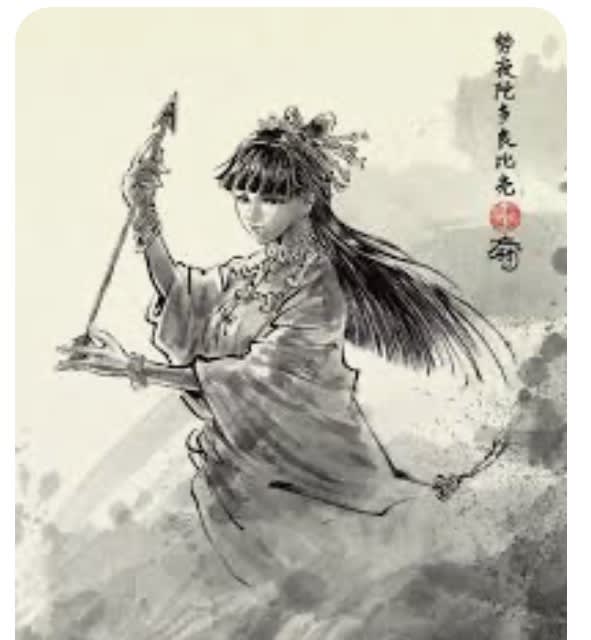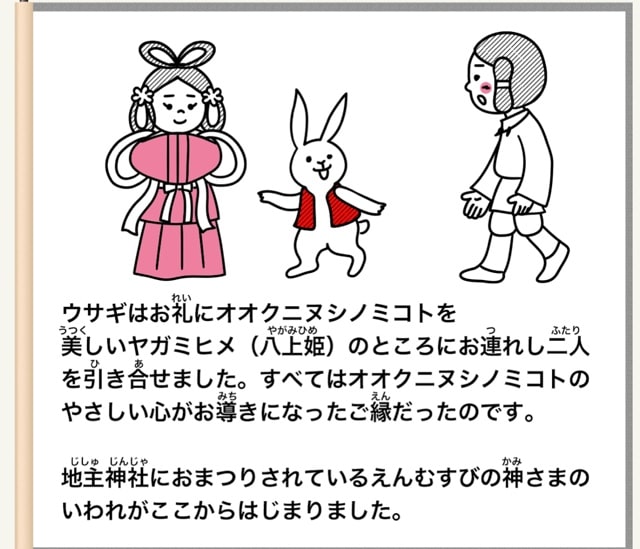三輪山登拝後は、三輪そうめんを食べました。暑い日でしたから、喉越しがよく、本当に美味しかったです。
その後、帰途には少し時間があるし、どうしようかなぁと思いましたが、話し合って六甲ヒメ神社に参拝する事にしました。妹は二回目で、私は初めてです。
六甲比咩神社は、祓戸筆頭、水の女神
瀬織津姫をお祀りします。


西宮の六甲山に以前いった時には越木岩神社や如意尼の神呪寺を参拝しました。六甲山は磐座が沢山あって、古代からの祈りの場だと感じました。
また、西宮にあります廣田神社は、今は天照大神荒御魂を主祭神としていますが、昔の御祭神は瀬織津姫だったようです。
廣田神社の御神体の神鏡は、元は宮中の賢所に祀られていたようですが、武内宿禰・神功皇后の御代に廣田神社にかえしたことが、廣田神社由緒書きに記されているようですね。
また、廣田神社の宝物には、剣珠があるようです。「日本書紀」に、「神功皇后が関門海峡長門豊浦の津に泊まり、海中より如意珠(こころままのたま)を得らると、見ゆるも是なり」とあり、八幡大神(應神天皇)、神功皇后に戦勝を授け、高野山を鳴動させた神通の霊宝として著名なものだと紹介されていました。
剣の形の現れたことから、剣珠と称され、現存する日本最高最古の如意宝珠のようです。

廣田神社ホームページより
『元亨釈書』の中の、甲山神呪寺の開基、如意尼の伝に、海中より得たる《如意宝珠= 劔珠》の件は記録されているようです。
空海の愛弟子、如意尼は真名井神社と縁深く、龍女のように感じています。
また、室町時代、五山文学の雄僧絶海中津は著書『蕉堅稿』の中で「所劔珠者絶世之奇観也」(←珠の中に剣があるのは世にもふしぎだたなぁ、、という意味かな?)と紹介し、
同じく室町時代の著名禅僧義堂周信もその書『空華集』に「霊光夜射九重天」「竜女神珠不直銭」と称賛しているとありました。
このお二人の僧、義堂 絶海は、母の故郷、高知県津野山出身で、十牛図を日本で紹介した御方です。
高知県津野町、津野山は龍仙界だと思っていますから、山奥の田舎から室町時代五山文学のトップがでたのを知った時には、津野山の龍神様の背に乗って飛んで行ったのかなぁと思いました。
瀬織津姫といえば、関東では、小野神社の主祭神でした。和邇氏や、龍神様に関連ある豊玉姫を想起させます。
また、伊勢神宮内宮別宮、荒祭宮の祭神の別名が「瀬織津姫」です。
荒祭宮は、かつては正宮に位置していたと推定されるとあります。伊勢神宮公式の由緒書きによると、御魂は、元は二宮に並べてお祭りされていたとあるようで、昔は式年遷宮のたびに位置を替えるのではなく、常に東に位置する正宮は天照大神、西に位置する正宮は瀬織津姫を祀っていたとWikipediaにはありました。西宮という地名の由来は、瀬織津姫様の坐す西に位置する宮、なのかもですね😌。勝手な空想かもしれませんが。
六甲ヒメ神社を管理されているお方がおり、神社の由来を色々お話をしてくださいました。宮司さんなのかはわかりませんが、とても宮を大切に思われていました。昔は常に伊勢神宮でニ宮並べて祀られており明治以降に?(☜記憶が曖昧、、)一宮に変えられたけれど、本来は二宮並べるのが望ましいとも言っておられました。

六甲比命大善神社は、女性的な優しい気を放つ神社です。


瀬織津姫様は饒速日命との関連もあると言われているようですね。夫婦神ということでしょう。
饒速日命が火、太陽、日なら、瀬織津姫は水、月というイメージですね。太陽(日)と月。水と火。調和。和。


お幸せに❤️