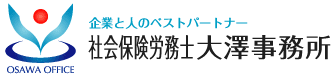顧問先の労災保険の請求は日常茶飯事といっても過言ではありません。
「そんなに労災事故ってあるんですか?」
と思われるかもしれませんが、ごく小さな負傷は日常茶飯事です。
1社でみれば数年に1件くらいかもしれませんが、労災申請を扱う社労士事務所
では、あの会社でも、この会社でもと、日常合わせると結構な件数になってしまいます。
不思議なもので、1回起きると、その会社では何度も起きるということもあります。
小さな負傷…。
例えば、作業中、何かを取ろうとして床ですべって転んで手や足を骨折。
何かが倒れてきて足に当たり骨折。
自転車に乗るとき、カバンのひもがひっかかって、自転車ごと転倒…。
一つひとつは取るにたらない「事故」でも、例えば「骨折した」となると、
休業日数も多く、作業の停滞、人員配置の見直しなどが迫られることもあります。
●ハイリッヒの法則
しかし、上のような取るにたらない小さな事故をほっておくと、
ある日突然、大きな事故が起こるかもしれません。
1つの重大な事故の陰には29の軽微な事故があり、その29の軽微な事故
の陰には300の危険(ヒヤリ・ハットした経験)が潜んでいると
言われているからです(ハイリッヒの法則)。
●ヒヤリ・ハット活動
300のささいな“ヒヤリ・ハット”を無くせば、重大な労災事故を防ぐことができる…。
作業現場、運転現場等では、ハイリッヒの法則から、ヒヤリ・ハット運動に取り組む
ことが作業場等での基本中の基本とされています。
ヒヤリ・ハット活動とは、全員で、自分が経験した「ヒヤリ・ハット」経験を
抽出し、そのような危険が起きないようにするには職場や作業をどう改善したらいいのか
を話し合い、その職場なりの決定の意志のもとに改善案を実施に移すことです。
●小規模事業所でもヒヤリ・ハット活動
小規模事業所ですと、なかなかこのような運動を展開するのは難しいと考える人は
多いかもしれません。
しかし、その一方で、大企業に比べて、会社としてまとまりやすいので、全員が
一丸となって取り組むことができるというメリットがあります。
●簡単なヒヤリ・ハット活動
小規模事業所でもできる簡単な活動の例を紹介しましょう。
・現状把握 どんな危険が潜んでいるか。
・本質追及 その危険の本質・影響は何か。
・対策樹立 危険をなくすにはどうしたいいのか。
・目標設定 話し合った内容をまとめ、重点目標を掲げる。
この4段階の活動は、班ごと、グループごとなど、比較的小さな集団の中で実施し、
アルバイト、パートを含めた全員が参加して話し合い、目標設定をします。
全員で決めた目標は、ポスターにして貼る、朝会で複数回に渡って確認するなど、
日常的に、全員参加型、見える化で進めていきます。
この、“日常的”、“見える化”がこの活動では大切なことです。
このような活動を定期的に進めていきます。
●ヒヤリ・ハットを無くす職場の力
どうでしょう。これならあなたの職場でもできそうではありませんか。
「イヤー、うちの職場ではちょっと…」と
二の足を踏む方は、例えば、
4S(整理、整頓、清潔、清掃)の推進などはどうでしょう。
これらの活動もヒヤリ・ハット活動に通じるものと思います。
ヒヤリ・ハット活動は、何よりも、費用がかかりません。
業種も問いません。
班ごとに活動を発表し合い、「優秀」な班には「表彰する」なども、
職場内にこの活動を定着させる工夫の一つと言えるでしょう。
コミュニケーション・ツールとしてもいいのではないでしょうか。
あなたの会社でも取り組んでみませんか。
 にほんブログ村
にほんブログ村
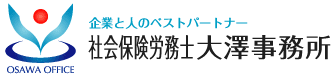
「そんなに労災事故ってあるんですか?」
と思われるかもしれませんが、ごく小さな負傷は日常茶飯事です。
1社でみれば数年に1件くらいかもしれませんが、労災申請を扱う社労士事務所
では、あの会社でも、この会社でもと、日常合わせると結構な件数になってしまいます。
不思議なもので、1回起きると、その会社では何度も起きるということもあります。
小さな負傷…。
例えば、作業中、何かを取ろうとして床ですべって転んで手や足を骨折。
何かが倒れてきて足に当たり骨折。
自転車に乗るとき、カバンのひもがひっかかって、自転車ごと転倒…。
一つひとつは取るにたらない「事故」でも、例えば「骨折した」となると、
休業日数も多く、作業の停滞、人員配置の見直しなどが迫られることもあります。
●ハイリッヒの法則
しかし、上のような取るにたらない小さな事故をほっておくと、
ある日突然、大きな事故が起こるかもしれません。
1つの重大な事故の陰には29の軽微な事故があり、その29の軽微な事故
の陰には300の危険(ヒヤリ・ハットした経験)が潜んでいると
言われているからです(ハイリッヒの法則)。
●ヒヤリ・ハット活動
300のささいな“ヒヤリ・ハット”を無くせば、重大な労災事故を防ぐことができる…。
作業現場、運転現場等では、ハイリッヒの法則から、ヒヤリ・ハット運動に取り組む
ことが作業場等での基本中の基本とされています。
ヒヤリ・ハット活動とは、全員で、自分が経験した「ヒヤリ・ハット」経験を
抽出し、そのような危険が起きないようにするには職場や作業をどう改善したらいいのか
を話し合い、その職場なりの決定の意志のもとに改善案を実施に移すことです。
●小規模事業所でもヒヤリ・ハット活動
小規模事業所ですと、なかなかこのような運動を展開するのは難しいと考える人は
多いかもしれません。
しかし、その一方で、大企業に比べて、会社としてまとまりやすいので、全員が
一丸となって取り組むことができるというメリットがあります。
●簡単なヒヤリ・ハット活動
小規模事業所でもできる簡単な活動の例を紹介しましょう。
・現状把握 どんな危険が潜んでいるか。
・本質追及 その危険の本質・影響は何か。
・対策樹立 危険をなくすにはどうしたいいのか。
・目標設定 話し合った内容をまとめ、重点目標を掲げる。
この4段階の活動は、班ごと、グループごとなど、比較的小さな集団の中で実施し、
アルバイト、パートを含めた全員が参加して話し合い、目標設定をします。
全員で決めた目標は、ポスターにして貼る、朝会で複数回に渡って確認するなど、
日常的に、全員参加型、見える化で進めていきます。
この、“日常的”、“見える化”がこの活動では大切なことです。
このような活動を定期的に進めていきます。
●ヒヤリ・ハットを無くす職場の力
どうでしょう。これならあなたの職場でもできそうではありませんか。
「イヤー、うちの職場ではちょっと…」と
二の足を踏む方は、例えば、
4S(整理、整頓、清潔、清掃)の推進などはどうでしょう。
これらの活動もヒヤリ・ハット活動に通じるものと思います。
ヒヤリ・ハット活動は、何よりも、費用がかかりません。
業種も問いません。
班ごとに活動を発表し合い、「優秀」な班には「表彰する」なども、
職場内にこの活動を定着させる工夫の一つと言えるでしょう。
コミュニケーション・ツールとしてもいいのではないでしょうか。
あなたの会社でも取り組んでみませんか。