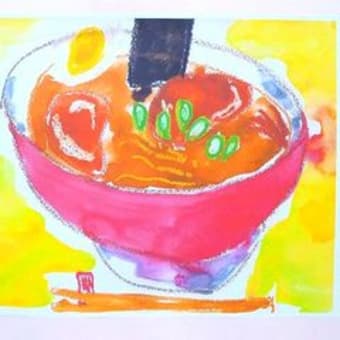「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
日常の面白い言葉にまた出会いました。今度は生徒さんから出てきた言葉です。
「ポワン、ポワン、フワ、フワ」
「クラゲがたくさんいた!」
「そう、クラゲはなに色?」
「クラゲは、とうめい!」
「クラゲは、どんな感じだった?」
「ポワン、ポワン、フワ、フワ」
「そう、ポワン、ポワン、フワ、フワ、・・・なるほど、ね」
「ポワン、ポワン、フワ、フワ」は、水族館で見たクラゲの形容です。自分から紡ぎだした言葉、楽しいですね。こんな言葉を紡ぎだす土壌は、どのように育てられたのでしょうか。
ひとつは、小さいときから絵本を通してたくさんの言葉に触れたきたことにあるのかもしれません。教室の月ごとのテーマに即して、親御さんはよくご自宅にある絵本を持ってきてくださいました。絵を描くことに加え、絵本を通して言葉の世界を広げてきました。ご本人も兄弟も大きくなって要らなくなった本は教室に下さるほど、ご家庭にはたくさんの本の環境があるのでしょう。
もう一つは、何につけても無理なく楽しく取り組んできたことにあるかもしれません。学校の授業や行事にも、地域の生活にも、もちろんご家庭での生活にも。教室でも、絵を描くことも工作をすることも、国語の勉強も算数の勉強も、どれも区別なく楽しんでしまうようなところがあります。これも、才能ですね!
仕事に就きながらも、毎日(月~金)の日記と決めた6枚のワークは必ずやってきます。でも時に、宿題の計算問題にまるをつけてあげようとすると、「計算機でやっちゃった・・・ふふふ」と笑っています。こちらも「えーっ、あらーっ」と言いながらも、「でも、宿題できたね」と大きなまるをあげます。お陰で、3桁でも4桁でも数の読みは得意です。計算機の操作もとても早いのです。思えば私たちだって、暗算で出来るもの意外は、計算機を使っています。携帯電話にも、計算機はついているのですから。
無理なく、楽しく、でもやるべきことはきちんと行い、本や、さまざまな場での人との交わりをもって豊かに生活していく、そんなところから言葉は紡ぎだされてくるのかもしれませんね。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp