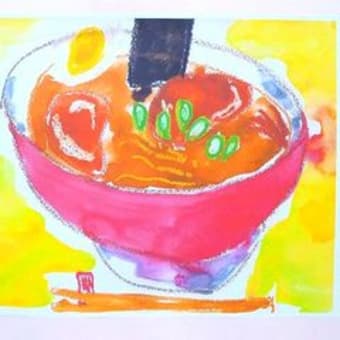「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
日曜日の新刊の欄(2009年12月6日読売新聞)に、山折哲雄「いま、こころを育むとは」が取り上げられていました。書評の冒頭に、「・・・全共闘の息の根をとめたのは、俵万智『サラダ記念日』だと説く」とあり、「えっ、どういうこと?」と思いつつ続きを読むと、その意図するところがすーっと浸透してきました。
少々長くなりますが、私の拙文ではお伝えしきれないものですので引用させていただきましょう、
「・・かつて紛争の嵐が吹き荒れたキャンパスで聞く学生の演説は、なぜ、心に響いてこなかったのか。それは、五七調や七五調と違う[われわれは、日帝の]式の”五五調”だったから。万葉集に始まる和歌のリズムこそが、日本人の呼吸や生命の根源なのではないか。女性歌人の人気沸騰の陰には、あのリズムの回復を待望する国民の<渇くような思い>があったはずだ」
学生運動の真っ只中だった頃、私は小学生でした。何かの雑誌の取材で学校で数人が選ばれ、インタビューに応じたことがあります。そこでどういう質問に対してであったかは忘れましたが、私が「全学連のー、ことはー、よくー、わかりませんがー、・・・」と何らかの返答をしたようです。その語調がこっけいだったのか、その後、父にさんざ茶化されたのでこの何語かだけが今でも思い出されます。
その頃のテレビニュースを見ていて、彼らの”五五調”のようなものが移ってしまったのでしょうか。語調というのは、すぐに人に移りやすいものです。それと同時に彼らの気持ちの高揚のようなものも多少入り込んでしまっていたのかもしれません。「学生運動」と聞くと、語調も気持ちの持ちようもパッと切り替わってしまうのです。言葉には、良くも悪くもそんな力があります。
いかがでしょう?私はさらに、日頃の授業での生徒さんへの言葉かけも振り返りました。
「さあ、数えるよ!よく見て!ずれないように!1、2、3、・・はい、ぜんぶで!」と一方的に言葉を発していることはないでしょうか?
ご家庭ではいかがでしょうか?
「さあ、時間よ!かばん持って!くつはいて!ほらっ、よく見て!」と一方的に言葉を発していることはないでしょうか?
生徒さん、お子さんはどんな言葉を渇望しているのでしょう。
「なぜ、心に響いてこなかったのか」・・・日常で五七調や七五調で言葉をかけることは難しくとも、呼吸や生命の根源をふと意識することはとても大切なことですね。「数えるよ!」「算数!」・・・と聞いただけで、生徒さんの気持ちがパッと堅く切り替わってしまうことがないように。むしろ「先生といっしょだからわかるよ」と生徒さんの中に安心感と意欲・興味がひろがるような言葉がけを日頃からこころがけたいものですね。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp