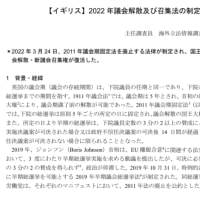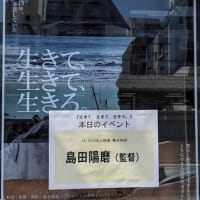学生だった頃はあまり勉強しなかったので、今になって不勉強を反省することが多い。
とはいえ、学び直しをしてみると、かつては気にもならなかったことが気になってくる。
そんなことを一つ述べてみたい。
世界史を学ぶと初期の文明の発展は、人間の使っていた道具とその素材が関係していると教わる。
石器時代(打製石器~磨製石器)から青銅器時代、そして鉄器時代へと変わり、鉄は今でも重要な素材であり続けている。
さてここで、打製石器や磨製石器は、どう作ったのかイメージすることはたやすい。
地域によっては、実際に作って、二つの違いを知ることも可能だろう。
ところが、青銅器~鉄器となるとそうはいかなくなる。
そもそも、なぜ青銅器が先で鉄器が後なのか?また、青銅は、銅と錫の合金だが、これは偶然に合金になったのだろうか?そ
れとも、それぞれ単体の銅と錫を作っていたが、合金にしたほうが、より固い金属になることを発見して青銅が生まれたのか?
そして次に世界を席巻することになる鉄器だが、いわゆる鉄の原料の鉄鉱石が含んでいるのは「酸化鉄」なので、これを鉄にするには「還元(=酸素を奪うこと)」が必要になる。なので、還元による製鉄法が確立される前人類は、隕鉄(隕石に含まれる鉄)が利用されていたという。
日本の近代史で、幕末のエピックとして「韮山反射炉」がある。自分がかつて勤務していた杉並区は伊豆の弓ヶ浜に宿泊施設があったので、移動教室の時の見学場所に入っていたのだが、今一つぴんと来なかった。
反射炉と溶鉱炉の違いが分かっていなかったのだ。
こうしたことを授業で扱うのは時間的な制約があって難しいだろうが、資料集や教科書のコラムのようなところで説明を入れてもらえると、理解が深まるのではなかろうか?
世界史の世界にも「科学の知識」が必要だと思う。
全く別の話だが、日本史の「征夷大将軍」のところで、「東夷、西戎、北狄、南蛮」という中国の思想を紹介しておくことも必要だと思う。
余談の断の余談だが、カレー南蛮やかも南蛮の「南蛮」は、南蛮とは無関係らしい。
共通する愚材の「葱」が大坂で栽培されていたので「なんば(難波)」がなまったものらしい。
(チコちゃんではないが、諸説あります!)
-K.H-
とはいえ、学び直しをしてみると、かつては気にもならなかったことが気になってくる。
そんなことを一つ述べてみたい。
世界史を学ぶと初期の文明の発展は、人間の使っていた道具とその素材が関係していると教わる。
石器時代(打製石器~磨製石器)から青銅器時代、そして鉄器時代へと変わり、鉄は今でも重要な素材であり続けている。
さてここで、打製石器や磨製石器は、どう作ったのかイメージすることはたやすい。
地域によっては、実際に作って、二つの違いを知ることも可能だろう。
ところが、青銅器~鉄器となるとそうはいかなくなる。
そもそも、なぜ青銅器が先で鉄器が後なのか?また、青銅は、銅と錫の合金だが、これは偶然に合金になったのだろうか?そ
れとも、それぞれ単体の銅と錫を作っていたが、合金にしたほうが、より固い金属になることを発見して青銅が生まれたのか?
そして次に世界を席巻することになる鉄器だが、いわゆる鉄の原料の鉄鉱石が含んでいるのは「酸化鉄」なので、これを鉄にするには「還元(=酸素を奪うこと)」が必要になる。なので、還元による製鉄法が確立される前人類は、隕鉄(隕石に含まれる鉄)が利用されていたという。
日本の近代史で、幕末のエピックとして「韮山反射炉」がある。自分がかつて勤務していた杉並区は伊豆の弓ヶ浜に宿泊施設があったので、移動教室の時の見学場所に入っていたのだが、今一つぴんと来なかった。
反射炉と溶鉱炉の違いが分かっていなかったのだ。
こうしたことを授業で扱うのは時間的な制約があって難しいだろうが、資料集や教科書のコラムのようなところで説明を入れてもらえると、理解が深まるのではなかろうか?
世界史の世界にも「科学の知識」が必要だと思う。
全く別の話だが、日本史の「征夷大将軍」のところで、「東夷、西戎、北狄、南蛮」という中国の思想を紹介しておくことも必要だと思う。
余談の断の余談だが、カレー南蛮やかも南蛮の「南蛮」は、南蛮とは無関係らしい。
共通する愚材の「葱」が大坂で栽培されていたので「なんば(難波)」がなまったものらしい。
(チコちゃんではないが、諸説あります!)
-K.H-