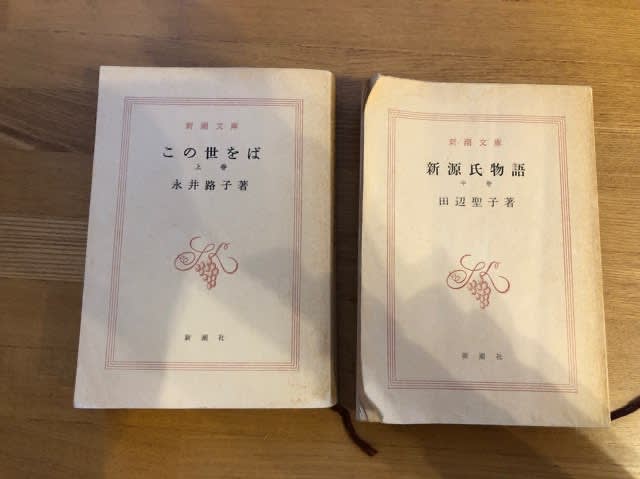吉川英治さんの新・平家物語2周目、七ヶ月ほど前から眠る前にチマチマ読み進めて、やっと終わりました。
私の印象に残ったシーン
最終回です。
平家が滅び、安徳帝の御母君、建礼門院は海に飛び込んだけれども源氏の兵にひきあげられ、助けられました。
子である安徳帝がいないのに生き延びてしまい、自分も後を追いたかった建礼門院の辛さはいかばかりか。
建礼門院の夫君、高倉天皇は早くに亡くなってしまいました。
高倉天皇のお父様、後白河法皇は建礼門院の舅君にあたります。
建礼門院は出家して、大原の寂光院で勤行三昧の日々を過ごしています。
後白河法皇はそんな建礼門院に会いに寂光院を訪れます。
女院(建礼門院)はお留守でした。
法皇様は庵室にあがりお待ちになります。

(人形スペクタクル 平家物語より)
内裏で煌びやかにときめいていらした女院には、あまりに寂しく粗末な生活よと、哀れに思いながら眺めていますと、誰かがじっと見つめている気がされました。
気がつくと、童子の絵がかけられていたのです。
これこそ、源平合戦で海の藻屑と消えられた安徳天皇、ご自分の孫なのです。
法皇様は、平家を倒すように言ったのはご自分である後ろめたさから、孫に対する愛や憐憫の情は湧いてこず、逆に何か背筋へ寒さをお覚えになったらしく、目をそらしてしまいます。
そのうちに女院はお戻りになりました。
女院はびっくりされて、外でへたりこんでしまいますが、法皇の随身に助けられて庵室にあがります。

(人形スペクタクル 平家物語より)
最初はお互い言葉もありませんでしたが、
法皇は近況などを問いかけますと、そのうち女院も少し微笑んでお答えします。
こちらへ来た当座は心細さ、いいようもありませんでしたが、生活するにはいく人かの助けもあり、物欠く事もございません。
今は逆にこの生活が有難いのだとお答えします。
ただ、いつまでも忘れえないのは先帝(安徳)のおいたわしさや、面影ではございますが…
法皇は安徳の話しになると何もおっしゃれなくなります。
法皇は女院に小箱の香木「無憂華」をお渡しになります。
「無憂華」は女院の父、平清盛が愛した香なのです。
女院はその薫を抱きしめると、白いおん頸をふるわせた。そしてついには、耐え難くなられたか、がばと、泣き伏してしまわれた。父の面影の香が、とつぜん、女院を幼な子に引き戻していたのである。

(無憂華をきく二人
人形スペクタクル 平家物語より)
このシーンが私の琴線にふれまして、ご紹介しました。
無憂華のくだりは吉川英治さんの創作です。
この後女院は亡くなり、古典の平家物語は終わりです。
新・平家物語では源義経のその後や、源頼朝の死を書き上げ、架空の人物である医師の麻鳥一家の大団円で終わります。
ふぅ〜😮💨
終わっちゃってなんか淋しい〜😢
何年かしたらまた読み直したい、平安時代末期から鎌倉時代前期の物語でした。
吉川英治さんの、
私本太平記も一度読みました。
これは鎌倉幕府の滅亡から南北朝時代を書いています。
こちらは私には平家物語ほどの楽しさは感じられなかったけど、また二回目を読んだら理解が深まりますので、そのうち読んでみようと思います。