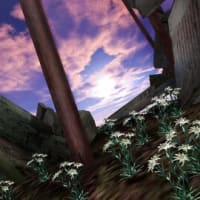半年以上前、2019年3月19日付の日本経済新聞にこんな記事があった。
「やさしい経済学」の中で宇都宮浄人教授(関西大学)によるものだ。
「交通まちづくりと地域再生(10)~財政支出、優先度見直し」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42589250Y9A310C1SHE000/
この連載ではまちづくりのツールとして、公共交通の土台を公的資金で支えつつ、
民間の交通事業者の力を発揮させるという考え方を説明してきました。
しかし、国も地方も財政難の中、その財源をどう確保するかという課題があります。
最後にこの点を考えてみましょう。
海外の場合、フランスのように、
地域の事業所あるいは住民から広く税を徴収し、交通の特定財源として活用する事例があります。
公共交通整備の受益者は今の利用者だけではありません。
渋滞が減れば車の利用者にも恩恵はあります。
さまざまな経路で公共交通恩恵を受ける地域全体が受益者と言えるのです。
したがって、地域の税を財源とするのは一つの方法です。
一方、オーストリアのように特定財源を持たずに公共交通の再生を進める国もあります。
日本の「県」に当たる「州」は連邦補助も受けつつ一般会計の配分を見直し、公共交通の近代化を支援しています。
具体的には道路整備にメリハリをつけ、予算をねん出しています。
日本の国道建設には「1kmあたり10億~20億円超」が支出されています。
道路に比べれば、地域の公共交通再生に必要な金額は大きくありません。
富山市のほか、福井市やひたちなか市など、
公的資金を用いて公共交通を活性化させる自治体が徐々に現れています。
富山市はコンパクトシティ化に向け、中心部への居住移転にも補助金を出す一方、
街中に建設した「市立中央図書館」に駐車場は作りませんでした。
高齢者の外出増が医療費の削減につながれば、「クロスセクター効果」として
一般会計を側面支援することになります。
要は、各地域が自らのまちづくりの目標をどのように定めるか、です。
郊外開発という目標には道路整備が効果的でした。
しかし、高齢化が進む社会では、「クルマなしでも暮らせる」という選択肢があり、
歴史ある中心市街地を活用した街のほうがQOL(生活の質)は高いのではないでしょうか。
人が住み続け、訪れたくなる地域をつくるための有力な手法の一つが「交通まちづくり」なのです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
この方のご意見は貴重です。
街の中心部から個人店舗が消えてシャッター通りになり、
メジャーな駅ビル内と郊外のショッピングモールばかりが栄える。
クルマを棄てざるを得なかった高齢者の移動の足たる「公共交通」が衰退の一途をたどって
買い物も満足にできない。
国道などの幹線道路が物流車・マイカーが入り乱れて渋滞する。
地方では新幹線と高速道路ばかりになって、在来線は第三セクターになって余計な乗り換えと負担が増える。
そんな今の日本がほんとうに「活気ある国」と言えるのでしょうか?
たいていの人は街から離れて生きていくのは難しい。
中心部に人の暮らしもお店もあってこそ、街に活気が生まれる。
郊外のショッピングモールも鉄道駅から歩ける距離に築く。
第三セクター会社間で提携して「直通快速列車」を設け、在来線だけでも旅ができると嬉しい。
例えば、越後湯沢~金沢間の「旧はくたか」など。
まちづくり・公共交通はまだまだ作り直しが必要なようです。
最後に、宇都宮浄人教授の著作物をご紹介します。
地域再生の戦略: 「交通まちづくり」というアプローチ (ちくま新書)
↓


鉄道復権―自動車社会からの「大逆流」 (新潮選書)
↓


「やさしい経済学」の中で宇都宮浄人教授(関西大学)によるものだ。
「交通まちづくりと地域再生(10)~財政支出、優先度見直し」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42589250Y9A310C1SHE000/
この連載ではまちづくりのツールとして、公共交通の土台を公的資金で支えつつ、
民間の交通事業者の力を発揮させるという考え方を説明してきました。
しかし、国も地方も財政難の中、その財源をどう確保するかという課題があります。
最後にこの点を考えてみましょう。
海外の場合、フランスのように、
地域の事業所あるいは住民から広く税を徴収し、交通の特定財源として活用する事例があります。
公共交通整備の受益者は今の利用者だけではありません。
渋滞が減れば車の利用者にも恩恵はあります。
さまざまな経路で公共交通恩恵を受ける地域全体が受益者と言えるのです。
したがって、地域の税を財源とするのは一つの方法です。
一方、オーストリアのように特定財源を持たずに公共交通の再生を進める国もあります。
日本の「県」に当たる「州」は連邦補助も受けつつ一般会計の配分を見直し、公共交通の近代化を支援しています。
具体的には道路整備にメリハリをつけ、予算をねん出しています。
日本の国道建設には「1kmあたり10億~20億円超」が支出されています。
道路に比べれば、地域の公共交通再生に必要な金額は大きくありません。
富山市のほか、福井市やひたちなか市など、
公的資金を用いて公共交通を活性化させる自治体が徐々に現れています。
富山市はコンパクトシティ化に向け、中心部への居住移転にも補助金を出す一方、
街中に建設した「市立中央図書館」に駐車場は作りませんでした。
高齢者の外出増が医療費の削減につながれば、「クロスセクター効果」として
一般会計を側面支援することになります。
要は、各地域が自らのまちづくりの目標をどのように定めるか、です。
郊外開発という目標には道路整備が効果的でした。
しかし、高齢化が進む社会では、「クルマなしでも暮らせる」という選択肢があり、
歴史ある中心市街地を活用した街のほうがQOL(生活の質)は高いのではないでしょうか。
人が住み続け、訪れたくなる地域をつくるための有力な手法の一つが「交通まちづくり」なのです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
この方のご意見は貴重です。
街の中心部から個人店舗が消えてシャッター通りになり、
メジャーな駅ビル内と郊外のショッピングモールばかりが栄える。
クルマを棄てざるを得なかった高齢者の移動の足たる「公共交通」が衰退の一途をたどって
買い物も満足にできない。
国道などの幹線道路が物流車・マイカーが入り乱れて渋滞する。
地方では新幹線と高速道路ばかりになって、在来線は第三セクターになって余計な乗り換えと負担が増える。
そんな今の日本がほんとうに「活気ある国」と言えるのでしょうか?
たいていの人は街から離れて生きていくのは難しい。
中心部に人の暮らしもお店もあってこそ、街に活気が生まれる。
郊外のショッピングモールも鉄道駅から歩ける距離に築く。
第三セクター会社間で提携して「直通快速列車」を設け、在来線だけでも旅ができると嬉しい。
例えば、越後湯沢~金沢間の「旧はくたか」など。
まちづくり・公共交通はまだまだ作り直しが必要なようです。
最後に、宇都宮浄人教授の著作物をご紹介します。
地域再生の戦略: 「交通まちづくり」というアプローチ (ちくま新書)
↓

鉄道復権―自動車社会からの「大逆流」 (新潮選書)
↓