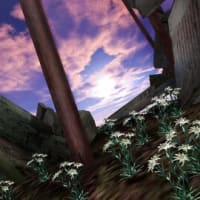東洋経済オンライン 2021年12月22日付記事
「北海道新幹線で分離「並行在来線」存続への妙手~道とJRには『やる気』が感じられず、廃線ありき」
https://toyokeizai.net/articles/-/475207
執筆:櫛田 泉 さん(経済ライター)
2030年度の北海道新幹線・「新函館北斗~札幌」間の延伸開業に向けて、
JR北海道からの経営分離が確定している並行在来線区間の今後についての議論が
「北海道新幹線並行在来線対策協議会」で続けられている。
議論の焦点は新幹線開業に合わせて並行在来線区間となる「函館~小樽」間の動向だ。
貨物列車の運行がない「長万部~小樽」間のうち、
とくに「長万部~余市」間の区間においては、鉄道の廃止を前提とした議論が進められており、
後志(しりべし)地方の小売事業者などからは
「新幹線開業を契機に地域経済の活性化を期待したいが、
このままでは後志地域を素通りされる結果となりかねない」
と落胆の声が漏れ聞こえてくる。
★ 経済効果の視点が欠落★
「並行在来線対策協議会」で議論されていることの何が問題なのであろうか。
それは、並行在来線を含めた「地域資源を活用して
地域の魅力を高めることにより地域経済の活性化を図ろうとする視点」が欠落していることと、
新幹線開業後の地域の活性化に向けた「ワークショップの場がない」ことの2点だ。
九州新幹線鹿児島ルート開業の際には、新幹線に接続する在来線の観光列車の充実化が図られ、
メディアからの注目も大きく集めたことで鉄道自体が魅力的な観光コンテンツとなった。
それにより在来線の増収が図られると同時に地域一帯の特産品の消費拡大が図られ、
土産品などの販売も伸び、新幹線の開業による地域経済活性化の成功モデルを構築することができた。
しかし、北海道新幹線の並行在来線協議会での協議は、
現状の輸送密度と赤字額などに基づき「長万部~余市」間のバス転換が妥当という
「結論ありき」での議論を進められているような印象があり、
他地域のように新幹線の開業を契機に地域経済をいかに活性化させるのか、という視点が欠落している。
★JR北海道は経営努力をしていない★
加えて、地域住民や事業者が新幹線開業後の地域の活性化について考えるような
「ワークショップの場」もまったく設けられていないのも問題だ。
前述の後志地域の事業者はこう語る。
「JR北海道と行政が主導して廃線ありきで議論を進めているように感じる。
他地域の事例をみるとやり方次第によっては在来線の増収を図ることも十分に可能にもかかわらず、
JR北海道が経営努力を何もしていないのが問題だ。
バス転換してしまえば鉄道に比べ所要時間が2倍近くかかるし、
観光列車の運行による地域産品の消費拡大も見込めなくなる。
地元の人間が積極的に発言できるような場が設けられていないのに、
廃線に向けた議論だけが進んでいくのではたまったものではない」
現在、北海道知事を務めている鈴木直道氏は、選挙の出馬時に公約として「稼ぐ道政」を掲げ、
北海道庁としても地域経済の振興策として「食と観光の推進」を進めているが、
「並行在来線対策協議会」の動きをみると道政の方針から乖離していると言わざるをえない。
★新幹線旅客は観光鉄道を好む★
閉塞感が漂う北海道とは裏腹に、
廃線危機を克服し、北海道とは対照的な取り組みを行ってきた地域がある。
それは佐賀県鹿島市を中心とした長崎本線「肥前山口~諫早」間の沿線自治体だ。
肥前鹿島駅や肥前浜駅を含む長崎本線「肥前山口~諫早」間は、
当初は九州新幹線長崎ルート(西九州新幹線)の並行在来線としてJR九州からの経営分離が前提とされ、
貨物列車の運行もないことから鉄路の存続も危ぶまれる状況であった。
「在来線の廃止により地域が衰退してしまうのではないか、
新幹線と長崎本線のルートが地理的にまったく違うにもかかわらず
並行在来線に位置づけられたことに問題があるのではないか、という地域の声があった。
新幹線の開業により特急列車が大きく減ること、
普通列車の今後についても不透明であり、
利便性の低下により市民生活に影響が出る懸念がある」 (鹿島市関係者)。
地域が一体となった粘り強い取り組みの結果、3者基本合意および6者合意を経て、
新幹線開業後も向こう23年間はJR九州が引き続き列車の運行を行うこととなった。
鉄道の維持に向けた取り組みは、
観光面からも地域経済の活性化に向けて好影響を及ぼしている。
現在、肥前浜駅で西九州新幹線の開業に向けて観光列車「36ぷらす3」のおもてなしイベントを行っている
鹿島市観光協会の中村雄一郎代表理事は次のように話す。
「肥前浜駅での観光列車のおもてなしイベントは
2013年の『ななつ星in九州』の運行開始に合わせてスタートしたが、
初運行には2000人もの人が集まった。
その集客力に度肝を抜かれ、それから1年半にわたって毎週土曜日、
地域全体で観光列車のおもてなしを行うことになった」
活動の原動力は並行在来線問題への懸念だったのかもしれないと、
中村氏は振り返る。
現在は、ホーム直結の日本酒バーも開店し、
観光列車の停車による経済効果は絶大だという。
「撮り鉄、乗り鉄、果てはスタンプや切符の収集など幅広いファンを持つ鉄道の魅力があるからこそなせる業であり、
バスでは同様の効果は得られない」(中村氏)。
日本国内にはライトな層も含めた鉄道ファンは150万~200万人存在し、
これは航空機の3~4倍、バスの10倍にものぼる。
地域への経済効果の波及を考えると鉄道の観光路線化が集客の面では最も効果的と言える。
★後志地方の活性化に必要なことは?★
地域経済活性化の側面からの在来線維持の利点については、
「鉄道存続による交通利便性の維持」、
「鉄道の観光化による地域への経済効果の波及」、
そして「パブリシティ効果」の3点が挙げられる。
函館本線の「長万部~小樽」間の収支状況については
コロナ前の2015年から2019年にかけては収入が4.5億円前後に対して費用が27億円前後で推移はしているが、
「余市~小樽」間の区間については、輸送密度が2144人と現状で鉄道として維持ができる水準に達していること、
バスの半分程度の所要時間で移動できることなどから、
途中駅を増やした「高頻度運転」によるさらなる利用促進により、鉄道として維持する方針が具体化しつつある。
余市町は人口1.8万人を擁し堅実な通勤・通学・観光需要があるほか、
新幹線駅が設置される予定の倶知安方面についても、
倶知安駅のある倶知安町が1.4万人で世界的に有名なリゾート地である「ニセコ」を控えていること、
隣の小沢駅のある共和町は人口6000人程度ではあるが、
同地域は14km先にある人口1.1万人の 岩内町を中心とした岩内都市圏を構成しており、
「倶知安~余市」間においても3.1万人程度の人口を擁していることから、
地域内における高速交通機関というポテンシャルを発揮できれば収支均衡を目指すことは不可能ではない。
高価格帯の観光列車の運行についても新幹線との相乗効果が十分に見込めることから増収を図るうえでは有効だ。
簡易的な試算ではあるが、
客単価が3万円程度の観光列車を1列車50席の座席販売目標で
年間150日程度1往復運行を行うだけで4.5億円程度の増収が可能となり、
土産物販売などによる経済効果も期待できる。
また、鉄道があることによっていちばん無視できない効果はパブリシティ効果である。
いすみ鉄道社長時代にさまざまな活性化の成果を上げてきた
「えちごトキめき鉄道」の鳥塚亮社長は、
鉄道によるパブリシティ効果の重要性について「パブリシティ効果は広告換算値として評価が可能で、
例えばテレビのスポットCM料金を基準に算出をすると、ゴールデンタイムの広告換算値は1秒間で6万円ほどになる」
と話す。
つまり、バラエティ番組で30分間取り上げてもらうことができれば
その広告換算値は1億円以上になる。
鉄道会社に出資する沿線自治体にとっては、その鉄道会社がテレビに登場することで
自治体の観光PRにつながる。
そのための広告を無料でやってもらっていると考えれば
鉄道の赤字は実質的には緩和される。
★バス転換では経済は活性化しない★
そもそも、鉄道があることが全国的な注目を浴びるポテンシャルとなっていることは
紛れもない事実である。
並行在来線を完全にバス転換してしまうと、倶知安駅を中心とした北海道後志地域が完全に素通りされ、
新幹線開業を契機とした地域経済の活性化に向けてのハードルが非常に高くなってしまうことが
容易に予想される。
地方創生を推進する日本の国益の観点からも好ましくない。
この北海道後志地域において事業活動に携わっている筆者自身も大変な危機感を感じており、
今後の鉄道維持の活動に向けて、ぜひ日本全国の方々の知恵を借りたい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
北海道新聞 2021年12月28日付社説
「JR函館線存廃 知事の調整力が見えぬ」 より抜粋
調整役としての鈴木直道知事の顔が全く見えない。
知事は夕張市長時代に夕張支線廃止を巡り
「持続可能な公共交通体系を再構築」したと強調してきた。
今回も巨額赤字でJRが経営を継続しない点では同じだ。
むろん夕張のような廃止前提は避けたい。
140.2キロもの区間をどう守るかを模索し、知事が国と地元の調整に乗り出すべきだ。
整備新幹線と並行する在来線は旅客減でJRの経営を圧迫するため、国は経営分離を認めている。
全国でも大半が三セク存続だ。
廃止は長野新幹線に並行した一部のみで11.2キロにすぎない。
「長万部~小樽」間では道が
「第三セクターで維持」
「すべてバス転換」
「小樽~余市間のみ鉄路で他はバス転換」の3案を示した。
各地で開かれた住民説明会では、
巨額負担を避けバス転換を望む声や通勤通学に鉄路維持を求める意見が出た。
道は試算だけで後は地域に丸投げしてはいまいか。
きのうの会合では小樽市などが態度保留とし、余市町は「小樽~余市間」存続を求めた。
だが倶知安町などがバス転換を表明し、全区間維持断念の流れは強まっている。
新幹線では途中は倶知安駅しか残らない。
観光アクセスからも広域的視点で考えるべきだろう。
余市町の斉藤啓輔町長は
「鉄道の話なのに国土交通省を巻きこまないのはなぜか」と問題提起してきた。
本質的な指摘と言えよう。
JRも「地域への的確な輸送サービス提供」目的で国の巨額支援を受ける立場だ。
斉藤町長はその点も言及したが、道の担当者レベルでは関係者間の調整は難しい。
鈴木氏は知事選の出馬会見で鉄道網について
「市民、道民の足をいかに確保していくかの観点で考えるべきだ」と述べた。
議論を深め、手腕を発揮してほしい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
自分は現在東京在住の身なので本来発言権はないのだが、
JR北海道の「整備新幹線が無条件最優先、在来線は札幌圏以外切り棄てやむなし」的姿勢は
もはや公共交通の使命を放棄しているし、
北海道庁と北海道新聞も“在来線を守ろうと言うやる気のなさ”が目に余る。
今はコロナ禍の最中なので無理ではあるが、
インバウンド(外国客)が道内観光地、特にニセコにわんさと押し寄せてきた時期、
スイスの「ベルニナ急行」を意識した、週末に新千歳空港から倶知安・ニセコへ結ぶ特急列車も
企画できたはずだ。
福島県が沿線地域とともに「只見線を守ろう」としている努力とは雲泥の差だ。
あちらはふるさと納税を駆使したり「只見線応援団」というパンフレットを定期的に送付して
鉄道ファンとの連絡を絶やさずに来たから、平成29(2017)年6月に
「只見線(会津川口~只見間)の鉄道復旧に関する基本合意書・覚書」を締結するまでに至ったのだ。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005g/kentou.html
それに比べれば、北海道は並行在来線も根室線富良野~新得間も 「職務放棄」 に等しい。
情けない。
ほんとうに情けない。
この時点で「長万部~余市間在来線」はすでに “万事休す” の可能性が高いかもしれないが、
日本人観光客を意識した観光列車の企画を止めてはいけない。
秋の連休にウィスキー&ワイン&ビーフ試食会とセットの臨時特急とか、
冬は週末限定で新千歳空港~札幌~ニセコ間に「はまなす&ラベンダー編成の新世代シュプール号」
(往路の夜行なら朝食つき、スキー帰りに「ニセコ駅前温泉綺羅乃湯」入浴券つきパック)とか、
ニセコライナー(キハ201系)を余市発で1日3往復(朝出勤・昼買物・夕帰宅)設定するとかの、
できることは何でもやってみる発想が欲しいです。
できる事をなんにもやらない。
新幹線しかアタマにない。
やらないから客も流れない。
客が来ないから稼げない。
稼げないから、切り棄てる発想しか生まれない。
そのツケは全部利用者が被る。
JR北海道経営陣の刷新が必要な段階まで来ているのではないでしょうか。
「北海道新幹線で分離「並行在来線」存続への妙手~道とJRには『やる気』が感じられず、廃線ありき」
https://toyokeizai.net/articles/-/475207
執筆:櫛田 泉 さん(経済ライター)
2030年度の北海道新幹線・「新函館北斗~札幌」間の延伸開業に向けて、
JR北海道からの経営分離が確定している並行在来線区間の今後についての議論が
「北海道新幹線並行在来線対策協議会」で続けられている。
議論の焦点は新幹線開業に合わせて並行在来線区間となる「函館~小樽」間の動向だ。
貨物列車の運行がない「長万部~小樽」間のうち、
とくに「長万部~余市」間の区間においては、鉄道の廃止を前提とした議論が進められており、
後志(しりべし)地方の小売事業者などからは
「新幹線開業を契機に地域経済の活性化を期待したいが、
このままでは後志地域を素通りされる結果となりかねない」
と落胆の声が漏れ聞こえてくる。
★ 経済効果の視点が欠落★
「並行在来線対策協議会」で議論されていることの何が問題なのであろうか。
それは、並行在来線を含めた「地域資源を活用して
地域の魅力を高めることにより地域経済の活性化を図ろうとする視点」が欠落していることと、
新幹線開業後の地域の活性化に向けた「ワークショップの場がない」ことの2点だ。
九州新幹線鹿児島ルート開業の際には、新幹線に接続する在来線の観光列車の充実化が図られ、
メディアからの注目も大きく集めたことで鉄道自体が魅力的な観光コンテンツとなった。
それにより在来線の増収が図られると同時に地域一帯の特産品の消費拡大が図られ、
土産品などの販売も伸び、新幹線の開業による地域経済活性化の成功モデルを構築することができた。
しかし、北海道新幹線の並行在来線協議会での協議は、
現状の輸送密度と赤字額などに基づき「長万部~余市」間のバス転換が妥当という
「結論ありき」での議論を進められているような印象があり、
他地域のように新幹線の開業を契機に地域経済をいかに活性化させるのか、という視点が欠落している。
★JR北海道は経営努力をしていない★
加えて、地域住民や事業者が新幹線開業後の地域の活性化について考えるような
「ワークショップの場」もまったく設けられていないのも問題だ。
前述の後志地域の事業者はこう語る。
「JR北海道と行政が主導して廃線ありきで議論を進めているように感じる。
他地域の事例をみるとやり方次第によっては在来線の増収を図ることも十分に可能にもかかわらず、
JR北海道が経営努力を何もしていないのが問題だ。
バス転換してしまえば鉄道に比べ所要時間が2倍近くかかるし、
観光列車の運行による地域産品の消費拡大も見込めなくなる。
地元の人間が積極的に発言できるような場が設けられていないのに、
廃線に向けた議論だけが進んでいくのではたまったものではない」
現在、北海道知事を務めている鈴木直道氏は、選挙の出馬時に公約として「稼ぐ道政」を掲げ、
北海道庁としても地域経済の振興策として「食と観光の推進」を進めているが、
「並行在来線対策協議会」の動きをみると道政の方針から乖離していると言わざるをえない。
★新幹線旅客は観光鉄道を好む★
閉塞感が漂う北海道とは裏腹に、
廃線危機を克服し、北海道とは対照的な取り組みを行ってきた地域がある。
それは佐賀県鹿島市を中心とした長崎本線「肥前山口~諫早」間の沿線自治体だ。
肥前鹿島駅や肥前浜駅を含む長崎本線「肥前山口~諫早」間は、
当初は九州新幹線長崎ルート(西九州新幹線)の並行在来線としてJR九州からの経営分離が前提とされ、
貨物列車の運行もないことから鉄路の存続も危ぶまれる状況であった。
「在来線の廃止により地域が衰退してしまうのではないか、
新幹線と長崎本線のルートが地理的にまったく違うにもかかわらず
並行在来線に位置づけられたことに問題があるのではないか、という地域の声があった。
新幹線の開業により特急列車が大きく減ること、
普通列車の今後についても不透明であり、
利便性の低下により市民生活に影響が出る懸念がある」 (鹿島市関係者)。
地域が一体となった粘り強い取り組みの結果、3者基本合意および6者合意を経て、
新幹線開業後も向こう23年間はJR九州が引き続き列車の運行を行うこととなった。
鉄道の維持に向けた取り組みは、
観光面からも地域経済の活性化に向けて好影響を及ぼしている。
現在、肥前浜駅で西九州新幹線の開業に向けて観光列車「36ぷらす3」のおもてなしイベントを行っている
鹿島市観光協会の中村雄一郎代表理事は次のように話す。
「肥前浜駅での観光列車のおもてなしイベントは
2013年の『ななつ星in九州』の運行開始に合わせてスタートしたが、
初運行には2000人もの人が集まった。
その集客力に度肝を抜かれ、それから1年半にわたって毎週土曜日、
地域全体で観光列車のおもてなしを行うことになった」
活動の原動力は並行在来線問題への懸念だったのかもしれないと、
中村氏は振り返る。
現在は、ホーム直結の日本酒バーも開店し、
観光列車の停車による経済効果は絶大だという。
「撮り鉄、乗り鉄、果てはスタンプや切符の収集など幅広いファンを持つ鉄道の魅力があるからこそなせる業であり、
バスでは同様の効果は得られない」(中村氏)。
日本国内にはライトな層も含めた鉄道ファンは150万~200万人存在し、
これは航空機の3~4倍、バスの10倍にものぼる。
地域への経済効果の波及を考えると鉄道の観光路線化が集客の面では最も効果的と言える。
★後志地方の活性化に必要なことは?★
地域経済活性化の側面からの在来線維持の利点については、
「鉄道存続による交通利便性の維持」、
「鉄道の観光化による地域への経済効果の波及」、
そして「パブリシティ効果」の3点が挙げられる。
函館本線の「長万部~小樽」間の収支状況については
コロナ前の2015年から2019年にかけては収入が4.5億円前後に対して費用が27億円前後で推移はしているが、
「余市~小樽」間の区間については、輸送密度が2144人と現状で鉄道として維持ができる水準に達していること、
バスの半分程度の所要時間で移動できることなどから、
途中駅を増やした「高頻度運転」によるさらなる利用促進により、鉄道として維持する方針が具体化しつつある。
余市町は人口1.8万人を擁し堅実な通勤・通学・観光需要があるほか、
新幹線駅が設置される予定の倶知安方面についても、
倶知安駅のある倶知安町が1.4万人で世界的に有名なリゾート地である「ニセコ」を控えていること、
隣の小沢駅のある共和町は人口6000人程度ではあるが、
同地域は14km先にある人口1.1万人の 岩内町を中心とした岩内都市圏を構成しており、
「倶知安~余市」間においても3.1万人程度の人口を擁していることから、
地域内における高速交通機関というポテンシャルを発揮できれば収支均衡を目指すことは不可能ではない。
高価格帯の観光列車の運行についても新幹線との相乗効果が十分に見込めることから増収を図るうえでは有効だ。
簡易的な試算ではあるが、
客単価が3万円程度の観光列車を1列車50席の座席販売目標で
年間150日程度1往復運行を行うだけで4.5億円程度の増収が可能となり、
土産物販売などによる経済効果も期待できる。
また、鉄道があることによっていちばん無視できない効果はパブリシティ効果である。
いすみ鉄道社長時代にさまざまな活性化の成果を上げてきた
「えちごトキめき鉄道」の鳥塚亮社長は、
鉄道によるパブリシティ効果の重要性について「パブリシティ効果は広告換算値として評価が可能で、
例えばテレビのスポットCM料金を基準に算出をすると、ゴールデンタイムの広告換算値は1秒間で6万円ほどになる」
と話す。
つまり、バラエティ番組で30分間取り上げてもらうことができれば
その広告換算値は1億円以上になる。
鉄道会社に出資する沿線自治体にとっては、その鉄道会社がテレビに登場することで
自治体の観光PRにつながる。
そのための広告を無料でやってもらっていると考えれば
鉄道の赤字は実質的には緩和される。
★バス転換では経済は活性化しない★
そもそも、鉄道があることが全国的な注目を浴びるポテンシャルとなっていることは
紛れもない事実である。
並行在来線を完全にバス転換してしまうと、倶知安駅を中心とした北海道後志地域が完全に素通りされ、
新幹線開業を契機とした地域経済の活性化に向けてのハードルが非常に高くなってしまうことが
容易に予想される。
地方創生を推進する日本の国益の観点からも好ましくない。
この北海道後志地域において事業活動に携わっている筆者自身も大変な危機感を感じており、
今後の鉄道維持の活動に向けて、ぜひ日本全国の方々の知恵を借りたい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
北海道新聞 2021年12月28日付社説
「JR函館線存廃 知事の調整力が見えぬ」 より抜粋
調整役としての鈴木直道知事の顔が全く見えない。
知事は夕張市長時代に夕張支線廃止を巡り
「持続可能な公共交通体系を再構築」したと強調してきた。
今回も巨額赤字でJRが経営を継続しない点では同じだ。
むろん夕張のような廃止前提は避けたい。
140.2キロもの区間をどう守るかを模索し、知事が国と地元の調整に乗り出すべきだ。
整備新幹線と並行する在来線は旅客減でJRの経営を圧迫するため、国は経営分離を認めている。
全国でも大半が三セク存続だ。
廃止は長野新幹線に並行した一部のみで11.2キロにすぎない。
「長万部~小樽」間では道が
「第三セクターで維持」
「すべてバス転換」
「小樽~余市間のみ鉄路で他はバス転換」の3案を示した。
各地で開かれた住民説明会では、
巨額負担を避けバス転換を望む声や通勤通学に鉄路維持を求める意見が出た。
道は試算だけで後は地域に丸投げしてはいまいか。
きのうの会合では小樽市などが態度保留とし、余市町は「小樽~余市間」存続を求めた。
だが倶知安町などがバス転換を表明し、全区間維持断念の流れは強まっている。
新幹線では途中は倶知安駅しか残らない。
観光アクセスからも広域的視点で考えるべきだろう。
余市町の斉藤啓輔町長は
「鉄道の話なのに国土交通省を巻きこまないのはなぜか」と問題提起してきた。
本質的な指摘と言えよう。
JRも「地域への的確な輸送サービス提供」目的で国の巨額支援を受ける立場だ。
斉藤町長はその点も言及したが、道の担当者レベルでは関係者間の調整は難しい。
鈴木氏は知事選の出馬会見で鉄道網について
「市民、道民の足をいかに確保していくかの観点で考えるべきだ」と述べた。
議論を深め、手腕を発揮してほしい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
自分は現在東京在住の身なので本来発言権はないのだが、
JR北海道の「整備新幹線が無条件最優先、在来線は札幌圏以外切り棄てやむなし」的姿勢は
もはや公共交通の使命を放棄しているし、
北海道庁と北海道新聞も“在来線を守ろうと言うやる気のなさ”が目に余る。
今はコロナ禍の最中なので無理ではあるが、
インバウンド(外国客)が道内観光地、特にニセコにわんさと押し寄せてきた時期、
スイスの「ベルニナ急行」を意識した、週末に新千歳空港から倶知安・ニセコへ結ぶ特急列車も
企画できたはずだ。
福島県が沿線地域とともに「只見線を守ろう」としている努力とは雲泥の差だ。
あちらはふるさと納税を駆使したり「只見線応援団」というパンフレットを定期的に送付して
鉄道ファンとの連絡を絶やさずに来たから、平成29(2017)年6月に
「只見線(会津川口~只見間)の鉄道復旧に関する基本合意書・覚書」を締結するまでに至ったのだ。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005g/kentou.html
それに比べれば、北海道は並行在来線も根室線富良野~新得間も 「職務放棄」 に等しい。
情けない。
ほんとうに情けない。
この時点で「長万部~余市間在来線」はすでに “万事休す” の可能性が高いかもしれないが、
日本人観光客を意識した観光列車の企画を止めてはいけない。
秋の連休にウィスキー&ワイン&ビーフ試食会とセットの臨時特急とか、
冬は週末限定で新千歳空港~札幌~ニセコ間に「はまなす&ラベンダー編成の新世代シュプール号」
(往路の夜行なら朝食つき、スキー帰りに「ニセコ駅前温泉綺羅乃湯」入浴券つきパック)とか、
ニセコライナー(キハ201系)を余市発で1日3往復(朝出勤・昼買物・夕帰宅)設定するとかの、
できることは何でもやってみる発想が欲しいです。
できる事をなんにもやらない。
新幹線しかアタマにない。
やらないから客も流れない。
客が来ないから稼げない。
稼げないから、切り棄てる発想しか生まれない。
そのツケは全部利用者が被る。
JR北海道経営陣の刷新が必要な段階まで来ているのではないでしょうか。