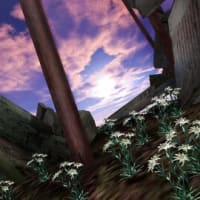Merkmal 2025年3月8日付記事
「夜行列車消滅 = 正常な進化」は本当か? 新幹線礼賛論に異議あり!
鉄道オタクに決定的に欠けた「利用者視点」とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/29f22b55064b72e469477e1b0a585e53fb797fb8
◆宿泊費制限が浮き彫りにする旅行需要◆
2025年3月6日に、
「夜行列車はなぜなくなってしまったのか?
新幹線網の速達性向上で夜行需要が喪失した」
という記事が配信された。
この記事はフリーライターの小林拓矢氏によるものである。
筆者(北條慶太、交通経済ライター)は、
当媒体で感傷的な視点やノスタルジーを排し、
経済的合理性と社会的課題をもとに夜行列車の可能性を探る連載「夜行列車現実論」を
7回にわたって執筆してきた
(2025年3月4日終了)。
この立場から、今回は小林氏の記事に対し、批判的な視点を示す。
財務省は2025年4月から、国家公務員の出張時の宿泊費を都道府県別に定めて公表することとなる。
この変更で問題となるのは、課長級職員でさえ、東京での出張の場合、
上限宿泊費が1泊1万9000円、愛知が1万1000円、
大阪が1万3000円、福岡が1万8000円に設定されている点だ。
これらの都道府県は観光需要が高く、
インバウンド需要の影響もあって観光地としての人気を集めている。
そのため、出張に便利な場所ほど1泊2万円を超えるケースが都市部では多く見られる。
また、経営が厳しい企業では、全国一律で”1泊1万円”を下回ることも少なくない。
多くの企業は出張にかかる交通費や宿泊費を抑えることを重視しており、
このような背景が国内旅行ニーズに影響を与えている。
こうした状況を踏まえて、筆者は連載を通じて夜行列車の実現可能性を探求してきた。
本稿では、夜行列車の消滅が果たしてどのように正常な進化と見なされるべきかについて、
改めて考察を加えていく。
◆改装車両で再生する夜行列車◆
小林氏の主張を箇条書きでまとめる。
・3月15日のダイヤ改正が近づき、新しい時刻表が書店に並び始めた。
・19時00分東京発の「のぞみ」博多行きが5月2日のみ運行され、驚異的な速達ダイヤで注目されている。
・夜行列車があった時代を知る人々にとって、東京発19時の列車で博多にその日のうちに到着することは夢のような話となっている。
・他の新幹線ダイヤでも、夜間帯に速達性の高い列車が増加し、夜行列車の必要性が低くなっている。
・例えば、新大阪19時54分発の「みずほ」、東京から函館や新青森へのアクセスも夜間に完結することができる。
・夜行列車「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」は特別な選択肢として設定されており、実用的な移動手段としては利用されていない。
・新幹線の発展により、夜行列車の需要は消失し、飛行機や新幹線の速達性がその役割を果たしている。
・1968(昭和43)年の時刻表を参考にすると、夜行列車が必要だった時代と現在の便利さの違いが際立つ。
・新幹線網や航空網の充実により、夜行列車がなくなるのは進化と受け入れるべき現象である。
確かにブルートレインを中心に夜行列車は減少してきたが、
山陰や四国を目指す「サンライズ」などは根強い人気があり、
「WEST EXPRESS 銀河」のように従来の車両を改装して運行される夜行便も高い需要を誇る。
この現象からもわかるように、
夜行列車が完全に無駄で不要なものであれば、運行されることはないはずだ。
しかし、これらの人気列車は発売と同時に売り切れることが多く、
持続的な需要も期待されている。
この状況自体が鉄道業界の進化を示している。
たとえばサンライズは、大手住宅メーカーのミサワホームが提供する「M-Wood」を採用し、
木の温もりと曲線的なデザインを取り入れたインテリアで、
夜行列車の新たな形を実現している。
WEST EXPRESS 銀河は車齢40年の車両を改装し、
さまざまな座席タイプを導入して、
さまざまなニーズに応じた利用を促進している。
重要なのは、夜行列車を実現するための工夫であり、
最初から「夜行列車を運行するか否か」を議論することが
鉄道の未来を考える上で正しいアプローチとはいえない。
もちろん、新造車両や改装車両にかかるコストについて懸念する声は多いだろうが、
筆者はこれまでの連載で、そのために必要な工夫についても触れてきた。
鉄道業界の厳しい経営状況を考えると、
新幹線と飛行機の発展で夜行列車の役割がなくなった、と一概に判断することはできない。
小林氏は
「夜行列車がなくなるのは残念だけど、正常な進化というほかないのである」
と書くが、
進化とは環境に適応して変化することであり、
環境の変化に応じた夜行列車の形態を考えることも十分に可能である。
公共交通は、生活者にとって
・物 ・情報 ・場所を得るために不可欠なインフラであり、
重要なツールである。
昭和時代、公共交通は国家的な政策として
「シビルミニマム」(基本的な生活を維持するために必要不可欠な最低限度のインフラやサービス)
が国の政策テーマとなっている。
現在、
・SDGs(持続可能な開発目標)
・DEI(多様性・公平性・包括性)が国際的に掲げられるなかで、
多様性を認め、あらゆる人々のウェルビーイングの向上を目指す社会において、
単なる「速さ」や「効率化」だけを追求することが公共交通の進化であるとはいえない。
夜行列車が果たしていた役割は、
・時間の有効活用支援
・非日常的な移動体験
・需要の多様性への対応
など多岐にわたる。
「夜行列車がなくなるのは残念だけど、正常な進化というほかないのである」という見方は、
新幹線や航空機の発展だけに注目し、その現象に偏った意見が多い。
環境変化に対応する進化の本質を見極めずに語られている部分が多く、
これには疑問を感じざるを得ない。
◆深夜移動の減少がもたらす影響◆
「深夜移動に対するニーズがない」
という意見を当媒体の記事のコメントで目にすることがある。
しかし、夜行高速バスが未だに多く存在し続けているのは、バス業界にとって収益源であり、
一定のニーズが存在しているからである。
特に郊外地域では、大都市圏との直通便が
ビジネスチャンスや観光の機会を向上させる重要な役割を果たしている。
例えば、箱根地域の観光事業者は、コロナ以降、小田急ロマンスカーの小田原・箱根湯本への運行便数が減少し、
その回復を強く求めていることからも、公共交通の「便の存在」が地域にとってどれほど重要かがわかる。
夜行列車が消えてしまうと、大都市への直通便が失われ、
地域のブランドに悪影響を与える可能性がある。
公共交通と地域のつながりを考えると、夜行列車は地域のブランディングに大きな影響を与えていることがわかる。
また、夜行列車がなくなることで、個人レベルでは”深夜移動の選択肢”が減り、
都市間移動の効率が低下することになる。
夜行列車を利用すれば、地方観光で朝から夜までアクティビティを楽しむことができる可能性が広がる。
その非日常的な移動の楽しさや特別な体験が失われることも懸念される。
例えば、東京から大阪への1泊2日の出張では、
のぞみ号を利用した場合、往復運賃は2万7740円(所要時間2時間30分、走行距離556.4km)となり、
ホテル代1泊朝食付き1万円、日当2日間6000円を合わせると、
合計支給額は4万3740円になる。
一方、サンライズを利用すると、東京~大阪間の「ノビノビ座席」の運賃と特急料金を合わせた片道は1万2400円で、
B寝台個室ソロは1万8470円、B寝台個室シングルは1万9570円となる。
新幹線代とホテル代を合わせると、「寝台列車の料金よりも高額」となり、
寝台列車を片道利用することで費用を抑えられ、職場にもメリットがある。
こうしたメリットを損なうことが本当に正しい方向といえるのだろうか。
◆「鉄道オタク」が陥りやすい誤認◆
いわゆる「鉄道オタク」には、交通事業者側の行動が常に合理的だと判断する傾向が見受けられる。
「新幹線・航空機 = 最新 = 最適」
という単純な思考に陥っていることが多い。
この点については、環境変化に適応していない、
つまり進化が停滞しているように感じる。
鉄道に対する強い愛情が、
・現行ダイヤ
・事業者の姿勢 に共感を生み、
それを最適化と見なす思考に偏らせているようだ。
しかし、技術面での進歩が必ずしも利便性の向上に直結するわけではないことも多い。
それならば、なぜ各地に観光周遊列車が登場しているのか――。
速達性だけを重視するのであれば「ななつ星in九州」や「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」、「四季島」のような
クルーズトレインが各地で生まれることはないだろう。
さらに、「伊予灘ものがたり」や「四国まんなか千年ものがたり」といったエリア周遊の観光列車が人気を集める理由も理解できる。
昼行便と夜行便を組み合わせた「WEST EXPRESS 銀河」のようなリーズナブルで人気の高い周遊列車も存在している。
鉄道に求められるものは、もはや速さと効率だけではない。
重要なのは、社会全体でユーザー体験(UX)を議論し、
鉄道利用者の体験やウェルビーイングの向上を目指すことだ。
しかし、この視点を持つ人が、専門家以外には少ないことが問題だ。
次に、「なぜ高速化だけを進化と考えてしまうのか」という問いを考えてみると、
「鉄道オタク」の多くが時刻表やダイヤの最適化に関心を持ち、
既存の枠組みに固執しがちであることがわかる。
長距離移動の手段として、夜行列車の必要性を否定する「システム側の論理」に同調する心理も見え隠れする。
鉄道好きであるがゆえに、鉄道事業者の視点に立ち、
「あたかも自分が経営者である」かのように語る人々もいる。
そのため、現行の新幹線中心のビジネスが正しいと考える人も多い。
しかし、最も重要なのは、鉄道システムを動かす鉄道事業者と利用者との「合意形成」だ。
最近では、人間中心設計(Human Centered Design)が注目されており、
生活者のアクティビティや心理特性に基づいた環境デザインやサービスデザインが求められている。
筆者も仕事仲間や友人と話していると、
「出張費用が自腹で避けられない」
「夜行バスを利用しているが、列車もあるとよい」
といった声をよく耳にする。
これらのニーズを知る機会があっても、「高速化だけが進化」と語っているわけではないだろう。
事業者と利用者が共創を実現するためには、しっかりとコミュニケーションをとり、
双方の理解を深める必要があるのだ。
◆移動の質を高める選択肢◆
結論からいえば、
我々の未来の生活を見据え、「あるべき姿」から夜行列車の形を議論し、定めることが重要だ。
想像で構わないから、未来の理想的な姿から逆算して夜行列車を考えるべきである。
まさに英国発の「スペキュラティブ・デザイン」
(現実の技術や社会の枠組みを超えて、未来や理想的な社会を想像し、そのビジョンを具現化するデザインのアプローチ)
のアプローチが示唆するように、可能性を広げて議論を進めるべきだ。
筆者が「夜行列車現実論」で取り上げたように、
夜行列車の復活に向けた選択肢は多岐にわたる。
これを不可能だと考えることはできない。
歴史を踏まえたうえで、
・寝台列車と座席車の混結
・鈍行で安価な夜行座席列車
・貨物輸送と夜行列車の混結
・上下分離方式と夜行専用鉄道会社の新設など、
さまざまな提案を行ってきた。
さらには、「WEST EXPRESS 銀河」のような旧車を改装して新しいビジネスを展開する方法もある。
これらはハード面、ソフト面を問わず、移動の「質」を重視した提案である。
過去にマスコミュニケーションの研究で、テレビの視聴率だけでなく「視聴質」も測るべきだという議論があったように、
鉄道の世界でも、速さという量的側面ではなく、
「生活者の心を満たしているかどうか」という
質的な評価が必要な時期に来ている。
実際、鉄道事業者の一部はすでにその重要性に気づき、観光列車を走らせている。
筆者も多くのクルーズトレインや観光列車に乗車し、
車内スタッフによるもてなしや、地域の人々との交流、
高速鉄道では見過ごしがちな美しい風景を目にすることで、
ウェルビーイングが確実に向上することを実感している。
新幹線の流れを「正常な進化」とするのではなく、
むしろ「選択肢の縮小」と捉えるべきだ。
このように、視聴率と視聴質の議論に見られるように、
評価の軸を変えた議論を行うことが、今後求められているのだ。
◆量的評価に潜む限界◆
交通経済ライターとしての立場からいうと、
「速いからよい」という考え方や論調には「危険性」を感じる。
前述のDEIを意識し、多様な移動手段が存在する状態の実現が重要だ。
環境デザインの哲学だと指摘する人もいるかもしれないが、
哲学を基盤に持続可能なビジネスを考える方法論も存在する。
また量的評価だけでなく、質的評価という視点も忘れてはならない。
公共交通は事業者と生活者の共創によって成り立っているという意識も大切だ。
そのため、夜行列車の消滅を「正常な進化」として受け入れる考え方には
「限界」があると考える。
量的な評価だけでは俯瞰的な視点を持つことができないからだ。
今後の公共交通政策や鉄道のあり方を考えるにあたり、
移動手段の多様性を量と質の両方、事業者と生活者の視点を交えて再評価する必要がある。
効率と効果のバランスも重要だが、効果には経済的なものだけでなく、
精神的、体力的な効果も含まれる。
真に望ましい公共交通は、経済的な効果やスピードだけでなく、
生活者の心や精神にも配慮し、それらすべての効果を高めることが求められる。
公共交通のあり方を考える際には、この視点が欠かせない。
しかし、「鉄道オタク」にはこの重要な点が欠けていることが多いのである。
北條慶太(交通経済ライター)
「夜行列車消滅 = 正常な進化」は本当か? 新幹線礼賛論に異議あり!
鉄道オタクに決定的に欠けた「利用者視点」とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/29f22b55064b72e469477e1b0a585e53fb797fb8
◆宿泊費制限が浮き彫りにする旅行需要◆
2025年3月6日に、
「夜行列車はなぜなくなってしまったのか?
新幹線網の速達性向上で夜行需要が喪失した」
という記事が配信された。
この記事はフリーライターの小林拓矢氏によるものである。
筆者(北條慶太、交通経済ライター)は、
当媒体で感傷的な視点やノスタルジーを排し、
経済的合理性と社会的課題をもとに夜行列車の可能性を探る連載「夜行列車現実論」を
7回にわたって執筆してきた
(2025年3月4日終了)。
この立場から、今回は小林氏の記事に対し、批判的な視点を示す。
財務省は2025年4月から、国家公務員の出張時の宿泊費を都道府県別に定めて公表することとなる。
この変更で問題となるのは、課長級職員でさえ、東京での出張の場合、
上限宿泊費が1泊1万9000円、愛知が1万1000円、
大阪が1万3000円、福岡が1万8000円に設定されている点だ。
これらの都道府県は観光需要が高く、
インバウンド需要の影響もあって観光地としての人気を集めている。
そのため、出張に便利な場所ほど1泊2万円を超えるケースが都市部では多く見られる。
また、経営が厳しい企業では、全国一律で”1泊1万円”を下回ることも少なくない。
多くの企業は出張にかかる交通費や宿泊費を抑えることを重視しており、
このような背景が国内旅行ニーズに影響を与えている。
こうした状況を踏まえて、筆者は連載を通じて夜行列車の実現可能性を探求してきた。
本稿では、夜行列車の消滅が果たしてどのように正常な進化と見なされるべきかについて、
改めて考察を加えていく。
◆改装車両で再生する夜行列車◆
小林氏の主張を箇条書きでまとめる。
・3月15日のダイヤ改正が近づき、新しい時刻表が書店に並び始めた。
・19時00分東京発の「のぞみ」博多行きが5月2日のみ運行され、驚異的な速達ダイヤで注目されている。
・夜行列車があった時代を知る人々にとって、東京発19時の列車で博多にその日のうちに到着することは夢のような話となっている。
・他の新幹線ダイヤでも、夜間帯に速達性の高い列車が増加し、夜行列車の必要性が低くなっている。
・例えば、新大阪19時54分発の「みずほ」、東京から函館や新青森へのアクセスも夜間に完結することができる。
・夜行列車「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」は特別な選択肢として設定されており、実用的な移動手段としては利用されていない。
・新幹線の発展により、夜行列車の需要は消失し、飛行機や新幹線の速達性がその役割を果たしている。
・1968(昭和43)年の時刻表を参考にすると、夜行列車が必要だった時代と現在の便利さの違いが際立つ。
・新幹線網や航空網の充実により、夜行列車がなくなるのは進化と受け入れるべき現象である。
確かにブルートレインを中心に夜行列車は減少してきたが、
山陰や四国を目指す「サンライズ」などは根強い人気があり、
「WEST EXPRESS 銀河」のように従来の車両を改装して運行される夜行便も高い需要を誇る。
この現象からもわかるように、
夜行列車が完全に無駄で不要なものであれば、運行されることはないはずだ。
しかし、これらの人気列車は発売と同時に売り切れることが多く、
持続的な需要も期待されている。
この状況自体が鉄道業界の進化を示している。
たとえばサンライズは、大手住宅メーカーのミサワホームが提供する「M-Wood」を採用し、
木の温もりと曲線的なデザインを取り入れたインテリアで、
夜行列車の新たな形を実現している。
WEST EXPRESS 銀河は車齢40年の車両を改装し、
さまざまな座席タイプを導入して、
さまざまなニーズに応じた利用を促進している。
重要なのは、夜行列車を実現するための工夫であり、
最初から「夜行列車を運行するか否か」を議論することが
鉄道の未来を考える上で正しいアプローチとはいえない。
もちろん、新造車両や改装車両にかかるコストについて懸念する声は多いだろうが、
筆者はこれまでの連載で、そのために必要な工夫についても触れてきた。
鉄道業界の厳しい経営状況を考えると、
新幹線と飛行機の発展で夜行列車の役割がなくなった、と一概に判断することはできない。
小林氏は
「夜行列車がなくなるのは残念だけど、正常な進化というほかないのである」
と書くが、
進化とは環境に適応して変化することであり、
環境の変化に応じた夜行列車の形態を考えることも十分に可能である。
公共交通は、生活者にとって
・物 ・情報 ・場所を得るために不可欠なインフラであり、
重要なツールである。
昭和時代、公共交通は国家的な政策として
「シビルミニマム」(基本的な生活を維持するために必要不可欠な最低限度のインフラやサービス)
が国の政策テーマとなっている。
現在、
・SDGs(持続可能な開発目標)
・DEI(多様性・公平性・包括性)が国際的に掲げられるなかで、
多様性を認め、あらゆる人々のウェルビーイングの向上を目指す社会において、
単なる「速さ」や「効率化」だけを追求することが公共交通の進化であるとはいえない。
夜行列車が果たしていた役割は、
・時間の有効活用支援
・非日常的な移動体験
・需要の多様性への対応
など多岐にわたる。
「夜行列車がなくなるのは残念だけど、正常な進化というほかないのである」という見方は、
新幹線や航空機の発展だけに注目し、その現象に偏った意見が多い。
環境変化に対応する進化の本質を見極めずに語られている部分が多く、
これには疑問を感じざるを得ない。
◆深夜移動の減少がもたらす影響◆
「深夜移動に対するニーズがない」
という意見を当媒体の記事のコメントで目にすることがある。
しかし、夜行高速バスが未だに多く存在し続けているのは、バス業界にとって収益源であり、
一定のニーズが存在しているからである。
特に郊外地域では、大都市圏との直通便が
ビジネスチャンスや観光の機会を向上させる重要な役割を果たしている。
例えば、箱根地域の観光事業者は、コロナ以降、小田急ロマンスカーの小田原・箱根湯本への運行便数が減少し、
その回復を強く求めていることからも、公共交通の「便の存在」が地域にとってどれほど重要かがわかる。
夜行列車が消えてしまうと、大都市への直通便が失われ、
地域のブランドに悪影響を与える可能性がある。
公共交通と地域のつながりを考えると、夜行列車は地域のブランディングに大きな影響を与えていることがわかる。
また、夜行列車がなくなることで、個人レベルでは”深夜移動の選択肢”が減り、
都市間移動の効率が低下することになる。
夜行列車を利用すれば、地方観光で朝から夜までアクティビティを楽しむことができる可能性が広がる。
その非日常的な移動の楽しさや特別な体験が失われることも懸念される。
例えば、東京から大阪への1泊2日の出張では、
のぞみ号を利用した場合、往復運賃は2万7740円(所要時間2時間30分、走行距離556.4km)となり、
ホテル代1泊朝食付き1万円、日当2日間6000円を合わせると、
合計支給額は4万3740円になる。
一方、サンライズを利用すると、東京~大阪間の「ノビノビ座席」の運賃と特急料金を合わせた片道は1万2400円で、
B寝台個室ソロは1万8470円、B寝台個室シングルは1万9570円となる。
新幹線代とホテル代を合わせると、「寝台列車の料金よりも高額」となり、
寝台列車を片道利用することで費用を抑えられ、職場にもメリットがある。
こうしたメリットを損なうことが本当に正しい方向といえるのだろうか。
◆「鉄道オタク」が陥りやすい誤認◆
いわゆる「鉄道オタク」には、交通事業者側の行動が常に合理的だと判断する傾向が見受けられる。
「新幹線・航空機 = 最新 = 最適」
という単純な思考に陥っていることが多い。
この点については、環境変化に適応していない、
つまり進化が停滞しているように感じる。
鉄道に対する強い愛情が、
・現行ダイヤ
・事業者の姿勢 に共感を生み、
それを最適化と見なす思考に偏らせているようだ。
しかし、技術面での進歩が必ずしも利便性の向上に直結するわけではないことも多い。
それならば、なぜ各地に観光周遊列車が登場しているのか――。
速達性だけを重視するのであれば「ななつ星in九州」や「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」、「四季島」のような
クルーズトレインが各地で生まれることはないだろう。
さらに、「伊予灘ものがたり」や「四国まんなか千年ものがたり」といったエリア周遊の観光列車が人気を集める理由も理解できる。
昼行便と夜行便を組み合わせた「WEST EXPRESS 銀河」のようなリーズナブルで人気の高い周遊列車も存在している。
鉄道に求められるものは、もはや速さと効率だけではない。
重要なのは、社会全体でユーザー体験(UX)を議論し、
鉄道利用者の体験やウェルビーイングの向上を目指すことだ。
しかし、この視点を持つ人が、専門家以外には少ないことが問題だ。
次に、「なぜ高速化だけを進化と考えてしまうのか」という問いを考えてみると、
「鉄道オタク」の多くが時刻表やダイヤの最適化に関心を持ち、
既存の枠組みに固執しがちであることがわかる。
長距離移動の手段として、夜行列車の必要性を否定する「システム側の論理」に同調する心理も見え隠れする。
鉄道好きであるがゆえに、鉄道事業者の視点に立ち、
「あたかも自分が経営者である」かのように語る人々もいる。
そのため、現行の新幹線中心のビジネスが正しいと考える人も多い。
しかし、最も重要なのは、鉄道システムを動かす鉄道事業者と利用者との「合意形成」だ。
最近では、人間中心設計(Human Centered Design)が注目されており、
生活者のアクティビティや心理特性に基づいた環境デザインやサービスデザインが求められている。
筆者も仕事仲間や友人と話していると、
「出張費用が自腹で避けられない」
「夜行バスを利用しているが、列車もあるとよい」
といった声をよく耳にする。
これらのニーズを知る機会があっても、「高速化だけが進化」と語っているわけではないだろう。
事業者と利用者が共創を実現するためには、しっかりとコミュニケーションをとり、
双方の理解を深める必要があるのだ。
◆移動の質を高める選択肢◆
結論からいえば、
我々の未来の生活を見据え、「あるべき姿」から夜行列車の形を議論し、定めることが重要だ。
想像で構わないから、未来の理想的な姿から逆算して夜行列車を考えるべきである。
まさに英国発の「スペキュラティブ・デザイン」
(現実の技術や社会の枠組みを超えて、未来や理想的な社会を想像し、そのビジョンを具現化するデザインのアプローチ)
のアプローチが示唆するように、可能性を広げて議論を進めるべきだ。
筆者が「夜行列車現実論」で取り上げたように、
夜行列車の復活に向けた選択肢は多岐にわたる。
これを不可能だと考えることはできない。
歴史を踏まえたうえで、
・寝台列車と座席車の混結
・鈍行で安価な夜行座席列車
・貨物輸送と夜行列車の混結
・上下分離方式と夜行専用鉄道会社の新設など、
さまざまな提案を行ってきた。
さらには、「WEST EXPRESS 銀河」のような旧車を改装して新しいビジネスを展開する方法もある。
これらはハード面、ソフト面を問わず、移動の「質」を重視した提案である。
過去にマスコミュニケーションの研究で、テレビの視聴率だけでなく「視聴質」も測るべきだという議論があったように、
鉄道の世界でも、速さという量的側面ではなく、
「生活者の心を満たしているかどうか」という
質的な評価が必要な時期に来ている。
実際、鉄道事業者の一部はすでにその重要性に気づき、観光列車を走らせている。
筆者も多くのクルーズトレインや観光列車に乗車し、
車内スタッフによるもてなしや、地域の人々との交流、
高速鉄道では見過ごしがちな美しい風景を目にすることで、
ウェルビーイングが確実に向上することを実感している。
新幹線の流れを「正常な進化」とするのではなく、
むしろ「選択肢の縮小」と捉えるべきだ。
このように、視聴率と視聴質の議論に見られるように、
評価の軸を変えた議論を行うことが、今後求められているのだ。
◆量的評価に潜む限界◆
交通経済ライターとしての立場からいうと、
「速いからよい」という考え方や論調には「危険性」を感じる。
前述のDEIを意識し、多様な移動手段が存在する状態の実現が重要だ。
環境デザインの哲学だと指摘する人もいるかもしれないが、
哲学を基盤に持続可能なビジネスを考える方法論も存在する。
また量的評価だけでなく、質的評価という視点も忘れてはならない。
公共交通は事業者と生活者の共創によって成り立っているという意識も大切だ。
そのため、夜行列車の消滅を「正常な進化」として受け入れる考え方には
「限界」があると考える。
量的な評価だけでは俯瞰的な視点を持つことができないからだ。
今後の公共交通政策や鉄道のあり方を考えるにあたり、
移動手段の多様性を量と質の両方、事業者と生活者の視点を交えて再評価する必要がある。
効率と効果のバランスも重要だが、効果には経済的なものだけでなく、
精神的、体力的な効果も含まれる。
真に望ましい公共交通は、経済的な効果やスピードだけでなく、
生活者の心や精神にも配慮し、それらすべての効果を高めることが求められる。
公共交通のあり方を考える際には、この視点が欠かせない。
しかし、「鉄道オタク」にはこの重要な点が欠けていることが多いのである。
北條慶太(交通経済ライター)