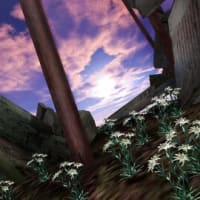Rising Sun ―風の勲章 (ON THE ROAD 2011 "The Last Weekend")


↑
オリジナルアルバム『Father's Son 』初出


↑
浜省の雄姿をぜひDVD(or Blu-ray)でどうぞ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
北海道新聞 2020年8月15日付社説
「終戦から75年 命の尊さをかみしめたい」
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/450578?rct=c_editorial
日本だけで310万人、アジア太平洋地域では2千万人とも言われる犠牲者を出した戦争の終結から、
きょうで75年を迎える。
戦後の日本は戦争の放棄と戦力不保持をうたう平和憲法を掲げ、戦争当事国にはならない道を、
4分の3世紀歩んできた。
だが、その平和がこの先も保たれるのか。
安倍晋三首相のこれまでの取り組みを見れば、懸念は膨らむばかりだ。
米中対立など、国際社会は不安定さを増している。
それに合わせるかのように、首相は新たな攻撃力の整備に関心を向ける。
これでは、ますます「戦争ができる国」に近づこうとしているとしか思えない。
悲惨な戦争を二度と繰り返さないと誓い、戦後をスタートさせた日本である。
力に頼る道を突き進むことは、その原点を顧みていないに等しい。
新型コロナウイルスの感染拡大で、命の尊さをかつてないほど意識する毎日だ。
だからこそ、この日に平和な社会をいかにしてつくるか、じっくり考えたい。
■憲法の理念に反する
首相は今月初め、自民党が提言した「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有」について、
「しっかり新しい方向性を打ち出し、速やかに実行する」と前向きな姿勢を見せた。
自民党が求めたのは事実上の「敵基地攻撃能力」の保有だ。
相手国のミサイルを迎撃するシステム「イージス・アショア」の導入断念を受けて浮上した。
ただ相手側のミサイル発射の兆候を誤判断すれば、専守防衛を逸脱する先制攻撃となり得る。
だから歴代政権は否定してきた。
保有を認めれば安全保障政策の大転換であり、憲法の理念に反する可能性が大きい。
これまで安倍政権は「積極的平和主義」を掲げて、集団的自衛権の容認を強引に進め、
自衛隊が戦争に巻き込まれかねない安全保障関連法を制定した。
「敵基地攻撃能力」はそれ以上の危険をはらむ。
世界を見れば、自国第一主義や強権的な政治の志向が目につく。
米国をはじめ中国やロシア、東欧や南米などに広がっている。
協調を失いかけている世界が眼前にある。
対立が深まれば、緊急の国際課題であるコロナ対策だけでなく、地球温暖化防止や核廃絶にも影響する。
日本周辺でも、中国は公船を沖縄県・尖閣諸島の周辺海域に頻繁に侵入させる。
香港に統制を強化する国家安全維持法を施行し、台湾には武力統一をちらつかせる。
自由や民主主義を抑え込もうとする姿勢があからさまだ。
核開発を進める北朝鮮を考えれば、日本は情報収集などで韓国と協力することが重要なのに、
関係は冷え切ったままになっている。
だからといって日本が攻撃的な姿勢を強めれば、地域の緊張をいっそう高める。
専守防衛に徹し、外交を通じた多国間の協調態勢を構築することこそが求められる。
■戦禍の記憶を記録に
「きさらぎの/はつかの空の月深し/まだ生きて子は/たたかふらむか」
国文学者で歌人の折口信夫(おりくちしのぶ)の歌だ。
徴兵され、南洋で戦う弟子の姿を思った。
東大の加藤陽子教授は
「むざむざ必敗の戦いに愛する若者を引き込んだ国家への静かな怒りが伝わる」と解説する。
戦争に対する、その時を生きた人々の思いは、あまた残る。
そんな記憶に接すれば、日々の平穏な暮らしは平和があってこそ成り立つと強く実感する。
だから次代へ伝えていかねばならない。
ただ戦争を知る世代は減り、今や「戦後生まれ」は全人口の8割を超える。
戦争の体験や教訓を直接聞く機会は失われつつある。
そんな中で注目したいのが、インターネット技術などを駆使して、後世に残そうとする動きだ。
文章はもちろん、映像やアニメなどさまざまな形にして記録しておくことが、記憶の風化を防ぐ。
戦禍を知る術(すべ)を増やし、多くの人に利用してもらう。
それが未来の戦争抑止につながる。
■効率を重視した結果
戦後75年、戦火は交えなかったが、日本は人の命を大事にする社会を築いてきたのだろうか。
焦土から立ち上がり、経済大国にはなった。
だが近年は効率重視の風潮が蔓延(まんえん)し、
その影響で公立病院などは整理統合され、保健所もここ30年でほぼ半減したとの指摘がある。
これは一例にすぎない。
その結果、格差は拡大し、コロナ禍が広がる中、医療体制を揺るがせている。
個人を徹底的に踏みにじる戦争を否定し、何よりも命と自由を尊重する。
その原点に返り、人に優しい社会を築いていく必要がある。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
民主主義は努力なくして継続出来ない。簡単に壊れてしまう。
戦争を二度と起こさないために、過去の史実にきちんと向き合い、
誤ちを誤ちとして認め、繰り返さない努力を常にしていかなければならない。
まだ75年、常に戦後でいられるように。
totoco さんのツイッターより。
現在の平和と繁栄が過去の犠牲の上に築かれているとするなら、
未来の平和と繁栄のためには、現在の人間が犠牲になるべきだという話になります。
安倍さんが展開しているのは、国民に犠牲を要求する理屈ですね。
個人的には、犠牲を尊ぶ首相の立論より、失われた命を悲しむ陛下の言葉に共感します。
小田嶋隆 さんのツイッターより。
戦後75年。
政治家も経営者も官僚も学者も記者も
本当の戦争を知る者はほとんどいない。
今や日本は長老も重鎮も「戦争を知らない世代」なのだ。
まずはそれを自覚したい。
戦争を知る者がいなくなっても、その痛みを忘れないように刻み込まれたのが日本国憲法なのだ。
鮫島浩さんのツイートより。
子供は刃物の使い方も怖さも知らない。
そんな状態で刃物を使わせるバカはいないはずだ。
「戦争を知らない世代」は、やっぱりまだ“子供”なのだ。
戦争ゲームで戦争を語る奴ほど、危ないものもない。
ゲームでは血を流し、やけどなど負傷する人間を語ることは絶対できないのだ。
緒方貞子さんのように、紛争の地を歩き、解決に奔走した者や
中村哲さんのように、現場の発展に必要なものこそ築こうとした人間こそ、政府に欲しい。

↑
オリジナルアルバム『Father's Son 』初出

↑
浜省の雄姿をぜひDVD(or Blu-ray)でどうぞ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
北海道新聞 2020年8月15日付社説
「終戦から75年 命の尊さをかみしめたい」
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/450578?rct=c_editorial
日本だけで310万人、アジア太平洋地域では2千万人とも言われる犠牲者を出した戦争の終結から、
きょうで75年を迎える。
戦後の日本は戦争の放棄と戦力不保持をうたう平和憲法を掲げ、戦争当事国にはならない道を、
4分の3世紀歩んできた。
だが、その平和がこの先も保たれるのか。
安倍晋三首相のこれまでの取り組みを見れば、懸念は膨らむばかりだ。
米中対立など、国際社会は不安定さを増している。
それに合わせるかのように、首相は新たな攻撃力の整備に関心を向ける。
これでは、ますます「戦争ができる国」に近づこうとしているとしか思えない。
悲惨な戦争を二度と繰り返さないと誓い、戦後をスタートさせた日本である。
力に頼る道を突き進むことは、その原点を顧みていないに等しい。
新型コロナウイルスの感染拡大で、命の尊さをかつてないほど意識する毎日だ。
だからこそ、この日に平和な社会をいかにしてつくるか、じっくり考えたい。
■憲法の理念に反する
首相は今月初め、自民党が提言した「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有」について、
「しっかり新しい方向性を打ち出し、速やかに実行する」と前向きな姿勢を見せた。
自民党が求めたのは事実上の「敵基地攻撃能力」の保有だ。
相手国のミサイルを迎撃するシステム「イージス・アショア」の導入断念を受けて浮上した。
ただ相手側のミサイル発射の兆候を誤判断すれば、専守防衛を逸脱する先制攻撃となり得る。
だから歴代政権は否定してきた。
保有を認めれば安全保障政策の大転換であり、憲法の理念に反する可能性が大きい。
これまで安倍政権は「積極的平和主義」を掲げて、集団的自衛権の容認を強引に進め、
自衛隊が戦争に巻き込まれかねない安全保障関連法を制定した。
「敵基地攻撃能力」はそれ以上の危険をはらむ。
世界を見れば、自国第一主義や強権的な政治の志向が目につく。
米国をはじめ中国やロシア、東欧や南米などに広がっている。
協調を失いかけている世界が眼前にある。
対立が深まれば、緊急の国際課題であるコロナ対策だけでなく、地球温暖化防止や核廃絶にも影響する。
日本周辺でも、中国は公船を沖縄県・尖閣諸島の周辺海域に頻繁に侵入させる。
香港に統制を強化する国家安全維持法を施行し、台湾には武力統一をちらつかせる。
自由や民主主義を抑え込もうとする姿勢があからさまだ。
核開発を進める北朝鮮を考えれば、日本は情報収集などで韓国と協力することが重要なのに、
関係は冷え切ったままになっている。
だからといって日本が攻撃的な姿勢を強めれば、地域の緊張をいっそう高める。
専守防衛に徹し、外交を通じた多国間の協調態勢を構築することこそが求められる。
■戦禍の記憶を記録に
「きさらぎの/はつかの空の月深し/まだ生きて子は/たたかふらむか」
国文学者で歌人の折口信夫(おりくちしのぶ)の歌だ。
徴兵され、南洋で戦う弟子の姿を思った。
東大の加藤陽子教授は
「むざむざ必敗の戦いに愛する若者を引き込んだ国家への静かな怒りが伝わる」と解説する。
戦争に対する、その時を生きた人々の思いは、あまた残る。
そんな記憶に接すれば、日々の平穏な暮らしは平和があってこそ成り立つと強く実感する。
だから次代へ伝えていかねばならない。
ただ戦争を知る世代は減り、今や「戦後生まれ」は全人口の8割を超える。
戦争の体験や教訓を直接聞く機会は失われつつある。
そんな中で注目したいのが、インターネット技術などを駆使して、後世に残そうとする動きだ。
文章はもちろん、映像やアニメなどさまざまな形にして記録しておくことが、記憶の風化を防ぐ。
戦禍を知る術(すべ)を増やし、多くの人に利用してもらう。
それが未来の戦争抑止につながる。
■効率を重視した結果
戦後75年、戦火は交えなかったが、日本は人の命を大事にする社会を築いてきたのだろうか。
焦土から立ち上がり、経済大国にはなった。
だが近年は効率重視の風潮が蔓延(まんえん)し、
その影響で公立病院などは整理統合され、保健所もここ30年でほぼ半減したとの指摘がある。
これは一例にすぎない。
その結果、格差は拡大し、コロナ禍が広がる中、医療体制を揺るがせている。
個人を徹底的に踏みにじる戦争を否定し、何よりも命と自由を尊重する。
その原点に返り、人に優しい社会を築いていく必要がある。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
民主主義は努力なくして継続出来ない。簡単に壊れてしまう。
戦争を二度と起こさないために、過去の史実にきちんと向き合い、
誤ちを誤ちとして認め、繰り返さない努力を常にしていかなければならない。
まだ75年、常に戦後でいられるように。
totoco さんのツイッターより。
現在の平和と繁栄が過去の犠牲の上に築かれているとするなら、
未来の平和と繁栄のためには、現在の人間が犠牲になるべきだという話になります。
安倍さんが展開しているのは、国民に犠牲を要求する理屈ですね。
個人的には、犠牲を尊ぶ首相の立論より、失われた命を悲しむ陛下の言葉に共感します。
小田嶋隆 さんのツイッターより。
戦後75年。
政治家も経営者も官僚も学者も記者も
本当の戦争を知る者はほとんどいない。
今や日本は長老も重鎮も「戦争を知らない世代」なのだ。
まずはそれを自覚したい。
戦争を知る者がいなくなっても、その痛みを忘れないように刻み込まれたのが日本国憲法なのだ。
鮫島浩さんのツイートより。
子供は刃物の使い方も怖さも知らない。
そんな状態で刃物を使わせるバカはいないはずだ。
「戦争を知らない世代」は、やっぱりまだ“子供”なのだ。
戦争ゲームで戦争を語る奴ほど、危ないものもない。
ゲームでは血を流し、やけどなど負傷する人間を語ることは絶対できないのだ。
緒方貞子さんのように、紛争の地を歩き、解決に奔走した者や
中村哲さんのように、現場の発展に必要なものこそ築こうとした人間こそ、政府に欲しい。